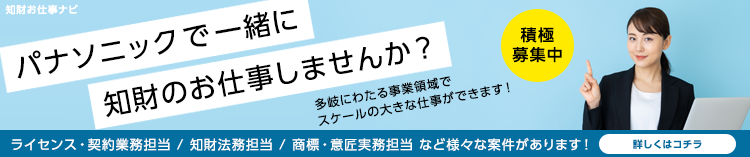この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
| 審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
|---|---|---|
| 平成25ネ10080損害賠償本訴,著作権確認等反訴請求控訴事件,同附帯控訴事件 | 判例 | 特許権 |
| 平成25ワ28859著作権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許権 |
| 平成24ワ32339著作権侵害差止等請求事件 | 判例 | 特許権 |
| 平成24ワ24300損害賠償請求事件 | 判例 | 特許権 |
| 平成25ネ10068損害賠償請求控訴事件 | 判例 | 特許権 |
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|
| 事件 |
出版差止等請求事件
|
|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 2014/09/12 |
| 権利種別 | 著作権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 判例全文 | |
|---|---|
|
判例全文
平成26年9月12日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 平成24年(ワ)第29975号 出版差止等請求事件(以下「A事件」という。) 平成24年(ワ)第10544号 出版契約無効確認請求事件(以下「B事件」 という。) 口頭弁論終結日 平成26年7月9日 判 決 東京都千代田区<以下略> A事件及びB事件原告 株式会社読売新聞東京本社 (以下「原告」という。) 同訴訟代理人弁護士 喜 田 村 洋 一 同 升 本 喜 郎 同 稲 垣 勝 之 同 金 子 剛 大 同 那 須 勇 太 東京都文京区<以下略> A事件及びB事件被告 株 式 会 社 七 つ 森 書 館 (以下「被告」という。) 同訴訟代理人弁護士 岡 邦 俊 同 小 畑 明 彦 同 前 原 一 輝 主 文 1 被告は,別紙出版物目録記載の出版物を,発売等頒布してはならない。 2 被告は,原告に対し,171万円及びこれに対する平成24年11月 21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告と被告との間において,別紙著作物目録記載の著作物に関する出 版権が被告に存在しないことを確認する。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,A事件に生じた部分はこれを5分し,その3を被告の負 担とし,その余を原告の負担とし,B事件に生じた部分は被告の負担と する。 6 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 1 A事件 (1) 主文第1項と同旨 (2) 被告は,原告に対し,688万円及びこれに対する平成24年11月2 1日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 (3) 2項につき仮執行宣言 2 B事件 (1) 原告 主文第3項と同旨 (2) 被告 ア 本案前の答弁 (ア) 本件訴えを却下する。 (イ) 訴訟費用は,原告の負担とする。 イ 本案の答弁 (ア) 原告の請求を棄却する。 (イ) 訴訟費用は,原告の負担とする。 第2 事案の概要 1 前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,本判 決を通して,証拠番号はA事件において付記された番号であり,枝番の記載 を省略することがある。) (1) 当事者 ア 原告は,日刊新聞の発行等を目的とする会社であり,「讀賣新聞」を 発行している。同新聞は,以前,株式会社読売新聞社(以下「読売新聞 社」という。)が発行していたところ,平成14年7月1日,読売新聞 グループの再編に伴い,同社は,商法(平成17年7月26日法律第8 7号による改正前のもの。以下「旧商法」という。)373条の新設分 割により,原告を新設分割会社として,読売新聞グループの持株会社で ある株式会社読売新聞グループ本社(以下「読売新聞グループ本社」と いう。)と,上記新聞の編集・発行事業等を行う原告とに会社分割され た。〔弁論の全趣旨〕 イ 被告は,図書の出版及び販売等を目的とする会社である。 (2) 原書籍 ア 平成3年頃から平成10年頃にかけて発生した大手証券会社や都市銀 行による,総会屋や衆議院議員に対する利益供与事件,日本道路公団, 大蔵省,日本銀行の職員に対する接待汚職事件(以下,これらを総称し て「本件利益供与及び接待汚職事件」という。)について,読売新聞社 社会部の記者らは,平成8年夏頃から,当時読売新聞社の社会部次長で あったC(以下「C」という。)を中心に取材を行った。 この取材結果を基に,その成果を書名「会長はなぜ自殺したか-金融 腐敗=呪縛の検証」という著作物として一つの単行本にまとめ,同書は, 平成10年9月20日,株式会社新潮社(以下「新潮社」という。)か ら発行された(甲1。以下「原書籍1」という。)。 その後,この単行本は,平成12年10月1日,同じ題名で,新潮文 庫として新潮社から発行された(甲2。以下「原書籍2」という。)。 イ 原書籍1には,その255頁から259頁にかけて,平成10年8月 付けの「あとがき」が付されており,その末尾には「読売新聞社東京本 社社会部次長 C」と記載されている。 また,原書籍2には,その306頁から310頁にかけて,上記「あ とがき」が,さらにその311頁から315頁にかけて,平成12年8 月付けの「文庫化にあたっての付記」が付されている。 原書籍1及び2の「あとがき」には,執筆者として当時読売新聞社の 社会部に所属していたD,E,F(以下「F」という。),G,H,I, J,K及びC,以上9名の記者(以下「本件執筆者9名」という。)の 氏名が記載されている。〔甲1,2,乙3〕 ウ 原書籍1及び2の著作者表示は,いずれも,「読売新聞社会部」であ る。〔甲1,2,乙3〕 (3) 出版契約 ア 被告は,原書籍1及び2について,その復刻版の発行を企画した。 そして,平成23年5月9日付けで,原書籍1及び2に記載された著 作物に関する出版契約書(甲4。以下「本件出版契約書」といい,同契 約書に基づく契約を「本件出版契約」と,同契約書の対象となった別紙 著作物目録記載の著作物を「本件著作物」という。)が作成された。 イ 本件出版契約書は,被告側においてその原稿を作成し,当時,原告の 社会部次長であったFとの間で行ったやりとりを経て修正されたもので あり,その体裁及び内容は,次のとおりである。すなわち,「出版契約 書」との表題の下に,「著作代表者名 F」,「書名 会長はなぜ自殺 したか 金融腐敗=呪縛の検証」と不動文字で記載され,さらにその下 に,「上記著作物を出版することについて,著作権者 読売新聞東京本 社を甲とし,出版者 株式会社七つ森書館を乙とし,両者の間に次のと おり契約する。2011年5月9日」と不動文字で記載されている(た だし,上記日付部分の「5」 「9」 と のみは,手書きで記載されている。 。 ) さらに,「甲(著作権者) 住所 東京都中央区<以下略> 氏名 読 売新聞東京本社」との不動文字名下に「社会部次長 F」と手書きで記 載され,「F」との印影の個人名印の押印がなされており,その下に, 「乙(出版権者)」として被告の記名押印がなされている。なお,その 「第1条(出版権の設定)」には,「甲は,表記の著作物(以下「本著 作物」という)の出版権を乙に対して設定する。2. 乙は,本著作物を 出版物(中略)として複製し,頒布する権利を専有する。」などと規定 されている。〔甲4,乙2〕 ところで,本件出版契約書には,付箋が貼付されており,その付箋に は,「L様 本社の法務部門と協議の上,私個人の捺印と致しました。 今後の手続きよろしくお願い致します。」と,また,当該記載の末尾に は,「F」と,それぞれ手書きで記載されている。 (4) 被告による書籍の出版 被告は,本件出版契約に基づき,別紙出版物目録記載の書籍(以下「本 件書籍」という。)を製本し,これを発売等頒布している。 (5) 本件書籍におけるあとがき及び著作者表示 本件書籍には,その262頁から269頁にかけて,「本シリーズにあ たってのあとがき」という表題の文章が記載されており,その末尾には, 「2012年4月」「元読売新聞社会部 C」と記載されている(以下, この文章全体を「本件あとがき」という。)。 本件あとがきは,全136行の8頁にわたる文章であり,その内容は基 本的に,本件書籍の表題であり,本文のテーマでもある金融腐敗の検証に 関連する記載から構成されているが,そのうち7頁目において,6行にわ たり,Cが,株式会社読売巨人軍(以下「読売巨人軍」という。)の専務 取締役球団代表兼GMの職にあった2011年(平成23年)11月,読 売新聞グループ本社代表取締役M会長(以下「M会長」という。)を記者 会見で告発して解任されたこと,同告発は既に報告し確定していたコーチ 人事を「鶴の一声」で覆す同会長の球団私物化の非を訴えたものであった などと記述されている。 また,本件書籍の著作者表示は,「読売社会部C班」である。〔甲3, 乙4〕 2 本件のうちA事件は,原告が,被告に対し,被告が行う本件書籍の発売等 頒布は,原書籍1及び2について原告が有する著作権(複製権,譲渡権及び 翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権等),さらに原告の 名誉権を侵害すると主張して,著作権法112条1項及び名誉権に基づき本 件書籍の発売等頒布の差止めを求めるとともに,民法709条に基づく損害 賠償金688万円及びこれに対する平成24年11月21日(訴状送達日の 翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を 求め,B事件は,原告が,原告と被告との間において,本件著作物に関する 出版権が被告に存在しないことの確認を求めた事案である。 3 争点 (1) 確認の利益の有無 (2) 原告は原書籍1及び2につき著作権を有するか (3) 本件出版契約の有効性 (4) 著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権等)侵害の有無 (5) 名誉権侵害の有無 (6) 損害の有無及びその額 (7) 本件著作物に関する被告の出版権の有無 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点(1)(確認の利益の有無)について 〔原告の主張〕 B事件における原告の訴えは確認の利益を十分に備えている。すなわち, 本件出版契約に定める規定によれば,仮に同契約が有効であるとすると,原 告は,少なくとも平成27年5月31日まで,本件著作物の全部又は一部を 転載した書籍や,本件著作物と明らかに類似すると認められる内容の書籍, さらには,本件著作物と同一書名の書籍を,自ら出版することはもとより, 第三者をして出版させることも許されないことになる。これは,原告の権利 又は法律的地位について現に存在する不安の一内容であり,かかる原告の不 安を除去するには,B事件のように被告が本件著作物に関する出版権を有し ないことを確認する旨の確認判決を得ることが有効適切な方法になるとい うべきである。 この点に関し,確かに,本件書籍の出版差止等請求事件であるA事件にお いて本件出版契約の有効性が争点になっていることは事実であるが,A事件 において裁判所が当該争点について判断するとしても,その判断は判決理由 中の判断にすぎず,既判力が及ばない。そうすると,被告は,今後,本件出 版契約が有効であることを前提に,原告が上記のように自ら,又は第三者を して出版する際に,これを差し止める請求をするおそれがある。 したがって,B事件のような確認判決を得ることは原告の上記不安を除去 するに有効適切な方法というべきである。 よって,B事件における原告の訴えは,適法である。 〔被告の主張〕 B事件における原告の訴えには確認の利益がない。すなわち,原告は,被 告が本件書籍を出版することにより原告の原書籍1及び2にかかる著作権 が侵害されていると主張するが,かかる著作権侵害の不安を除去するには, 本件書籍の出版等の差止請求をするほかに有効適切な方法はなく,B事件の ように被告が本件著作物に関する出版権を有しないことが確認されたとし ても,仮に被告が原書籍1及び2の著作権の帰属を争えば,原告の上記不安 は除去されない。 したがって,B事件における原告の訴えは,不適法である。 2 争点(2)(原告は原書籍1及び2につき著作権を有するか)について 〔原告の主張〕 原書籍1及び2は,次のとおり,職務著作(著作権法15条1項)である から,その著作者は,読売新聞社である。 したがって,前記第2,1(1)アのとおり会社分割により同社の権利を承 継した原告は,その著作権を有する。 (1) 「法人…の発意」の要件について 職務著作における「法人…の発意」とは,著作物の作成の意思が直接又 は間接に使用者の判断にかかっていればよく,具体的な命令がなくとも, 雇用関係等から見て使用者の間接的な意図の下に創作した場合も含み,例 えば,会社の従業員が自分からアイデアを出して上司の了承を得たという 場合においても認められる。 原書籍1及び2は,当時から原告と雇用関係にあるFが書籍化のアイデ アを出し,当時原告の社会部長であったN(以下「N」という。)の了承 を得て出版されたものであるから,「法人…の発意」の要件を満たすとい うべきである。 (2) 「法人等の業務に従事する者」の要件について 原書籍1及び2の「あとがき」によれば,原書籍1及び2の執筆を行っ たのは,本件執筆者9名であるところ,これらの者は,いずれも,原書籍 1及び2の発行当時,読売新聞社と雇用関係にある従業員であったから, 「法人等の業務に従事する者」の要件を満たすというべきである。 (3) 「職務上作成」の要件について 読売新聞社は,日刊新聞の発行のほか,書籍の発行もその事業目的とし ており,その従業員が書籍を執筆,発行することが職務と評価し得るもの であるところ,原書籍1及び2は,原告の社会部に所属する多数の記者が, 社会部長の了解の下,その職務に含まれていた本件利益供与及び接待汚職 事件の取材を行い,その取材結果をまとめたものであり,その職務と密接 に関連する内容の書籍といえる。また,本件執筆者9名は,業務時間も利 用しながら原書籍1及び2の執筆を行ったのであって,自らの職務と無関 係に執筆活動をしたものではない。 したがって,原書籍1及び2は職務上作成されたものであることは明ら かであり,「職務上作成」の要件を満たすというべきである。 (4) 「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」の要件について 原書籍1及び2は,「読売新聞社会部」の名義で公表されたものである。 この名義は法人組織である読売新聞社,若しくはその一部門である編集局 社会部を名義として表示するものであることは明らかであり,原書籍1及 び2は「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」の要件を満たす というべきである。 (5) 「その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない」の 要件について 原書籍1及び2について,読売新聞社の社内規則において,本件執筆者 9名を著作者とする契約その他別段の定めはなかった。 この点,読売新聞社の「職務上著作物の著作権に関する規定」(甲49。 以下「本件職務著作規定」という。)の1項は,読売新聞社ないし原告が 発行する刊行物についてのみ職務著作物に当たると定めたものではない。 同項は,読売新聞社ないし原告の従業員が,職務上執筆若しくは撮影して, 会社発行の新聞や,会社発行に限られないその他の刊行物に掲載した著作 物を職務著作物とし,これについて原則として著作権が読売新聞社ないし 原告に帰属することを定めたものである。そもそも,読売新聞社ないし原 告が,その従業員が職務上執筆した書籍を自ら出版するケースは限られて おり,原告にとって職務著作物を会社発行の刊行物に限定すべき理由がな い。 したがって,原書籍1及び2は「その作成の時における契約,勤務規則 その他に別段の定めがない」の要件を満たすというべきである。 〔被告の主張〕 原書籍1及び2の著作者は,本件執筆者9名であるから,原告の上記主張 は失当である。本件は,次のとおり,職務著作の要件を何ら具備していない。 (1) 「法人…の発意」の要件について 原書籍1及び2の作成を発意したのは,本件あとがきの執筆者であり原 書籍1及び2が出版された当時社会部次長であったCであり,発意の相手 方は新潮社である。Cは,その職務上行った一連の新聞記事の執筆作成と は別に,その取材班と同じメンバーで新たな追加取材をしてその成果をま とめ,社外で出版することを企画し,その企画を新潮社の常務取締役Oに 伝え,その承認を得て新潮社において原書籍1及び2の出版が実現した。 この点,原書籍1及び2の出版に関する契約は,新潮社と著作代表者であ るCとの間で締結された。 また,原書籍1及び2の印税は,新潮社から本件執筆者9名のうちC外 4名の主要メンバーに直接支払われた。この点,印税額及びその配分につ いては,Cと新潮社で取り決めており,読売新聞社が関与することは一切 なかった。 なお,当該契約に際して,印税支払に関する「覚書」(乙6)は上記当 事者間で作成されたが,ほかに出版契約書等の契約に関する書面は作成さ れなかった。 この点,原書籍1及び2について当時社会部長であったNの了解が得ら れているが,このことは,「法人…の発意」があることを意味しない。「読 売新聞社会部」は,特定の自然人である本件執筆者9名の総称であり,そ の著作名義で原書籍1及び2を新潮社から出版することについて,読売新 聞社員であることを表示した個人名で出版を行う場合として,読売新聞社 の「従業員就業規則」(甲17。以下「本件就業規則」という。)の7条 所定の「従業員が読売新聞社員たるの名をもって他の新聞,雑誌,刊行物 等に寄稿通信し,または出版する場合」に該当するため,Cにおいて,予 め当時社会部長であったNに届け出て,同人を経由して読売新聞社の了承 を得たものであるにすぎない。 (2) 「法人等の業務に従事する者」の要件について 原書籍1及び2の「あとがき」に,執筆者として表示されている本件執 筆者9名が,原書籍1及び2の発行当時,読売新聞社と雇用関係にある従 業員であったことは認めるが,「法人等の業務に従事する者」の要件該当 性については争う。 (3) 「職務上作成」の要件について 原書籍1及び2は,読売新聞社の業務の一つとして出版されたものでは なく,読売新聞社とは無関係の別法人である新潮社の業務として出版され ているから,「職務上作成」の要件を満たさない。 また,原書籍1及び2は,社外で出版するというCの明白な意識の下に, 職務外のものとして作成されたものであり,「職務上」作成されたもので はない。 (4) 「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」の要件について 原書籍1及び2の「読売新聞社会部」との著作者表示は,いずれも,本 件執筆者9名の総称であるから,「法人等が自己の著作の名義の下に公表 するもの」の要件を満たさない。 この点,原書籍1及び2は,執筆者であるCらの個性が反映された,極 めて創作性の高い著作物であり,その著者者表示とCが執筆したあとがき を総合すれば,本件執筆者9名が著者であることは明らかである。 (5) 「その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない」の 要件について 本件就業規則7条は,「従業員が読売新聞社員たるの名をもって他の新 聞,雑誌,刊行物等に寄稿通信し,または出版する場合…はあらかじめ所 属部課長を経て会社の了解を得なければならない。」と規定するが,本件 職務著作規定は,その1項に,「従業員が職務上,執筆…して,会社発行 の新聞その他の刊行物に掲載した記事…等の著作物(…職務上著作物…) についての著作権は,従業員署名の有無にかかわらず,原則として会社に 帰属する。」と規定している。本件職務著作規定は,本件就業規則の特別 規定であり,職務著作の成立を「会社発行の」新聞やその他刊行物に限定 する「別段の定め」と解すべきであるから,本件では,著作権法15条1 項の「その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定め」がある。 この点,本件職務著作規定の1項の規定には「原則として」との文言が あるが,それは「会社発行の」刊行物であっても職務著作物に該当しない 例外があるとして職務著作の成立する範囲をより狭める趣旨であり,社外 刊行物については一律に職務著作物の範囲外とするものであることは明ら かである。 また,本件職務著作規定付記1の規定文言に照らせば,同項の「会社発 行の新聞」は「刊行物」の例示にすぎないと解することはできない。 さらに,本件職務著作規定は,その2項や,5項,8項の規定から社外 で刊行される職務著作物の存在を予定しているということはできない。本 件職務著作規定は,1項において「会社発行の」刊行物を職務著作物に当 たると定義することを前提に,形式的には第三者が発売元となるとしても 実質的には読売新聞社側が自ら発行する場合や,読売新聞社側と第三者と の間に出版事業を共同事業とするような契約関係が存在する場合,読売新 聞社が従業員を社外事業の担当者に任命する業務命令を発した場合,その 他,後発的理由により読売新聞社側が出版する意図を失った場合について 規定するものにすぎない。 3 争点(3)(本件出版契約の有効性)について 〔被告の主張〕 (1) 仮に,原書籍1及び2について,原告の職務著作物であると認められる としても,被告と原告との間で本件出版契約が成立しており,同契約に基 づいて被告に本件書籍を出版する権限が生じているから,本件書籍の発売 等頒布は原告の有する著作権(複製権,譲渡権及び翻案権)侵害に該当し ない。 ア 原告が本件出版契約の締結に先立って,Fに代理権を授与したことは 明らかである。 すなわち,被告は,その担当社員であるL(以下「L」という。)に おいて,原告側に原書籍の復刊について申入れをしたところ,原告側の 知的財産部がFに対し,被告の申入れを連絡して,被告と折衝するよう 指示した。当該指示を受けたFは,Lに対してCに上記申入れについて 連絡するよう求めた。そこで,被告代表者らはCに会い,復刊について 賛同を得た。Fは,以後,たえず原告側の知的財産部の意向を確認し, その指示を受けながら被告との折衝に当たったもので,復刊に必要な「社 内的な手続き」(乙1の9及び11),「社内の調整」(乙1の10), 「本社の法務部門との協議」(乙2)を行い,被告には,本件書籍の著 者名を「読売社会部C班」とすることや,本件出版契約書の「著作代表 者名」を「F」とし,著作権者の表示を「読売新聞東京本社」とするこ と,ほかに印税は被告が原告の口座に振り込み,それを原告から各執筆 者の口座に振り込むことなどの具体的な指示をした。そして,Fは,本 件出版契約書の「著作権者」欄に署名押印し,同契約書を被告に送付し た。Fは,その個人印を押捺したことについて,同契約書に,「L様 本 社の法務部門と協議の上,私個人の捺印と致しました。今後の手続をよ ろしくお願い致します。 F」と記載した付箋を添付して,その理由を 示していた。 このような経緯からして,原告が,本件出版契約の締結に先立ち,F に代理権を付与し,Fが原告の任意代理人として本件出版契約を締結し たことは疑いの余地がない。 しかるに,原告は本件出版契約の効力を否定するが,それは,Cが, M会長に「重大なコンプライアンス違反」があることを公表したからで あり,原告側は被告に対して,「そのような人間の本を読売新聞として 出すわけにはいかない」との理由を示し,金銭的補償を伴う本件出版契 約の合意解約の申入れをしており,原告において本件出版契約が成立し たことを前提に被告と交渉していた。 よって,本件出版契約は有効である。 イ この点に関して原告は,Fが「社会部次長」であり,原告はFに本件 出版契約締結の権限を授与していなかったと反論する。 しかし,原告の上記主張は職制上の一定の地位の者に当然に与えられ る代理権についていうものにすぎず,本件における代理権授与の事実と は関連しない。現に,原告における出版契約の事例をみると,出版契約 の締結を業務とする営業・庶務部門の職制ではない「社会部長」等の職 制にある者が原告から契約締結の権限を授与されている。 ウ また,原告は,Fが事前に部長職以上の者の了解を得る手続を経た事 実がないとして,契約締結の代理権の授与を否定するが,その根拠とす る本件就業規則7条は従業員が非職務著作物を読売新聞社員たるの個人 名で出版する場合について規定するものであって前提を誤っており,失 当である。そして,原書籍2が新潮社から文庫化された際には上記手続 は取られていないが,それはいったん社外で適法に出版された書籍を文 庫化する場合の規定がないからであり,原書籍の復刊である本件書籍に ついても,上記手続を経る必要がなかったことは明らかである。 エ さらに,本件出版契約書には,Fが社印ではなく個人名印の押印をし ているが,原告における他の出版契約の事例でも同様に個人名印が押印 されているのであるから,個人名の押印がされていることは契約締結の 代理権授与の事実を否定するものではない。 (2) 仮に,原告がFに本件出版契約の締結権限を授与していなかったとして も,前記(1)アのとおり,原告がFにLとの折衝を担当させたことは,被告 に対する本件出版契約の締結の代理権の授与を表示したことにほかならな いし,通常人においてFに契約締結の権限が授与されていると認識するの が当然であるから,被告がFの無権代理を知らなかったことに何ら過失は ない。 したがって,原告が被告に対し,本件出版契約上の責任を負うことは明 らかである(民法109条)。 (3) 仮に,原告がFに対し,被告と折衝する代理権は授与したが,本件出版 契約の締結の代理権を授与していなかった,若しくは,本件出版契約の締 結の代理権を授与したが,契約締結前に消滅していたとしても,原告がF にLとの折衝を担当させたことから,上記(2)と同様,被告は,Fに本件出 版契約の締結の代理権があると信じたことに何ら過失はない。 したがって,これらの場合でも,原告は被告に対し,本件出版契約上の 責任を負うこと(同法110条),又は,本件出版契約の締結の代理権の 消滅について被告に対抗することができないこと(同法112条)は明ら かである。 (4) よって,上記(2)あるいは(3)の場合でも,本件出版契約に基づいて被告 に本件書籍を出版する権限が生じているから,本件書籍の発売等頒布は原 告の有する著作権(複製権,譲渡権及び翻案権)侵害に該当しない。 〔原告の主張〕 (1) 本件出版契約において,著作権者である原告の代表者とされているFは, 当時,社会部次長であり,本件について原告を代理又は代表して本件出版 契約を締結する権限を有していなかったから,本件書籍の発売等頒布は原 告の有する著作権(複製権,譲渡権及び翻案権)侵害に該当する。 すなわち,原告においては,従業員が職務上執筆した記事等を外部の出 版社から発行するときは,事前に部長職以上の者の了解を得ることとされ ている。本件就業規則7条の「所属部課長」とは,各局の部課長を,また, 編集局内では社会部長や政治部長,経済部長等の部長職を指す。「会社の 了解を得る。」とは,これら各部長を通じて,各局の局長(編集局であれ ば編集局長)の了解を得ることを意味しており,実務の運用としては,部 長又は編集局長の了解を得て出版することとされていた。 実際,原書籍1及び2についても,社内手続に従って部長職以上の了承 を得て出版がなされている。これに対して,本件書籍については,そのよ うな手続は履践されておらず,Fは本件出版契約を締結する権限を授与さ れていなかった。なお,Lの復刊許諾に関する申入れについて,原告は, Fにかかる権限を与えたことはなく,原告の知的財産部は上記申入れがあ った旨をFに連絡する趣旨で,申入れに係るメールを転送するとともに電 話で伝えたにすぎず,何ら指示をしたことはない。また,FがLに本件出 版契約書に付箋を添付したのは,Fが実際に知的財産部や法務部と協議を したことはなかったものの,以前にLに「正式に社印を押した契約書を作 成する」とメールを送っていたため,そう説明しておけば,後日にLから 正式な社印がない等の問い合わせが寄せられることもないと考えたためで ある。 したがって,本件出版契約は,そもそも成立しておらず,無効である。 よって,被告に本件書籍を出版する権限は一切ない。 この点,被告は,Fが本件出版契約書の形式について具体的に指示をし ていたとして,本件出版契約の締結に向けて積極的に働きかけていたかの ように主張する。しかし,Fは,Cが上司だった時に何度となく厳しい要 求や命令を受けてCに対する恐怖心を抱いていたのであり,Cの意向に背 くことができなかったにすぎない。Fは,Cに対し,他の執筆者の了解を 得る必要があるのではないかと疑義を唱えたが,Cから「あの本は会社で やったんじゃなくて,俺たちで書いたんだ。残りのやつは俺が承諾を取る からいいんだ。 と激しく叱責され, 」 その意向に背くことができなかった。 また,原告が本件出版契約の存在を知ったのは,平成23年11月11 日に開かれたCの記者会見の後にFから報告を受けた時である。そして, 原告は,その直後から,読売新聞グループ本社の法務部を中心に,本件出 版契約が無効であるとして被告に本件書籍の出版を取りやめるよう要求し ていた。 確かに,原告は,Pにおいて合意解約の提案をしたことはあるが,それ は,本件出版契約が無効であるとはいえ,被告との紛争を穏便に解決する ために,方策として,上記提案をしたにすぎない。 (2) 被告は,仮定的主張として表見代理の成立を主張する。しかし,FにL との折衝を担当させたのは,Cであり,原告ではない。Cは原書籍1及び 2の著作権者ではなく,平成22年10月には著作権者である原告を退職 しており,CがFにLとの折衝を担当させたことは,原告が被告に対して Fに本件出版契約の締結の代理権を授与したことを表示したとはいえない ことは明らかである。 また,原告側の知的財産部の部長が被告の復刊許諾の申入れについて伝 えた者をFにしたのは,Fが原書籍1の執筆担当者のうち,原告の社会部 に所属する者で最年長だったからにすぎず,上記復刊許諾の申入れについ てFに連絡したことは,原告がFに何らかの代理権を授与したものという ことはできない。したがって,本件では,表見代理が成立する前提となる 基本代理権が存在しない。 さらに,被告は,昭和60年に設立され,経験豊富な出版社であり,「社 会部次長」が原告を代理又は代表して本件出版契約を締結する権限を有し ていないことを知っていたか,少なくとも,これ知り得べきであったこと は,明らかである。 よって,いずれにしても,本件で表見代理が成立する余地はない。 4 争点(4)(著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権等)侵害の有無)につい て 〔原告の主張〕 本件書籍は,次のとおり,読売新聞社が有し,原告が承継した著作者人格 権(同一性保持権,氏名表示権,名誉・声望権)を侵害する。 (1) 同一性保持権について 被告は,本件書籍において,原告の承諾なしに,原告と敵対関係にある Cをして,原書籍1及び2に新たに本件あとがきを追記させ,このあとが きを追加した本件書籍を製本の上,発売等頒布した。しかも,その内容は, 本件書籍の内容とは全く関係のない,Cの読売巨人軍における役職解任に 関する記載であり,かつ,原告を含む読売新聞グループの名誉を毀損し, 自らを正当化するC個人の一方的な主張(「M会長が,読売ジャイアンツ のコーチ人事を鶴の一声で覆すというコンプライアンス違反行為を行っ た」「球団を私物化している」などという主張)を記載するものとなって いる。このように,被告は,著作者である原告に無断で加筆し,その他の 改変を行っており,かつ,その内容は,原告の意思に反するものである。 したがって,このような被告の行為は,原告の有する同一性保持権(著 作権法20条1項)を侵害する。 (2) 氏名表示権について 原書籍1及び2の著作者名は「読売新聞社会部」とされているところ, 被告は,本件書籍を発行するに当たり,原告の承諾なしに,著作者名の表 示を「読売新聞社会部」 「読売社会部C班」 から と変更して出版しており, かかる被告の行為は,原告の著作者人格権(氏名表示権)を侵害する。 (3) 名誉・声望権について 被告が本件書籍を出版する行為は,原告にとって,自らの名誉を毀損し, その意思に強く反する記載部分(本件あとがき)及び著作者表示が存在す る状態で出版される行為であって,Cの記者会見(平成24年11月11 日)以降における原告を含む読売新聞グループとCの激しい対立状態や, その関係が社会的耳目を集めていることに鑑みると,かかる被告の行為は, あたかも原告が,本件書籍の著作者であるにもかかわらず,全く相容れな い立場にあるCの個人名を冠した著者名の表示を許し,かつCの主張内容 の掲載を許したかのように一般に受け取られることになる。被告の行為が 原告の名誉又は声望を害する方法での本件書籍の利用行為であることは明 らかである。 したがって,被告による本件書籍の発売等頒布は,原告の著作者人格権 を侵害する行為とみなされる(著作権法113条6項)。 (4) 著作者人格権の承継について 読売新聞社は会社分割を実施したが,その際,それまで読売新聞社が行 っていた事業のうち,土地の賃貸に関する事業を除く全ての事業が,新設 会社である原告に承継された。また,グループ会社の株式と一部の土地, 預金を除くほとんど全ての資産は,原告に承継されている。さらに,定款 上も,持ち株会社となった読売新聞グループ本社は,日刊紙の発行や図書 の発行及び販売に係る業務等を行う子会社の株式を保有し,その事業活動 を支配,管理することを目的とする会社としてのみ存在しており,読売新 聞社が有していた著作権及び著作者人格権を管理し,これを行使する機能 や法的地位は,すべて原告が包括承継している。 以上のことからすれば,読売新聞社が有していた著作権及び著作者人格 権は,全て原告に承継されているというべきであるから,原書籍1及び2 の著作者人格権についても,原告に包括的に承継されたことは明らかであ る。 〔被告の主張〕 原告の上記主張は,いずれも争う。 なお,著作権法59条によれば,仮に,会社分割に際して,原告が読売新 聞社から原書籍1及び2に係る著作財産権を承継したとしても,その著作者 人格権までを承継することはあり得ない。 5 争点(5)(名誉権侵害の有無)について 〔原告の主張〕 前提として,被告による本件書籍の出版は,事件関係者のプライバシーを 侵害する重大な不法行為に該当する。その上で,被告は,本件書籍の著者名 を「読売社会部C班」と表示して,本件書籍を販売している。 この表示は,一般読者からは,「読売新聞社会部のC班」と理解されるか ら,本件書籍は「読売新聞社」(原告)が著作したものと認識される。そう すると,本件書籍に触れた一般読者は,「原告は,報道機関であるにもかか わらず,事件関係者を含む第三者のプライバシー権を侵害する書籍を著作す るような会社である」との印象を持つことは明らかである。そして,原告は 報道機関の担い手として,国民のプライバシーに対しては慎重な配慮が求め られる立場にあるのであるから,一般読者に上記のような印象を持たれるこ とにより,原告の社会的評価が著しく低下することは明らかである。 したがって,被告による本件書籍の出版行為は,原告の名誉を毀損するも のである。 〔被告の主張〕 否認ないし争う。本件書籍には,原告が報道機関であるにもかかわらず, 本件利益供与及び接待汚職事件関係者を含む第三者のプライバシー権を侵害 する書籍を出版するような会社であるとの表現はない。 なお,原告は出版差止仮処分命令の申立て(東京地方裁判所平成24年(ヨ) 第1809号)において,本件と同じ主張をしたが,上記申立ては,当裁判 所に却下され,同却下決定は確定した。 6 争点(6)(損害の有無及びその額)について 〔原告の主張〕 (1) 著作権侵害及び著作者人格権侵害に基づく損害 ア 著作権侵害に基づく損害(逸失利益) 被告は,平成24年5月19日以降,本件書籍を2100円(税込み) で発売し,現在までに少なくとも2000部を出版している。そして, 本件書籍が,過去に出版された原書籍1及び2の復刻版であることや, 本件書籍について印税が支払われた事実がないこと等を勘案すれば,そ の利益率は,少なくとも30%を下らないから,本件書籍の出版によっ て被告が受けた利益の額は,少なくとも2100円×2000部×30 %=126万円を下ることはない。 したがって,本件書籍の出版による原告の損害の額は,少なくとも1 26万円を下らない(著作権法第114条第2項)。 イ 著作者人格権侵害に基づく損害(慰謝料) 被告は,本件書籍において,Cによる新たな「あとがき」を加え,著 者名も「読売社会部C班」に改変しているが,原告を含む読売新聞グル ープとCとの激しい対立関係が広く社会に知られている現在,著作者で ある原告の意思や意向に真っ向から反する著作者表示や,あとがき部分 の記述を含む本件書籍が販売されたことにより,原告の同一性保持権及 び氏名表示権が大きく害され,とりわけ原告の名誉及び声望が著しく毀 損された。 原告が受けた損害は到底金銭に換算し得るものではないが,これをあ えて評価すれば300万円を下らない。 (2) 名誉毀損に基づく損害 上記のとおり,本件書籍の出版によって,報道機関としての原告の社会 的評価は著しく低下しており,これによって原告が被った損害は極めて甚 大である。原告が受けた損害は,到底金銭に換算し得るものではないが, あえて評価すれば200万円を下らない。 (3) 弁護士費用 被告の上記各侵害行為に対抗するため,原告はやむなく原告訴訟代理人 に依頼して,出版禁止の仮処分を2件申し立て,さらに本件訴訟の提起を 余儀なくされた。その弁護士費用の相当額は被告の不法行為と相当因果関 係にある損害として,被告が負担すべきものである。その金額は,本訴の 難易度や費消すべき時間等を勘案すれば62万円を下らない。 (4) 小括 以上のことからすれば,本件書籍の出版により原告が被った損害の額は, 合計すると688万円を下らない。 〔被告の主張〕 いずれも否認ないし争う。 7 争点(7)(本件著作物に関する被告の出版権の有無)について 〔原告の主張〕 被告は,本件著作物に関する出版権を有すると主張する。しかし,本件出 版契約は,そもそも原告と被告との間で成立しておらず,無効である。よっ て,原告は,原告と被告との間において,本件著作物に関する出版権が被告 に存在しないことの確認を求める。 〔被告の主張〕 本件出版契約は有効であり,被告は,本件著作物に関する出版権を有する。 第4 当裁判所の判断 1 争点(1)(確認の利益の有無)について 被告は,B事件における原告の訴えは,著作権侵害の不安を除去するには A事件のように出版等の差止請求をするほかに有効適切な方法はなく,確認 の利益がないと主張するので,この点について検討するに,確定判決の既判 力は,訴訟物として主張された法律関係の存否に関する判断の結論そのもの について及ぶだけで,その前提である法律関係の存否にまで及ぶものではな く,当事者間において現に当該法律関係の存否を争い即時確定の利益が認め られる限り,確認の利益があるものと認めるのが相当である(昭和33年3 月25日第三小法廷判決・民集12巻4号589頁参照)。 これを本件についてみると,証拠(甲3,4,乙2,4)によれば,本件 出版契約には,「第4条(排他的使用) 甲(注:原告を指す。)は,この 契約の有効期間中に,本著作物の全部もしくは一部を転載ないし出版せず, あるいは他人をして転載ないし出版させない。」,「第5条(類似著作物の 出版) 甲(前同)は,この契約の有効期間中に,本著作物と明らかに類似 すると認められる内容の著作物もしくは本著作物と同一書名の著作物を出版 せず,あるいは他人をして出版させない。」と定められており,また,「第 26条(契約の有効期間) この契約の有効期間は,契約の日から初版発行 の日まで,および初版発行後満3カ年間とする。」と定められていて,本件 出版契約の有効期間は本件書籍の発行日である2012年(平成24年)6 月1日から満3年後の平成27年5月31日までであると認められる。 そうすると,仮に同契約が有効であるとするとき,原告は,少なくとも平 成27年5月31日まで,本件著作物の全部又は一部を転載した書籍や,本 件著作物と明らかに類似すると認められる内容の書籍,さらには,本件著作 物と同一書名の書籍を,自ら出版することはもとより,第三者をして出版さ せることも許されないことになるという現在の権利又は法律関係に関する不 安が存するところ,原告はA事件において本件出版契約が無効であることを 前提に本件書籍の発売等頒布の差止めを請求しているが,仮に審理の結果本 件出版契約が無効であることを理由として本件書籍の発売等頒布の差止めが 認められたとしても,出版契約が無効であるとの判断には既判力は及ばない ところ,それとは別途に本件出版契約の無効そのものが確認されない限り, 原告の上記現在の権利又は法律関係に関する不安は除去されないから,原告 が原告と被告との間において,被告が本件著作物に関する出版権を有しない ことを確認する旨の確認判決を得ることには即時確定の利益があるというべ きである。 したがって,B事件における原告の請求には確認の利益があると認められ るのが相当である。 2 争点(2)(原告は原書籍1及び2につき著作権を有するか)について (1) 著作権法15条1項は,法人その他使用者の発意に基づきその法人等 の業務に従事する者が職務上作成する著作物で,その法人等が自己の著作 の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務 規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする旨規定する。そこ で,本件につき,原書籍1及び2が原告の職務著作といえるかについて, 以下検討する。 (2) 前記第2,1の前提事実並びに証拠(甲1ないし3,5ないし8,18, 27,40ないし43,49,乙5,31ないし33,証人F)及び弁論 の全趣旨によれば,次の事実が認められ,同認定を覆すに足りる的確な証 拠はない。 ア 原書籍1は,当時読売新聞社の社会部に所属する本件執筆者9名が執 筆した。 その本文の内容は,多くの部分が本件利益供与及び接待汚職事件に関 する讀賣新聞の連載記事の記述をベースにしており,連載記事の記述が ほぼそのまま用いられていたり,記述に肉付けがされたりしたものであ って,記事化されていない部分も,Cを含む,読売新聞社の社会部に所 属する延べ41名の記者が平成8年(1996年)夏から,本件利益供 与及び接待汚職事件について500人以上の関係者に取材して得た大部 の取材メモ等が元となり,執筆されたものである。 本件執筆者9名は,原書籍1の出版について当時の社会部長であった Nから了解を得た上,原書籍1の執筆に当たり,原稿を読売新聞社の社 内で,同社のワープロを使用して執筆し,追加取材には,同社のハイヤ ーを使うこともあり,出張取材も認められ,その出張費は会社負担とな っていて,ほかに取材相手との飲食にかかる取材懇談費も会社負担とな っていた。〔甲1,5ないし8,27,40ないし43,乙5,31, 32〕 イ 原書籍1の印税は,執筆をした本件執筆者9名のほかに,読売新聞社 の社会部や写真部にも分配された。〔乙33〕 ウ 原書籍2は,本文の内容が原書籍1と同一であり,原書籍1のCが執 筆した「あとがき」に続けて,「文庫化にあたっての付記」が記載され ているにすぎないものである。〔甲2〕 エ 原書籍1及び2の著作者表示は,いずれも「読売新聞社会部」である。 また,原書籍1及び2の奥書には,「著者」として「読売新聞社会部」 と表示され,「The Yomiuri Shimbun City News Department 1998」の記 が表示されている。〔甲1,2〕 オ 本件書籍は,本文の内容が原書籍1及び2と同一であり,原書籍1の 「あとがき」,原書籍2の「文庫化に当たっての付記」に続けて,Cが 執筆した「本シリーズにあたってのあとがき」(本件あとがき)が追加 されている。〔甲3〕 カ 読売新聞社は,日刊新聞の発行及び販売のほか,雑誌,図書の発行及 び販売も,その事業目的としていた。〔甲16〕 キ 本件就業規則(甲18)には,第7条に「従業員が読売新聞社員たる の名をもって他の新聞,雑誌,刊行物等に寄稿通信し,または出版する 場合および講演,放送,出演等の場合はあらかじめ所属部課長を経て会 社の了解を得なければならない。」と規定されており,職務上著作物の 取扱いについて,本件職務著作規定(甲49)には,「1.従業員が職 務上,執筆もしくは撮影して,会社発行の新聞その他の刊行物に掲載し た記事,写真等の著作物(中略)についての著作権は,従業員署名の有 無にかかわらず,原則として会社に帰属する。 などと規定されている。 」 (3) 上記(2)の認定事実から,原書籍1及び2が職務著作であるかについて, 以下,要件ごとに検討する。 ア 「法人…の発意」の要件について (ア) 「法人…の発意」の要件を満たすためには,著作物の作成の意思が 直接又は間接に使用者の判断にかかっていればよく,著作物作成に至 る経緯,業務従事者の職務,作成された著作物の内容や性質,両者の 関連性の程度等を総合考慮して,従業者が職務を遂行するために著作 物を作成することが必要であることを想定していたか,想定し得たと きは,上記要件を満たすと解するのが相当である。 これを本件についてみると,上記(2)で認定したとおり,原書籍1及 び2の記載は,Cによる「あとがき」(原書籍1),さらに「文庫化 にあたっての付記」(原書籍2)が付加されているが,本文は,いず れも同一の内容であること,同本文の内容は,Cを含む,当時,読売 新聞社の社会部に所属していた延べ41人の記者が,社会部長の了解 の下に,平成8年(1996年)夏から,本件利益供与及び接待汚職 事件について,500人以上の関係者に取材して得られた大部の証言 メモ等を元に執筆されたものであり,讀賣新聞での連載記事から記述 をそのまま転載した部分もあれば,記事に肉付けをした部分もあるこ と,さらに,執筆をした記者は,原書籍1の出版につき社会部長の了 解を得た上,執務時間中に社内のワープロを使用して執筆したほか, 読売新聞社の費用負担において出張を含めた追加取材を行ったこと, 読売新聞社が日刊新聞の発行,販売に限らず図書の発行,販売も事業 目的としていたこと,以上の事実が認められる。 そうすると,原書籍1及び2については,読売新聞社という報道機 関の社会部に所属していた記者らが,社会部長の了解の下,その職務 に含まれていた本件利益供与及び接待汚職事件についての取材を行い, その取材結果をまとめたものとして,その職務と密接に関連する内容 の書籍を執筆したことが明らかであるから,原書籍1及び2の執筆は, 当時の読売新聞社の従業者が職務を遂行するために著作物を作成する ことが必要であることを想定していたか,想定し得た場合に当たると 認めるのが相当である。 したがって,原書籍1及び2は,読売新聞社の発意に基づき作成さ れたというべきであり,「法人…の発意」の要件を満たすということ ができる。 (イ) この点に関して被告は,原書籍1及び2の作成を発意したのは,本 件あとがきの執筆者である当時の社会部次長であったCであって,発 意の相手方は新潮社であること,当時の社会部長の了解は,本件就業 規則7条所定の社外原稿の執筆に関する手続であったにすぎず,原書 籍1及び2の印税は,新潮社から本件執筆者9名のうちC外4名の主 要メンバーに直接支払われているのであるから「法人…の発意」があ ったことを何ら意味しない旨主張し,同主張に沿うCの供述も存する。 しかし,上記Cの供述は何ら客観的な証拠に基づくものではなく, かえって,Fが原書籍 1 及び2の作成を最初に発案した者は自分自身 であり,そのきっかけは,平成9年8月7日に本件利益供与及び接待 汚職事件の関係者への取材から得た事実関係が膨大であり新聞の連載 記事に収まる内容ではなかったことによるものであると述べ(甲27 及び証人F),その根拠として同取材後に直ちに作成したとする資料 (甲50)を提出しており,それらの証拠には特に不自然・不合理な 点は認められず信用するに足りるものであるから,被告の上記主張に 沿うCの供述はたやすく措信できず,他にCが最初に発案したと認め るに足りる証拠はない。 また,原書籍1及び2の作成を最初に発案した人物が誰であれ,上 記(ア)のとおり,そもそも原書籍1及び2は,その内容が,延べ41名 にも及ぶ社会部の記者らがその職務上行った取材の結果をまとめたも のであり,その職務と密接に関連するものであるから,本件執筆者9 名限りで,社会部記者としての職務を離れて執筆した社外原稿である と見ることは相当ではないし,原書籍1及び2の奥書に「著者」とし て表示されているのが,本件執筆者9名の氏名ではなく「読売新聞社 会部」であることとも整合しない。 この点に関して被告は,「読売新聞社会部」との表示は,特定の自 然人である本件執筆者9名の総称である旨主張する。しかし, (甲 証拠 29)によれば,「読売新聞社会部」との著者表示は,「社会部」と いう担当部門がその表示に付されているものの,あくまで法人である 読売新聞社を示すものとして,原書籍1及び2以外にも原書籍1及び 2の発行の前後にわたり,多数の書籍において使用されており,しか も,読売新聞社の社会部に所属していた記者が執筆したものである旨 があとがきに記載されたものであっても上記表示が付されているもの が存在することが認められるところ,「社会部」は読売新聞社の一部 門の表示にすぎないから,その表示自体からしても,法人である読売 新聞社の略称として周知である「読売新聞」という表示が著作者名と して通常の方法により表示されていると評価することができる。 また,「読売新聞社会部」との著者表示を使用する上記多数の書籍 においてはそれぞれ執筆を担当した特定の社会部記者が異なるもので あることが認められるところ,原書籍1及び2やその他複数の書籍の 執筆担当者が書籍ごとに異なるのに,同じ「読売新聞社会部」という 法人の部門名を著作者名として用いていることからしても,「読売新 聞社会部」という表示は,個々の執筆者の総称などではなく,法人名 を表示したものと認めるのが相当であるから,被告の上記主張は採用 することができない。 また,印税の支払については,そもそも原書籍1の印税は,執筆を した本件執筆者9名のほかに読売新聞社の社会部や写真部にも分配さ れているし,また,本件職務著作規定(甲49)の5項及び同項を前 提とする7項によれば,読売新聞社において,同社が職務上著作物を 出版する意図を持たず,執筆者等が職務上著作物を社外で出版する場 合は,それによる印税等の収入を執筆者等に帰属させることがある, と規定していることから,原書籍1及び2の印税がCら同書籍の執筆 者に直接支払われたとしても,そのことをもって直ちに,原書籍1及 び2の作成の意思が直接又は間接に使用者である読売新聞社の判断に かかっていることを否定する事情になるとはいえない。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。 イ 「法人等の業務に従事する者」の要件について 前記(2)アのとおり,原書籍1及び2の執筆者は,本件執筆者9名であ るところ,これらの者が,原書籍1及び2の発行当時,読売新聞社と雇 用関係にある従業員であったことは当事者間に争いがない。 したがって,原書籍1及び2は,読売新聞社の業務に従事する者が作 成したというべきであるから,「法人等の業務に従事する者」の要件を 満たす。 ウ 「職務上作成」の要件について (ア) 「職務上作成」とは,業務に従事する者の職務上,著作物を作成す ることが予定又は予期される行為も含まれると解され,これに該当す るか否かは,法人等の業務の内容,著作物を作成する者が従事する業 務の種類や内容,著作物の種類や内容,著作物作成が行われた時間と 場所等を総合して判断すべきである。 これを本件についてみると,前記第2,1(1)アのとおり,読売新聞 社は,日刊新聞の発行等を目的としており,その業務の内容が事件の 報道であることは明らかであるから,原書籍1及び2を作成した読売 新聞社の記者であった本件執筆者9名が従事する業務には事件の取材 や記事の執筆も含まれるというべきである。さらに,前記(2)アのとお り,本件執筆者9名は,執務時間中に社内のワープロを使用して執筆 したほか,読売新聞社の費用負担で出張を含めた追加取材を行ったの であり,そうすると,原書籍1及び2は,報道機関の社会部に所属す る記者らが,その社会部長の了解の下,報道機関の記者としてのその 職務に含まれていた本件利益供与及び接待汚職事件についての取材か ら得られた情報をまとめ,社会部記者としての職務と密接に関連する 内容の書籍として執筆されたものということができる。 以上によれば,原書籍1及び2は,読売新聞社の業務に従事する者 が,その職務上作成したというべきであるから,「職務上作成」の要 件を満たすと認めるのが相当である。 (イ) この点に関して被告は,原書籍1及び2は,読売新聞社の業務の一 つとして出版されたのではなく,読売新聞社とは無関係の別法人であ る新潮社の業務として出版されているから,「職務上作成」との要件 を満たさない旨主張する。 しかし,上記(ア)のとおり,原書籍1及び2の内容は,読売新聞社の 記者の取材に基づいて,社会的に問題となった本件利益供与及び接待 汚職事件に関して執筆されたものであるから,これが,報道機関たる 読売新聞社の業務の範囲に当たることは明らかである。 また,被告は,原書籍1が,Cの社外で出版するという明白な意識 の下に,職務外のものとして作成されたものであり,「職務上」作成 されたものではないと主張し,同主張に沿うCの供述も存する。 しかし,前記ア(イ)のとおり,原書籍1の作成を最初に発案したのが Cであると認めることはできないから,原書籍1がCの社外で出版す るという明白な意識の下に職務外のものとして作成されたものである との前提を欠いているし,本件執筆者9名のなかには,Cの上記供述 を否定する旨の供述をする者がいること(甲7,27,証人F),前 記(2)アのとおり,原書籍1は,本件執筆者9名によって,執務時間中 に社内のワープロを使用して執筆され,読売新聞社の費用負担で出張 を含めた追加取材に基づいて作成されたものであって,原書籍1及び 2の執筆に関連する諸作業(取材,分析や検討,執筆や校正等の作業) が行われた時間と場所が専ら読売新聞社の社外であり同社のものを用 いていないことを裏付けるに足りる客観的な証拠が提出されていない から,Cの上記供述はたやすく措信できず,他に被告の上記主張を裏 付ける証拠はない。 したがって,「職務上作成」との要件を満たさないとする被告の主 張は採用することができない。 エ 「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」の要件について (ア) 上記要件につき,その名義の認定については,その表示されている 場所,体裁やその著作物の性質等から総合的に判断すべきである。 これを本件についてみると,前記説示のとおり,原書籍1及び2の 本文は,当時,読売新聞社の従業員であって,その社会部に所属して いた記者らが,社会的に問題となった本件利益供与及び接待汚職事件 に関して,報道のために職務上行った取材に基づいて執筆し,これを 職務上作成したものであること,原書籍1及び2の奥書には,「著者」 として「読売新聞社会部」と表示され,「The Yomiuri Shimbun City News Department 1998 が表示されていること が認められる。 以上のような表示の場所,体裁や原書籍1の著作物としての性質等 によれば,原書籍1及び2は,読売新聞社の著作名義の下に公表され たものと認めるのが相当である。 (イ) この点に関して被告は,原書籍1及び2の「読売新聞社会部」との 著者表示は,本件執筆者9名の総称であるから,職務著作の成立要件 を具備しない旨主張するが,同主張に理由がないことは,前記ア(イ) で説示したとおりである。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。 オ 「その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない」 の要件について (ア) 上記要件は,著作物作成の時における契約,勤務規則その他におい て,職務著作に該当する場合であっても使用者ではなく従業者が著作 者となる旨の定めが存在しない,との意味であると解されるところ, 本件全証拠を精査しても,本件において上記のような定めが存在する ことを認めるに足りない。 したがって,本件においては,「その作成の時における契約,勤務 規則その他に別段の定めがない」という要件を満たすというべきであ る。 (イ) この点に関して被告は,本件職務著作規定の1項は,職務著作の成 立を「会社発行の」新聞その他の刊行物に限定しているから,本件に おいては,著作権法15条1項の「その作成の時における契約,勤務 規則その他に別段の定め」が存在する旨主張する。 しかし,本件職務著作規定は,1項において,「従業員が職務上, 執筆もしくは撮影して,会社発行の新聞その他の刊行物に掲載した記 事,写真等の著作物」を「職務上著作物」と定義するところ,会社発 行のものに限って「職務上著作物」とする旨は明示していないから, 「会社発行の新聞」は「刊行物」の例示にすぎないとする解釈を排除 する規定であるとは解されず,ほかに同解釈を否定する根拠となる規 定は存在しない。かえって,本件職務著作規定の2項,8項は,「会 社もしくは社外で職務上著作物を出版するに当たり」 5項は, と, 「会 社が職務上著作物を出版する意図を持たない場合」と規定し,社外出 版物の存在を当然の前提としているところ,「それについての著作権 は会社に帰属するものとする。」(2項),「その執筆者等に著作権 を譲渡し,もしくはその使用を許可して」(5項)と規定しており, これらの規定は,会社発行の刊行物以外においても職務上著作物があ り得ることを規定するものとみるべきであるから,同社において,社 外で刊行される職務著作の存在は予定されていたというべきであり, このことは,同規定の1項の解釈に当たっても斟酌されるべきである。 この点に関しては,原告の社会部長であるP(以下「P」という。) が,被告の主張を前提にすると,原告に所属する記者が職務著作に属 する著作物をあえて社外刊行物として執筆して,印税を直接収受しよ うとする事態を招きかねないとして,被告の上記主張は誤りであると 述べている(甲30)ことにも一定の合理性があるというべきである。 また,被告は,本件職務著作規定が,その2項や,5項,8項の規 定から社外で刊行される職務著作物の存在を予定しているということ はできないのであり,本件職務著作規定は,1項において「会社発行 の」刊行物を職務著作物に当たると定義することを前提に,形式的に は第三者が発売元となるとしても実質的には原告側が自ら発行する場 合や,原告側と第三者との間に出版事業を共同事業とするような契約 関係が存在する場合,原告が従業員を社外事業の担当者に任命する業 務命令を発した場合,ほかに,後発的理由により原告側が出版する意 図を失った場合について規定するものにすぎないとも主張する。 しかし,本件職務著作規定を被告が主張するような場合に限定して 解釈しなければならない理由はなく,被告の上記主張は,その前提と する本件職務著作規定の1項について解釈を誤るものである。 したがって,被告の上記主張はいずれも採用することができない。 (4) 以上によれば,著作権法15条1項に基づき,原書籍1及び2の著作者 は,読売新聞社であると認められるから,同社が原書籍1及び2の著作権 を有していたと認めるのが相当である(著作権法17条)。 そうすると,後記4(4)のとおり,その後,同社が,読売新聞グループ本 社とその子会社である原告とに会社分割された際,原告が読売新聞社の著 作者たる地位を包括承継したものと認められるから,原告は,原書籍1及 び2につき著作権を有すると認められる。 3 争点(3)(本件出版契約の有効性)について (1) 前記2のとおり,本件書籍は,その本文が原書籍1及び2と同一であり, 原告は,原書籍1及び2の著作権を有すると認められるところ,前記第2, 1(5)のとおり,被告は,本件あとがきを付記した本件書籍を製本して,こ れを発売等頒布したことが認められる。そこで,被告の同行為による原告 の著作権(複製権,譲渡権及び翻案権)侵害の成否に関し,本件出版契約 の成否及び有効性について,以下検討する。 (2) 証拠(甲5ないし8,18,19,30,31,39,乙1,2,34, 35,41,証人F,被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実 が認められ,同認定を覆すに足りる的確な証拠はない。 ア 被告は,同社が企画する「ノンフィクション・シリーズ “人間”」 で原書籍1及び2の復刊を企画し,被告の担当者であるLにおいて,平 成22年12月17日,原告のホームページを通じて,原告に,復刊の 許諾について申入れをした。読売新聞グループ本社の知的財産部は,当 時原告の社会部次長であったFに対し,上記申入れがあった旨を連絡す るとともに,同申入れの電子メールをそのまま転送した。Fは,当時, 読売巨人軍の球団代表になっていたCに同申入れを伝えた。そして,C から,「出版社と話をしたい。」との話があり,それを受けて,Fが被 告の担当者であるLと折衝を始めた。〔甲31,39,乙1の1~3〕 イ Lは,出版契約書案(乙41)をCに送り,Cとの協議の結果,本件 書籍の印税を本体価格の8%から10%に変更した。 また,Cは,Lに対し,平成23年1月29日,同書籍の出版につい て,①復刻版の著者名は,「読売新聞社会部」ではなく,「読売新聞社 会部C班」か「読売社会部C班」にしてもらいたい,このことについて は,かつての部下らの同意を得ている,後者のほうが簡潔かもしれない こと,②契約書の検討は,Fを通じて原告でやってもらう予定である旨 伝えた。〔乙1の4〕 ウ Fは,平成23年2月2日,L宛てにメールをし,著者名は「読売社 会部C班」でお願いしたいと伝え,また,契約の手続については,若干 社内の著作権管理の部署に相談しなければならないので,今しばらく時 間をいただきたいと伝えた。〔乙1の7〕 エ Fは,平成23年2月14日にも,L宛てにメールをした。その内容 は,次のとおりであった。 すなわち,「ご連絡が大変遅くなりました。社内の調整が終えました ので,以下のような形で契約書を交わさせていただければ,と考えてい ます。 1) Cはすでに読売新聞を退社して,球団の取締役になっているため, 冒頭の『著作代表者』については,社員である『F』とさせて下さい。 署名については,現行通りでお願いします。 2)著作権者は,『読売新聞東京本社』でお願いします。従って,甲(著 作権者)についても住所 東京都中央区<以下略> 氏名 読売新聞 東京本社としてください。 3)15条と16条について 印税については,読売新聞東京本社の口座に振り込んでいただいて から,従業員の分については,本社が給与口座に,Cの分については Cの個人口座にそれぞれ源泉徴収した上で振り込むという形をとりた いと考えています(後略)。 当方の条件は,以上になりますので,ご検討いただきますようお願 い申し上げます。了承いただけましたら,正式に『社印』を押印した 契約書を作成したいと思います。」〔乙1の10〕 オ Fは,平成23年5月10日頃,被告宛てに,本件出版契約書1通を 郵送した。その記載内容や,添付された付箋及びその記載内容は,前記 第2,1(3)イのとおりであり,「社会部次長 F」と手書きで署名し た上,「F」との印影の個人名印の押印をして,Lに返送したものであ る。その際,Fは,本件出版契約書に「L様 本社の法務部門と協議の 上私個人の捺印と致しました。今後の手続きよろしくお願い致します。 F」と手書きで書いた付箋を貼付していた。〔乙2〕 カ Fは本件書籍のゲラのチェックを進めていたが(乙1の15),平成 23年11月23日,被告にこの件に関しては「法務部へ預けた。」と 電話で連絡した。 キ 原告の法務部長であるPは,平成23年12月1日及び同月26日に 被告を訪れ,原告の弁護士から本件出版契約の有効性に疑義があるとの 指摘を受けている,仮に本件出版契約が有効としても契約の解除をお願 いしたい,契約解除に当たっては合計300万円(逸失利益200万円 及び解決金100万円)での金銭解決をしたい,と申し入れた。〔乙1 4の2〕 ク 被告が原告の上記申入れを拒み,本件書籍初版の印刷等に着手したこ とから,原告は,平成24年4月11日,B事件を当裁判所に提起した。 さらに,原告は,同年5月18日,被告に対し,著作権仮処分命令申立 事件(当庁平成24年(ヨ)第22032号。以下「本件仮処分命令申 立て」という。)を当裁判所に提起した。 また,原告は,同月23日,被告に対し,出版差止仮処分命令申立事 件(当庁平成24年(ヨ)第1809号)を当裁判所に提起した。〔顕 著な事実〕 ケ 本件書籍については,Fのほかに,社会部長,編集局長等を含めた原 告社内の部門において,本件出版契約書の作成,署名等に関わったり, その出版について了承していたり,ゲラの校正等に関わったりした形跡 はない。原書籍1及び2の本文の執筆を行ったJ(甲5),I(甲6), E(甲7),K(甲8)は,いずれも本件書籍の出版について事前の連 絡は一切なかったと各陳述書で述べている。 なお,Fは,平成13年に,同僚記者と取材,執筆し,著者名「読売 新聞社会部」の書籍「外務省激震」を出版したことがあり,前記イの時 点において,本件就業規則により,読売新聞社の社員が書籍を出版する には少なくとも社会部長の了解を得なければならないことは知ってい た。〔甲31〕 コ ところで,原告では,従業員が職務上執筆した記事等を外部の出版社 から発行するときの定めとして,本件就業規則の7条に,「従業員が読 売新聞社員たるの名をもって他の新聞,雑誌,刊行物等に寄稿通信し, または出版する場合および講演,放送,出演等の場合はあらかじめ所属 部課長を経て会社の了解を得なければならない。」と規定されており, 同「所属部課長」とは編集局内では社会部長,政治部長,経済部長等の 部長職を指し,同「会社の了解」とは編集局であればこれら各部長の上 司である編集局長の了解を得ることを意味するところ,原告における実 際の運用としては,少なくとも,その所属する部の部長の了解を得て出 版することとされていた。〔甲18,19,30,31〕 サ 原告において,著者名を「読売新聞社会部」として出版された約50 冊の書籍については,いずれも上記コの手続がとられていた。例えば, Pは,同人が読売新聞社の社会部次長であった平成18年(2006年) 9月,「ドキュメント検察官」という書籍を取りまとめ,中央公論新社 から出版したが,その際,同出版について,当時の社会部長を通じて当 時の編集局長の了解を得ていた。〔甲19〕 シ 本件で本件出版契約書のほかに当事者から提出された出版契約書は, いずれも原告の部長職以上の者によって締結されている。〔甲19,3 2,乙34〕 (3) 上記(2)の認定事実によれば,Fは,当初,被告に対し,正式に社印を押 した契約書を作成する意向を伝えた際には,原告の実際の運用に従って社 会部長等の了解を得ることを考えていたとみる余地があるとしても,その 後,実際に,直属の上司である社会部長やその他の上司の了解をとったり, 原告における法務部等の原書籍 1 及び2の著作権に関して所管する部門と 協議を行ったりといった行動をとった具体的な形跡は何ら認められない。 そうすると,本件出版契約書(乙2)や,Fの被告に宛てたメール(乙1) の存在をもって,原告がFに,本件出版契約の締結につき,原告を代理す る権限を授与したとは認めるに足りず,本件全証拠を精査しても,原告が Fに上記権限を授与したことを認めるに足りる証拠はないといわざるを得 ない。 したがって,本件出版契約が原告と被告との間で成立したことを認める ことはできない。 (4) 被告の主張について ア 被告は,Fは原告側の知的財産部から受けた指示に従って被告と折衝 していたから,原告がFに前記権限を授与したと認められるべきである 旨主張する。 しかし,前記(2)アのとおり,読売新聞グループ本社の知的財産部は, Lから申入れがあった事実をFに伝えるとともにLから受信したメール をFに転送したにすぎず,Lの申入れをFに伝達したにとどまるから, Fに被告と折衝するよう指示したと認めることはできない。 この点において確かに,FがLに対して送った電子メール(乙1)に は,「契約の手続きについては,若干,社内の著作権管理の部署に相談 しなければなりませんので,今しばらくお時間を頂きたいと思います。」 (平成23年2月2日。乙1の7),「契約の関係は,社内的な手続き はほぼメドがつきつつあります。」(同月8日。乙1の9),「社内の 調整が終えました…」(同月14日。乙1の10)等の記載があり,本 件出版契約書(乙2)に貼付された付箋には,「本社の法務部門と協議 の上」との記載がある。 しかし,Fが原告のどの部門の誰と,いつ,どのような協議をしてい たかについて,Fは上記メールの中で何ら具体的に示しておらず,本件 全証拠を精査してもかかる事実を具体的に示す客観的な証拠は提出され ていない。かえって,F自身が,原告の社内において協議を行ったこと や,原告の上司等の了承を得ていたことはない旨を陳述している(甲3 1)。 また,上記電子メール(乙1)をみても,FがLに送付した平成23 年2月14日付けの電子メール(乙1の10)には,「社内の調整が終 えました…。Cはすでに読売新聞を退社して,球団の取締役になってい るため,冒頭の『著作代表者』については,社員である『F』とさせて 下さい。…了承いただけましたら,正式に『社印』を押印した契約書を 作成したいと思います。」と社内手続を遂げており,本件出版契約書に は社印が押印されるかのように記載されているが,平成23年4月27 日付けのメール(乙1の11)には,「…頂いた契約書がしばらくの間, 社内に放置されておりました。…もし今からでも可能であれば,契約書 を交わす社内的な手続きを進めたいと考えます。…」と従前のメールに 反して社内手続が進んでいない旨が記載されており,さらに被告に届い た本件出版契約書には,「F」との印影の個人名印が押印されていたも のである。 以上のとおり,Fは,被告に対し,社内の調整を終えたことを前提に して正式に社印を押した契約書を作成する意向を伝えていたにもかかわ らず,これに反して,実際には,契約書が社内に放置されていた事実を 明らかにした後に個人名印の押印をした本件出版契約書を被告に送付し ているのであって,かかる経過は,原告の社内において,編集局長ない しは社会部長の了解がとられ,Fに対して,原告のために本件出版契約 を締結する権限が与えられていたこととは相容れない事実というべきで ある。 また,確かに,本件出版契約書に貼付された付箋には「本社の法務部 門と協議の上,私個人の捺印と致しました。…」と記載されていたが, 上記経過に照らすと,Fは,当初こそ原告の実際の運用に従って社会部 長等の了解を得た上で「社印」を押印することを考えており,メールで はあたかも社内手続が進んでいるかのように説明したが,実際には,契 約書を社内に放置して,結局,編集局長ないしは社会部長の了解を得る 手続をとっていなかったために,上記の付箋を付した上,個人名印を押 したものと推認される。そうすると,上記付箋の存在によっても原告が Fに上記代理権限を授与したことを基礎付ける事実と認めるのは相当で はない。 イ 被告は,Fが,印税の振込先として原告の当座預金口座を指定したこ とは,前記知的財産部の具体的な指示によるものであるとして,代理権 限授与の事実を基礎付けるものである旨主張する。 しかし,この点に関しては,Fが,原告の経理局に対し,一般論とし て社外の出版社と出版契約を締結するときの印税の振込先の指定につい て尋ねたと供述しているのであって,本件全証拠を精査しても,前記知 的財産部がFに指示したことを窺わせる事情は認められない。また,本 件は,Fが,印税の振込先として,原告の当座預金口座を指定したもの の(2011年(平成23年)2月14日付けの電子メール。乙1の1 0),その後に,当初の連絡に反して個人名印の押印がされた本件出版 契約書が被告に送付されるという,原告がFに原告のために本件出版契 約を締結する権限が与えられていたこととは相容れない事実とみるべき 経過をたどっており,Fが印税の振込先を指定した事実は,代理権限授 与の事実を基礎付けるものとはいえない。 以上によれば,被告の上記主張は採用することができない。 ウ 被告は,本件で提出された契約締結例(甲32の1,乙34の2,4, 5)につき,個人が,原告(著作権者)欄に記名又は署名した上で,個 人印を押捺していることを指摘し,本件出版契約書にFの個人名印が押 印されていても,Fが契約締結の代理権を付与されていたことと何ら矛 盾はない旨主張する。 確かに,上記契約締結例における契約書は,社印ではなく,個人名印 が押印されているものであるが,証拠(甲32の1,乙34の2,4, 5)によれば,代理人として記載されている個人はいずれも部長職以上 の者であり,本件就業規則により契約締結権限を有すると認められるか ら,社会部次長の役職にあって少なくとも部長職以上の了解を必要とす るFとは立場を異にするものである。そうすると,本件は,その点にお いて,上記契約締結例とは前提を異にする事案といわなければならない。 以上によれば,被告の上記主張は採用することができない。 (5) 表見代理の主張について ア 被告は,原告がFに被告との折衝を担当させたことから,上記代理権 限授与の表示があったとして,民法109条により,本件出版契約が原 告と被告との間において成立している旨主張する。 しかし,前記(4)アのとおり,知的財産部がFに被告との折衝に当たっ て何らかの指示をしたとみるべき事実は認められないから,上記代理権 限授与の表示があったということはできない。また,FがLと継続的に 連絡をとり続けたのは,契約書の検討はFを通じてやってもらう旨のC の指示によるものであり,その連絡の内容も,著作代表者や著作権者の 表示,印税の支払先の指定といった形式面にとどまっており,かえって, 本件出版契約における印税の割合を協議してこれを定めたのはCであっ て,本件出版契約における重要部分について折衝したのは,Fではなく Cであるということができる。 したがって,被告の上記主張は採用することができない。 イ また,被告は,原告がFに被告と折衝する代理権を授与していること から,それは本件出版契約締結の基本代理権を授与したものであるとし て,民法110条により,若しくは,原告がFに本件出版契約締結の代 理権限を授与したが契約締結以前に同代理権限が消滅したとして同法1 12条により,表見代理が成立する旨主張する。 しかし,そもそも,折衝する代理権とはいかなる法律行為についての 代理権をいうのか判然としないが,前記(4)アのとおり,知的財産部がF に被告との折衝に当たって何らかの指示をしたとみるべき事実は何ら認 められないから,原告がFに被告と折衝する代理権を授与したというこ とはできないし,その他,本件全証拠を精査しても,本件において,原 告から,Fに対して同交渉についての基本代理権が授与されたことを具 体的に認めるに足りる客観的証拠はない。 また,本件全証拠を精査しても,本件において原告からFに一度でも, 本件出版契約締結の代理権限が授与したと認めるに足りる証拠はない。 以上によれば,被告の上記主張はいずれも前提を欠き,採用すること ができない。 (6) 小括 よって,被告が本件書籍を製本して,これを発売等頒布した行為は原告 の有する著作権(複製権,譲渡権及び翻案権)を侵害する行為に該当する。 4 争点(4)(著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権等)侵害の有無)につ いて (1) 同一性保持権侵害について 前記第2,1(2),(5)及び証拠(甲3,乙1の4ないし7)によれば, 本件書籍は,その本文が原書籍1及び2のものと同一であり,さらに,原 書籍1の「あとがき」と原書籍2の「文庫化にあたっての付記」に,Cが 執筆した「本シリーズにあたってのあとがき」(本件あとがき)を追記し たものであり,加えて,本件あとがきは本件書籍の記述部分全285頁の うち,262頁から269頁まで8頁にわたる記述であること,さらにそ のうち7頁目において,6行にわたって,前記第2,1(5)記載の記述があ ることが認められる。 上記記述の内容は本件書籍の本文の内容とは全く関係のない,Cの読売 巨人軍における役職解任に関する記載であって,その記載内容からすれば 原告の意に反していることは明らかであり,また,本文と密接な関係を有 するあとがきという文章の性質に鑑みれば,これを本文と一体のものと考 えるべきであるから,このように,原書籍1及び2に本件あとがきを原告 に無断で追加した本件書籍を製本した被告の行為は,原告の意に反する原 書籍1及び2の改変に当たるというべきである。 したがって,上記被告の行為は原書籍1及び2について原告が保有する 同一性保持権の侵害行為に該当すると認めるのが相当である。 (2) 氏名表示権侵害について 著作権法19条1項によれば,著作者は,その著作物の原作品に,又は 著作物を利用するに当たって著作者名を表示するか否か,表示するとすれ ばいかなる著作者名を表示するかを決定することができると解されるとこ ろ,前記第2,1(2),(5)及び証拠(甲5,7,31,証人F)によれば, 原告は,原書籍 1 及び2の出版に当たり,その著作者名を「読売新聞社会 部」とすることに決定して表示したこと,ところが,本件書籍は,原書籍 1及び2の復刻版であるにもかかわらず,その著者名を原書籍 1 及び2の ように「読売新聞社会部」とはせず,「読売社会部C班」とするものであ ること,原告は,本件書籍の著者名を「読売社会部C班」とすることに強 く異議を述べていることが認められる。 かかる事情に鑑みると,著者名を「読売社会部C班」として本件書籍を 発売等頒布した被告の行為は,著作者である原告が決定した著作者名の表 示を原告の意に反して改変した上,これを公衆へ提供したものと認められ るから,被告の上記行為は,原書籍1及び2について原告が保有する氏名 表示権の侵害行為に該当すると認めるのが相当である。 (3) 名誉・声望権侵害について 原告は,被告が本件書籍を発売等頒布した行為は,被告がCに執筆させ た本件書籍の本件あとがきの内容が,原告を含む読売新聞グループの名誉 を毀損し,自らを正当化するC個人の一方的な主張を含んでおり,読売新 聞グループとCが対立関係にあり,かつその関係が広く報道されて世間も 耳目を集めるなかでは,原告が,Cの個人名を冠した著者名の表示や同人 の主張を本件書籍に掲載することを許したかのように一般に受け取られる ことになるから,原告の名誉又は声望を害する方法による原書籍1及び2 の利用行為に当たり,著作者人格権のみなし侵害行為(著作権法113条 6項)に該当すると主張する。 しかし,著作権法113条6項は,著作物を創作した著作者の創作意図 を外れた利用がされることによってその創作意図に疑いを抱かせたり,著 作物に表現されている芸術的価値を損なうような形で著作物が利用される ことにより,著作者の社会的名誉声望が害されるのを防ぐ趣旨であると認 められるから,同項の「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著 作物を利用する行為」とは,社会的に見て,著作者の創作意図や著作物の 芸術的価値を害するような著作物の利用行為をいうと解すべきであるとこ ろ,前記(1)で認定したとおり,本件あとがきには,Cが読売新聞グループ 本社代表取締役会長を名指しで批判する部分が含まれているものの,その 内容は,原書籍1及び2の著作物とは何ら関係のない事実に対する批判で あって,本件書籍は本文のほか,原書籍1及び2にそれぞれ付加されてい た「あとがき」及び「文庫化にあたっての付記」も忠実に再現しているこ とからしても,原書籍1及び2の著作者の創作意図や著作物の芸術的価値 を害するものではないから,被告が本件書籍を発売等頒布した行為は,原 告の名誉又は声望を害する方法による原書籍1及び2の利用行為には当た らないと認めるのが相当である。 よって,原告の上記主張は,理由がない。 (4) 著作者人格権の承継について 被告は,原告が会社分割に際して,読売新聞社から原書籍1及び2に係 る著作財産権を承継したとしても,その著作者人格権までも承継すること はあり得ないとして,原告について著作者人格権侵害が成立する余地はな い旨主張する。 しかし,著作者人格権の一身専属性(著作権法59条)は,会社等の法 人については,合併・分割を経ても同一性を失うことなく存続していると 評価できる場合には,当該法人は著作者たる地位を失わないと解するのが 相当であるところ,前記第2,1(1)ア及び証拠(甲16,17)によれ ば,読売新聞社は,読売新聞グループの再編に伴い,旧商法373条の新 設分割により,原告を新設分割会社として,読売新聞グループの持株会社 である読売新聞グループ本社と原告とに会社分割され,原告には,それま で読売新聞社が行っていた事業のうち,土地の賃貸に関する事業を除く全 ての事業が承継されており,また,グループ会社の株式と一部の土地,預 金を除くほとんど全ての資産が承継されていること,読売新聞グループ本 社は,原告を含む子会社の株式を保有し,その事業活動を支配・管理する ことを目的としており,読売新聞社が有していた著作権及び著作者人格権 は全て原告が承継して,それらを管理・行使するものとされていることが 認められる。以上によると,原告は,旧商法373条の新設分割による設 立会社であり,同法374条の10第1項により読売新聞社の権利義務を 承継しており,当該承継は,当該権利に関する読売新聞社の地位を承継す る包括承継と解される。 したがって,原告は,上記新設分割において,原書籍1及び2に関して, 読売新聞社との同一性を失うことなく存続しているのであって,原書籍 1 及び2に関する著作者人格権をも承継したものと認められるから,被告の 上記主張は採用することができない。 5 争点(5)(名誉権侵害の有無)について 原告は,被告が本件書籍の著者名を「読売社会部C班」と表示し,これを 発売等頒布しており,当該表示は一般読者をして,本件書籍は原告が著作し たものと認識させ,本件書籍の内容が事件関係者のプライバシーを侵害する ものであることから,一般読者は,原告が報道機関であるにもかかわらずプ ライバシーを侵害する書籍を著作する会社であるとの印象を持つことになり, そうすると,原告の社会的評価は著しく低下することになるのであって,被 告による本件書籍の発売等頒布は,原告の名誉を毀損するものであると主張 する。 この点,ある書籍の販売等の行為が他人の社会的評価を低下させるもので あるかどうかは,当該書籍に対する一般の読者の普通の注意と読み方を基準 として判断するのが相当と解される。 これを本件についてみると,本件あとがきを含めて本件書籍の記載を詳細 に検討しても,原告が本件利益供与及び接待汚職事件の事件関係者ら第三者 のプライバシーを侵害する書籍を出版する会社である旨を表現する記載は認 められない。確かに,本件書籍には,本件利益供与及び接待汚職事件で有罪 判決を受けた者の実名及び判決結果や,逮捕,起訴に至っていないにもかか わらず贈賄者として本件利益供与及び接待汚職事件に関与したとされる者の 実名及びその贈賄の概要が記載された部分が存在することが認められるが, 本件書籍は読売新聞社会部の取材結果を基にしたノンフィクション作品であ る原書籍1及び2を復刊したものであって,その復刊をした者は本件利益供 与及び接待汚職事件に関して報道した原告とは関係のない被告であることか ら,本件書籍に対する一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,上 記記載部分は,原告が主張するような第三者のプライバシーに対する原告の 姿勢を認識させるものということはできない。 したがって,被告による本件書籍の発売等頒布行為は,原告の社会的評価 を低下させ,原告の名誉を毀損するものであるとは認められないから,その 余の点について検討するまでもなく,原告の上記主張は理由がない。 6 差止めの必要性について 前記2ないし4のとおり,被告による本件書籍の出版に係る著作権(複製 権,譲渡権及び翻案権)侵害及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示 権)侵害の事実が認められるところ,証拠(甲11,22,23,28,3 8,乙13ないし18)及び弁論の全趣旨によれば,本件仮処分命令申立て を行った平成24年5月18日の当日午後5時頃から,原告が「七つ森書館 に対する販売禁止の仮処分申立てについて」と題した文書を取次店,書店に 配布して,本件仮処分命令申立ての結論が出るまで本件書籍を販売しないよ うに強く要請したにもかかわらず,本件書籍は,平成24年5月18日から, 都内の大手書店の一部店舗で販売が開始され,本件仮処分決定発令に至るま で一般の顧客に対して販売が継続されていたこと,その後,同販売は自粛さ れていることが認められるものの,発令後に発行された月刊「創」8月号に おいて,仮処分決定に対して「『意地でも売るぞという気持ち』(中里社長) だという。」と掲載されていて,被告代表者の本件書籍の発売等頒布に向け た並々ならぬ強い意欲が表明されていたことからすれば,上記販売の自粛は, 本件仮処分決定を受け,一時的に自粛しているにすぎないと推認される。 そうすると,本件の口頭弁論終結時において本件書籍の発売等頒布が再開 されるおそれがなお存在するというべきであるから,本件書籍の発売等頒布 に係る差止請求については,それを認める必要性があると認められる。 7 争点(6)(損害の有無及びその額)について (1) 被告による本件書籍の出版行為が,原告が保有する著作権(複製権,譲 渡権及び翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵 害行為に当たることは,前記2ないし4のとおりである。 そして,前記3(2)アないしオ認定の事実によれば,被告は原書籍1及び 2の復刊を企画し,原告のホームページを通じて,原告に,復刊の許諾に ついて申入れをしたこと,それを受けて当時原告の社会部次長であったF が被告の担当者であるLと折衝を始めたこと,Lは当時読売巨人軍の球団 代表であったCとも協議を持ったこと,Cは契約書の検討は,Fを通じて 原告でやってもらう予定である旨Lに伝えたこと,Fは,L宛てに「社内 の調整が終えましたので,以下のような形で契約書を交わさせていただけ れば,と考えています。」などと記載したメールを送っていたこと,その 後,Fは,本件出版契約書1通を郵送するに当たって,本件出版契約書に 「本社の法務部門と協議の上私個人の捺印と致しました。今後の手続きよ ろしくお願い致します。」と手書きで書いた付箋を貼付していたことなど の本件出版契約の契約締結交渉における一連の事実を考慮すると,原告に 帰責性がなく表見代理の成立を認めることはできないにしても,原告社内 の決裁権限に関する規定や運用を知り得ない被告が,当時読売巨人軍の球 団代表であったCから契約書の検討はFを通じて原告でやってもらう旨等 の連絡を受けたことと相まって,当時原告の社会部次長であったFに契約 を締結する権限があると信じて本件出版契約の締結手続を進めたとしても, その当時としては無理のないことであって,本件出版契約の効力が原告に 及ばない結果になったことは,無権限であるにもかかわらずそれを秘して 契約の締結手続を進めたFに主要な責任があると認められる。 しかしながら,前記3(2)カ,キの認定事実及び弁論の全趣旨によれば, その後,被告は,本件書籍の発売等頒布に先立ち,ゲラのチェックを進め るFから,「法務部に預けた」との連絡を受け,さらに,原告の法務部長 Pから,本件出版契約の有効性に疑義があると指摘され,仮に同契約が有 効であるとしても合意解除をしたい旨申入れを受けていたにもかかわらず, 原告からFへの本件出版契約の契約締結に係る代理権授与の有無について 何らの調査確認もせずに,一方的に本件書籍の発売等頒布に踏み切ったこ とが認められるから,その点において被告には過失があるものといわざる を得ない。 したがって,被告は,原告が保有する著作権(複製権,譲渡権及び翻案 権)並びに著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害行為によ り原告が被った損害を賠償すべき責任を負うというべきである。 (2) 被告による原告の著作権(複製権,譲渡権及び翻案権)侵害について 証拠(甲3,23)によれば,被告が平成24年5月18日以降におい て,本件書籍を2100円(消費税込み)で発売し,少なくとも2000 部を出版したことが認められる。そして,本件書籍が原書籍1及び2の復 刻版であることや,本件全証拠を精査しても印税が支払われたことを伺わ せる形跡がないこと等を鑑み,その利益率は,30%と認めるのが相当で ある。 したがって,原告が保有する著作権侵害に係る損害は,次のとおり,1 26万円となる。 2,100(円)×2,000(部)×30%=1,260,000(円) (3) 被告による原告の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害に ついて 前記4(1)のとおり,被告は,原書籍1及び2に本件書籍の内容とは関係 のない,Cの読売巨人軍における役職解任に関する記載が含まれた本件あ とがきを加え,著者名を無断で「読売社会部C班」に改変し,原告の意に 反して,上記役職解任を巡る読売新聞グループとCの対立関係が報道され るなかで本件書籍をあえて出版したこと,他方,改変行為自体は本件あと がきを追加したのみで,原書籍1及び2の本文には何ら改変行為を行って いないこと,「読売社会部C班」との表示は「C班」という原告とは別個 の主体を指すものとはいえないことなど,本件審理の経過,その他本件に 現れた一切の事情を総合考慮すれば,被告による著作者人格権(同一性保 持権及び氏名表示権)の侵害行為により原告が受けた精神的苦痛に対する 慰謝料は,30万円と認めるのが相当である。 (4) 弁護士費用 本件事案の内容やその難易,認容額等諸般の事情を総合考慮すると,被 告による侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当損害金は15万円 と認めるのが相当である。 8 争点(7)(本件著作物に関する被告の出版権の有無)について 前記3のとおり,本件出版契約はFの無権代理行為によるものとして無効 であり,表見代理が成立する余地もないから,被告には,本件著作物に関す る出版権が存在しないものと認められる。 9 結論 以上によれば,A事件について,原告の被告に対する請求は,本件書籍の 発売等頒布の差止め並びに損害賠償金171万円及びこれに対する平成24 年11月21日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求 める限度で理由があり,さらに,B事件について,原告と被告との間におい て本件著作物に関する出版権が被告に存在しないことを確認することについ て理由があるから,これらを認容することとし,その余は理由がないから棄 却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 東 海 林 保 裁判官 実 本 滋 裁判官 足 立 拓 人 (別紙) 出 版 物 目 録 題 名 「会長はなぜ自殺したか-金融腐敗=呪縛の検証」 著 者 読売社会部C班 発行所 被告(株式会社七つ森書館) (別紙) 著 作 物 目 録 原告と被告との間における2011年(平成23年)5月9日付け出版契約書記 載の下記の著作物 記 書 名 「会長はなぜ自殺したか-金融腐敗=呪縛の検証」 以上 |