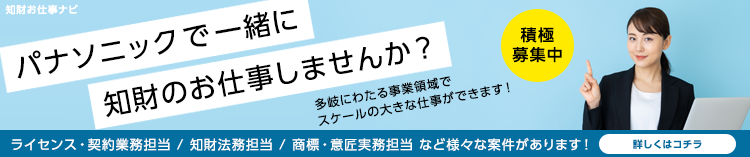| 関連ワード | 氏名表示権 / 複製権 / 引用 / 著作権侵害 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|
| 事件 |
平成
3年
(ネ)
835号
|
|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 1992/09/24 |
| 権利種別 | 著作権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
本件各控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
当事者の求めた裁判
一 控訴人(第一審原告)「一 原判決を取し消す。二 被控訴人株式会社中央公論社は、原判決添付別紙目録記載の書籍を出版、販売、頒布してはならない。三 被控訴人株式会社中央公論社は、発行済の右書籍を廃棄せよ。四 被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して金三〇〇〇万円及びこれに対する昭和五九年一一月一五日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。五 訴訟費用は、第一、二審共被控訴人らの負担とする。」との判決及び四、五項について仮執行の宣言二 被控訴人(第一審被告)ら主文と同旨の判決 |
|
|
当事者の主張
次に付加、訂正する他は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。 一 控訴人1 原判決六頁五行目「同月八日ころ、」を「同月四、五日ころ、」と訂正する。 2 原判決は、昭和五八年六月一三日及び同年七月二二日に、被控訴人【A】から同【B】に本件原書の完成した翻訳原稿(乙第二四号証、以下「【A】翻訳原稿」という。)が交付されたと認定するが、右認定は以下のとおり誤っている。 【A】翻訳原稿について、上智大学文学部教授【C】作成に係る意見書(甲第二〇号証)が「修正部分が少ないのみならず、その修正が僅かな語の削除・追加にとどまり、文の構造にまで及ぶことがありません。」と指摘するとおり、殆ど書き下ろした文章がそのまま生きている。このようなことは、少なくとも日常、文章を書く機会の多い者にとっては常識外のことであり、このことは、同教授の原稿を見ても明らかなところである。このことは、【A】翻訳原稿は、下書きに基づいて清書したものと考えられ、前記の日に【A】翻訳原稿が被控訴人【B】に交付され、これがそのまま入稿されたとする原判決の事実認定は誤っている。 次に、前記の【A】翻訳原稿の授受の日について原判決が認定に供した証拠には、以下のような疑問がある。すなわち、原判決は、乙第一五号証のレストラン「プルニエ」の領収証(七月二二日付け)、 同第一六号証の出金伝票の「6/13【A】氏」の記載をもって【A】翻訳原稿の授受の日を認定している。しかし、右乙第一五号証には「翻訳打合せ」、同第一六号証には「Leo Malet翻訳の件」としか記載されておらず、【A】翻訳原稿の受取りを証する記載はない。そして、このような記載は、【A】翻訳原稿完成前の作成であることを被控訴人らも自認している昭和五七年一〇月二一日付けの出金伝票(乙第九号証)、同五八年一月二四日付けの出金伝票(同第一〇号証)、同年四月四日付けの出金伝票(同第一三号証)などの記載と全く同一である。他方、 被控訴人【B】は、原稿受取りの際には出金伝票に「原稿受取り」と明示しており(同第一八号証)、そのほかにも著書を届ける場合は「お届け他の件」(同第一〇号証)、校正の時は「出張校正」(同第一三号証)、「著者校」(同第一四号証)、見本を渡す時は「見本お渡し」(同第一四号証)などと交通費の用途を出金伝票に具体的に記載しているのであり、こうした事実に照らせば、単に「翻訳打合せ」や「Leo Malet翻訳の件」としか記載されていない前記の伝票で【A】翻訳原稿の授受の日を認定することは誤りである。なお、【A】翻訳原稿の授受については、被控訴人【A】にとっては初めての翻訳の仕事であるにもかかわらず、被控訴人【A】は【A】翻訳原稿の授受の場所についてあいまいな記憶しか有していないことも、前記書証に基づく授受の日時の認定に対する不信を一層深めるものである。 3 原判決は、被控訴人らが昭和五九年一月に、控訴人作成に係る本件原書の翻訳原稿(以下「控訴人翻訳原稿」という。)に接する以前に【A】翻訳原稿はできていたから、【A】翻訳原稿は控訴人翻訳原稿に基づいて再製されたものではないと判断している。 しかし、仮に、右の時期以前に【A】翻訳原稿が完成していたとしても、控訴人が問題としているのは、被控訴人らが控訴人翻訳原稿を使用し、その訳語・訳文を冒用したことなのであるから、【A】翻訳原稿が完成していたとの事実は、何ら、 本件訳書が控訴人翻訳原稿に依拠して再製されたとの認定の妨げとなるものではない。 4 原判決が、 【A】翻訳原稿が控訴人翻訳原稿が届けられる前に完成していたとする認定判断の裏付けとする証拠は、以下のとおり、その裏付けとなるものではない。 (一) 昭和五七年一二月一〇日付け「エンジョイ・グラフティー」の記載について 被控訴人【A】による本件原書の一部の翻訳が右雑誌に掲載されていたとの事実は、その時点で被控訴人【A】が本件原書を読んでいたことを示すにすぎない。このような一部の翻訳文があったからといって、控訴人翻訳原稿が使用されなかったことの裏付けとなるものではない。確かに、右雑誌掲載の翻訳は控訴人翻訳原稿と異なる文体であるが、このことはこの部分については控訴人翻訳原稿を使用しなかったことを示すにすぎず、他の箇所において使用しなかったことまで示すものではない。 (二) 文体と語調の違いについて 【A】翻訳原稿と控訴人翻訳原稿とが文体・語調に大きな違いがあることは控訴人も認めるところであり、文章の骨格は原判決が認定するとおり、「全く別個に執筆されたものであると推認する」ことができよう。 むしろ、問題なのは、これほどにも文体・語調が異なる翻訳文の中に随所に全く同一の訳語・訳文が見られることにある。この点について原判決は、「複数の翻訳文が存在する場合、基にした原書が同一である限り、互いに他を複製したものでなくとも、内容や用語自体の多くが同一の表現となることは、むしろ当然ともいえるのであり、右の点に同一の部分があるからといって、それだけで直ちに両者のどちらかが他を複製したものと認めることはできない」としているが、かかる判旨自体、両翻訳原稿における文体・語調の相違を強調する前記の判断部分とそぐわないばかりか、文学書の翻訳のように訳文自体が訳者の解釈や思想を示すものとしての文学的価値を有する場合、たとえ基にする原書が同一であっても、訳語や訳文が大きく異なっているのが当然であり、現に本件の場合、控訴人翻訳原稿と【A】翻訳原稿では全体的にみると全く異なる文章となっているのである。原判決が示した前記の経験則は一般論としても間違っており、本件にも妥当しない。 これほど異なる文体や語調の違う翻訳文の中で、時として全く同一の訳語、訳文が不自然に挿入された場合、どちらかが他を冒用して複製したものと推認すべきなのである。 5 時間的制約について 原判決は、被控訴人【A】が控訴人翻訳原稿に接し得たのは昭和五九年一月二八日から翌月二〇日までであるとしている。しかし、控訴人翻訳原稿が被控訴人中央公論社に到達したのは同年一月四、五日頃であるから、被控訴人【A】が控訴人翻訳原稿をパリに携帯して行くことは十分に可能というべきである。してみると、被控訴人【A】が控訴人翻訳原稿を入手してから入稿するまでには約一箇月半の期間があったのであるから、この間に被控訴人【A】がこれを使用して自己の原稿を完成させて入稿することは、十分できたものであり、被控訴人【B】が虚言を用いて控訴人翻訳原稿を留め置いたのも右目的のためであり、原判決が疑問とする入稿を急がせた事情もいつまでも控訴人翻訳原稿を留め置くことができないためである。 6 控訴人主張の冒用を裏付ける主張に対する原判決の判断について 控訴人翻訳原稿を約二箇月にわたって留め置いた事実について 原判決は、この事実について何らの検討をしていないが、不当である。 被控訴人らの主張及び供述によれば、昭和五九年一月九日の被控訴人【B】から控訴人に対する電話で、本件原書については他の訳者による翻訳が完成しており、 控訴人翻訳原稿を被控訴人中央公論社から出版することはあり得ないと断言した上で、今後刊行するシリーズの訳者として採用する可能性があるので控訴人翻訳原稿を預からせて欲しい旨述べ、控訴人の了承を得たというのである。しかしながら、 被控訴人【B】からの控訴人翻訳原稿を返送してきた際に同封された手紙(甲第一五号証の一)において、「すでに組版にかかっておりますため、【D】様の御意向には残念ながら沿いかねる次第です。」と述べ、ここではじめて控訴人翻訳原稿を採用できないことを告げているのである。もし、前記一月九日の電話で控訴人翻訳原稿の不採用を断言していたのであるならば、かかる記述は不要である。また、 今後刊行するシリーズの訳者として採用しないというのなら、その旨を述べているはずである。 控訴人は、その日記の中で「どうなるかわからないが、私の原稿をぜひ検討したいというものだった」、「四冊以外は出版する予定はないとの事」(甲第一三号証)と記しており、また、被控訴人【B】の前記の電話の結果、【E】と接触して控訴人翻訳原稿が被控訴人中央公論社で採用されるよう有利な条件作りをしていることからすると、被控訴人【B】の前記供述は全く信用できないものである。被控訴人【B】は、虚言を用いて控訴人翻訳原稿を二箇月も留め置き、控訴人翻訳原稿を点検しようとしたものであり、原判決はこの点を全く看過しているものである。 7 被控訴人【A】が控訴人の訳語、訳文を使用したことは殊に、以下の事実からも明白である。原判決別表一一ー2に示したように、右【A】の翻訳に係る「シャンゼリゼは死体がいっぱい」と本件訳書の第一章、第七章及び第一三章を対比すると、同一単語及び文章が四五個出てくるが、右翻訳原稿では、控訴人翻訳原稿と同じ訳語、訳文を用いているのに対して、「シャンゼリゼは死体がいっぱい」では右翻訳原稿と異なる訳語・訳文を使用して誤訳している事実からも明らかである。 また、本件訳書では、主人公である私立探偵ネストール・ビュルマのしゃべり言葉の一人称は「俺」であるところ、前後では「俺」であるのに、訳文、訳語が極めて類似しているところでは、控訴人翻訳原稿と同様に「私」となっている箇所があり、「俺」と「私」の変遷は法則性もなく不自然に変遷している。一人の人物と話している最中に、自分のことを「俺」と言ったり「私」と言ったりするという翻訳上の不一致は、他人の訳文を使用しないと生じないものであり、被控訴人【A】が控訴人翻訳原稿を使用した事実を明白に物語っているのである。 二 被控訴人ら1 控訴人は、【C】教授作成に係る意見書(甲第二〇号証)を援用して、その主張の論拠とするが、同意見書は、「これが下書きなしの書き下ろし原稿であるとすれば」という仮定のもとに意見を述べているものであるから、 右仮定が事実であることの証明がなければ、右意見書は本件にとって証拠価値はない。ところで、被控訴人【A】は、本件原書の翻訳に当たり、訳文を一度別の用紙に下書きし、これを原稿用紙に清書するという原稿作成方法を採ったものであることは、同人の供述するところであるから、前記意見書の仮定する事実と前提を異にするものである。したがって、【C】教授作成に係る意見書は、本件において何らの証拠価値も有しない。 次に、控訴人は、【A】翻訳原稿の授受の日についての原判決の認定を非難するが、右非難も失当である。すなわち、原判決は、控訴人の非難する出金伝票のみにより右原稿授受の日を認定したものではないのみならず、右伝票の記載は右認定の資料とはなり得ても、何らその妨げとなるものではない。これらの伝票類は、その作成の経緯とその性格上、記載内容は簡略であり、その記載のみから、用件を判断することは困難である。なお、控訴人は、右原稿授受の日に関し、被控訴人【A】の記憶があいまいであると非難するが、日記をつける習慣のない被控訴人【A】が、四年余り経過した本件訴訟における尋問期日に、右原稿授受の日を思い出せなかったとしても、無理からぬことである。 2 控訴人は、控訴人翻訳原稿が被控訴人中央公論社に投稿される以前に【A】翻訳原稿が完成していたとしても、被控訴人らが控訴人翻訳原稿を使用し、その訳語、訳文を冒用して【A】翻訳原稿を作成又は修正して、本件出版に及んだものであると主張しているが、右主張も、以下に述べるように、失当である。 まず、控訴人は、両翻訳原稿相互間の訳語の一致を右主張の論拠とする。しかしながら、複数の翻訳文が存在する場合、原書が同一である限り、互いに他を真似したものでなくとも、内容や用語自体の多くが同一の表現となることは、むしろ当然で、控訴人が自己の独創的な訳であると主張する部分は、いずれも広く出版されている辞典に掲載されているか、あるいは控訴人以外の者でも訳出することが可能であり、特に、控訴人でなければ訳出することができないようなものではないことは、原判決の認定するとおりである。 なお、 控訴人が主張するいわゆる独創的な訳語、短文節の訳文自体は、著作物ではないから、著作権法の保護を受けるものでないことは、原審で主張したとおりであり、これを使用する場合にも、控訴人の承諾を必要とするものではない。 3 本件訳書と控訴人翻訳原稿とが文体、語調に大きな違いがあることは控訴人も認めるところであり、文章の骨格が原判決が認定するとおり、「全く別個に執筆されたものであると推認する」ことができるとする点についても控訴人はこれを認めている。 控訴人は、これ程異なる文体や語調の違う翻訳文の中で時として全く同一の訳語、訳文が不自然に挿入されている場合、どちらかが他を冒用して複製したものと推認すべきである旨主張するが、原書が同じであるため、本件訳書に、控訴人翻訳原稿と同一の訳語、訳文が当然の一致又は偶然の暗合として存在することはあっても、それが不自然に挿入されている箇所はない。 4 被控訴人中央公論社は、昭和五九年一月五日、控訴人翻訳原稿を受領し、同月六日、七日の休日明けの同月九日に、控訴人翻訳原稿は被控訴人【B】に届けられた。控訴人翻訳原稿を受領した被控訴人【B】は、右時点においては、控訴人翻訳原稿の優劣は不明であり、その採否を決することはできないことから、右原稿を預かり検討することとし、その後、被控訴人【A】が帰国した同月二八日の前後ころまでには、右翻訳原稿を閲読して、検討したところ、文体が不適当であり、かつ、 固い訳であったため、ハードボイルドの類の小説には向かないと判断した。 一方、被控訴人【A】は、同九日、パリへ向けて成田空港から出国し、同月二八日に帰国しているのである。 したがって、被控訴人【A】が、控訴人翻訳原稿を見る機会はなかったし、被控訴人【B】においても、控訴人翻訳原稿を被控訴人【A】に見せる必要はなかったものであるから、控訴人の主張は失当である。 5 控訴人は、本件訳書においては、主人公であるネストール・ビュルマ等の自称代名詞の訳に不一致があるとし、かかる不一致は、控訴人翻訳原稿の訳を使用したことの現れであると主張する。しかし、被控訴人【A】は、人称代名詞の訳語を、 時と場合に応じて言葉使いを変えて訳す手法を用いているのであり、控訴人指摘の不一致があったとしても、何ら不自然ではない。これをネストール・ビュルマの自称代名詞の訳についてみると、原則として「俺」、時に「私」と訳しているもので、ビュルマは、自分と対等かそれ以下の相手には決して「私」とは言っていないのである。相手や時と場合もかまわず最初から終わりまで私立探偵ビュルマの自称代名詞を「私」で通すことの方がぎこちなく不自然であり、控訴人の主張は失当である。 |
|
|
証拠(省略)
理 由一 原判決一八頁八行目から同一九頁二行目までを引用する。 二 原判決一九頁三行目から同三二頁二行目までを、次のとおり付加、変更して引用する。 原判決一九頁六行目「1」の次に、「原審における控訴人本人尋問の結果により成立の認められる甲第五号証、同第一二、一三号証及び同第一四号証の一並びに右本人尋問の結果、」を、同六行目「各本人尋問の結果」の次に、「(いずれも一部)」をそれぞれ付加し、同頁七行目「乙第八ないし第一九号証」を「乙第八ないし第一四、第一七ないし第一九」と訂正し、同頁九行目「甲第一四号証の二」の次に、「同第一五号証の一ないし三」を、同九行目「乙第二〇号証」の「乙第」の次に、「一号証、同第」を、右「二〇号証」の次に、「及び同第二二号証並びに弁論の全趣旨により成立の認められる乙第六、七号証及び同第三八号証」を、それぞれ付加し、原判決二一頁三行目「(7)被告【A】は、」から三二頁二行目までを次のとおり訂正する。 「(7)被控訴人中央公論社は、【E】の「新編パリの秘密」シリーズの著作権を有していたフランスのフルーブ・ノワール社の役員が昭和五八年四月に来日した際、当時、翻訳刊行を計画していた右シリーズ中の四編、すなわち、本件原書であるLA NUIT DE SAINT-GERMAN-DESPR●S(翻訳書題名「サンジェルマン殺人狂騒曲」)のほか、CORRIDA AUX CHAMPS-●LYS●ES(同「シャンゼリゼは死体がいっぱい」)、 M’AS-TU VU EN CADAVERE?(同「殺意の運河サンマルタン」)及びLEX EAUX TROUBLES DE JAVEL(同「ミラボー橋に消えた男」)の我が国における翻訳出版問題について右役員と協議を開始し、結局、昭和五九年六月、右四編について、フルーブ・ノワール社との間で翻訳出版についての合意が成立した、(8)被控訴人【A】は、昭和五八年四月ころから本件原書の本格的な訳出作業に入り、同五八年一一月頃までには翻訳原稿を完成し、これを被控訴人【B】に交付した(なお、原審における右被控訴人両名の本人尋問の結果中には、昭和五八年六月一三日及び同年七月二二日の二回にわたり、被控訴人【A】が翻訳原稿を同【B】に手渡ししたとの供述が存し、成立に争いのない乙第一五、一六号証によれば、右両日に右被控訴人らが本件原書の翻訳に関連して会合している事実までは認められる。しかし、右各乙号証にはそれ以上の事実関係を明らかにするに足る記載はなく、その上、この点に関する右被控訴人両名の供述は具体性に欠けて不明確であり、他に右各機会に被控訴人【A】がその翻訳原稿を同【B】に交付した事実を的確に裏付けるに足りる証拠もないから、前記両日に被控訴人【A】の翻訳原稿が同【B】に交付されたとまで認定することは困難であるといわざるを得ない。)、(9)そして、被控訴人中央公論社は、Cノベルズの判形を新書判から文庫判に変更することとし、同年一一月ころまでに、右の【E】のシリーズを文庫判によって翌五九年五月に発行することに決定し、そのころ、被控訴人【B】は、被控訴人【A】に対しその旨通知した。(10)控訴人は、昭和五九年一月三日、控訴人翻訳原稿に自己の略歴及び原著者【E】の紹介文並びに被控訴人中央公論社の海外室長である【F】とパリ等で面識があることを追記した文を添え、書留郵便に付して同社宛発送し、控訴人翻訳原稿は同月九日、被控訴人【B】に右海外室の者を通じて届けられた(右九日に、控訴人翻訳原稿が被控訴人【B】のもとに届けられた事実は、被控訴人らの認めるところである。)、(11)控訴人翻訳原稿を受領した被控訴人【B】は、"同日の午後の早い時間に、同日夜の飛行機でフランスに出発する予定になっていた被控訴人【A】に、右翻訳原稿受領の事実を電話連絡する一方、同日午後六時すぎ、控訴人に対し、電話により、要旨、被控訴人中央公論社では、本件原書を含む【E】の作品四冊(前記(7)に説示した四冊)について翻訳刊行の計画が進行中であり、既に三冊の翻訳が終了していること、右四冊以外については、当面刊行の予定がないこと、控訴人翻訳原稿については、検討の上、採否を決める予定であるから、控訴人翻訳原稿を預からせてほしいこと、控訴人翻訳原稿については、著作権法上の障害がないことから、他社からの出版も可能であるが、他社から刊行しないで欲しいことなどを申し入れ、後日、必ず連絡を取る旨を約した。控訴人は、右申入れに対し、【E】についての自己の見解を披瀝するとともに、前記の他社から刊行しない旨の要望を受け入れることを約した(なお、被控訴人【B】は、原審における本人尋問において、控訴人に対する右電話連絡の内容について、既に本件原書の翻訳は完成しているから、被控訴人中央公論社からは控訴人翻訳原稿は刊行できない、と言明した上、被控訴人中央公論社において、前記四作以外の【E】の作品を将来刊行する場合の訳者に控訴人が相応しいか否かを判断する資料として控訴人翻訳原稿を検討したいから預からせて欲しい旨告げたと供述するところであるが、被控訴人中央公論社が前記四冊以外の【E】の作品について将来において翻訳刊行の具体的計画を有していたことを認めるに足りる証拠がない上、後記の(12)、(14)に認定の事実に照らすと、右供述は採用し難いものといわざるを得ない。)、(12)自己の翻訳原稿の採用につき不安を覚えた控訴人は、右採用の一助とするべく、本件原書及び他一点についての翻訳の承認を求める内容の手紙を昭和五九年一月一八日付けで原著者【E】に対して出したところ、【E】から、同年二月一四日付けで、全作品の著作権を出版社のフルーブ・ノワール社に譲渡済みであるから、同社に連絡を取るようにとの連絡を受けた。そこで、控訴人は、"同月二〇日付けで、フルーブ・ノワール社に対し、前記二作品の翻訳の承認を希望する旨の申入れを行った、(13)本件訳書は、昭和五九年二月二〇日及び同月二八日、二九日に、原稿が被控訴人中央公論社から三晃印刷に持ち込まれて、印刷に付され、同年五月一〇日に発行された、(14)被控訴人【B】は、昭和五九年三月八日、控訴人に対し、所持していた控訴人翻訳原稿に、「先日お電話で申し上げましたように、この五月より毎月一点ずつ、とりあえずは四点の刊行を予定しており、すでに組版にかかっておりますため、【D】様の御意向には残念ながら沿いかねる次第です。また、五作目以降については、現在まったくの白紙で、いずれ四点の結果を見てから、ということにしております。」と記載した文書を添えて返送し、控訴人は、同月一〇日、これを受領した(なお、右添書にいう「先日のお電話」が、前記(11)に認定の被控訴人【B】から控訴人に対する電話を指すものであることは、右両名の前記各本人尋問の結果から疑問の余地がなく、そして、右電話の時点においては、本件訳書の組版がいまだ開始していないことは前記(13)に認定のとおりであることからすると、前記添書の中心となる点は、控訴人翻訳原稿は、既に他の翻訳原稿で印刷に取り掛かっているから、採用できない、とする点にあると解するのが相当というべきであり、この点からも、被控訴人【B】が、前記の電話において、控訴人翻訳原稿それ自体の採否の検討を約したものと推認して差し支えないものというべきである。)、以上の事実が認められ、原審における被控訴人【B】及び同【A】の各本人尋問の結果中右認定に反する部分は、前掲各証拠に照らしてにわかに採用し難い。 以上の事実によれば、被控訴人【B】は、被控訴人中央公論社においては、控訴人翻訳原稿を受領した時点において、既に、被控訴人【A】の翻訳により本件原書の翻訳本を出版することが確定しており、控訴人翻訳原稿を採用する余地がなかったにもかかわらず、なお採用の余地があるかのような言動により、採否を検討すると称して、控訴人翻訳原稿を昭和五九年一月九日から同年三月八日までの約二箇月間、 自己の手元に留め置いたものと認めざるを得ない。 2 そこで、控訴人が控訴人翻訳原稿と本件訳書の表現とが類似し、右部分は控訴人翻訳原稿の訳語、訳文を被控訴人【A】及び同【B】において盗用したものであると主張する点について、以下、検討する。 (一) 原判決添付別表三ないし八の各記載のうち、各欄記載の本件原書中の合計二二五箇所の語句ないし文に対応する控訴人翻訳原稿及び本件訳書における各訳文が同表各欄記載のとおりであることは前掲甲第二号証及び同乙第一号証により認めることができる。 この事実によれば、別表三ないし八に記載された合計二二五箇所の本件原書中の語句ないし文に対する控訴人翻訳原稿における訳文と本件訳書の訳文は、表現形式及び内容のいずれにおいても、全く同一ないしは極めて近似しているものということができる。 (二) 成立に争いのない乙第三号証及び原審における被控訴人【A】の本人尋問の結果によれば、被控訴人【A】は、本件原書の著者である【E】のCORRIDA AUX CHAMPS-●LYS●ES(翻訳書の題名は、「シャンゼリゼは死体がいっぱい」)を翻訳している事実が認められるところであり、そして、原判決別表一一-1及び2によれば、CORRIDA AUX CHAMPS-●LYS●ESにおける右別表の各欄記載の各語句ないし文に対応する「シャンゼリゼは死体がいっぱい」における訳文が同表各欄記載のとおりであることは、被控訴人らにおいて認めるところである。一方、本件原書における右各語句、文と同一の語句、文又はこれを含む語句、文に対する控訴人翻訳原稿の訳文が「本件の作品」欄中の「原告の翻訳原稿」欄記載のとおりであることは弁論の全趣旨により認められ、また、これに対応する本件訳書の訳文が「被告【A】の翻訳書」欄記載のとおりであることは、被控訴人らにおいて認めるところである。 この事実によれば、控訴人翻訳原稿と本件訳書における各訳文は、別表一一-1及び2で採り上げられた合計三四二箇所において、表現形式ないしは表現内容において全く同一ないし極めて近似しているのに対し、これと同一の語句、 文又はこれを含む語句、文に対応する「シャンゼリゼは死体がいっぱい」における被控訴人【A】の訳文は、表現形式のみならず、意味内容においても相当異なるものであることが認められる。 (三) 原審における控訴人本人尋問の結果により成立の認められる甲第二〇号証(【C】教授作成に係る意見書)によれば、同教授の【A】翻訳原稿(乙第二四号証)に対する見解の要旨は、【A】翻訳原稿は、修正部分が僅かな語の削除、追加に止まり、文の構造にまで及ぶことのないほぼ完全な原稿であるとし、同教授自身の翻訳経験に照らし、右原稿が下書きなしの書き下し原稿であるとする点に対し、 婉曲な表現を用いながら疑念を呈している点にあるものと理解することができる。 そこで、【A】翻訳原稿についてみるに、前掲乙第二四号証によれば、右原稿における修正は、語句の修正、削除がほとんどで、文章の基本的構造に及ぶものはないことが認められるから、この点を指摘する前記意見書は正当というべきである。ところで、被控訴人らは、被控訴人【A】の翻訳原稿作成の方法について、当初、 「被告【A】は、翻訳に際しては、原著を読み、これを日本語に転換して思考し、 そのままこれを原稿用紙に書き下すのを常とし(このようにして作成されたものが、乙第二四号証である)、それ以前に草稿・下書き又はこれに類するものは、一切作成していない。」(被控訴人らの原審における昭和六一年三月一二日付け準備書面二枚目表四行目から八行目)と主張したことから、右主張における被控訴人【A】の翻訳原稿の作成方法を前提とした上で、前記意見書が作成されたものであることは、原審における控訴人本人尋問の結果から認められるところであり、これが甲第二〇号証として、昭和六二年六月一〇日の原審第一六回口頭弁論期日に提出されたことは記録上明らかである。これに対して、被控訴人【A】は、昭和六二年九月二一日に行われた本人尋問においては、翻訳原稿の作成は、「いらなくなった原稿用紙、あとメモ用紙などを右に置きまして、それであるフレーズまでを直訳または訳してみて、それから、検討した結果を要するに原稿用紙に書いていくというやり方です。 」と述べ、「下書き原稿というようなものは、ないわけですか。」との問いに対し「ありません。」と供述しているところである。そうすると、右供述からすると、 前記意見書はその前提とする翻訳原稿の作成方法を異にする面があることは否定し得ないが、それにしても、下書き原稿を作らないという点においてはなお前記意見書の前提と合致する面を有しているのであるから、【A】翻訳原稿に対する前記意見書の見解はなお傾聴すべき価値を有するものというべきであり、右意見書には証拠価値がないとする被控訴人らの主張は採用できない。 (四) 以上に認定の(一)ないし(三)の事実に、前項に認定の、被控訴人【B】における控訴人翻訳原稿の二箇月間に及ぶ留め置きの事実を勘案すると、被控訴人【B】及び同【A】において、本件訳書の出版に至る過程において、控訴人翻訳原稿を参照しながら、既に完成していた被控訴人【A】の翻訳原稿に部分的改変を加え、本件訳書を完成した事実を推認するのが相当というべきである。 (五) 被控訴人らは、被控訴人【A】は、控訴人翻訳原稿が被控訴人【B】に届いた日に、パリへ向けて成田空港から出国し、昭和五九年一月二八日に帰国しているから控訴人翻訳原稿を見る機会はなかったし、被控訴人【B】においても、右原稿を被控訴人【A】に見せる必要はなかったと主張する。 確かに、被控訴人【A】が控訴人翻訳原稿が被控訴人【B】に届いた昭和五九年一月九日に成田空港からフランスに向けて出国した事実は既に認定したとおりであり、前掲乙第二二号証によれば、同人が同月二八日に帰国した事実が認められるところである。しかしながら、かかる出国の事実があるからといって、被控訴人【B】が同【A】に対し、しかるべき時期に控訴人翻訳原稿ないしはその写しを渡すことの妨げとなるものでないことはいうまでもないことであるし、現に、既に認定したように、被控訴人【B】は、控訴人翻訳原稿を入手するや直ちに、フランスへ向けて出国する直前の被控訴人【A】に右事実を連絡しているのである。したがって、被控訴人らの右主張は採用できない。 次に、被控訴人らは、 本件訳書と控訴人翻訳原稿とが文体・語調に大きな違いがあることは控訴人も認めるところであり、また、原書が同じである以上、本件訳書に、控訴人翻訳原稿と同一の訳語、訳文が当然の一致又は偶然の暗合として存在することはあっても、それが不自然に挿入されている箇所はないと主張する。 前記控訴人本人尋問の結果及び同被控訴人【A】本人尋問の結果によれば、控訴人の本件原書に対する翻訳上の基本的態度は、原文どおり忠実に訳出することを絶対の原則とする結果、原文に対する付加、削除はもとより、長文を短文に分けたり、逆に、短文を長文にまとめることを厳格に避けるとの観点から訳出していることが認められる。これに対し、被控訴人【A】においては、読者に原書の雰囲気がより良く理解が得られるように訳出すべきであるとの観点から、必要に応じて原書にない言葉を補い、また、原文の逐語訳に陥らず、ハードボイルド小説に相応しいように、短文を長文にまとめたり、逆に長文を短文に分けることも許されるべきであるとの観点から訳出していることが認められる。右両者の翻訳に対するかかる基本的態度の相違に起因して、控訴人翻訳原稿と本件訳書が文体、語調において顕著な差異を有することは、両者を読み比べれば、一見して明らかであり、この点は、 控訴人においても認めるところである。 しかしながら、かかる文体、語調の差異が存在するとしても、既に完成していた被控訴人【A】の翻訳原稿に部分的改変を加えることの障害となるものでないことは明らかであるから、何ら前項の推認を妨げるものではない。 また、原書が同一である場合には、同一訳語となることは何ら不思議なことではなく、本件訳書においても不自然な点はないとの点についてみると、確かに、一般論としては、同一原書を翻訳した場合、同一訳語が生ずることは十分予想し得るところであるが、既に、これまで、本件訳書に即して具体的に検討したところによれば、本件訳書と控訴人翻訳原稿の前記一致箇所が、当然の一致又は偶然の暗合として理解することは困難といわざるを得ず、したがって、この点に関する被控訴人らの主張も採用できない。 被控訴人らは、控訴人が「原告の独創的な訳語を使用した例」として主張する原判決添付別表三ないし五記載の各訳語、訳文(合計五〇例)につき、各種の仏和辞典等(クラウン仏和辞典・乙第二六号証、スタンダード仏和辞典・同第二七号証、 仏和大辞典・同第二九号証、新仏和中辞典・同第三二号証、フランス俗語辞・同第三〇号証典、スタンダード和仏辞典・同第三三号証等及び各種国語辞典)を援用して、これら各種辞典の記載から訳出可能である旨主張するところである。確かに、 これらの各種辞典には、原判決添付別紙二ないし四(「独創的表現との原告主張に対する被告らの見解」)に記載の各表現が記載されていることが認められるところである。そして、右記載の表現中には、控訴人が独創的であると主張する訳語と殆ど同一あるいはこれに近似する表現が存することが認められるところである(例えば、別紙二、①「immacul●e」控訴人訳の「しみ一つない」に対し、「汚点ひとつない」、同⑧「Alorsnous sommes quittes.」同「それじゃ、私たちはおあいこですよ。」に対し「これでおあいこだ」、別紙三⑬「Exactement」共に「そのとおりさ」等)。しかしながら、そもそも、原語を同一とする以上、各種辞典を調査すれば、そこに類似した表現の記載がみられることはむしろ当然のことというべきであるし、翻訳の適否は、前後の文脈との関係において、当該語句に対応する日本語としていかなる表現が最も適切であるか否かの問題であるから、各種の辞典類に類似した表現が記載されているというだけでは、直ちに、右辞典類の表現が当該語句の訳語として適切であることを意味するものということはできない。そうすると、被控訴人らの指摘は、前記控訴人の採用した訳語への到達の一つの可能性を指摘しているに止まるにすぎないといわざるを得ない。しかも、前記別紙二ないし四の記載自体から明らかなように、各種の辞典の記載に基づき更に推敲を重ねなければ、控訴人の訳語に到達しないものも相当程度存在することは明らかであるから、これらの点を考慮すると、"前記の別表三ないし五の合計五〇例の訳語の表現形式が、控訴人翻訳原稿と本件訳書とにおいて殆ど一致しているという事実を軽視することはできず、これに前項に説示した諸事情を勘案すると、前記の各種辞典類の記載をもって、前項の推認を左右することはできず、被控訴人らの前記主張は直ちに採用し難いものといわざるを得ない。 最後に、被控訴人【A】が、本件原書の翻訳の一部を事前に公表していたとの点について検討しておくと、原審における被控訴人【A】本人尋問の結果により成立の認められる乙第五号証によれば、被控訴人【A】は、雑誌「エンジョイ・グラフィティー」の昭和五七年一二月号に「ミステリー界の復古調の気分」と題するフランスミステリー界の状況を紹介する文章を執筆し、その中で【E】の本件原書を「サンジェルマン・デ・プレの夜」として採り上げ、その一節を「〈エショデ通り〉は、ある親愛なる呑んべえ、アルフレッド・ジャリが、脳味噌の洗濯に足しげく通った、彼を車に例えるなら、さしずめ、ガソリンスタンドという按配の飲み屋があったところだ。」と翻訳掲載している事実が認められるところである。そして、前掲乙第一号証及び同第二四号証によれば、右部分は、本件訳書及び被控訴人【A】翻訳原稿においては「あの親愛なる呑んべえ、アルフレッド・ジャリが、脳味噌の洗濯に足しげく通った、彼を車に例えるならさしずめガソリンスタンドという按配の飲み屋があった路地である。」であることが認められ、これによれば、右部分は前記雑誌に公表された翻訳文と殆ど同一ということができる。これに対し、 右部分を控訴人翻訳原稿でみると、前掲甲第二号証によれば、「両角で屁をひりあっている二つのビストロの間のアルフレッド・ジャリ(一九世紀のフランスの詩人。放蕩癖があった。)のお気に入りでその精を抜くサービス・ステーションのあった細いレショデ通りが、涼しさと静けさのオアシスのように思われた。」であることが認められ、この両者を対比すると、右部分の表現形式が顕著に相違すること、及び、被控訴人【A】が、 雑誌に公表した翻訳を殆どそのまま本件訳書においても採用した事実が認められるところであるが、前記の雑誌公表部分は本件原書の全体からみると極めて僅かな一節である上、既に一般に公表した部分について他人の訳文を無断使用することは通常考え難いことを考慮すると、かかる事実は、何ら前記の推認の妨げとなるものではないというべきである。 四 ところで、控訴人は控訴人翻訳原稿に用いられている個々の訳語の無断使用について著作権侵害を主張しているものではなく、右無断使用により翻訳原稿全体についての著作権侵害、すなわち複製権及び氏名表示権が侵害された旨主張するので、以上の認定判断を前提として、右主張について、以下判断する。 1 まず、複製権の侵害の点についてみるに、著作物の複製とは、「既存の著作物に依拠し、その内容及び形体を覚知させるに足りるものを再製することをいう」ものと解される(最高裁昭和五三年九月七日第一小法廷判決、民集三二巻六号一一四五頁)から、右見地から、以下検討する。 本件訳書が控訴人翻訳原稿に部分的に依拠しているものと推認し得ることは、既に前項に認定判断したとおりであるから、進んで、本件訳書が、控訴人翻訳原稿の全体についてその内容及び形体を覚知させるに足りるものか否かについて、以下、 両者の翻訳文に即して検討することとする。 本件原書の翻訳上の基本的態度が、控訴人においては、原文に絶対的に忠実であることを最も重視するのに対し、被控訴人【A】のそれが、読者の理解を第一とする結果、原文からの拘束を極めて緩やかに解することは、既に前項に認定したとおりであり、かかる翻訳上の基本的態度の相違に基づき、控訴人翻訳原稿においては、原文に付加、削除を加えず、かつ、原文の表現形式を尊重する結果、原文が長文であれば、訳文も長文となる傾向を有するのに対し、本件訳書においては、本件原書をハードボイルド小説と捉え、読者の理解の得られ易さを第一とする結果、原文に対する付加、削除を必要に応じて行うとともに原文の長文も短文に分解して翻訳する傾向を有するなど、両者は、その基本的構造、語調、 語感を大きく異にすることは、控訴人翻訳原稿と本件訳書を読み比べれば、一見して明らかであり、この点は、控訴人においても認めるところである。 これを具体的にみてみると、例えば、控訴人が控訴人翻訳原稿における控訴人の訳語を使用したとする別表三の1及び2の「しみ一つない」及び「興じていた」についてみるに、右部分は、前掲乙第一号証の本件訳書においては、「カウンターでは、染みひとつない上着に身を包み、礼儀正しく非の打ちどころのないバーテン、 ルイが、山羊髭の客とダイスに興じていた。甘い音楽の調べがラジオから流れている。だがそのラジオは目につく場所には置かれていなかった。」との訳文であり、 三文に訳出されているのに対し、控訴人翻訳原稿の前掲第二号証における該当部分は、「バーの方では、しみ一つないぱりっとした上衣を一部のすきもなくぴしっときめたバーテンのルイが、どこかにあるのかラジオから流れ出るムード音楽を伴奏に、客の髭男とサイコロ勝負に興じていた。」との訳文であり、一文に訳出されていることが認められるところ、成立に争いのない甲第一号証によれば、右翻訳部分に対応する原文は一文により表現されていることが認められる。のみならず、右の二つの訳文を読み比べれば、同じ原文の訳文でありながら両者の語調、語感等の相違から文章全体から受ける印象は異なるものがあり、被控訴人【A】の訳文が控訴人の訳文に依拠したものと認められないことは明らかであるし、丹念に対比しない限り、一読しただけでは、控訴人が盗用と主張している「しみひとつない」との同じ訳語が右各翻訳文において使用されていることすら気付かないまま読み過ごされてしまうものといっても過言ではない。また、本件原書第一章冒頭に近い文章を対比してみると、控訴人翻訳原稿においては、「私は大通りの教会側へ出て、国際色ゆたかな散歩者たちのかしましい人波をかきわけて行った。彼らは、安青銅のベルナール・パリシイ(一六世紀の陶芸家、うわ薬の合成に成功す。)が台座の上で倦まず弛まずさし出している歴史的な皿には目もくれず、小公園の鉄柵にそった広い歩道をねり歩いていた。 」(甲第二号証五丁裏三行目から九行目)と二文で訳出されているのに対し、本件訳書のこれに対応する部分は、「私は、教会が影を落としている大通りに出た。幅広い歩道が小さな広場の鉄柵に沿って拡がっている。いろいろなところから集まってきた連中が、波打つように行ったり来たりしていた。賑やかだ。そんな人込みを掻き分け私は歩いていた。陶芸家ベルナール・パリシイのブロンズ像の台座の上から、歴史上意義あるものとされている勲章を、どうだい、とばかりにひけらかしている。まるで露天商人みたいだった。だが、目をくれる奴はひとりもいやしない。」(乙第一号証七頁本文七行目から一二行目)と八文で訳出されている。そして、二つの訳文を読み比べてみた場合、その文章全体から受ける印象の相違により、被控訴人【A】の訳文が控訴人の訳文に依拠したものと認められないことが明らかであることは、前記訳文の対比と変わるところはない。 以上のように、控訴人翻訳原稿と被控訴人【A】の本件訳書とは、右両者の翻訳に対する基本的態度の根本的な相違を反映して、訳文の基本的構造、語調、語感を大きく異にしているものであり、かかる相違は、その基本的性格の故に、控訴人翻訳原稿に依拠したと推認される部分的訳語、訳文の存在を考慮しても、これによって何らの影響を受けるものではないことは、前記具体例の対比をみれば明らかというべきである。 してみると、本件訳書には、個々の訳語、訳文において、控訴人翻訳原稿に依拠したと推認するのが相当な部分があるとしても、訳書全体を対比するならば、右の依拠した部分は、両訳文間の基本的構造、語調、語感における大きな相違に埋没してしまう結果、本件訳書が控訴人翻訳原稿を全体として、内容及び形体において覚知せしめるものとまではいえない、といわざるを得ない。 2 そうすると、控訴人翻訳原稿全体の著作権(複製権)侵害のみを問題とする本訴請求は、結局、右侵害の立証がないことに帰するから、その余の点について判断するまでもなく、失当といわざるを得ない。 また、氏名表示権の侵害の点についても、複製権の侵害がない以上、 右氏名表示権の侵害もないことに帰するから、その余の点について判断するまでもなく、この点も失当といわざるを得ず、結局、控訴人翻訳原稿の著作権に基づく本訴請求はいずれも理由がないというべきである。」三 以上の次第であるから、本訴請求はいずれも理由がなく、原判決は相当であるから、本件控訴をいずれも棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法95条、89条を適用して主文のとおり判決する。 |
| 裁判官 | 松野嘉貞 |
|---|---|
| 裁判官 | 濱崎浩一 |
| 裁判官 | 田中信義 |