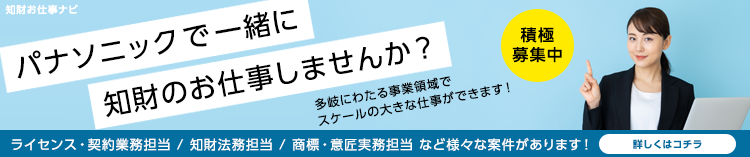この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
| 審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
|---|---|---|
| 平成11ネ1150損害賠償請求控訴事件 | 判例 | 特許権 |
| 昭和61ネ833 | 判例 | 特許権 |
| 平成2ネ2733 | 判例 | 特許権 |
| 関連ワード | 著作物性 / 創作性 / 創作的表現 / 著作者 / 著作者人格権 / 公表権 / 複製権 / 引用 / 著作権侵害 / 差止 / 損害賠償 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|
| 事件 |
平成
11年
(ネ)
5631号
著作物発行差止等請求控訴事件
|
|---|---|
|
控訴人 株式会社文藝春秋 右代表者代表取締役 【A】 控訴人 【B】 控訴人 【C】 三名訴訟代理人弁護士 古賀正義 被控訴人 【D】 被控訴人 【E】 両名訴訟代理人弁護士 今野勝彦 同 前田惠三 同 加藤裕也 同 岩田廣一 |
|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2000/05/23 |
| 権利種別 | 著作権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
当事者の求めた裁判
一 控訴人 1 原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。 2 右部分に係る被控訴人らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。 二 被控訴人 主文と同旨 |
|
|
事案の概要
事案の概要は、次のとおり付加するほか、原判決の事実及び理由「第二 事案の概要」のとおりであるから、これを引用する。なお、当裁判所も、 「【F】」、「本件書籍」、「控訴人会社」、「控訴人【C】」、「本件手紙⑮」、「本件各手紙」の用語を、原判決の用法に従って用いる。 (当審における控訴人の主張の要点) 一 不法行為の成否について 手紙の著作物性については、法律に明文がなく、それを否定した裁判例(高松高等裁判所平成八年四月二六日判例タイムズ九二六号二〇八頁)はあるものの、 肯定した裁判例はない。学説も、手紙の著作物性について触れるものはほとんどなく、例外的にこれに触れた学説も、手紙をカタログ類、広告、劇場プロ、アルバム等と並記して著作物性を生じるボーダーライン・ケースとし、「もちろん、実際には、個々の場合について、著作物性を備えているかを判定することが必要で、一般論としてここにあげたカタログその他がすべて著作物だといえるわけではない」(【G】・【H】著「著作権」)とし、【I】「概説著作権法」がやや詳細にこれを論じている程度である。 本件書籍に本件各手紙が公表された当時、素人はもとより専門家でも、手紙の著作物性について確かな見解(司法判断の予測)を持することは不可能であった。このような状況の下においては、手紙の著作物性は誰にも知られていないに等しく、国民の依拠すべき法は、事実上存在しなかったのである。 このように、手紙の著作物性については、法律の明文も判例も全くなく、学説も寥々たるうえ区々たる有様で、それだけを論じた単行の論文などなく、せいぜい教科書の中で結論だけが一、二行述べられているにすぎず、有力な多数説のごときものは形成されていなかった。このような状況の下において、日本で初めて公権的判断を下した裁判所が、自らの見解を理由として、それに反した当事者の行動に過失責任を問うのは酷である。控訴人らには、故意はもちろん過失もない。 二 差止めについて 1 著作権法60条ただし書きの適用 本件においては次の事情があるから、本件各手紙の公表は、【F】の意を害しない。したがって、謝罪広告の請求は許されない。また、同人の意を害することを根拠とする限り、差止め請求もできない。 ①本件各手紙は、【F】が生きているとして、恥じ入るようなところは全くない。②本件各手紙は、控訴人【C】に私信として送ったものであり、控訴人【C】は自分のもらった手紙を自己の作品に引用したのである(罪の意識の不存在)。③文芸出版において伝統と実績のある控訴人会社から出版された真面目な文学作品の中に引用されている。④手紙利用の仕方も、小説の展開に応じた自然なもので、いささかも礼を失していない。⑤今も毎夕仏壇の前で【F】の成仏を祈っているという控訴人【C】が、【F】にもらった手紙を自己の小説に利用したのであって、手紙の利用にはいわば祈りが籠められており、【F】の人格を傷つけるような意図は毛頭ない。⑥【F】の死亡から二八年、最初の手紙が書かれた年から約三七年、最後の手紙が書かれた年から三一年が経過している。⑦本件各手紙が著作物といえるかどうか疑問である。 2 頒布についての知情の主張・立証の不存在 本訴状の請求原因には、頒布の差止めを求めるとの記述がなく、その他にも、被控訴人らからは、頒布との関連で、知情についての主張、立証はなされていない。被控訴人らは、頒布差止請求についての「情を知って」という要件を主張しないものとして扱われるべきである。しかし、頒布が禁止されるのが「情を知って」の場合に限られることは、著作権法113条1項2号が明文をもって定めるところである。 3 信義誠実義務違反、権利濫用 本件差止請求は、控訴人【C】が公開したことにより、降って湧いたように具体的財産として現実化した故人の手紙、それもわずか一五通で、書いた本人も、創作性、芸術性など全く意識せず、作品として書いていないことが歴然としている手紙を盾として、芥川賞候補にもなった有望な新人作家である控訴人【C】の苦心の作の出版を差し止めようとするものである。 そして、仮に右出版が被控訴人らの有する複製権の侵害に当たるとしても、損害の填補は容易であり、差止めにより控訴人ら側に生じる損害、文化、芸術等の育成という著作権法本来の目的の不達成、【F】という文学者の正確なイメージが伝わらないという文化的損失等々を比較衡量すれば、本訴の差止請求は、信義誠実義務に違反し、権利濫用に該当するものというべきである。 4 憲法21条違反 本訴は、本件書籍の同性愛というテーマが被控訴人らの感情を刺激したために提起されたにすぎない。本訴差止請求は、同性愛者に対する差別感情に基づき、本来ならば公表を差し止める意思も必要もない手紙の著作権に名を借りて、文学的水準の高い本件書籍の発行を差し止め、これにより控訴人らの表現・言論・出版の自由を侵すものである。本訴の差止請求を認めることは、憲法21条に違反する。 三 名誉回復措置について 1 最高裁判所昭和六一年五月三〇日第二小法廷判決は、現行著作権法の前身というべき旧著作権法36条の2について、右規定にいう著作者の「著作者の声望名誉とは、著作者がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的声望名誉を指すものであつて、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まれない」と判示している。本件各手紙は、【F】の名誉や声望を低下させるようなものを一切含んでいないから、名誉回復措置の請求はできない。 2 原判決別紙広告目録(二)の広告文中の、「私どもがご遺族に無断で公表、 出版したものであります。」という部分は、遺族らには公表につき承諾を与える権原がないから、法の論理に反する。 また、同広告文の「これにより、大変ご迷惑をおかけしました。」という部分は、誰に迷惑をかけたのかが曖昧で、それゆえに取消しを免れない。法115条による「適当な措置」を要求し得ない遺族に対して迷惑をかけたと詫びさせるのは道理に合わないし、故人に対して詫びさせるのもおかしいのである。 右の広告文は、憲法違反の疑いも完全には免れない。 3 原判決が、広告文の掲載を命じることの必要性の根拠とした事情①ないし⑤(二三頁ないし二五頁)は、名誉声望とは何の関係もない事項である。 四 損害賠償について 損害賠償についての原判決の判断は、裁判所が、控訴人【C】の文学について乙号各証に表れている多数の著名な文学評論家が与えた評価に一顧も与えず、反面において、評論家が本件各手紙の本件書籍における重要性に一片の言及もしていない事実を黙殺して、自らは何ら専門的知見を有しない文学の領域において、 【F】の書き流しの手紙である本件各手紙と【C】の作品とについての金銭的評価を公権的に与える、という意味を有するものである。しかし、これは、控えめに言っても行き過ぎではないだろうか。素人考えでも、本にして一〇頁そこそこの手紙(それも苦心して書いた作品としての手紙ではなく、多少の教育のある日本人なら誰でも書けるような書き捨ての手紙)について、五〇〇万円の印税が生じるなどというのは文学史上の奇観というをはばからない。 本件の場合、本訴提起の実際上の動機は、【F】と控訴人【C】の同性愛的交遊の隠蔽にあったことは、多くの評論家が曇りのない目で洞察し、指摘しているところである。すなわち、本件各手紙が著作権者によって公表される可能性はゼロ、したがって逸失利益もゼロというのが通常の感覚である。 |
|
|
当裁判所の判断
当裁判所も、被控訴人らの本訴請求は、原判決が認容した限度で理由があり、その余は理由がないと判断する。その理由は、次のとおり付加するほか、原判決の事実及び理由「第三 争点に対する判断」と同じであるから、これを引用する。 (当審における控訴人らの主張に対する判断) 一 不法行為の成否について 控訴人らは、本件書籍に本件各手紙が公表された当時、素人はもとより専門家でも、手紙の著作物性について確かな見解(司法判断の予測)を持することは不可能であり、手紙の著作物性は誰にも知られていないに等しく、国民の依拠すべき法は、事実上存在しなかったから、控訴人らには、故意がないのはもちろん過失もないと主張する。 1 著作権法は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義し、特に「手紙」を除外していないから、右の定義に該当する限り、手紙であっても、著作物であることは明らかである。この点について、手紙の著作物性は誰にも知られていなかったとか、国民の依拠すべき法が事実上存在しなかったとか、ということはできない。 2 甲第一七号証によれば、一九七五(昭和五〇)年七月一〇日付け週刊文春(一四一頁)には、交際相手にあてた【F】の私信が受取人により「週刊朝日」に公開されたことに関し、「作家の著作権は私信にも及ぶというのが法解釈上の通説だそうで、確かに『手紙』を公開するには夫人の了解が必要だろう。」、「3月10日に朝日側が著作権侵害を認めた念書を渡すまで、両者の交渉は延々と続く。」、「著作権者の了解をとらなかっただけに、どうも朝日側の分が悪かったとみえる。」との記載があることが認められる。週刊文春が、一流の出版社であることを被控訴人らも認める(当審答弁書四頁五行)控訴人会社によって発行される一般向け週刊誌であることは当裁判所に顕著であるから、右記載は、適切な裏付けのもとに書かれたものと推認される。 右認定の事実によれば、昭和五〇年ころには既に、交際相手にあてた私信という程度の手紙も著作物(すなわち、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)であること、及び、右のような手紙にも著作者の著作権が及ぶということが、週刊文春のような一般向け週刊誌にも、「法解釈上の通説」として説明される程度の事柄であったことが認められる(ちなみに、当庁第六民事部の書棚の入門書、実務書等にも、「問17・・・日記や手紙を発表するのは、著作者人格権侵害になりますか。・・・日記や手紙は、やはり著作物である場合が多いわけですから、著作物である以上は、人格権の問題が起こる。原則的には普通の著作物と同じように、公表については著作者の同意がいるということになります。死後であれば遺族の諒解を得なければいけないということになる。・・・もちろん、著作権は手紙を出したほうにある。・・・もらった手紙であるからといって、それを勝手に本にするとかいうことはいけない。複製権の侵害と、人格権の侵害と、両方ひっかかってくるおそれがあるということですね。」(【J】・【K】著「新著作権法問答」八〇頁・株式会社新時代社一九七二年一二月一〇日第二刷発行)、「書簡の内容が、発信人の思想、感情を創作的に表現している場合は、文書の著作物として著作権が発生する。・・・著作権のある書簡の著作権者は発信人であり・・・これが発信人以外の者(受信人も含めて)により公表される場合、発信人の許諾が必要なことはいうまでもない。」(社団法人著作権資料協会編「著作権事典 改訂版」一六二頁・株式会社出版ニュース社昭和六〇年一〇月二五日発行)、「Qー58 日記・手記は著作者に無断で公表できますか。書簡の場合はどうですか。 いずれも著作者に無断で公表できない。創作したものを公表するかしないかは著作者の自由である・・・書簡の場合には、受取人は書簡の所有者にすぎず、著作者は発信人であるから、受取人の了解を得ただけでは発表できないのである。」(【L】編「新版Q&A著作権入門」一四六頁(【M】執筆)・世界思想社一九九一年一〇月一日発行)、「手紙も日記も著作物。その著作権者の許諾なしに転載できない。・・・なお、手紙や日記の所有者は、著作者でもなければ著作権者でもない場合が多い。」(【N】編著「著作権実務百科」一ー九四頁ないし九五頁・学陽書房一九九二年一一月五日発行)、「書簡 時候の挨拶、転居通知、出欠の問合わせなどの日常の通信文とか、品物の発注、代金の督促など商用文は著作物とはなりえないが、その他の書簡であって文芸、学術の範囲に属すると認められるものについては著作物として保護される。この場合・・・特約なきかぎり著作権は差出人に留保される。したがって名宛人は差出人の同意を得ることなしに書簡を公表することはできない。」(【I】著「著作権法概説」八七ないし八八頁・株式会社一粒社平成九年五月二〇日第八版第一刷発行)等、手紙の著作物性を説明し、その著作権は著作者(発信人)にあるとする記述がみられるところである。)。 3 本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候のあいさつ等の日常の通信文の範囲にとどまるものではなく、【F】の思想又は感情を創作的に表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである。また、控訴人らが本件各手紙を読むことができたことも明らかである。そうである以上、控訴人らは、本件各手紙の著作物性を認識することが容易にできたものというべきである。控訴人らに過失がないとの主張は、採用することができない。 二 差止めについて 1 著作権法60条ただし書きの適用の主張について 控訴人らは、種々の事情をあげて、本件各手紙の公表は【F】の意を害しないと主張する。 しかし、控訴人ら主張に係る⑦の事情を認めることができないのは、前記一及び原判決の事実及び理由「第三 当裁判所の判断」一2のとおりである。そして、本件各手紙が、もともと私信であって公表を予期しないで書かれたものであることに照らせば(例えば、本件手紙⑮には、「貴兄が小生から、かういふ警告を受けたといふことは極秘にして下さい。」との記載がある。右のような記載は、少なくとも書かれた当時は公表を予期しない私信であるからこそ書かれたことが明らかである。)、控訴人ら主張に係るその余の事情を考慮しても、本件各手紙の公表が【F】の意を害しないものと認めることはできない。 2 頒布の差止めについて知情の主張・立証がないとの主張について 控訴人らは、頒布が禁止されるのが「情を知って」の場合に限られることは、著作権法113条1項2号が明文をもって定めるところであるのに、被控訴人らは、頒布差止め請求についての「情を知って」という要件を主張していない旨主張する。 しかし、著作権法113条1項2号は、著作権侵害行為、著作者人格権侵害の行為や著作権法60条の規定に違反する行為によって作成された物がいったん流通過程に置かれた後に、それを更に転売・貸与する者を全部権利侵害とすることには問題があるために、その場合に限って「情を知って」との要件を付加しているものと解すべきであり、控訴人らは、本件各手紙を本件書籍に掲載して出版した当の本人であって、物がいったん流通過程に置かれた後に、それを更に転売・貸与する者ではないから、控訴人らの行為は、同法113条1項2号にいう「頒布」の問題として扱われるべき事柄ではないというべきである。 控訴人らは、本件各手紙を本件書籍に掲載して出版行為をすること自体が許されなかったのであるから、右違法な行為によって自らが作成した物を自ら頒布することもまた許されないことは、むしろ自明である。すなわち、本件各手紙を本件書籍に掲載して出版したうえで頒布するという控訴人らの一連の行為全体が、全部であれ一部であれ、複製権を侵害する行為及び著作権法60条の規定に違反する行為に該当するというべきである。 3 信義誠実義務違反、権利濫用の主張について。 (一) 甲一二ないし一四、一六、一七、一九、二〇号証及び弁論の全趣旨によれば、【F】の遺族は、その了解なしに【F】の手紙が公表、複製された場合には、そのテーマが同性愛であるか否かとは関係なく必ず抗議し、その手紙が掲載された書籍の出版継続を阻止していること、現在は右遺族の了解の下に出版されている書籍の中にも、出版当初了解を得ていなかったために抗議を受け、著者及び出版者の謝罪、書籍の残部の断裁等が行われ、了解が得られるまで一〇年以上の間出版が中止された、という経緯のあるものがあることが認められる。 (二) 本訴が著作権及び著作者人格権に関するものであることに右(一)の事実を総合して考慮すれば、被控訴人らが本件各手紙の存在を知らなかったこと、本件各手紙は文学作品として書かれたものではないこと、差止めによる控訴人ら側の損害、控訴人【C】が芥川賞候補にもなった有望な新人作家であること、本件書籍の文学的水準、【F】という文学者の正確なイメージを伝えるという目的、その他本件証拠によって認められる一切の事情を斟酌しても、それゆえに、被控訴人らが、著作権侵害を受忍しなければならないとか、被控訴人らが同法116条1項所定の権利を行使することが許されず、結果的に著作権法60条の規定にもかかわらず控訴人らが【F】の著作者人格権の侵害となるべき行為をすることが放置されるとか、と解することはできない。したがって、本訴差止請求を信義誠実義務違反、 権利濫用と認めることはできない。 4 憲法21条違反の主張について 控訴人らは、本訴差止請求は、同性愛者に対する差別感情に基づき、本来ならば公表を差し止める意思も必要もない手紙の著作権に名を借りたものであると主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。前記3(一)、(二)の事情、特に、 右差止めは、本来、控訴人らが控訴人ら自身の思想、感情を創作的に表現することを差し止めようとするものではなく、控訴人らが、控訴人ら自身の思想、感情を創作的に表現するのに役立てるためとはいえ、他人の思想、感情の創作的表現を複製、公表することを差し止めようとするものにすぎないものであることに照らせば、本訴差止請求を認めることを憲法21条に違反するものということはできない。 三 名誉回復措置について 1 控訴人らは、本件各手紙は、【F】の名誉や声望を低下させるようなものを一切含んでいないから、名誉回復措置の請求はできないと主張する。 しかし、著作物の公表権は著作者にあるから、本件各手紙を公表することは、【F】が生前、本件各手紙を公表することを了解していたか(私信であっても、事前又は事後に著作者が公表を了解することは、十分あり得ることである。)、又は、その遺族が公表を了解した(すなわち、公表に対して、【F】が存していたとしたならその著作者人格権となるべきものの保護のための措置を採らないことを約束した)という世人の誤解を招くものということができる。そして、世人が右のように誤解すれば、これにより【F】の社会的名誉声望が低下することは明らかである。すなわち、本件各手紙は、【F】の思想又は感情を個性的に表現したものではあるものの、公表を予定しない私信であることがあずかって、少なくとも控訴人らからは、「氏の文名を貶めこそすれ、高めるに資するようなものではない」(原判決四九頁)、「中学生風の言いまわし・・・どこの言葉か判らぬ単語・・・悪趣味な表現・・・本当に【F】氏が書いたのかと、首を傾げざるを得ないことになるのである」(同五二頁)と評価されているものであるから、その文学的・内容的水準を右と同様に評価したうえ、このような低い水準のものについて【F】自身が公表を了解した、あるいは【F】は肉親である遺族からこのような低い水準のものでも公表を了解するであろう人物と思われているからこそ遺族が公表を了解したのであろうなどと誤解して、【F】の文学性や品性に対する評価を下げる者が出ることは、避けられないところであるからである。 2 控訴人らは、原判決別紙広告目録(二)の広告文について、①「私どもがご遺族に無断で公表、出版したものであります」という部分は、遺族らには公表につき承諾を与える権原がないから、法の論理に反する、②「これにより、大変ご迷惑をおかけしました」という部分は、誰に迷惑をかけたのかが曖昧であり、著作権法115条による「適当な措置」を要求し得ない遺族に対して迷惑をかけたと詫びさせるのは道理に合わないし、故人に対して詫びさせるのもおかしいと主張する。 しかし、著作権法は、著作権者の遺族は、故意又は過失により、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をした者に対し、 同法115条の適当な措置を請求できることとしており(同法116条1項、60条)、その意味で、遺族が、著作権者の死後において著作者の人格的利益を保護する権利を有することを認めているのであるから、その権利者である遺族に「無断で公表、出版した」ものであることをも明らかにすることが、【F】の名誉声望を回復するために適当な措置の一つとなることは、明らかというべきである。このことは、前記1において説示したとおり、本件各手紙の公表について、遺族が了解したと誤解されるおそれがあることからも明らかである。控訴人らが、遺族が同法115条の適当な措置を請求できないことを前提として右主張をするものとすれば、それは失当である。 また、「これにより、大変ご迷惑をおかけしました。」との部分は、控訴人らが、本件書籍の出版により、【F】又はその遺族が本件各手紙の公表に了解を与えたものと、広告文の読者に誤解を与えたことを、読者にとっての迷惑ととらえ、これについて謝罪したものと優に理解することができ、新聞掲載の広告文の一部であることを前提にすれば、これが最も自然な理解というべきである。この点についての控訴人らの主張も採用できない。 以上のように解して原判決主文第四項のとおり広告の掲載を命じたとしても、憲法に違反するものではない。 3 控訴人らは、原判決が、広告文の掲載を命じることを必要とするものとした事情①ないし⑤(二三頁ないし二五頁)について、名誉声望とは何の関係もない事項であると主張する。 しかし、右①ないし⑤が、【F】の名誉回復のための適当な措置として、 広告文の掲載を命じるか否かの判断に当たって重要な要素であることは明らかである。例えば、①及び③は、本件各手紙が多数の者に公表されたために名誉声望の低下が大きいことを裏付ける事実、②は、本件各手紙の公表権侵害について、「被控訴人らが【F】の人格的利益を低く見て事実上保護していなかったためであり、被控訴人ら(ひいては【F】)の自業自得である」というような事情がないことを示す事実、④は、将来の公表の可能性を念頭に置いていた場合(例えば、著名作家への手紙については、将来往復書簡集として刊行される可能性を考える場合もある。)には、表現にも注意することは当然であるから、それでもなお本件各手紙の程度のものを書いたとすれば、多少の文名の低下はやむを得ないというべき場合もあり得るが、本件はそのような場合ではないことを示す事実、⑤は、控訴人らが既に【F】の社会的な名誉声望を回復するための適切な措置を採っていれば、その内容によっては、広告文が必要なくなったり、あるいは、掲載場所や大きさが小さくてすんだりする場合もあるが、本件はそのような場合ではないことを示す事実であり、これらの事情を考慮することは当然である。 控訴人らの主張は、採用することができない。 四 損害賠償について 控訴人らは、何人かの文学評論家が控訴人【C】の文学を評価し、本件各手紙の本件書籍における重要性に言及していないことを根拠として、損害賠償についての原判決の判断を非難する。 しかし、著作権侵害による損害賠償は、文学的価値ではなく財産的価値の侵害による賠償であって、【F】と控訴人【C】の知名度や文学者としての名声を比較すれば、本件各手紙が本件書籍において、財産的に重要なものであること、すなわち、本件書籍購入の意欲をそそり、本件書籍の商業的成功をもたらすという点で重要なものであることは明らかである。評論家が、文学的観点から、控訴人【C】の文学を評価し、本件各手紙の重要性に言及していないとしても、そのことによって、本件書籍における本件各手紙の商業的重要性が否定されるものではない。 また、控訴人らは、本件各手紙が著作権者によって公表される可能性はゼロ、したがって逸失利益もゼロというのが通常の感覚であると主張する。 しかし、本件各手紙は、著名な文学者である【F】の著作物であるから、その文学的価値が高いか否かはともかくとして、これについての著作権に相当な財産的価値があることは明らかである。そして、このように財産的価値のある著作権を侵害された場合には、著作権者に損害が発生すると推認すべきであることは当然である。控訴人らは、本件各手紙が著作権者によって公表される可能性がゼロであると主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。本件各手紙を公表すれば【F】の名誉声望が低下することはあるとしても、そのことを受忍した場合には、著作権者において本件各手紙を複製して販売する等して経済的利益を得ることが容易であることは明白である。そうである以上、そのようにして経済的利益を得るか否かは、著作権者の意思次第であって、著作権者である被控訴人らがそのような選択をする可能性がゼロなどということは到底できないのである。控訴人らの主張は、採用できない。 |
|
|
結論
以上のとおり、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条、65条、67条を適用して、 主文のとおり判決する。 |
| 裁判長裁判官 | 山下和明 |
|---|---|
| 裁判官 | 山田知司 |
| 裁判官 | 宍戸充 |