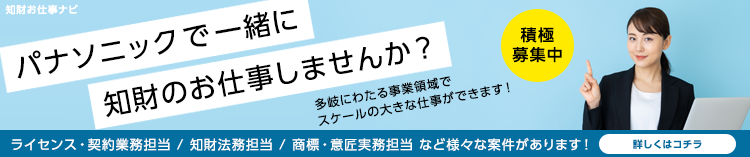| 関連ワード | 著作物性 / 創作性 / 創作的表現 / 著作者 / 表現物 / 著作者人格権 / 公表権 / 複製権 / 引用 / 著作権侵害 / 差止 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|
| 事件 |
平成
21年
(ネ)
10030号
著作権に基づく侵害差止請求控訴事件
|
|---|---|
|
控訴人X 訴訟代理人弁護 士喜田村洋一 被控訴人Y 訴訟代理人弁護 士馬奈木昭雄 同 江上武幸 同 椛島隆 同 市橋康之 同 大西啓文 同 紫藤拓也 同 高峰真 同 迫田登紀子 同 岩元理恵 同 小林正幸 同 毛利倫 同 白水由布子 |
|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2009/09/16 |
| 権利種別 | 著作権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
1本件控訴を棄却する。 2控訴費用は控訴人の負担とする。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。 2被控訴人は,URLを「http://www.geocities.jp/shinbunhanbai/」とするインターネットウェブサイトから,原判決添付の別紙「文章目録1」記載の文章を削除せよ。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 |
|
|
事案の概要
1 原審の経緯等控訴人(1審原告。以下,「原告」という。)は,株式会社読売新聞西部本社(以下「読売新聞西部本社」という。)の法務室長である。ところで,読売新聞西部本社は,福岡県所在の読売新聞販売店の経営者から,訴訟を提起されたが,原告は,読売新聞西部本社の担当者の一人として,同訴訟に関与していた。同訴訟の過程で,読売新聞西部本社は,読売新聞販売店の経営者の訴訟代理人から質問書の送付を受け,原告は,読売新聞西部本社を代理する立場で,同訴訟代理人に対し,回答書(別紙文章目録2)を,ファイルを添付する形式でメール送信した。 他方,被控訴人(1審被告。以下,「被告」という。)は,フリージャーナリストであり,インターネットウェブサイト(以下「被告サイト」という。)を開設し,新聞社と新聞販売店との販売部数を巡る問題等を取り上げ,上記訴訟の推移等についても,取材し,執筆した記事等を,被告サイトへ掲載公表していた。その過程で,被告は,被告サイトに,原告作成に係る上記回答書を掲載した。 原告は,平成19年12月21日,原告作成に係る回答書を被告サイトに掲載されているのを発見し,同日午後6時26分に,上記回答書の削除を求める旨の「催告書」(別紙文章目録1,以下「本件催告書」という。)を添付ファイル形式で送信した。被告は,本件催告書も被告サイトに掲載したため,原告が被告に対して,原告が本件催告書を作成し,本件催告書が著作物に当たると主張して,公表権及び複製権に基づき,被告に対し,本件催告書を被告サイトから削除することを求めた。 原判決は,?@原告は,本件催告書を作成した者であると認めることができないから,原告の主張は理由がない,?Aまた,事案にかんがみ,本件催告書の著作物性を検討し,本件催告書は,著作権法2条1項1号所定の「創作的に表現したもの」であるとはいえないから著作物に当たらないと判断して,原告の被告に対する請求を棄却した。 原告は,原判決を不服として本件控訴を提起した。 2 当事者間に争いがない事実,争点及びこれに関する当事者の主張次のとおり当審における主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「1争いのない事実等」,「2争点」及び「3争点に対する当事者の主張」(原判決2頁12行目から27頁25行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。なお,略語は,すべて原判決と同様の表記とする。 (1) 原告の補足的な主張ア 本件催告書の作成者について(ア)原告が勤務する法務室には,六法はもとより,著作権に関する書籍も4,5冊程度は備えられていたため(甲10~13),原告は,これらを参照しながら,本件催告書を執筆した。原告が,自ら作成していないにもかかわらず,自ら作成したと主張をする動機は存在しない。仮に,原告代理人が作成したのであれば,読売新聞西部本社が原告となって,被告に対し削除を求める訴訟を提起すれば足りる。それにもかかわらず,原告が自ら執筆していないのに,あえて事実と異なる主張をして,争点を増やす動機は存在しない。 そのような点に照らすならば,原告が執筆したものと認定されるべきである。 (イ)本件催告書と原告代理人催告書とを対比すると,本件催告書では公表権に言及しているのに対し,原告代理人催告書では,公表権及び複製権について言及している点で相違する。したがって,本件催告書と原告代理人催告書とは,別の者によって作成されたと認定されるべきである。 イ 本件催告書の著作物性について言語表現物が著作物に該当するか否かは,表現それ自体に独創性が存在するかを判断基準とすべきではなく,「誰が書いても同じになる」とはいえない程度の表現の配列や全体的な構成であるかを判断基準とすべきである。 本件催告書は,回答書の無断公表という事態に対し,回答書が未公表である所以を述べていること,その公表が著作権法の何に抵触するかを明らかにしていること,これによって生じる法的結果に言及していること,要求内容を明確にしていること等の点で,表現の配列や全体的構成において「誰が書いても同じになる」というものでないから,著作物に該当する。 (2) 被告の反論ア 本件催告書の作成者が原告ではないこと(ア)原告の経歴に照らし,法律に素人であり,それまで1度も催告書を作成した経験がない原告が,本件催告書のような文書を,六法全書と数冊の著作権法関連書籍を参考にして,他の催告書等の書式や市販の文例集などを一切参考にせずに,短時間で作成したことは,経験則上考えられない。また,本件催告書のような重要なメール文書を送信履歴から削除することは考えられない。 (イ)原告は,原告が作成していないにもかかわらず,原告が作成したと述べる動機はないと主張する。 しかし,原告の上記主張は失当である。すなわち,本件催告書の送付及び本件訴訟の提起は,新聞社と新聞販売店との販売部数を巡る問題等を被告サイトに掲載公表する被告の活動を萎縮させることを目的としたものである。そのような背景からすると,原告代理人ないし読売新聞西部本社が自らの名義で催告書を送付して,裁判の当事者となることを,躊躇せざるを得なかったものと推認される。 イ 本件催告書の著作物性について原告は,言語表現物に著作物性があるか否かは,「誰が書いても同じになるものではないか否か」を判断基準とすべきであり,同じにならない以上著作物性を肯定すべきであると主張する。 しかし,言語表現に著作物性があるか否かは,何らかの個性が発揮されていれば足り,厳密な意味で,独創性が発揮されたものであることまでは必要ないが,作成者の個性が何ら現れていない場合は,「創作的に表現したもの」ということはできないと解すべきである。言語による表現では,文章がごく短いものであったり,表現形式に制約があるため,他の表現が想定できない場合や,表現が平凡かつありふれたものである場合は,作成者の個性が現れておらず,「創作的に表現したもの」ということはできない。 上記の判断基準によれば,本件催告書の著作物性は認められない。 |
|
|
当裁判所の判断
当裁判所も,原告の請求は理由がないものと判断する。 その理由は,次のとおり,付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」(原判決28頁1行目から40頁12行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する(なお,本判決で再掲した部分がある。)。 1 本件催告書を作成したのは,原告であるかについて(1)原判決の該当部分(原判決28頁2行目から33頁21行目)のとおりであり,再掲する。 「(1)ア前記争いのない事実等,証拠(甲2ないし6,乙11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。 (ア) 当事者a原告は,昭和54年に読売新聞西部本社に取材記者として入社し,社会部を中心に福岡及び九州の地方支局に勤務した後,編集局地方部次長,配信センター次長,大分支局長などを経て,平成19年5月1日から,同社の法務室長の地位にある。同人は,社会部記者として警察や裁判所を取材担当とする経験を有するものの,大学時代を含めて,これまでの間,専門的に法律を習得した機会を有するものではない。 原告の勤務する法務室の担当職務は,読売新聞西部本社に関係する裁判への対応や法律問題への対応等であり,法務室には,原告を含めて3名が在籍している。法務室においては,外部の第三者に対して催告書等を作成する機会があるが,原告自身は,本件催告書の作成に至るまで,催告書を作成した経験を有するものではない。 b被告は,フリージャーナリストであり,被告サイトを主宰し,同サイトに自ら執筆した文章等を掲載している。 (イ)読売新聞西部本社は,同社の販売店であるYC広川の所長の真村との間で,民事上の紛争を抱え,同紛争は真村が仮処分申立て及び訴訟(真村訴訟)提起をするに至っていたところ,真村訴訟の係属中に,同訴訟における真村の訴訟代理人である江上弁護士から,読売新聞西部本社の真村への対応についての質問の書面が送付されてきたので,原告は,平成19年12月19日,同質問に回答すべく,江上弁護士に対して,本件回答書をファクシミリによって送信した。 (ウ)その後,平成19年12月21日,原告が被告サイトを閲覧していたところ,本件回答書が被告サイトに掲載されているのを発見したため,原告代理人に,上記の点に関しての今後の対応について相談した。 これを受けて,原告代理人は,原告に対して,本件回答書を被告サイトに掲載することは,本件回答書について原告が有する公表権を侵害することになるから,本件回答書の被告サイトからの削除を求める旨の催告書を,被告に対して送付することを提案し,原告代理人事務所において,催告書の文案(本件催告書)を作成し,そのデータをメールに添付する方法により,原告に送信した。 原告は,同日の午後6時26分,原告代理人事務所から受け取った上記の本件催告書に係るデータを,メールに添付して,被告に送信した。 なお,被告に送信された本件催告書の上記データはPDFファイル形式であった。 イ上記の認定事実によれば,本件催告書には,読売新聞西部本社の法務室長の肩書きを付して原告の名前が表示されているものの,その実質的な作成者(本件催告書が著作物と認められる場合は,著作者)は,原告とは認められず,原告代理人(又は同代理人事務所の者)である可能性が極めて高いものと認められる。 これに対して,原告は,本件催告書を作成したのは原告である旨主張し,原告本人尋問において,本件催告書は,原告が作成したものであり,原告代理人には,本件催告書の文末の部分の添削を受けただけであると供述する。 そこで,この点について,以下,検討する。 (ア)前記アで判示したように,本件催告書は,平成19年12月21日の午後6時26分に,メールで被告に送信されたところ,原告は,原告本人尋問において,同日に,被告サイトに本件回答書が掲載されていることを発見したため,原告代理人に対し,その対処方法について相談した結果,本件催告書を被告に送信することになったこと,原告がまず本件催告書の草案を作成し,これを原告代理人に対しメールによって送信し,原告代理人から上記草案の末尾のみ修正を受けたことを供述する。 また,原告は,この点に関連して,本件催告書を作成するに当たって,法務室において過去に作成されパソコン等に保存された催告書等の文例を一切参考することなく,しかも,市販の文例集等も参考にせずに,法務室に備え付けの著作権法関係の本を5,6冊読み,六法全書を見て作成した(原告本人調書4頁及び12頁)旨供述する。 しかしながら,前記アで判示したとおり,原告は,社会部を中心とする取材記者の経歴が長く,大学時代を含めて,これまで専門的に法律を習得した機会はなく,読売新聞西部本社において,法務室に配属されたのも,本件催告書を作成する7か月余り前のことであり,また,これまで,催告書を作成した経験もないところ,このような経歴,素養を有する原告が,上記のような数時間程度の期間内で,作成済みの催告書や文例を一切参考にせずに,六法全書と著作権法関係の本を参考にして,本件催告書とほぼ同一の内容の草案を作成できるとは到底考え難いところである。 (イ)また,原告は,原告本人尋問において,日常の業務においては,ワープロソフトとしてはワードを使用していることを自認するところ,本件催告書の作成に当たっては,会社にあるパソコンで作成したことは覚えているが,使用したワープロソフトは覚えていない旨供述する(原告本人尋問調書14,15頁)。 しかしながら,原告が,本件催告書を,会社に備え付けのパソコンで作成したのであれば,通常,日常の業務において使用しているワープロソフトであることを自認するワードによって本件催告書を作成したものと考えられ,原告本人尋問においても,そのように供述するのが自然と解される。また,原告が,本件催告書を日常の業務で使用しているワープロソフト以外のソフトで作成した可能性があるのであれば,そのことの説明をするのが自然であるというべきであり,それにもかかわらず,上記のような供述をすることは理解し難いところである(このような供述の不自然さから,原告は,本件催告書の作成において使用されたワープロソフトがワードではない可能性や,そもそも読売新聞西部本社の法務室に備えてあるパソコンにPDF作成ソフトがインストールされていない可能性があることを考え,上記のような供述をしたのではないかとの疑念が生じる。)。 さらに,原告は,原告本人尋問において,本件催告書のうち,原告自身が創作性があると考える部分は具体的にどこであるかという質問に対しては,全体として創作性がある,又は自分で考えて作成したことに創作性がある旨の供述に終始しており(原告本人尋問調書9ないし12,23,25頁),具体的な創作的表現を指摘できず,また,本件催告書の作成に当たって留意した点などの本件催告書の作成経緯についても,一切触れておらず,この点も不自然といわなければならない。 (ウ)なお,原告は,原告本人尋問において,自ら作成した本件催告書の草案を原告代理人に確認してもらうために,そのデータをメールに添付することにより送信した旨供述するが,原告及び原告代理人の両名とも,現在,上記メールのデータを有しておらず(第3回口頭弁論調書),この点も,不自然であるとの感は否めない。 (エ)ところで,代理人催告書(乙21)は,原告代理人が作成したものであることは争いがないところ,同催告書は,宛先会社に対して,同社が開設するウェブサイトから原告代理人作成に係る文章の削除を求めるという内容の催告書であるが,証拠(甲3,乙21)によれば,本件催告書は,代理人催告書と,1行の文字数及びフォントが同一であり(なお,原告は,原告代理人による本件催告書の草案の修正は,原告が原告代理人に対して本件催告書の草案をメールで送信した上で,同草案を確認した原告代理人から電話で指示を受けて,原告が自ら行うという方法でされたものと思われる旨供述しており(原告本人尋問調書21,29頁),同供述のとおりとすれば,原告代理人が,原告から送信されてきた本件催告書の草案の修正をした際に,その文字数及びフォントを,自己の業務で使用している書式と同一のものと変更し,この修正後のデータを原告に送信したものとは考えられない。),また,前文として「冠省」という言葉を,結語として「不一」という言葉を使用している点で一致しており,文章の構成も類似している(両者とも,?@中止を求める被告の行為の指摘,?A原告が有する権利の主張,?B上記の被告の行為が原告の上記権利を侵害する旨の主張,?C上記の被告の行為の中止の要求,?D同要求に従わなかった場合,法的手段に訴えることの通告という構造になっている。)ことが認められる。 さらに,本件催告書及び代理人催告書とも,公表権を有することを表現するために,「専有」という用語を使用しているところ,著作権法上,著作財産権については,「専有」という用語が使用されるが,著作者人格権については,同用語は使用されないのであるから,公表権について「専有」という用語を使用した本件催告書及び代理人催告書は,特徴的な用語の使用法をしており,その特徴的部分が一致していると認められる。しかも,原告は,原告本人尋問において,六法全書を見て本件催告書を作成したと供述しており,また,本件催告書には,「私が専有しています(著作権法18条1項)」と,公表権の根拠条文が記載されているところ,原告が,著作権法18条1項の条文を参考としながら,本件催告書を作成したのであれば,公表権を「専有」するという記載をした根拠が不明である。一方,原告代理人は,代理人催告書に限らず,本件訴訟における訴状及び準備書面においても,公表権を有することを表現する際に,「専有」という用語を使用していることから,このような用法による場合が多いものと推測される。 これに対して,原告は,本件催告書と代理人催告書とが類似しているのは,代理人催告書の宛先会社が,本件催告書の宛先である被告と連絡を取り合って原告代理人の権利を侵害していると考えられたことから,「同じ相手には同じ書面で対応している」ことを示すため,代理人催告書を本件催告書と基本的に同じ構成としたからであると主張する。しかしながら,仮に,代理人催告書の宛先会社が,本件催告書の宛先である被告と連絡を取り合って原告代理人の権利を侵害しているとしても,同社に対し,本件催告書と同じ書面で対応していることを示す合理的な必要性は認められず,また,法律専門家である原告代理人が,そのような資格を有しない原告の作成した文章に追従して同じ構成の文章を作成することも,不自然というほかなく,原告の上記主張は,理由がない。 (2)以上の諸点を考慮すると,本件催告書は,原告が作成したものではないと認められる。」(以上,原判決再掲部分)(2) 本件催告書の作成者に関する当裁判所の補足的判断原告は,原告が勤務する法務室には,六法はもとより,著作権に関する書籍も4,5冊程度は備えられていたため,本件催告書を作成することができた旨主張し,原告が勤務する読売新聞西部本社法務室には,半田正夫「著作権法概説(第11版)」,田村善之「著作権法概説(第2版)」,半田正夫・紋谷暢男編「著作権のノウハウ(第6版),TMI総合法律事務所編「著作権の法律相談(第2版)」が備えられていたとして,その写しを提出する。 しかし,原告本人の下記の供述内容に照らすならば,上記各書籍が備えられていた事実があったとしても,本件催告書の作成者が原告であると認めることはできない。 ア 原告本人の供述内容原告本人は,本件催告書を作成した経緯について,概要,以下のとおり供述する。 (ア)原告が,被告サイトに,原告の作成した回答書が掲載されたのを発見したのは,平成19年12月21日午前中であった(午後ではなかった。)。そして,原告は,第三者によって,回答書が公開されることは,紛争解決を難しくするなどの点で,非常に困ったため,原告代理人に対し,電話で「文章が無断で公開されたんで,どうにかならないか」という趣旨の相談をした。 その際,原告は,原告代理人から,無断で公表することは,公表権や複製権侵害になるというアドバイスを受けた。 原告代理人との相談に費やした時間が,どの程度の長さであったかは,覚えていない。 (イ)そして,原告は,自ら本件催告書の作成を開始した。本件催告書を作成するに当たっては,法務室に備付けの著作権法関係の本を5,6冊読み,六法全書を見て完成させた。著作権関係の図書について,「もう既に何冊もあるので,ぱらぱらとそのときに見たと思います,そこにある本を」と供述する。 その際,原告は,法務室において過去に作成されパソコン等に保存された催告書等の文例を参考とすることもなく,市販の文例集等を一切参考とすることもなかった。また,催告書の書き方や内容証明の書き方に関する実務書も参考にしたことはなかった。 (ウ)原告は,本件催告書の作成を終えて,原告代理人に確認のために,見てもらった。原告は,自ら作成した本件催告書を,原告代理人にあてて,メールで送信したことは確かであるが,本件催告書の送信方法については,メール本文として送信したか,添付ファイルとして送信したか覚えていない。また,ファイル形式についても,PDF形式かどうかも覚えていない。 (エ)原告は,原告が自ら作成した本件催告書について,原告代理人から,修正を受けたことは事実であるが,その修正内容については,「文末くらいちょっとあったかも知れませんけど,内容的には修正されていないと思います。」と供述する。 また,原告代理人から受けた修正方法が,メールの返信形式なのかその他の方法であったかについては,「電話じゃなかったかと思います。 ちょっとよく覚えていません。」と供述している。 なお,原告は,原審の法廷で原告本人尋問を受けるに当たって,本件催告書に関する原告代理人からの修正指示の内容等に関して,記憶喚起のための準備は,一切していないと供述する。 そして,原告は被告に対して,同日午後6時26分に,本件催告書を添付メールの形式で送信した。 (オ)原告は,読売新聞西部本社の法務室内で,パソコンによって作成した法的紛争に関連して作成された文章については,「保存していると思いますけど」と供述している。他方,原告が原告代理人あてに送信した本件催告書については,パソコンで作成したと供述するものの,そのデータの保存はない。 (カ)原告ないし読売新聞西部本社と被告との法的紛争については,原告代理人に一切を委任していた。しかし,本件催告書については,原告が作成した。また,原告自身が法的紛争に関連して,催告書を作成したのは,本件催告書のみであった。 イ 原告の供述に対する評価原告の上記供述の内容,すなわち,原告は,平成19年12月21日,被告サイトに本件回答書が掲載されていることを発見したため,原告代理人に対し,その対処方法について相談し,著作権侵害を理由として本件催告書を送信することの示唆を受けて,原告が本件催告書の作成を開始し,これを原告代理人に対しメールによって送信し,原告代理人から末尾のみ修正を受けて,これを被告に対して送信したという供述内容は,原判決の第3「当裁判所の判断」1(1)イ(ア)ないし(エ)(上記再掲部分)等に記載したとおり,極めて不自然である。すなわち,?@原告の著作権法や法的紛争の解決に関する知識経験の程度,?A読売新聞西部本社と販売店経営者との法的紛争の重要性に関する同社の認識の程度等,?B原告及び原告代理人のいずれからも,本件催告書作成過程を示す客観的なデータが提出されていないこと等に照らすならば,本件催告書は,原告から相談を受けた,原告代理人事務所において,本件催告書を作成し,そのデータをメールに添付する方法により,原告に送信し,これを受信した原告が,被告に対して送信したものと認定することによって,辻褄が合うといえる。 ウ原告は,原告が自ら執筆していないのに,あえて事実と異なる主張をして,争点を増やす動機は存在しないなどと主張する。しかし,読売新聞西部本社又は原告代理人が被告に対して訴えを提起した際に生ずる影響等を考慮して,原告が本件催告書を作成したこととして訴えを提起することに,動機がないわけではない。原告の主張は採用の限りでない。 エ原告は,「代理人催告書」と「本件催告書」とを対比すると,「代理人催告書」は公表権及び複製権を根拠とするのに対し,「本件催告書」は公表権のみを根拠としている点で相違するから,両書面の作成者は異なるなどと主張する。 しかし,「代理人催告書」と「本件催告書」は,いずれも,?@冒頭に「冠省」,末尾に「不一」との,やや特異な語を使用している点,?A文章の構成が酷似している点,?B一行の文字数が同一であること,?B著作者人格権についても「専有」という独特の語を使用している点等を総合考慮すると,「代理人催告書」と「本件催告書」は,同一の作成者に係る書面であると推認される。 原告主張の上記相違点をもって,本件催告書が,原告代理人事務所において作成されたのではなく,原告において作成されたと認める根拠とすることはできない。 2 結論その他,原告は,縷々主張するが,いずれも理由がない。以上によれば,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 |
| 裁判長裁判官 | 飯村敏明 |
|---|---|
| 裁判官 | 大須賀滋 |
| 裁判官 | 齊木教朗 |