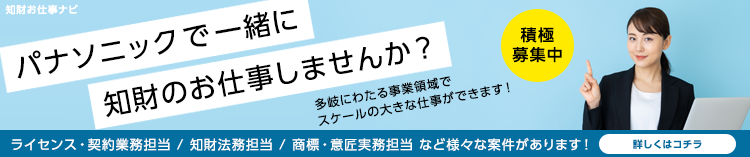| 関連ワード | 著作者 / アイデア / 言語の著作物 / 複製物 / 同一性 / 共同著作物 / 録音 / 再生 / 著作者人格権 / 複製権 / 引用 / 差止 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|
| 事件 |
平成
2年
(ワ)
2177号
|
|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 1992/08/27 |
| 権利種別 | 著作権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
一 原告らが、別紙書籍目録記載の書籍一章冒頭から二章八九頁五行目までの文章の著作権の共有持分二分の一を共有することを確認する。 二 被告株式会社祥文社は、別紙書籍目録記載の書籍を出版してはならない。 三 原告らのその余の請求を棄却する。 四 訴訟費用は、これを二分し、その一を原告らの負担とし、その余を被告らの負担とする。 五 この判決の第二項は仮に執行することができる。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
請求の趣旨
一 原告らが、別紙書籍目録記載の書籍一章から三章までの文章の著作権を共有することを確認する。 二 被告らは、別紙書籍目録記載の書籍を出版頒布してはならない。 |
|
|
事案の概要
一 著作物 別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)一章から三章までの文章(以下「本件著作物」という。)は、思想及び感情を創作的に表現したものであって、文芸の範囲に属する、言語の著作物である。(甲一)二 原告ら 原告【A】は亡【B】(以下「【B】」という。)の父、原告【C】(以下「原告【C】」という。)は【B】の母であり、【B】は昭和六三年一〇月二九日に死亡した(争いがない。)。【B】には子及び配偶者がなかった(被告【D】本人、 原告【C】本人)から、原告らが【B】の相続人であり、その相続分は各二分の一である。 三 被告らの行為 被告【D】(以下「被告【D】」という。)は被告株式会社祥文社(以下「被告会社」という。)に対し自己を著者として本件書籍を出版することを許諾し、被告会社は平成二年一月頃本件書籍を出版し、書店での販売を開始した(争いがない。)。 被告らは、本件著作物の著作者は被告【D】であると主張して、原告らが著作権を有することを争っている。 四 原告らの請求の概要 本件著作物の著作者は【B】であり、原告らが相続により本件著作物についての著作権を承継取得したとして、被告らに対して、原告らが本件著作物についての著作権を共有することの確認を求めるとともに、右著作権に基づいて本件書籍の出版頒布の停止を請求。 五 争点1 本件著作物の著作者は【B】か被告【D】か。 (原告らの主張) 本件著作物の著作者は【B】である。本件書籍で九〇頁位までの部分の文章は、 当初は【B】が自ら原稿を執筆し、その後は【B】がテープに吹き込んだ後被告【D】がそれを文章化したものを【B】が点検し了承して完成させたものである。 同頁位以降の部分は、一部は【B】が吹き込んだテープに基づき【B】の死後被告【D】が文章化したものであり、その余の部分も、被告【D】が【B】が所持していた資料やテープ等に基づいて執筆したものであるが、一般通常人の出版については出版社がかなり自由に文章化するのが通例であるから、その場合は素材となるものを作成すれば完成した文章の著作者ということができ、【B】は右部分についても素材をはるかに越えるものを提供しているから著作者というべきである。 仮に【B】が単独で本件著作物を創作したものと認められないとしても、少なくとも、本件著作物は【B】と被告【D】を著作者とする共同著作物である。 (被告らの主張) 初め、本件著作物中、本件書籍で二割程度の部分は、【B】が口述を録音テープに吹き込んだものを被告【D】が文章化し、【B】が検討して最終仕上げをし、両者が共同して創作したものであって、両者を著作者とする共同著作物であることを認めたが、それは真実に反する陳述で錯誤に基づいてしたものであるから、その自白を撤回し、【B】が本件著作物の全部又は一部の単独ないし共同の著作者であることは否認する(右自白の撤回につき、原告らは同意しない)。 本件著作物は全て被告【D】が単独で創作したものである。しからずとしても、 多くとも本件書籍の本文九〇頁前後までの文章のみが【B】と被告【D】を著作者とする共同著作物であるにすぎない。 すなわち、本件著作物を文章化する作業は全部当初から被告【D】が行っており、本件書籍の四〇頁までは、【B】の口述を録音したテープをもとにしてはいるが、被告【D】が文章構成、文体を考慮しながら文章化したもので、録音テープに収録された【B】の口述と本件著作物とではその文章構成、表現の豊かさに格段の相違がある。そして、【B】が若干でも関与したのは、 被告【D】が【B】と相談して執筆した部分を含めても、本件書籍の本文九〇頁前後までであり、それ以降の部分は被告【D】が資料や記憶に基づいて執筆したものであり、【B】の関与部分は全くない。 2 本件著作物の全部又は一部が【B】と被告【D】を著作者とする共同著作物である場合、【B】が被告【D】にその著作権共有持分を譲渡したか。 (被告らの主張) 【B】は、意識を回復した昭和六二年九月中旬、被告【D】から本件著作物の執筆の進行状況の報告を受けた際、その著作の完成及び出版を希求し、著作の完成のために共同著作部分についての自己の著作権共有持分を被告【D】に譲渡した。したがって、原告らが【B】の著作権共有持分を相続する余地はない。 3 本件著作物の全部又は一部が【B】と被告【D】を著作者とする共同著作物である場合、原告らは被告会社に対し本件書籍の出版停止を求め得ないか。 (被告会社の主張)(一) 【B】は、被告会社の出版依頼に応じて本件著作物を創作したものであり、生前、被告会社がその出版をすることを当然のこととして許諾していた。 (二) 本件著作物の一部が【B】と被告【D】を著作者とする共同著作物であるとしても、【B】自身において、被告会社が本件著作物を出版することを望み、被告会社の依頼に応じてテープに口述を録音したり、アイデア、素材を被告【D】に提供したりして、出版を前提とした創作活動に寄与貢献していたのであるから、原告らが被告会社に対し本件著作物の出版停止を求めることは信義に反する。著作権法64条2項は、共同著作物の各著作者は、信義に反して著作者人格権の行使に関する合意の成立を妨げることができない旨、また、同法65条3項は、共有著作権の各共有者は、正当な理由がない限り、共有著作権の行使に関する合意の成立を妨げることができない旨、規定しているから、結局、原告らは、被告会社の出版公表を妨げることは許されない。しかも共同著作物の著作者人格権の行使は共同著作者が死亡した場合は残る生存共同著作者が行使しうるものである。 また、同法60条は、「……著作者が存しなくなった後においても、 著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。」と規定しているところ、本件著作物は、【B】が積極的に被告会社の出版依頼に応じ、被告会社が本件著作物を出版することを期待して創作活動をしていたもので、被告会社が本件著作物を含む本件書籍を出版することは【B】の意思に合致するものであるから、原告らが被告会社に対しその出版停止を求めることは許されない。 |
|
|
争点に対する判断等
一 争点1(著作者)について1 (事実関係) 証拠(甲一、二〔被告会社が大阪大学【E】教授を通じて原告等に提示した、被告会社保管の原稿のコピーとして〕、三~九、一一、乙一〔被告会社保管の原稿のコピーとして〕、二の1、2、三~七、証人【F】、被告【D】本人、原告【C】本人)及び弁論の全趣旨を総合考慮すると、本件著作物が創作された経緯に関して、次の事実が認められる。 (一) 【B】は、昭和五八年九月一四日に突然吐血したことから重篤な肝硬変に罹患していることが判明し、その後、昭和六二年八月に英国において肝臓移植手術を受け、その手術は成功した。 (二) 被告【D】は、【B】と高校在学当時の同級生で、昭和五九年二月に入院中の【B】を見舞ったことを契機に【B】と交際を続け、昭和六〇年一二月頃には結婚することを約し、昭和六一年二月に【B】の病状が悪化した後は病院に通って看病を続け、昭和六一年四月からは入院中の【B】の留守宅に居住するようになった。更に、【B】が昭和六二年七月から一一月まで肝臓移植手術を受けるために英国に渡航した際も同行して【B】の看病にあたり、一一月に一緒に帰国した後は、 【B】と同居していた。 (三) 被告会社代表者【G】及び企画営業担当者【F】は、【B】が肝臓移植手術を受け成功したとマスコミに広く報道された後の昭和六三年五月二〇日に、 【B】が肝臓移植を受けた体験を一般読者にも分かりやすい読み物として書籍にまとめて出版したい旨を記載した企画趣意書を【B】に提示して、 その体験を文章化して出版することを働き掛け、【B】は、これを応じて、完成した際には被告会社に出版を許諾する予定で自らの体験を記した文章を執筆することを承諾した。 しかしながら、【B】は、被告【D】と相談して、自ら執筆することにより過度な肉体的疲労やストレスを招来することを避けるため、被告【D】も【B】と多くの体験を共にしていることから、まず【B】の口述をカセットテープに録音し、その後被告【D】がこのテープの再生を聞いてそれを文章化する方法で原稿を作成することにした。 (四) 【B】は、昭和六三年六月初め頃から、吐血した昭和五八年九月一四日以降【B】と被告【D】が結婚を約した昭和六〇年一二月頃までの出来事を、口述してカセットテープに録音した。被告【D】はこのテープをもとに文章化したが、その具体的方法は、パーソナルコンピューターでワープロソフトを用いて、まず、ほぼ【B】の口述したとおりの文章を入力したうえで、文章構成、文体を考慮しながら、重複する部分を削除し、【B】に、趣旨の不明な部分を聞き質して読者に分るよう書き改めたり、その時どのような気持ちであったか等の詳細や、他に読者が興味を惹かれるような出来事が無かったかなどを尋ね、その結果を自分なりに取捨選択して文章を補充訂正し、文章として完成させた。【B】は、そのようにして作成された文章を点検のうえ補充訂正した。 (なお、原告らは、当初は【B】が自ら原稿を執筆していた旨主張するが、右主張事実を認めるに足りる証拠はない。)(五) その後【B】は、昭和六〇年一二月末頃以降の部分については口述してカセットテープに録音することをしなくなり、【B】が書いて欲しい事柄を口頭で被告【D】に伝え、被告【D】が、その【B】の指示に基づいて、【B】が明確に伝えた事柄とそれから推測される【B】が書きたいと思っているであろう事柄に関して、【B】と行動を共にした際の自らの体験や、それまでに【B】から聞いて記憶している事実関係を基礎に自由に作文を進め、それだけではできないときには、 【B】に具体的状況や気持ちを聞き質し補充しながら文章を作成した。【B】はそのようにして被告【D】が作成した文章を点検し、 削除や補充訂正をした。 少なくとも、本件著作物のうち、本件書籍二章冒頭から八九頁五行目までの文章の原稿はこのような方法で作成された。 右部分までの原稿は、八月四日までの間に数回に分けて、フロッピィディスクに保存した状態で、【B】から被告会社に交付された。 (六) ところが【B】は、突然罹患した重症の感染症が発症して昭和六三年八月一五日に入院し、同年一〇月二九日に死亡したため、【B】の本件著作物創作への関与はその段階で中断した。 (七) 被告【D】は、【B】の死後に被告会社から執筆の継続、完成を勧められて、一一月末頃から、右以降の部分の執筆を開始したが、その際には、自己の記憶や、英国滞在中に書いた自分の日記の他、【B】が生前に作成した文章で出版され、あるいはメモとして残っていて、手元にあったものを参考とし、【B】に関する部分はできるだけ【B】の意思に沿うように心掛けて執筆した。右参考にした文章には、①「中央公論」昭和六三年三月号掲載の「他国の肝臓移植で救われた医師として」と題する【B】の手記、②そこから転載した「阪大第二外科同窓会々誌」二四号掲載の手記及び③昭和六二年一一月二六日に【B】が行った講演内容を収録した「SSKO胆道閉鎖症の子供を守る会No.63付録」に掲載の講演録の、全部又は一部或いはそれらの原稿、④「科学朝日」一九八八年一一月号に掲載された「患者として肝臓移植を受けて」と題する【B】の手記及び【B】が本件著作物の一部とする意図で書いた英国に渡航した際の状況についての原稿が含まれており、 特に、本件書籍一三六頁一二行目の「同じ医師の中にも」から一三七頁七行目までの部分は、②二七頁一二行目から一七行目、二八頁九行目から一三行目及び③五頁の記述と類似しており、本件書籍一八七頁の末尾から二行目から一八八頁一行目の部分は、②冒頭の記述、③二頁末尾から七行目ないし五行目の記述及び④四〇頁左欄末尾から七行目ないし一行目の記述と類似しているが、【B】が作成した文章をそのまま引用したと認められる部分は存しない。被告【D】は、 そのようにして作成した本件著作物の原稿及び本件書籍中の本件著作物以外の部分(「四章」及び「序にかえて」)の原稿をフロッピィディスクに保存した状態で被告会社に交付した。 (八) 被告会社の担当者は、右各原稿の文章について、例えば、「『肝硬変と診断されたからといって、全ての人間が十年以内に死ぬんと違うんや。生き続けてる人かているんや。』と私は彼女に言った。」という文章(乙一、二四枚目)を、 『肝硬変と診断されたからといって、全ての人間が十年以内に死ぬんと違うんや。 生き続けてる人かているんや。』私は彼女にそう言った。」(本件書籍三八頁)と変更したり、「もう一度念をおして『いいのか?』と聞きなおした。すると涙をためながら、『あなたが死ぬとき、私も一緒に死ぬ』と、言ってくれた。」との文章(乙一、二五枚目)を「『いいのか?』『あなたが死ぬとき、私も一緒に死ぬ』もう一度念をおして聞き直すと、彼女は目に涙をためながらそう言ってくれた。」(本件書籍三九頁)とするなど、言葉の引用の仕方を変更した他、一部を削除し、 一部の表現を簡潔にしたり修辞的文句を付加する等の変更を加えたうえ、小見出しを付加し、それらの変更につき被告【D】の了解を得たうえで、本件書籍を出版した。 2 (判断)(一) 以上によれば、本件著作物のうち、本件書籍一章冒頭から末尾(同書籍四〇頁目)まで(以下「A部分」という。)の文章については、被告【D】も、単なる補助者としての関与にとどまらず、自らの創意を働かせて創作に従事していたと認められ、他方、【B】もまた、単に被告【D】の創作のためのヒントやテーマを与えたという程度にとどまらず、その創作に従事していたと認めることができるから、この部分は、【B】と被告【D】が共同して創作した著作物であって、各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものであると認めるのが相当である。なお、被告会社の担当者もこの部分の文章に若干の加工を加えているが、その態様は、【B】と被告【D】が共同で作成した著作の同一性を害しない程度のものであるから、 右部分が【B】と被告【D】を著作者とする共同著作物であるとの右認定に影響を及ぼすことはない。 次に、本件著作物のうち、本件書籍二章冒頭から八九頁五行目まで(以下「B部分」という。)の文章については、【B】が具体的に口述して被告【D】に記録させた部分は【B】が創作したと認めるべきであり、【B】が抽象的に書いて欲しい事柄を指示しただけで文章表現は被告【D】が自分で考えた部分や、【B】の明示の指示はなかったが【B】の意思を推測して被告【D】が自由に書いた部分は被告【D】が創作したというべきであり、被告【D】が書いた文章を【B】が点検して補充訂正した部分は両名が共同して創作したというべきであるが、B部分のうちのどの文章で【B】と被告【D】のどちらがどれだけ創意を働かせたかは具体的には明らかでなく、その関与の態様毎に明確に区分することはできないから、結局、B部分全体が【B】と被告【D】が共同して創作したものであって、各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものであると認めるのが相当であり、被告会社担当者の関与に関してはA部分についてと同様であるから、B部分も【B】と被告【D】を著作者とする共同著作物に該当するというべきである。 そうすると、被告らの自白が真実に反するとは認められないことになるから、被告らの自白の撤回は許されず、結局、本件書籍一章冒頭から五〇頁(本文の二割弱にあたる)までの文章は【B】と被告【D】を著作者とする共同著作物であることに争いがなく、五一頁から八九頁五行目までの文章は、【B】と被告【D】を著作者とする共同著作物であると認定することになる。 (二) 本件著作物のうち、A及びB部分を除く本件書籍二章八九頁六行目から三章末尾まで(以下「C部分」という。)の文章については、【B】が、単独では勿論、被告【D】と共同ででも、これを創作したと認めるに足りる証拠はない。なお、被告【D】は、同部分を執筆するにあたり、【B】が生前に作成した文章を参考にしており、一部には【B】作成の文章中の記述と類似する記述も存するが、 【B】が生前に作成した文章をそのまま引用しているわけではなく、 被告【D】が【B】の死後に新たに作成したものであって、【B】は作成に関与していないから、【B】がC部分の文章を共同して創作したとはいえない(類似の部分が【B】の著作物の複製権侵害となるか否かの問題は別論である。)。 また、A部分は、昭和五八年九月の吐血から昭和六〇年一二月頃に【B】と被告【D】が結婚同居を約するに至るまでの出来事を記したもの、B部分は昭和六〇年一二月三〇日の病状の悪化から、昭和六一年七月末頃までの入院中の病院における出来事を記したもの、C部分は、同年八月頃以降の、病院における出来事や、渡英及び英国における手術を経て昭和六二年一一月に帰国するまでの出来事を記したものであって、連続する事柄を記したものではあるが、それぞれにまとまりを有する文章であり、分離しても個別的に利用することが可能であると認められる(甲一)ので、AB部分の文章とC部分の文章が全体として【B】と被告【D】を著作者とする共同著作物にあたると認めることはできない。 (三) したがって、【B】は、被告【D】とAB部分の文章の著作権を共有(その割合は民法250条により二分の一と推定される。)していた。 二 争点2(【B】が被告【D】に自己の共有持分を譲渡したか)について1 【B】は、昭和六二年九月中旬に意識を回復した際に被告ら主張の如き意思表示をなしうる状態になかったことが明らかであり(被告【D】本人)、著作権の共有持分を譲渡した事実を認めるに足りる証拠はない。 2 したがって、【B】は、死亡当時、AB部分の文章の著作権の共有持分二分の一を有しており、原告らは【B】の相続人として【B】の右共有持分を【B】から相続により承継取得したというべきである。 三 争点3(被告会社に対する差止請求の当否)等について1 被告会社の主張(一)(【B】が被告会社に出版を許諾したか)について 【B】が、被告会社に出版を許諾する予定で被告【D】とともにAB部分を執筆し、被告会社に原稿を交付したことは前記判示のとおりであるが、【B】が被告会社に出版を許諾した事実を認めるに足りる証拠はない。 2 被告会社の主張(二)(著作権法64条2項等に基づく主張)について 被告会社の主張(二)の趣旨は明らかでないが、本件請求は、著作権に基づくものであることが明示されており、著作者人格権に基づき、あるいは著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護としてなされているものではない。そして、 著作権は著作者人格権とは別個の財産権であるから、著作権法64条2項の規定が存し、被告【D】が著作者人格権を有するからといって、財産権としての著作権を有する原告らが著作権を侵害する者に対してその侵害の停止を請求することが制限される理由はなく、同様に、同法60条を根拠とする主張も理由がない。 また、被告会社は、著作権法65条3項を根拠に、原告らは、被告会社の本件書籍の出版を差し止めるべき正当な理由がないから、差止請求には法的根拠がない旨主張するが、同条二項は、共有著作権はその共有者全員の合意によらなければ行使することができない旨定め、三項で、各共有者は正当な理由がない限り共有著作権行使の合意の成立を妨げることができない旨規定するものであり、一部の共有者が合意を拒む場合に、それに正当な理由がないと他の共有者が判断すれば、他の共有者のみで著作権を行使しうるとの効果が同項の規定から生じるとは解されない。しかも、本件においては、【B】が、被告会社に出版を許諾する予定で被告【D】とともにAB部分を執筆し、被告会社に原稿を交付したとはいうものの、【B】及び被告会社の双方とも、右部分のみを出版することはなく、右部分は出版予定の著作物の半分にも達していない小部分であると認識していたことは明白であり、また、 【B】は、自分がこのように突然に再び発病して短期間のうちに死に至ること、この突然の再発病及び死を契機に【B】の両親と被告【D】との間に決定的な感情的断絶が生じること、自分の死後被告【D】が【B】及びその両親が全く関与しない文章を執筆し右部分の後部に結合して一体のものとし、【B】の両親の猛反対を無視して、それも被告【D】の著作物として、出版されることは全く予想していなかったことは明らかであるうえ、被告【D】は、 右部分についても自己のみが著作権者であると主張し、【B】が右部分の共同著作者であること及び原告らが右部分につき著作権の共有持分を相続したことを認めず、同条二項所定の合意成立のための協議を求めることすらせず、勝手に単独で被告会社に出版を許諾しており、原告らが被告会社に出版停止を求めた際にも、何ら合意成立のための努力をしていない(被告【D】本人、原告【C】本人)のであるから、原告らには共有著作権行使についての合意を拒む正当な理由があるといえる。 したがって、被告会社の右主張はいずれも採用できない。 3 AB部分は本件書籍の一部(約三割)であるが、同部分はその余の部分と一体に一冊の書籍となっており、両部分は不可分であるから、AB部分に対する侵害の停止として、本件書籍の出版の停止を求めうると解される。 したがって、原告らの出版等差止請求のうち、被告会社に対して出版の停止を求める部分は理由がある。なお、原告らは「出版頒布」の停止を求めているが、出版とは、著作物を文書又は図画として複製し、その複製物を刊行物として発売・頒布することを意味するから、出版の停止には頒布の停止が含まれ、頒布の停止を重ねて求める理由はない。 4 被告【D】は、被告会社に出版を許諾しただけであって、自ら複製ないし頒布しているわけではなく、その予定があるとも認められないから、原告らの出版等差止請求のうち、被告【D】に対する請求は理由がない。 |
| 裁判官 | 庵前重和 |
|---|---|
| 裁判官 | 小澤一郎 |
| 裁判官 | 辻川靖夫 |