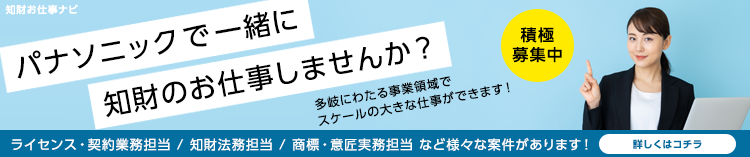| 関連ワード | 著作者 / 地図 / 同一性 / 著作者人格権 / 同一性保持権 / 複製権 / 引用 / 出版権 / 損害賠償 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 事件 |
昭和
61年
(ワ)
2867号
|
|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 1990/11/16 |
| 権利種別 | 著作権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
一 被告は、原告に対し、三〇万円及びこれに対する昭和六一年三月二八日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。 二 原告のその余の請求を棄却する。 三 訴訟費用は、これを一〇分し、その一を被告、その余を原告の各負担とする。 四 この判決は、原告勝訴部分に限り仮に執行することができる。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨1 被告は、原告に対し、二五〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。 2 被告は、その費用をもって、原告のために、訴外株式会社朝日新聞社東京本社発行の朝日新聞全国版朝刊社会面広告欄に、二段抜き、幅五センチメートルの大きさで、別紙記載の謝罪広告を一回掲載せよ。 3 訴訟費用は、被告の負担とする。 4 仮執行の宣言二 請求の趣旨に対する答弁1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。 |
|
|
当事者の主張
一 請求の原因1 原告は、被告大学社会学部に入学し、昭和五四年四月に同学部応用経済学科三年に進級するとともに、同学部【A】教授のゼミナールに参加して農村社会学の研究を始め、同五六年三月に同学部を卒業し、同年一〇月に被告大学通信教育課程経済学部経済学科に編入し、引き続いて右【A】教授のゼミナールに参加して農村社会学の研究を続けた。 2 原告は、その研究の一つとして、昭和五七年九月ころまでの間に、自己の出身地である長野県南佐久郡<以下略>において社会調査をし、その調査に基づく研究を次の論文(以下「原告論文」という。)にまとめた。 主題「【A】先生追悼論文ー過疎地域青年のUターン行動と生活意識の変容」副題「長野県南佐久郡<以下略>における労働力還流現象」目次 八〇〇字詰原稿用紙 二枚本文 右同 三九枚添付資料 三通、二〇頁3 原告論文は、過疎という高度経済成長の過程で引き起こされた社会問題を実証主義的に研究したものであり、郷里である過疎地域から都市に転出し、再び戻ってきた青年層の「Uターン行動」と出郷から都市生活を経て現在に至るまでの生活意識を、調査、分析によってまとめあげた、独創性に溢れたものとして、研究者の間で高い評価を得た論文である。そして、原告論文は、昭和五七年度第五回被告大学懸賞論文選考において、周到な調査の中に筆者の情熱がひしひしと感じられる好論文と評価され、優秀賞が与えられた。 原告論文は、昭和五八年二月ころ、被告大学通信教育部の依頼により、同部の定期刊行誌「法政通信」同月号に掲載され、更に、同五九年一一月ころ、原告論文を要約した「過疎地域青年のUターン行動」が、全農林労組発行の雑誌「農村と都市をむすぶ」同月号に掲載された。 4 被告は、昭和五八年四月上旬ころ発売された被告発行の雑誌「法政」(以下「被告雑誌」という。)同年二・三月合併号(通算第三三〇号)に、原告論文を掲載して出版した(以下「本件出版」という。)。 5 被告は、本件出版に際し、別表記載のとおり、原告論文について、五三か所にわたり削除、変更等の改変を行った。 6 被告の右4の行為は、原告が原告論文について有する複製権を侵害するものであり、また、右5の行為は、原告が原告論文について有する同一性保持権を侵害するものである。 7 被告の右著作権及び著作者人格権侵害の行為は、いずれも被告の故意又は過失に基づくものである。 8 著作者侵害に基づく損害(一) 原告は、被告に対し、その著作権の行使について通常受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。 ところで、原告が著述した学術論文を定期刊行物に掲載させる際には、四〇〇字詰原稿用紙一枚当り最低二〇〇〇円の割合による金員をその対価として受領するのが通常であるところ、原告論文は、同原稿用紙に換算して一〇〇枚分に相当するから、原告がその著作権の行使について通常受けるべき金銭の額に相当する額は、二〇万円である。 (二) 原告は、過疎地域の問題を一生の研究課題と自覚し、大きな情熱をもって取り組んでいたものである。そして、原告論文は、長い間暖めてきた企画を少なからぬ資力、労力を投入して実現した成果であり、原告にとって、極めて愛着の深いものであった。原告は、被告による本件出版により、右のような原告論文の利用を何人にいかなる条件で許諾するかを決定する自由という人格的利益を侵害されたものであって、かかる侵害行為によって原告が被った精神的損害に対する慰謝料は、 三〇万円が相当である。 9 著作者人格権侵害に基づく損害等(一) 被告による前記5の行為は、原告論文の同一性を破壊するばかりでなく、 その学問的価値を低下させ、原告の研究者としての名誉を傷つけるものであり、原告が原告論文に寄せる思いに泥水を掛けるものである。したがって、かかる著作者人格権侵害によって原告が被った精神的損害に対する慰謝料は、一五〇万円が相当である。 (二) 右同一性保持権侵害の行為は、原告の研究者としての知識及び能力に疑念を生じさせるようなものであり、かかる体裁の論文が原告の名前で公表されたことによって、原告の農村社会学の研究者としての社会的評価を毀損、下落させられたものである。そして、原告論文が掲載された被告雑誌の読者の大半は、全国に散在している。このような事情に鑑みると、毀損された原告の社会的評価を回復するためには、全国紙に謝罪広告を掲載することが必要である。 10 原告は、被告による原告の著作権及び著作者人格権を侵害した行為により、 本件訴えの提起を余儀なくされ、本件訴えの提起、追行のために弁護士を訴訟代理人に選任し、同代理人に対し、着手金二〇万円、成功報酬三〇万円の支払いを約した。 11 よって、原告は、被告に対し、著作権及び著作者人格権侵害に基づく損害賠償として、二五〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払い並びに請求の趣旨2記載の謝罪広告の掲載を求める。 二 請求の原因に対する認否請求の原因1ないし4の事実は認める。同5のうち、別表26を除き、別表記載のとおり表現の相違が存在することは認めるが、その余の事実は否認する。同6ないし9の事実は否認する。 同10の事実は知らない。 三 被告の主張1 被告雑誌及び被告大学懸賞論文について 被告雑誌は、被告大学の学生を対象に、学生教養の向上を目的として被告大学広報部が発行している学内誌であって、被告大学の教職員、学生等が執筆する論文、 報告、紀行文、講演録、座談会及び学内ニュース等で構成されている。一方、被告大学懸賞論文(以下単に「懸賞論文」ということもある。)の制度は、被告大学の学生の日頃の研さんの成果を発表する場を設けるために、昭和五三年度を第一回として始められたものであって、同年以降、毎年行われている。そして、被告大学の昭和五四年度学部長会議は、昭和五四年一二月一三日、第二回(同年度)法政大学懸賞論文の当選者の決定について協議し、その際、「優れた論文は公表し、論文に対する関心を喚起したい」との同論文審査委員会の意向の報告を受け、被告大学の「入学案内」や「学生生活の案内」にも同懸賞論文の制度を紹介すること及び被告雑誌に人文系、社会系各一編の論文を掲載することを決定した。その後、被告大学は、第二回(昭和五四年度)から第五回(同五七年度)までの間、いずれも優秀賞受賞論文各二篇を被告雑誌に掲載したが、原告論文は、右第五回の優秀賞受賞論文である。 2 原告論文掲載の適法性 原告は、被告大学懸賞論文の制度が始まって以来、第二回(昭和五四年度)及び第三回(同五五年度)の懸賞論文にも応募し、本件の第五回の懸賞論文の応募は三回目であり、そのうち第二回については優秀賞(ただし、被告雑誌には掲載されていない。)、第三回については努力賞を受賞している。このような経緯から考えて、原告は、被告大学懸賞論文の制度はもちろんのこと、少なくとも第三回の懸賞論文のとき以降は、優秀賞を受賞した論文は被告雑誌に掲載されることを了解したうえ、これに応募したものである。更に、被告大学は、原告に対し、昭和五八年一月八日付通知書で、原告論文が優秀賞を受賞したこと及びその受賞式、受賞祝賀会に招待する旨を知らせた。そして、原告は、同年一月二〇日に私学会館で行われた右受賞式に出席し、その際、 当時被告大学学務課員で懸賞論文事務担当者であった訴外【B】(以下「【B】」という。)から、原告論文が被告雑誌に掲載される旨知らされたが、これに対して何ら異議を述べることもなかったばかりか、本件出版を前提としている内容の同年二月一七日到達の手紙を被告大学あてに出している。 前記1の事実を前提にして右事実について考察すると、(一)被告大学懸賞論文の制度は、これに応募して提出された論文は、被告大学にその処置が委ねられ、被告大学の裁量により、いつでもこれを被告雑誌に掲載することができるものであるとの前提のもとに実施されているのであるから、これに応募した者は、その段階で、当該論文の著作者を被告大学に贈与し、出版権を設定し、又は出版を許諾したものと解され、原告は、このような趣旨で応募したものというべきであり、あるいは、(二)原告は、昭和五八年一月二〇日の第五回懸賞論文受賞祝賀会場において、原告論文を被告雑誌に掲載することを知らされ、これに何らの異議も留めずに聞き、これにより、被告に対し、原告論文の出版権を設定し又はその出版を許諾したのであり、あるいは、(三)原告は、被告大学に同年二月一七日到達の手紙により、被告に対し、原告論文について出版権を設定し又はその出版を許諾したものである。 3 原告論文の一部変更、削除の適法性(一) 被告大学が原告論文の表現の一部を変更し又は削除したことは、前記1に述べた被告大学懸賞論文の制度及び被告雑誌掲載の趣旨に合致するものである。すなわち、被告大学懸賞論文の制度は、被告大学の教育実践の一つとして行われるものであり、応募者は、自己の学習の結果である論文を教育者たる大学に提出し、教員の採点、批評、添削を受けることを予定してこれを執筆し、懸賞論文に応募するのであって、そのようにして提出された論文は、被告大学による添削、採点の結果、被告雑誌上で公表されるに当たって一定の変更、省略がなされることが当初から予定されているのである。したがって、右2の原告による被告雑誌への掲載の承諾には、被告大学の学生を対象とした一種の教材であり、かつ、大学の予算上の制約を免れ得ないという右雑誌の性格及び読者たる学生に論文執筆の範を示すという論文掲載の目的に照らし、相当の編集、校正を委ねる旨の意思表示も含まれているものと解すべきである。そして、被告大学は、かかる編集、校正の権限に基づき、 原告論文について、右の趣旨に応じた変更、削除をしたものである。 (二) 別表記載の削除、変更等は、以下の事情並びに前記1の被告雑誌の性質、 原告論文掲載の目的及び態様に照らし、やむを得ない変更であり、著作権法20条2項3号(昭和六〇年法律第六二号による改正前)によって適法とされるものである。 (1) 別表3、28、35、及び50について これらの変更は、「現われ」を「現れ」に、「表われ」を「表れ」に、「決って」を「決まって」に変更したものであるが、いずれも国語審議会昭和四七年六月答申の「改訂送り仮名の付け方」に基づいて、日本新聞協会の新聞用語懇談会が取り決めた方式に準拠して行ったものである。被告雑誌は、前記1の発行目的に沿うように、用字、用語については、広く一般に通用する用語法に則って表記しているのであり、原告論文も、他の記事と同様に、その意味内容に変更を来さない限りにおいて変更したものである。 (2) 別表2、4、7、10、13、14、18、19、30、34、44、45及び49について これらは、いずれも「…、等」とされている部分を「…等」として、「等」の前の読点を切除したものである。一般的に、事項を列挙する際、他を省略するために「等」の文字を用いる場合には、「等」の文字の直前に読点を入れていないことから、かかる一般的な用例に準拠して変更したものであり、右(1)と同様に、被告雑誌の発行目的に沿ったものとしてやむを得ないものである。 (3) 別表23、24、25、38、39、41及び42について これらは、「」・「」とされている部分を「」、「」として、中黒(・)を読点に変更したものである。これらのうち、別表23、24、25、38及び39については、原告作成原稿において、「」内にも更に中黒を使用しているため、「」と「」とを接続させるために中黒を用いると、読者において、「」内の中黒との混同を生じ、論述の内容に誤解を生じかねぬとの危惧から、これを明確に判別できるように、「」と「」を接続する中黒を読点に変更したものであり、別表41及び42は、右との表記上の統一を図るために行ったものであって、前記(1)と同様に、 被告雑誌の発行目的に沿ったものとしてやむを得ないものである。 (4) 別表26、27について 別表26についての原告作成原稿の記載は、同表原告論文欄の記載とは異なり、 同表雑誌「法政」の記載欄のとおりであるから、原告主張のような変更はない。別表27は、該当欄の数字のうち、27を28に、14を13に変更したものであるところ、この部分は、原告論文の表Ⅱー8の数値の合計欄の数字であり、同表記載の数値を合計すると、原告作成原稿の数値は明らかに誤りであるので、正しい合計数値に変更したものである。このように、明らかに誤りである事項をそのままにしておくことは、筆者本人の名誉を害することになり、被告雑誌の発行趣旨にも反することになるのであるから、この変更は、やむを得ないものである。 (5) 別表1、5、8、11、15、16、29、52及び53について これらは、目次(1)、あとがき中の日付及び「本調査を実施するにあたって相談に応じていただいただけでなく、推薦状まで書いて下さった【A】先生の御冥福を切に祈りながら。」という文(52)、原告論文の付録である調査票及び地図(53)並びに本文中の引用文言(5、8、11、15、16及び29)を削除したものである。 被告雑誌は、原則的には、三二頁ないし四〇頁で発行されていたものであり、原告論文を掲載した昭和五八年二・三月号は、懸賞論文を掲載し、更に、年度の最終号として多くの記事を掲載しなければならなかったため、特別に七六頁までの増頁を予定し、しかも、原告論文にはそのうちの三二頁を当てることになった。そもそも、被告は、第五回懸賞論文募集要項において、応募論文の枚数に関し、「B四版四〇〇字詰原稿用紙で四〇枚から六〇枚程度(図表、統計類を含む)」とその制限を示していたが、原告論文の原稿は、その制限を大きく超え、四〇〇字詰原稿用紙に換算すれば、目次四枚、本文七一枚、参考文献二枚、あとがき三枚、合計八〇枚のほかに、付録として、調査票(B五版用紙一八頁表紙付き)及び地図B四版用紙一枚を添付しているのであって、これらをすべて掲載することは不可能であった。 そこで、原告論文の内容面の優秀性に着目し、最大限の紙数を割き、次のような具体的な事情を考慮して、原告論文のうち、付属的な部分について、本文の論旨に影響を与えない限度で削除したものである。すなわち、まず、別表1の目次は、論述の内容とは別の独立した部分であり、原告論文中には詳細な小見出しが記載されていること、被告雑誌は原告論文を含む多くの論文や記事の集合体であって、巻頭に各標題が掲げてあることなどから考えて、削除することもやむを得ないものである。別表52は、懸賞論文制度の目的及び掲載の目的からすれば、必ずしも必要欠くべからざる部分ではないと思われる部分を削除したものであり、更に、原告の恩師に対する追悼の気持ちは、掲載した「あとがき」の中にも現れているので、この部分の削除はやむを得ないものである。別表53は、必ずしも論文の論旨に必要不可欠な要素の削除ではなく、また、この付録の部分は、分量的に本文に比して著しく過大となるのであるから、削除はやむを得ないものである。別表5、11、15、16及び29は、右53の削除に伴うものである。 (6) 別表20、22及び37について これらは、いずれも注記中での改行を行わず、文を連続させたものであるが、このような極めて短い文章では特に改行する必要がないと考えられ、更に、右(5)と同様に行数の削減になるところから行ったものであって、やむを得ないものである。 (7) 別表中、右(1)ないし(6)に述べたもの以外の部分は、いずれも単なる誤植である。 四 原告の反論1 被告の主張1及び2について 被告の主張1の事実は、認める。しかしながら、同2は、被告の一方的な主張であり、全く根拠のないものである。まず、被告による懸賞論文の募集要項には、応募論文の著作権の帰属等については何ら触れるところがなく、応募論文がどのように利用されるかも明らかではない。仮に応募者による応募行為が著作権の移転、出版権の設定又は出版の許諾の意思表示と解すべきであるとすれば、これに先立つ募集行為には、応募論文の著作権の移転、出版権の設定又は出版の許諾についての被告からの申込み行為であると応募者に認識することができるような事実が含まれていなければならない。しかしながら、そのような行為は、全くないのであって、そうである以上、応募者である原告が、被告に対し、著作権の移転、出版権の設定又は出版の許諾をする意思で応募したものと解することはできない。また、原告が、 昭和五八年一月二〇日に行われた授賞式において、【B】から、原告論文を被告雑誌に掲載する旨を伝えられたとしても、原告を含めた出席者が飲酒中になされた雑談にすぎず、このような行為をもって被告が主張するような承諾等の意思表示であると解するのは相当ではない。更に、その後、原告が被告あてに送付した手紙は、 被告大学の通信教育部の職員に対するものであり、この職員は、懸賞論文や被告雑誌の発行とは無関係である。したがって、右の手紙をもって被告が主張するような承諾等の意思表示と見ることもできない。 2 被告の主張3について(一) 被告が被告の主張3(一)で主張することは、全く適法性の理由にはならない。すなわち、別表記載の各変更等は、何ら学術的、専門的知識を有しない被告大学広報部職員が、その主観的判断によって行ったものであって、教育活動とは無関係なものであるからである。 (二) 被告の主張3(二)は、以下のとおり、やむを得ないものとはいえず、理由がないものである。 (1) 被告の主張3(二)(1)について 送り仮名をどのように付けるかという点については様々な立場があり、執筆者がその中で一般の用語法とは異なっていることを意識しつつ、種々の理由からあえてこれと異なる用語法を用いることも多い。このような執筆者の立場を尊重せず、了解も得ない変更は、正当なものとはいえない。 (2) 同3(二)(2)について 事項列挙に続く「等」は、事項の省略又は補充の意味を有するが、先行する列挙事項は、「等」の内容に対して、これを例示若しくは代表する関係となる。その際、「A、B、C等」と表現した場合、「等」の内容を例示ないし代表するものが、A、B、Cすべてなのか、Cだけなのかは、必ずしも明らかにはならない。しかし、これを「A、B、C、等と表現すれば、A、B、Cがいずれも「等」の内容の例示あるいは代表であることが極めて明確となる。原告は、このような意味から、かかる表現を選択したものであり、この原告の意思に反する変更は、正当なものとはいえない。 (3) 同3(二)(3)について 被告が主張する部分については、原告作成原稿のとおりであったとしても、「」と「」を接続する中黒と「」内の中黒とは明確に区別することができるのであり、 読者が混同するおそれがあるとはいえないから、かかる変更は、正当なものとはいえない。 (4) 同3(二)(4)について 被告は、算術的誤りがあったので訂正したものであるというが、その誤りの原因については、何らの判断材料を有してはいなかったのであるから、訂正することは、不可能なはずである。被告が原告に校正の機会を与えていれば、真の訂正がなされることは極めて容易であったのであるから、これは、改ざんあるいは改ざんと同視しうるものであるというほかはない。 (5) 同3(二)(5)及び(6)について 削除等の理由として被告が主張するところは、いずれも被告の一方的な判断であり、しかも、原告論文に関する専門的知識を有する教員等が行ったものではなく、 被告雑誌の編集担当者が行ったものであり、正当なものとはいえない。 (6) 同3(二)(7)について これは、単なる誤植ではなく、原告に校正の機会を与えないまま本件出版を強行したことの結果であり、正当なものとはいえない。 |
|
|
証拠関係(省略)
理 由一 請求の原因1ないし4及び同5のうち、別表26を除き、別表記載のとおり表現の相違が存在することは当事者間に争いがない。なお、成立に争いがない乙第一二号証(原告論文(原告作成原稿)の表紙と二七頁部分)によれば、別表26に係る原告作成原稿の記載は、同表原告論文欄記載の内容ではなく、同表雑誌「法政」の記載の欄の内容と同様のものであることが認められ、そして、成立に争いがない甲第一号証(原告論文(原告作成原稿)の写し)によれば、原告が所持している原稿の写しの当該欄の記載は、別表原告論文(原告作成原稿)欄の記載と同様になるよう書換えられたものと認められる。以上認定の事実によれば、原告が被告大学に提出した原告論文の原稿の同表26に係る部分は、同表雑誌「法政」の記載欄記載のものであったと認められる。 二 右争いのない事実によれば、請求の原因4の被告の行為は、原告論文を複製したものというべきであるが、被告は、右複製は適法なものである旨主張するので、 この点について判断する。 1 被告雑誌及び被告大学懸賞論文に関する被告の主張1の事実は当事者間に争いがなく、右事実並びに成立に争いがない甲第五号証、乙第一号証の一、二、第二号証、第一〇号証の一ないし三、証人【B】の証言により真正に成立したものと認められる乙第三号証ないし第八号証及び証人【B】の証言を総合すれば、(一)原告は、第五回被告大学懸賞論文の募集に対し、原告論文を提出して応募したものであるところ、この募集要項は、昭和五七年五月二四日付で被告大学内において頒布されたものであり、その後の同六二年五月二七日付第一〇回懸賞論文募集要項には、 「優秀な論文は、委員会で審議のうえ、雑誌「法政」(二・三月合併号)に掲載する。」という記載があるのに対し、第五回の募集要項には、右のような趣旨の記載はなく、その他応募論文の著作権の帰属、出版等の利用に関する事項の記載は全くない、(二)原告が第五回懸賞論文に応募する以前の第四回までに、被告雑誌に掲載された応募論文は、第一回については無し、第二回ないし第四回は優秀賞受賞論文のうち各二篇であり、各回の優秀賞受賞論文は、第二回が一二篇、第三回が四篇、第四回が二篇であるところ、その間、原告は、第二回に応募して優秀賞を受賞し、続く第三回にも応募して努力賞を受賞しているが、いずれも、被告雑誌には掲載されていない、(三)第五回被告大学懸賞論文授賞式及び受賞祝賀会が昭和五八年一月二〇日に行われ、原告も、これに参加したが、その際、被告大学学務部学務課職員として、被告大学懸賞論文に関する事務を担当していた【B】が、原告に対し、優秀賞受賞論文である原告論文を被告雑誌の同年二・三月合併号に掲載することになった旨伝えたところ、原告は、これに対して異議を唱えるなど、特別の意思表示をしないまま、【B】と雑談を続けた、(四)原告は、同年二月一六日付消印の郵便をもって、被告大学通信教育部の訴外【C】あてに書簡を送ったが、これには「授賞式の時に、学務課の担当の方が、雑誌「法政」にも載せると言っておりましたので、正しい原稿を渡して下さるようにお願いいたします。」との記載がある、以上の事実が認められる。 2 右認定の事実によれば、被告は、第五回懸賞論文募集に当たって、応募者に対し、応募論文の著作権の帰属、出版等の利用に関する事項を何ら明らかにしていないのであるから、被告雑誌発行の趣旨及び被告大学懸賞論文の制度の趣旨が前記被告の主張1のとおりであるとしても、そのことから直ちに、応募者の応募行為が、 応募論文の著作権の贈与、出版権の設定又は出版の許諾等の意思表示に当たるものと認定することは困難である。また、原告は、右認定の応募歴、受賞歴を有しているから、第五回懸賞論文に応募する際には、もし、優秀賞を受賞すれば、自分の論文が被告雑誌に掲載されることもありうるといった程度の認識を有していたであろうことは認定しえないではないが、第四回懸賞論文までの優秀賞受賞論文のすべてが被告雑誌に掲載されたわけでもなく、原告自身、優秀賞を受賞しながら、被告雑誌に掲載されなかったという経験を有しているといった右認定の事実に照らすと、 原告の第五回懸賞論文の応募行為自体が、直ちに被告に対する著作権の贈与、出版権の設定又は出版の許諾の意思表示であると認定することも困難である。しかしながら、右1(三)認定の事実によれば、【B】が、原告に対し、原告論文を被告雑誌に掲載することになった旨伝えたという事実は、これをもって、被告大学懸賞論文の事務担当者が、被告に対し、原告論文の出版の許諾を求めた行為に当たると認定することができ、また、これに対する原告の態度は、右に対する黙示の承諾に当たると認定することができる。そして、右1(四)認定の事実は、原告の右承諾の意思を裏付けるものであるということができる。この点について、原告は、【B】との会話は、祝賀会での飲酒中になされた雑談にすぎないから、承諾の意思表示というようなものではない旨主張するが、仮に飲酒中の雑談であったとしても、飲酒中であったため、意思表示に瑕疵があったという事実についての主張立証はなく、 かえって、原告の意思表示が承諾の意思表示であることを裏付けるに足りる事実が認められるのであるから、原告の右主張は、採用することができない。なお、原告は、その本人尋問の結果中、前認定に反する供述をしているが、右供述は、前掲各証拠に照らし、たやすく採用することができない。 3 以上によれば、被告の本件出版は、原告の許諾に基づくものであるといわざるを得ないから、被告の許諾による出版である旨の主張は、理由がある。 三 請求の原因5の被告の行為について、原告は、その意に反する改変である旨主張し、これに対して、被告は、これを争い、被告の右行為は適法である旨主張するので、この点について判断する(別表26については、前一の認定のとおり、原告主張の事実は認められないから、以下においては、それ以外の点について判断する。)。 1 前掲甲第一号証、乙第一二号証、成立に争いがない甲第二号証、第四号証の一、二、乙第一三号証、証人【D】及び同【B】の各証言を総合すれば、(一)原告論文は、昭和五七年一二月初めころに行われた懸賞論文審査委員会において、優秀賞に決定され、同時に、これを被告雑誌の同五八年二・三月合併号に掲載することが決定された。そして、懸賞論文の事務担当部局である学務部学務課職員は、被告雑誌の編集、発行の事務を担当する広報部広報課職員に対し、その旨伝えるとともに、原告論文(原告作成原稿)の写し(原告において作成し、原稿の原本と共に被告大学あて提出されていたもの)を広報課に届けた、(二)広報課は、右被告雑誌の編集作業を始めたが、被告大学通信教育部事務局から、原告論文が右通信教育部の機関誌「法政通信」(同五八年二月一日発行)にも掲載される旨の連絡を受けたため、被告雑誌に掲載する原告論文のいわゆるゲラ起しは、右「法政通信」を基本に、これに前記原稿の写しを参照して行うこととし、同月下旬ころまでに、そのゲラ刷り原稿を作成した、(三)その後、広報課の担当者であった訴外【E】は、 校正作業のため、原告作成原稿の表紙に記載してあった原告の住居の電話番号に基づいて原告に連絡を取ろうとしたが、これが通じないでいたところ、通信教育部の担当者から、「原告から、原告論文を掲載する際に訂正してほしいと、訂正事項の連絡を受けている。」旨伝えられたので、広報課は、その訂正事項の内容に基づいて右ゲラ刷り原稿に訂正を加え、広報課としては、これによって、原告との連絡は付いたものと判断した、(四)そして、広報課は、その判断によって、被告雑誌に与えられた予算の範囲内において、原告論文に割り当てることのできる頁数に納まるように原告論文の一部を削除し、その表現の一部を変更して確定稿を作成し、これに基づいて、被告雑誌同年二・三月合併号を発行した、(五)広報課は、被告雑誌掲載記事の表記については、国語審議会答申準拠の日本新聞協会の「記者ハンドブック」に準拠して、送り仮名、句読点その他の記号を表し、常用漢字表の漢字を使用するといった原則を採用し、記事の専門性によって例外的な取扱いをすることもあったものの、原告論文については、右の原則的な取扱いによって表記の一部を変更した、(六)前記「法政通信」に掲載された原告論文においては、別表11、 12、17、27及び53に該当する部分については、被告雑誌と同様の削除、変更が行われているが、その余の部分については、原告作成原稿と同様のものとなっていた、以上の事実が認められる。 2 右認定の事実によれば、原告論文を審査し、これを被告雑誌に掲載する旨を決定した審査委員会は、原告論文の内容に対して添削等を加えることなく、事務担当者を通じ、被告雑誌の編集、発行の事務担当部局である広報部広報課に対し、原告作成原稿の写しをそのまま交付したものであり、別表記載の削除、変更等は、右広報課の担当者が、その判断によって、一般的な被告雑誌の表記の基準及び予算上の都合に基づいて行ったものである。してみると、右の削除、変更等は、懸賞論文の制度等の趣旨に沿った教育的な措置であると認めることはできない。したがって、 被告の行為が右のような措置であることを前提とする適法性に関する被告の主張3(一)は、その前提を欠き、理由がないものといわざるをえない。 3 そこで、次に、別表記載の削除、変更が、著作権法20条1項所定の著作者である原告の意に反する改変に当たるか、仮に右の改変に当たるとしても、同条二項三号(昭和六〇年法律第六二号による改正前)所定の改変として適法なものであるか否かについて判断する。 (一) 被告の主張3(二)(1)ないし(3)及び(6)の部分について これらの部分は、送り仮名、読点の使い方等の表記方法に関する変更や、改行の有無に関するものであるところ、別表雑誌「法政」の記載欄の当該部分の記載は、 いずれも、一般の表記方法として使用されているものであり、しかも、この変更によって原告論文の当該部分の意味内容に格別の違いが生ずるものとは認められず、 著作物の同一性を実質的に害するものとはいえない。また、前掲甲第一号証によれば、原告論文の該当部分の改行は、その前後の文章の内容に照らし、必ずしも必然性のあるものとは認められず、したがって、改行しなかったことは、著作物の同一性を害するようなものとはいえない。そして、かかる変更は、原告論文以外の被告雑誌の記事との表記の統一といった類のものであり、少なくとも、このような変更は、本件出版が原告論文のみを出版したものではなく、雑誌の中の一記事としての掲載であるという性質並びに前記利用の目的及び右変更自体の態様に照らしやむを得ないものと認めるのが相当である。この点に関して、原告は、右変更が適法でないとする理由をるる主張するが、原告の主張は、右認定判断に照らし、採用することができない。 (二) 同3(二)(4)の部分について この部分のうち、別表26の部分については前示のとおりであり、別表27の部分についての原告作成原稿である前掲乙第一二号証によれば、右の部分は、表Ⅱー8の数字の合計欄であることが認められるところ、同表の合計されるべき数字を見れば、原告作成原稿の当該部分の数字は、加算の誤りによる誤字であることが認められる。したがって、これを正しく加算した結果に基づいて補正することは、原告論文の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないものというべきである。この点について、原告は、被告は、算術的誤りの原因については、何らの判断材料も有していなかった旨主張するが、右の表Ⅱー8の記載自体から、補正が必要か否かの判断は可能であり、したがって、原告の右主張は、採用の限りでない。 (三) 同3(二)(5)の部分について 被告雑誌のこれらの部分は、いずれも原告論文の表現の一部分を削除したものである。前掲甲第一号証によれば、ここで削除された部分は、未削除部分とは、著作物として一体となっているものと認められるのであるから、そのこと自体、著作物である原告論文の同一性を害する改変に当たるものというほかはない。被告は、その削除の理由を主張するが、その主張するところは、被告雑誌の発行自体とは無関係の論文応募上の制限の問題であったり、あるいは、予算上の都合という専ら被告側の一方的な理由によるものであって、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないものであるとは認められないから、被告の右主張は、採用することができない。 (四) 同3(二)(7)の部分について いわゆる誤植の類については、印刷技術の制約などから生じるような誤植であり、しかも、誤植であることが明らかであって、これによって、その部分の意味内容が異なるものになるような場合でない限りは、同一性保持権を侵害する改変には当たらない、と解するのが相当である。そこで、被告が誤植であると主張する部分を見るに、別表9記載の部分は、「困民軍」を「困民党」にしたものであるところ、原告本人尋問の結果によれば、かかる変更は、歴史的な事実に基づく固有の名称を異なるものに変更したものであると認められ、その意味内容が異なるものになっていると認められるから、かかる変更は、著作物の同一性を害するものというべきであるが、その余の部分は、一見して誤植であることが明らかであり、当該表現の意味内容を異なるものにするものではないと認められるから、著作物の同一性を害するものとはいえない。 4 以上によれば、請求の原因5の被告の行為のうち、別表1、5、8、9、11、15、16、29、52及び53に関する部分については、原告が原告論文について有する同一性保持権を侵害したものというべきである。 四 右三1認定の事実によれば、被告の右著作者人格権侵害の行為は、少なくとも被告の過失によるものと認められるところ、右侵害行為の内容、その程度、右侵害行為によって原告論文の内容に及ぼした影響の度合い、原告論文が被告大学の懸賞論文に応募した論文であること、被告大学の学内誌であるという被告雑誌の性質及びその配布状況、原告と被告の関係その他本件記録上認められる諸般の事情を総合すると、被告の右行為によって原告が被った精神的損害に対する慰謝料は、二五万円をもって相当と認めるべきであるが、右損害の賠償のほかに、名誉若しくは声望を回復する措置として、原告の求めるような謝罪広告を掲載する必要性まであるとは認められない。また、右認容額、本件訴訟の内容その他の諸事情に鑑みると、原告の弁護士費用のうち、被告の右侵害行為と相当因果関係がある損害として被告の負担すべき金額は、五万円をもって相当と認められる。 五 以上によれば、原告の本訴請求は、著作者人格権侵害に基づく損害賠償請求のうち、三〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが本件記録上明らかな昭和六一年三月二八日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度において理由があるから、これを認容し、その余の請求は、理由がないから、これを棄却することとし、 訴訟費用の負担について民事訴訟法89条及び92条本文、仮執行の宣言について同法196条1項の各規定を適用して、主文のとおり判決する。 |
| 裁判官 | 房村精一 |
|---|---|
| 裁判官 | 三村量一 |
| 裁判官 | 若林辰繁 |