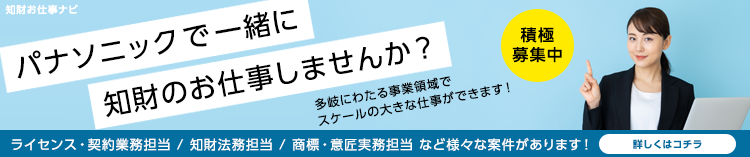| 関連ワード | 創作性 / 著作者 / 登録 / 差止 / 損害賠償 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|
| 事件 |
平成
2年
(ワ)
16372号
|
|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 1993/06/28 |
| 権利種別 | 著作権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
一 被告(反訴原告)らは、原告(反訴被告)に対し、各自金六九〇万円及び内金二〇〇万円に対する昭和六三年五月二六日から、内金二四〇万円に対する平成元年二月三日から、内金二五〇万円に対する平成元年二月二六日からそれぞれ支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 二 被告(反訴原告)らの反訴請求をいずれも棄却する。 三 訴訟費用は本訴反訴を通じ被告(反訴原告)らの負担とする。 四 この判決は第一、三項に限り仮に執行することができる。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
請求
一 本訴 主文一項同旨二 反訴1 原告(反訴被告。以下「原告」という。)は、被告(反訴原告。以下「被告」という。)らに対し、それぞれ金五〇〇万円及びこれに対する平成五年一月二七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 2 原告は、JAMICシステムの名称の使用、JAMICシステム・マスターカード、JAMICシステムに基づくあいうえお順及び製品別メーカーリストの各複製、販売、頒布をしてはならない。 3 原告は、被告らに対し、JAMICシステム・マスターカードを引き渡せ。 |
|
|
事案の概要
本件は、本訴で原告が被告らに対し、消費貸借契約及び保証契約に基づき、後記貸金(一)の元本残金二四〇万円及びこれに対する弁済期の後の日である平成元年二月三日から、後記貸金(二)の元本二五〇万円及びこれに対する最終弁済期の翌日である平成元年二月二六日から、後記貸金(三)の元本二〇〇万円及びこれに対する最終弁済期の翌日である昭和六三年五月二六日からそれぞれ支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求めたのに対し、反訴で被告らは、被告らは原告に対し被告らの考案した建築資材のカタログを分類して専用ボックスに収納するシステム(以下「JAMICシステム」という。)の使用を許諾したが、 無償での使用を許諾したことはないにもかかわらず、原告は使用料についての協議に応じず現在に至るまで無償で右システムを使用販売しているので、被告らは右使用許諾契約を解除し、 被告らのJAMICシステムについての人格権(右システムのうち一部については著作権)に基づき、JAMICシステムの使用販売を差し止め、不法行為に基づく損害賠償請求あるいは不当利得に基づく返還請求として昭和五九年から平成三年までの使用料相当額五九九五万二八〇〇円のうち一〇〇〇万円を反訴において請求し、また本訴請求に対して対当額で相殺した事案である。 一 争いのない事実など1(貸金一)(一) 原告は、昭和五九年七月三〇日、被告ら各自に対し、四〇〇万円を弁済期の定めなく貸し付けた。 (二) 原告は被告らに対し、昭和六〇年七月二五日までにはその返済を催告していた(被告【A】本人)。 2(貸金二)(一) 原告は、昭和五九年一二月一四日、被告【A】に対し、二五〇万円を昭和六〇年一月二五日から毎月二五日限り五万円宛返済するとの約定で貸し付けた(甲二)。 (二) 被告【B】は、昭和五九年一二月一四日、原告に対し、右(一)の債務を保証した(甲二)。 3(貸金三) 原告は、昭和六〇年一月二三日被告ら各自に対し、二〇〇万円を同年二月二五日より毎月二五日限り五万円宛返済するとの約定で貸し付けた(甲三)。 二 争点 被告ら主張のJAMICシステムについて被告らに人格権(あるいは一部については著作権)が認められるか(争点1)、被告らが原告に対しJAMICシステムの無償での使用を許諾していたか(争点2)が争点である。 |
|
|
争点に対する判断
一 争点1について1 証拠(乙一ないし五、一〇の1、2、一一ないし一四、一八、被告【A】本人)によれば次の事実が認められる。 (一) JAMICシステムは、工事分類項目索引を基本として工事分類項目別・五〇音分類別メーカーリストと専用ボックス(分類項目シール、分類ナンバーシール)により建材・設備資材カタログを分類整理するシステムである。 (二) 右システムの中核をなす工事分類項目索引の分類項目は、建設大臣官房の標準仕様による工事別分類に材料別、建物用途別を加味した分類項目に従って分類したものである(乙三)。 (三) 右分類項目索引については「JAMICシステム分類項目表」として被告らのために著作者の実名登録がなされている(乙一四)。 (四) 右工事分類項目別メーカーリスト(乙一二)は、右分類項目に各企業名を分類し、その電話番号を記載したものであり、五〇音分類別メーカーリスト(乙一一)は、各企業名を五〇音順に並べ、後記のボックス・ナンバーと右分類項目の該当項目を列記したものである。 (五) 右工事分類項目別・五〇音分類別メーカーリストを作成するために、工事分類項目別・五〇音分類別のマスターカードを作成している。 (六) カタログの整理保管のためにはファイルボックス様の専用ボックスを用い、これに右分類項目に沿った大項目、中項目のシールと分類ナンバー・シールを貼付している。 (七) 右システムにより、専門家でなくても膨大な量の建材・設備資材のカタログ等を整理保管することができ、また必要なカタログを容易に探すことができる。 2 右事実を総合すれば、右システムは全体として工夫されたものであり、商業的価値も存在するものと推認されるが、右システムの中核をなす分類項目自体は、前記のとおり、建設大臣官房の標準仕様による工事別分類を基礎としたものにすぎず創作性に乏しく、右分類項目に既存のファイルボックス等を組み合わせ機械的な労力さえ投入すれば、同様のシステムを完成することは容易であることからすると、 JAMICシステム全体について人格権(マスターカードや会社別、製品別メーカーリストについては著作権)が成立しているかは必ずしも明らかではない。 二 争点2について1 右システムについて被告らに人格権あるいは著作権が成立しているとしても、 次のとおり、原告は被告らの右権利を侵害しているものとはいえない。 2 すなわち、証拠(甲四、五、乙一、一三、一五、一六、一八、被告【A】本人)によると次の事実が認められる。 (一) 被告らは、昭和五六年四月ころから建材設備資材のカタログを収集し、分類項目やメーカー名簿の作成等を開始し、昭和五七年二月ころ、分類項目表を完成した。 (二) 被告らは、同年一一月一七日、 株式会社日本情報センターを設立し(以下「旧会社」という。)、同社の事業としてJAMICシステムの販売について設計事務所等への営業活動を開始したが、当初から事業資金が不足していた。 (三) 被告らは、昭和五八年一二月ころ、株式会社イチゼンの代表者【C】を通じて株式会社ヱスビーエンタープライズ(以下「ヱスビー」という。)に対し、旧会社への資金援助などの協力を求めた。ヱスビーとの話し合いでは、主に【C】が被告らの代理人として交渉していた。 (四) 昭和五九年六月ころ、右交渉の結果、ヱスビー、【C】、被告らとの間で、次の内容の合意が成立した。 (1) 東京都千代田区に建材のカタログや資材、情報の販売を目的とする株式会社日本情報センターという旧会社と同一名称の会社(原告)を設立する。 (2) 右会社の資本額は一〇〇〇万円とし、ヱスビーとのその関係者で五〇パーセント、【C】夫妻、被告ら、【D】で五〇パーセントの出資をする。 (3) 営業の実務は、被告らがこれまでの経験を生かし同人らの有する知識、情報の一切を駆使して当たる。 (4) 旧会社は本店を保谷市に移転し、商号も変更する。 (五) 右合意においては原告が旧会社の事業を引き継いでJAMICシステムの販売活動を続け、被告らは原告の株主となることが当然の前提となっており、被告らに対して原告が右システムの使用料を支払う旨の合意がなされたり、右システムの使用料の支払についての交渉がなされたりしたことはなかった。 (六) 原告は昭和五九年六月設立されたが、その株主構成は、前記出資額に応じヱスビーとのその関係者で一〇〇株、【C】夫妻が四〇株、被告ら、【D】で六〇株とされていた。被告らは【C】に交渉を一任していたところ、【C】が被告らの株券を所持していたが、結局、平成元年に【C】が破産した際に右株券も失われ、 被告らは原告の株主たる地位を主張できなくなった。 (七) 被告らはマスターカードなどを原告に持ち込み、原告の事業としてJAMICシステムの販売活動をしていたが、営業実績が上がらず原告は赤字であり、ヱスビーからの出向役員らとの経営方針の違いなどから、 被告【B】は昭和六〇年一〇月ころ原告を退社し、被告【A】も昭和六三年三月退社した。 3 以上の事実を総合すれば、原告は旧会社の事業を承継してJAMICシステムの販売活動を展開していくことが原告設立についての出資者間の当然の前提となっていたものであり、被告らが原告の株主であるかぎりは被告らは原告から株式配当の形で右システムの販売による利益の分配を受けることができたものが、被告らは【C】に交渉を一任していたために株券の引渡しを受けることができず、株主たる地位を失ってしまったために、被告らの当初の見込みとは異なる結果に至ったにすぎないものと認められるから、原告は設立当初から無償でJAMICシステムを使用することを許諾されていたものであって、被告らは右使用について使用料の支払や使用の差止めを請求しうる立場にはないものと認められる。 |
|
|
結論
よって、その余について判断するまでもなく、原告の本訴請求は理由があり、被告らの反訴請求は理由がない。 |