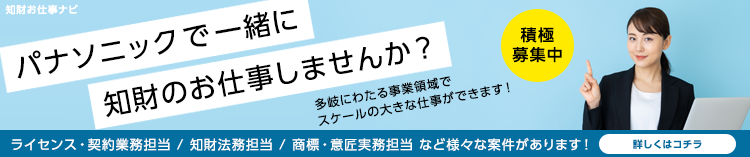この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
| 審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
|---|---|---|
| 平成15ワ12551損害賠償等請求事件 平成16ワ8021損害賠償等請求事件 | 判例 | 特許権 |
| 昭和60ワ4087 | 判例 | 特許権 |
| 平成3モ6310 | 判例 | 特許権 |
| 平成3ワ5651 | 判例 | 特許権 |
| 平成17ネ10049著作権侵害差止等請求控訴事件 | 判例 | 特許権 |
| 関連ワード | 著作物性 / 創作性 / 創作的表現 / 独自性 / 著作者 / アイデア / 表現方法 / 言語の著作物 / 二次的著作物 / 翻案 / 同一性 / 共同著作物 / 録音 / 録画 / 法人等の発意 / 法人等の業務 / 著作者人格権 / 氏名表示権 / 同一性保持権 / 複製権 / 著作権侵害 / 差止 / 損害賠償 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 事件 |
平成
7年
(ワ)
19455号
|
|---|---|
| 裁判所のデータが存在しません。 | |
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 1998/10/29 |
| 権利種別 | 著作権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
一 被告らは、別紙二「書籍目録」記載の書籍を複製し、頒布し、又は販売のための展示をしてはならない。 二 被告らは、別紙二「書籍目録」記載の書籍並びにその原稿、紙型及び版下を廃棄せよ。 三 被告らは、連帯して、原告株式会社主婦と生活社に対し金二九〇万円、同株式会社扶桑社に対し金一八万円、同株式会社学習研究社に対し金一八万円、同株式会社マガジンハウスに対し金一四〇万円及びこれらに対する平成七年六月一二日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 四 原告株式会社主婦と生活社、同株式会社扶桑社、同株式会社学習研究社及び同株式会社マガジンハウスのその余の請求をいずれも棄却する。 五 原告【A】、同【B】、同【C】、同【D】、同【E】及び同【F】の請求は、いずれもその全部を棄却する。 六 訴訟費用のうち、原告【A】、同【B】、同【C】、同【D】、同【E】及び同【F】と被告らの間に生じた部分は右原告らの連帯負担とし、原告株式会社主婦と生活社、同株式会社扶桑社、同株式会社学習研究社及び同株式会社マガジンハウスと被告らの間に生じた部分はこれを五分し、その二を右原告らの連帯負担とし、 その余を被告らの連帯負担とする。 七 この判決は、一項及び三項に限り、仮に執行することができる。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
原告らの請求
一 被告らは、別紙二「書籍目録」記載の書籍(以下「被告書籍」という。)を複製し、頒布し、又は販売のための展示をしてはならない。 二 被告らは、その所有する被告書籍並びにその原稿、紙型及び版下を廃棄せよ。 三 被告らは、朝日新聞、読売新聞及び毎日新聞に、別紙三「謝罪広告」記載の謝罪広告を、別紙四「掲載条件」記載の掲載条件で掲載せよ。 四 被告らは、連帯して、原告【A】に対し二三六万〇四九八円、原告【B】に対し一八二万〇一二〇円、原告【C】に対し一三九万四三六七円、原告【D】に対し二一三万九四三四円、原告【E】に対し二三〇万三一八五円、原告【F】に対し二四七万五一二四円、原告主婦と生活社に対し八三〇万三三〇〇円、原告扶桑社に対し一三七万六六二七円、原告学習研究社に対し一三八万四八一五円、原告マガジンハウスに対し三三一万七〇七八円及びこれらに対する平成七年六月一二日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 |
|
|
事案の概要
本件は、原告らが被告らに対し、被告らが出版し販売した被告書籍は、原告らが著作した雑誌の記事を複製又は翻案したものであり、原告らの著作権(複製権、翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)を侵害すると主張して、被告書籍の複製等の差止め及び廃棄、謝罪広告並びに損害賠償を求めている事案である。 一 争いのない事実等1 当事者(1) 原告個人らは、株式会社ジャニーズ事務所に所属する芸能人であって、 「SMAP」(スマップ)なる名称のグループを構成し、平成三年九月に芸能界にデビューして以降、グループ又は各人で、歌手、タレント又は俳優として、テレビ、ラジオ、舞台等への出演、コンサートの開催、コマーシャル出演等、各種マスメディアを通じての芸能活動を行っている。ただし、原告【D】は、平成八年ころ、同グループから離脱して芸能活動をやめた。 (2) 原告出版社らは、いずれも出版、書籍の発行等を業とする株式会社であり、原告主婦と生活社は雑誌「JUNON」を、原告扶桑社は雑誌「SPA!」を、原告学習研究社は雑誌「POTATO」を、原告マガジンハウスは雑誌「an・an」を、それぞれ発行している。 (3) 被告鹿砦社は、出版物の編集、発行等を業とする株式会社であり、被告【G】はその代表取締役である。 2 原告らの雑誌記事(甲二の1ないし17) 別紙五「原告記事目録」の「出版社」欄記載の各原告出版社らは、右目録の「記事の対象」欄記載の原告個人らに対するインタビュー等を内容とする記事(以下、 これらを一括して「原告記事」といい、各記事を右目録記載の番号により「原告記事①」などという。)を掲載した雑誌を発行した。原告記事中には、別紙六「対照表」の「原告記事」欄記載の記述がある。 3 被告書籍の発行 平成七年六月一二日、被告【G】は発行人、被告鹿砦社は発行所として、被告書籍を出版、発売した。被告書籍中には、別紙六「対照表」の「被告書籍」欄記載の記述がある。 4 被告書籍の販売による利益 被告書籍の定価は一部一〇〇〇円(消費税三パーセント込)、初版印刷部数は三万部であり、被告鹿砦社は、その販売により、収入額二〇〇九万七〇八七円(定価の六九パーセント相当の卸売価格から消費税を控除した金額)から、校正料その他の費用を差し引いた一五六〇万九一七一円の利益を得た。 二 争点及びこれに関する当事者の主張1 原告記事が著作物であるといえるか。 (一) 原告らの主張 原告記事は、原告個人らが、原告出版社らのインタビューに答えて、自分たちの少年時代、家族関係、芸能界に入ることになった経緯、芸能活動でのエピソード、 恋愛経験、女性観など私事にわたる様々な事柄を語り、右インタビューの中から、 原告出版社らが、雑誌のテーマ、想定する読者に与えるイメージといった判断基準及び編集者独自の感性を加味して話しの内容を選択し、構成し、表現したものであるから、その表現形式に原告らの個性、創作性が十分に表れている著作物である。 (二) 被告らの主張 原告記事は、その記事内容や、これが掲載された媒体が雑誌であるとの点に照らし、著作権法10条2項に規定する事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道というべきであり、著作権法上の著作物(著作権法2条1項1号、10条1項1号)に該当しない。 2 原告記事の著作権及び著作者人格権は誰に帰属するか。 (一) 原告らの主張(1) 原告出版社らは、企画、取材、執筆、編集、印刷、製本等の過程を経て原告記事を作成しており、その企画やテーマ、執筆者等を決めるのは原告出版社らの編集部である。執筆者は、編集部の指示に従って取材をし、記事を執筆するが、インタビューの内容を機械的に文書にするのではなく、企画やテーマに沿って記事に盛り込むエピソードを取捨選択して全体を構成し、要約、加筆、訂正をして原稿を作成するのであり、更に編集部において右原稿をチェックし、適宜修正を加えて記事を完成する。右のとおり、原告記事は、原告出版者らの発意に基づきその被用者によって執筆され、原告出版社らの著作名義で公表されたものであるから、著作権法15条1項により原告出版社らがその著作者である。 (2) 原告個人らは、取材に対してその思想感情を創作的に表現した具体的な発言をしており、原告記事の文章表現には、原告個人らの個性が端的に表れている。 したがって、原告個人らが原告記事の創作に従事したことは明らかであって、原告個人らもその著作者である。 (3) このように、原告記事は、原告個人らと原告出版社らが共同して創作に携わって製作されたものであり、各原告の寄与を分離して個別的に利用することが不可能なものであるから、原告出版社らと原告個人らは、原告記事を共同して著作した者としてその著作権を共有するものであって、原告記事につき著作権及び著作者人格権を有する。 (二) 被告らの主張(1) 原告記事が原告個人らに対するインタビューをもとに執筆、構成された記事であるとすると、原告出版社らは、あくまでインタビュー結果を正確に公開し、 伝達する役目を果たしたにすぎないから、原告出版社らの創作的表現を認めることはできない。したがって、原告出版社らは原告記事の著作者ではない。 (2) また、原告記事の著述自体につき原告個人らがいかなる方法、態様のもとに関与したのかは不明であり、原告個人らが原稿に目を通したりこれを補充訂正したりしたとは認められない。原告記事は、インタビュー記事の体裁をとっているものの、その実態は原告出版社らの創作に係るものというべきであり、その作成につき原告個人らの創作的活動としての関与は全くうかがえないから、原告個人らは著作者でない。 3 被告書籍の出版が原告記事の著作権及び著作者人格権を侵害することを理由として、原告らは出版の差止め等を求めることができるか。 (一) 原告らの主張 被告書籍の記述のうち別紙六「対照表」の「被告書籍」欄記載の部分は、その表現形式、文の構成、文意までもが、同対照表の「原告記事」欄の記載と酷似している。これらの記述は被告書籍全体の約六分の一に及び、しかも、被告書籍全体にまんべんなく存在している。被告らは、原告らに無断で原告記事を盗用し、切除、分断、付加等の変更を加えて被告書籍を作成し、しかも、これら盗用、改変部分について、著作者として原告らの氏名、名称を表示しないまま被告書籍を出版したのであって、右行為は、原告らの著作権(複製権、翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)の侵害に当たる。被告らは、原告記事を剽窃して原告らの創作意図と異なる内容に改変したり、原告記事をつなぎ合わせて一連の文章を作り上げたりしており(その詳細については、平成九年六月二七日付け原告ら準備書面(六)参照)、これにより原告らの同一性保持権は著しく侵害され、その精神的、 人格的利益を傷付けられた。被告らは、被告書籍が原告らの著作権及び著作者人格権を侵害する行為によって作成されたものであることを知りながらこれを頒布し、 販売のために展示している(著作権法113条1項2号)。よって、原告らは被告らに対し、著作権法112条に基づき、被告書籍の複製、頒布、販売のための展示の差止めを求めるとともに、被告書籍並びにその原稿、紙型及び版下の廃棄を求める。 なお、被告らは、本件において被告書籍の複製頒布行為の差止めを求める利益があることを争うが、被告書籍の在庫が販売されたり、増刷が行われたりする可能性があることや、被告らが本件訴訟係属中も次々と原告個人らに関する書籍を出版し、そのプライバシー侵害に及んでいるという状況に照らすと、差止めを求める利益は現存しているというべきである。 (二) 被告らの主張 被告書籍は、その執筆者の独自の取材と体験に基づいている部分、原告記事を参考に独自に取材し、これに基づいて執筆した部分及び原告個人らに関し既に周知となっている事実を基にした部分から成り、原告個人らの人気の秘密を探索し検証したものであって、研究発表的で一貫性のある著作内容であるのに対し、原告記事は、原告個人らが私事にわたる様々な事柄につき、個別にされたインタビューに答えて語った断片的な記事である。このように両者は、その表現形式上の本質的特徴が格段に相違し、内容的にも異なる創作であるから、被告書籍が原告記事の著作権や著作者人格権の侵害に当たることはない。 被告書籍中に原告記事を参考にした部分があることは認めるが、原告らが同一性保持権侵害と主張する部分は、原告個人らのインタビューに対する答えであって、 被告書籍は、その一部を引き合いに出しながら原告個人らの人間像を外部から客観的に描写したものであって、原告記事の性質、これを利用する目的及び態様においてやむを得ない改変であるから、著作権法20条2項4号により同一性保持権侵害とならない。 また、被告書籍の在庫は僅少しかなく、被告らにおいてこれを販売する意思はなく、取次店に対し絶版の通知をしており増刷の可能性もないものであって、本件においては、差止めの利益は存在しない。 4 原告らが被告らに請求できる損害の額はいくらか。 (一) 原告らの主張(1) 被告書籍の出版により被告らは一五六〇万九一七一円の利益を得たから、 原告らは被告らに対し、著作権法114条1項に基づき、著作権侵害による損害賠償として原告ら合計で一五六〇万円を請求することができる。原告らは、これと弁護士費用との合計額一八一六万円につき、原告ごとに著作権を侵害された原告記事の分量の割合に従って案分した金額を、各原告の損害として請求する。なお、原告出版社と原告個人の共同著作物である原告記事については、当該原告出版社と当該原告個人の損害を各二分の一とし、原告出版社と原告個人ら六名全員の共同著作に係る著作物については原告個人の損害を更に六分(原告個人は各一二分の一)した。また、原告出版社と第三者の共同著作物に当たるものは、損害額の二分の一を原告出版社の損害とした。右のように算定した損害額は、原告【A】が一三六万〇四九八円、原告【B】が八二万〇一二〇円、原告【C】が三九万四三六七円、原告【D】が一一三万九四三四円、原告【E】が一三〇万三一八五円、原告【F】が一四七万五一二四円、原告主婦と生活社が七三〇万三三〇〇円、原告扶桑社が三七万六六二七円、原告学習研究社が三八万四八一五円、原告マガジンハウスが二三一万七〇七八円(合計一六八七万四五四八円)である。(詳細は平成八年一月二六日付け原告ら準備書面(一)及び平成九年四月二一日付け原告ら準備書面(五)参照)(2) 被告書籍は、原告記事を恣意的に改変し、原告らの名誉感情を害するような表現を交え、読者の興味をそそることを意図したものであり、これにより原告らの名誉、声望は大きく損なわれた。さらに、被告らは、事前の警告を無視してその出版を強行しており、著作者人格権侵害の態様は極めて悪質で、原告らの受けた精神的損害は甚大である。これによる原告らの損害額は原告一人当たり一〇〇万円を下らない。 (3) したがって、各原告は、被告らに対し、右(1)及び(2)を合計した金額である前記第一「原告らの請求」四項記載の金額及びこれに対する被告書籍の発売日である平成七年六月一二日から各支払済みまでの民法所定の遅延損害金の連帯支払を求める。 (二) 被告らの主張(1) 被告書籍の販売による利益の額は認めるが、これは被告鹿砦社が取得したものであって、右利益をもって被告【G】が原告に与えた被害の金銭的評価をする理由はない。 (2) 被告書籍は、原告個人らをアイドルグループとして肯定的に評価した本であり、その名誉を毀損するような性質のものではない。また、原告記事はいずれも雑誌の記事で、被告書籍の出版時点では過去のものとなっているから、原告らに甚大な精神的損害が生じるはずがない。 5 原告らが被告らに対し謝罪広告の掲載を求めることができるか。 (一) 原告らの主張 被告らは、読者の興味をそそることを企図して、原告記事の表現を改変し、事実をねじ曲げた内容に書き換え、原告個人らの名誉を害するような表現にしたり、侮辱的表現に置き換えるなどしており、原告らは、このような被告書籍の出版により同一性保持権を侵害され、著しい精神的苦痛を被った。したがって、原告らの社会的な名誉、声望を回復するための措置として、著作権法115条に基づき、別紙三「謝罪広告」記載の謝罪広告を、別紙四「掲載条件」記載の掲載条件で掲載することを求める。 (二) 被告らの主張 被告書籍中には、原告らが社会一般から受けている社会的評価すなわち社会的声望名誉を毀損したと認められる箇所はないから、謝罪広告の掲載請求は失当というべきである。 |
|
|
争点に対する判断
一 争点1(著作物性)について1 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、 美術又は音楽の範囲に属するもの」をいい(著作権法2条1項1号)、その中には「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」(同法10条1項1号)が含まれるが、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しないとされている(同条二項)。 右の「思想又は感情」は人間の精神活動全般を指し、単に事実(社会的事実、歴史的事実、自然現象に関する事実等)のみを記載したものは著作物には当たらない。また、「創作的」とは、表現の内容について独創性や新規性があることを必要とするものではなく、思想又は感情を表現する具体的形式に作成者の個性が表れていれば足りる。したがって、客観的な事実を素材とする表現であっても、取り上げる素材の選択、配列や、具体的な用語の選択、言い回しその他の文章表現に創作性が認められ、作成者の評価、批判等の思想、感情が表現されていれば著作物に該当するということができ、著作権法10条2項は、単なる日々の社会事象そのままの報道や、人事異動、死亡記事等、事実だけを羅列した記事が著作物でないことを確認的に規定したものである。さらに、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」とは、知的、文化的精神活動の所産全般を指すものである。 また、一個の著作物の一部でも、その部分のみで右にいう思想又は感情の創作的表現であると認められれば、これを著作物ということができる。 2 これを本件についてみるに、原告記事のうち、原告らが著作権、著作者人格権の侵害があったと主張する別紙六「対照表」記載の原告記事のうちには、専ら原告個人らに関する事実を内容とするものもあるが、当該事実を別の表現方法を用いて記述することも可能であると解され、具体的な文章表現に各原告記事を作成した者の個性が表れているといえるから、これらも著作物であるということができる。 3 したがって、右対照表記載の原告記事は、いずれも著作権法にいう著作物に該当すると認められる。 二 争点2(著作者・著作権者)について1 著作者とは「著作物を創作する者」をいい(著作権法2条1項2号)、現実に当該著作物の創作活動に携わった者が著作者となるのであって、作成に当たり単にアイデアや素材を提供した者、補助的な役割を果たしたにすぎない者など、その関与の程度、態様からして当該著作物につき自己の思想又は感情を創作的に表現したと評価できない者は著作者に当たらない。そして、本件において原告らがその著作物であると主張する原告記事のように、文書として表現された言語の著作物の場合は、実際に文書の作成に創作的に携わり、文書としての表現を創作した者がその著作者であるというべきである。 また、法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものについては、別段の定めがない限り、その法人等が著作者となる(著作権法15条1項)。右の「法人等の業務に従事する者」には、法人等と雇用関係にある者だけでなく、法人等との間に著作物の作成に関する指揮命令関係があり、法人等に当該著作物の著作権を原始的に帰属させることを前提にしている関係にある者も含まれると解される。 2 これを本件についてみるに、《証拠略》によれば、以下の事実が認められる。 (一) 原告記事の作成経過は、記事ごとに若干の相違点はあるが、概ね次のとおりである。 (1) 原告出版社らの社内の各雑誌の編集部において、原告個人らに関する記事を雑誌に掲載する企画を立て、記事のテーマや作成方針、原告個人らに対する具体的な質問内容、取材の日時及び場所並びに実際に取材をして記事の文章を作成する執筆者を決める。 (2) 記事の作成を依頼された執筆者は、編集部の担当者と打合せをして、企画内容、記事のねらいやテーマ、取材の日時、原告個人らへの質問内容、原稿の頁数、締切等につき、編集部の指示を受ける。この際、執筆者が原告出版社らの従業員でないときは、原告出版社らから取材及び記事の作成業務を依頼され、その対価として原稿料の支払を受けるという形になるが、契約書等の書面を取り交わすことはない。 (3) 執筆者は、編集部の担当者やカメラマンとともに指定された日時に取材場所に赴いて、担当者と打ち合わせたところに従って原告個人らに対する取材を行う。取材は、執筆者が原告個人らに対して一問一答形式でインタビューをする形で進められ、執筆者は、インタビューの内容をテープに録音するとともに、取材相手の表情やその時の状況等を取材メモに書き留めていく。 (4) 取材が終わると、執筆者は、右の録音テープ及び取材メモをもとに記事の原稿を作成する。その際、インタビューの結果を一字一句そのまま機械的に記事にすることはなく、編集部が指定した文字数の範囲内で当該企画のテーマに沿った内容の文章を作るために、雑誌の読者が原告個人らについて知りたがっている事柄に答えているか、タレントの個性や素顔をよく表しているか、他社と違った独自性のある内容であるかといった観点から、執筆者自身の創意工夫を交えつつ、インタビューの中から記事に盛り込む話題を取捨選択したり、会話の順序を並べ替えたり、 読者が分かりやすい表現に変えたり、補足、要約したりする。 (5) 編集部においては、執筆者が作成した原稿が決められた企画のテーマに沿っているか、誰にでもわかりやすい内容になっているかなどの観点から原稿をチェックし、修正を要する箇所がある場合は、執筆者に対し原稿の手直しを指示する。 (二) 各原告記事を執筆したのは、原告記事①、③、④及び⑩が【H】、原告記事②及び⑦の一部(原告【A】及び原告【D】に関する部分)が【I】、原告記事⑤、⑧及び⑨が【J】、原告記事⑥が【K】、原告記事⑦の一部(原告【C】及び原告【F】に関する部分)が【L】、原告記事⑦の一部(原告【B】及び原告【E】に関する部分)が【M】、原告記事⑪ないし⑭が【N】、原告記事⑮及び⑯が【O】、原告記事⑰が【P】であった。右執筆者らのうち少なくとも【H】、 【N】及び【O】は原告出版社らの従業員ではなく、いわゆるフリーライターであるが、右九名の執筆者はいずれも、原告出版社らの指揮監督の下にその職務上原告記事の作成業務に従事したものであることを認め、その著作権が当初から原告出版社らに帰属することを了解している。 (三) 原告記事は、記事本文のほか、タイトル、見出し、原告個人らの写真、略歴の記載等により構成されており、本文部分は、原告記事⑤及び⑨を除き、原告個人らの発言を主として記載した体裁になっている。 すなわち、原告記事①ないし④、⑧、⑩ないし⑭は、個人原告らの発言をそのまま文章化した形になっている(このうち原告記事①ないし④、⑧及び⑩の冒頭部分には執筆者のコメントが付されている。)。原告記事⑦は、執筆者の発問を受けて、原告個人らが二人ずつ対談するという形式である(なお、原告記事⑪の後半は、原告【A】と原告【E】の対話形式になっているが、これは執筆者が右両名に別々にインタビューした内容をまとめたものである。)。原告記事⑥及び⑮は、原告個人らの発言として記載された部分と執筆者の意見や感想とが一体化した文章となっている。原告記事⑯には、原告個人らの発言のみを記載した部分、執筆者の意見や感想が挟み込まれた部分、第三者との対談形式の部分、第三者のコメントを記載した部分等がある。原告記事⑰は、執筆者の原告個人ら全員に対するインタビューの部分、原告個人ら各人への一問一答等から成っている。 これらに対し、原告記事⑤及び⑨は、その記事の対象となる原告個人らに関する第三者の発言を軸に、執筆者自らの意見や感想を交えて文章化したものであり、作成に当たり原告個人らへの取材は行われていない。 (四) 原告記事を掲載した雑誌には、原告出版社らの名称がそれぞれ記載されている。また、原告記事⑮及び⑯以外については、当該原告記事を掲載した雑誌の裏表紙に、著作権の帰属を示す「(C)」マーク並びに各原告出版者らの名称及び当該雑誌の発行年の表示がある。 3 右認定の事実を総合すれば、実際に原告記事の文書の作成に携わり、これを創作したのは、各記事の執筆者であるということができるが、各執筆者は、原告出版社らから記事の作成を依頼され、その指揮命令に従いながらこれを執筆したのであり、しかも、原告出版社らに原告記事の著作権を原始的に帰属させるという認識であったのであるから、原告記事は、いずれも原告出版社らの発意に基づきその業務に従事する者がその職務上作成した著作物であると認められる。また、原告記事が原告出版社らの著作名義の下に公表された点は被告らの争うところではなく、原告記事の著作者を誰とするかに関し別段の定めがあったことをうかがわせる証拠はない。したがって、原告主婦と生活社は原告記事①ないし⑩の、原告扶桑社は原告記事⑰の、原告学習研究社は原告記事⑪ないし⑭の、原告マガジンハウスは原告記事⑮及び⑯の著作者であると認められる。 4 原告らは、前述(第二、二2(一)(2))のとおり、原告個人らも原告記事の著作者であり著作権者であると主張するので、この点につき検討する。 (一) 原告記事⑤及び⑨は、右2(三)で認定した記事の体裁に照らし、原告個人らがその著作者又は著作権者でないことは明らかである。 (二) 右以外の原告記事は、その体裁上、原告個人らの発言を主たる内容として構成されているところ、インタビュー等の口述を基に作成された雑誌記事等の文書については、文書作成への関与の態様及び程度により、口述者が、文書の執筆者とともに共同著作者となる場合、当該文書を二次的著作物とする原著作物の著作者であると解すべき場合、文書作成のための素材を提供したにすぎず著作者とはいえない場合などがあると考えられる。すなわち、口述した言葉を逐語的にそのまま文書化した場合や、口述内容に基づいて作成された原稿を口述者が閲読し表現を加除訂正して文書を完成させた場合など、文書としての表現の作成に口述者が創作的に関与したといえる場合には、口述者が単独又は文書執筆者と共同で当該文書の著作者になるものと解すべきである。これに対し、あらかじめ用意された質問に口述者が回答した内容が執筆者側の企画、方針等に応じて取捨選択され、執筆者により更に表現上の加除訂正等が加えられて文書が作成され、その過程において口述者が手を加えていない場合には、口述者は、文書表現の作成に創作的に関与したということはできず、単に文書作成のための素材を提供したにとどまるものであるから、文書の著作者とはならないと解すべきである。 これを本件についてみるに、原告個人らが、発言がそのまま文書化されることを予定してインタビューに応じたり、記事の原稿を閲読してその内容、表現に加除訂正を加えたことをうかがわせる証拠はなく、かえって、前記認定の原告記事の作成経過からすれば、原告個人らに対するインタビューは、原告出版社らの企画に沿った原告記事を作成するに際して、素材収集のために行われたにすぎないものと認められる。 (三) したがって、原告個人らを原告記事の著作者ということはできない。 5 以上によれば、原告主婦と生活社は原告記事①ないし⑩につき、原告扶桑社は原告記事⑰につき、原告学習研究社は原告記事⑪ないし⑭につき、原告マガジンハウスは原告記事⑮及び⑯につき、それぞれ著作権及び著作者人格権を有すると認められる。 他方、右のとおり、原告個人らが原告記事につき著作権又は著作者人格権を有すると認めることはできないから、原告個人らの請求は、その余の点について判断するまでもなく、すべて理由がないというべきである。 三 争点3(著作権・著作者人格権の侵害)について1 まず、著作権侵害の有無につき、検討する。 (一)(1) 複製とは、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」であり(著作権法2条1項15号)、既存の著作物に依拠して、その内容及び形式を覚知させるに足りるもの、すなわち、これと表現形式上同一性を有するものを作成することをいう。複製には、表現が完全に一致する場合に限らず、具体的な表現形式(言語の著作物においては、叙述の順序、用語、言い回し等の文面上の表現がこれに当たる。)に多少の修正、増減、変更等が加えられていても、表現形式の同一性が実質的に維持されている場合も含まれるが、誰が書いても似たような表現にしかならない場合や、当該思想又は感情を表現する方法が限られている場合には、同一性の認められる範囲は狭くなると解される。 (2) 翻案とは、著作権法27条にいう「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化」する行為と同様に、いずれか一方の作品に接したときに他方の作品との同一性に思い至る程度に両者の基本的な内容が同一である著作物を創作することであり、既存の著作物に依拠して、それとは表現形式が異なるものの、その創作に係る本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を、創作する行為をいう。 (3) 他方、著作権は創作的な表現を保護するものであるから、既存の著作物の利用を著作権侵害というためには、その中の創作的な表現形式を複製又は翻案したものであることを要し、既存の著作物の内容となっている事実のみを抽出してこれを再製した場合など、既存の著作物中の創作性の認められない部分を利用したにすぎない場合には、複製権又は翻案権を侵害しないものというべきである。 (二) 本件において原告らが著作権を侵害されたと主張する別紙六「対照表」記載の部分につきこれを見るに、別紙七「一覧表」の「複製」欄に「○」印を付した部分は、被告書籍と原告記事の表現形式が実質的に同一であると認められ、被告書籍は原告記事の内容及び形式を覚知させるに足りるということができるから、複製権の侵害に当たるものというべきである。また、右一覧表の「翻案」欄に「○」印を付した部分は、被告書籍の記述から原告記事の創作に係る本質的な特徴を直接感得することができるから、翻案権を侵害するものというべきである。これに対し、 右一覧表の「非侵害」欄に「事実のみ同一」と記載したものは、対応する原告記事と被告書籍とで共通する点は記述の対象となっている事実内容のみであって、創作的特徴を含まないと認められるから、複製権又は翻案権の侵害には当たらない。また、右欄に「同一性なし」と記載したものは、両者の間に複製又は翻案の関係があるといえるほどの同一性があるとは認められず、原告記事の著作権を侵害するものではないと判断される。 (三) 被告書籍の執筆に当たり原告記事が参考とされたことは被告らが認めているところであり、さらに、右認定のとおり、両者の表現に同一性のある部分が多数認められることからすれば、被告書籍は原告記事に依拠して作成されたということができる。 (四) したがって、原告主婦と生活社が著作権者である原告記事については四四か所(複製権三〇か所、翻案権一四か所)の、原告扶桑社が著作権者である原告記事については二か所(複製権のみ)の、原告学習研究社が著作権者である原告記事については二か所(複製権のみ)の、原告マガジンハウスが著作権者である原告記事については二〇か所(複製権一六か所、翻案権四か所)の記述につき、被告らによる著作権侵害があると認められる。 2 次に、著作物人格権の侵害の有無につき検討する。 (一) 被告らが原告記事の一部につき複製権及び翻案権を侵害したことは、右に述べたとおりであり、被告書籍中には、原告記事を複製し又は翻案した記述があるのにもかかわらず、著作者として原告出版社らの名称が表示されていない。(甲一) したがって、被告らは、右のとおり著作権を侵害した部分につき、原告出版社らの氏名表示権(著作権法19条1項)をも侵害したものである。 (二) また、被告らは、原告記事を複製又は翻案するに際して、別紙六「対照表」記載のとおり、原告記事の表現に変更、切除その他の改変を加えているから、 原告記事のうち当該部分についての原告出版社らの同一性保持権(著作権法20条1項)を侵害したものと認められる。 なお、被告らは、前述(第二、二3(二))のとおり、被告らの行為は著作権法20条2項4号の除外事由に当たり同一性保持権の侵害にならないと主張している。しかし、右規定は、同一性保持権による著作者の人格的利益保護を例外的に制限する規定であり、かつ、同じく改変が許容される例外的場合として規定された同項一号ないし三号の掲げる内容との関係からすれば、同項四号の「やむを得ないと認められる改変」に該当するというためには、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らし、著作物の改変につき、同項一号ないし三号に掲げられた例外的場合と同様に強度の必要性が存在することを要するものと解するのが相当である。 ところが、本件においては、被告書籍の発行に当たり原告記事に改変を加えるにつき、右のような強度の必要性が存在したとは認められないから、被告らの右主張は採用できない。 (三) したがって、被告らの行為により原告出版社らの著作者人格権が侵害されたものと認められる。 3 以上によれば、被告らが被告書籍を出版した行為は、原告出版社らの著作権及び著作者人格権を侵害するから、原告出版社らは被告らに対し、侵害行為の停止及び予防を求めることができる。 そして、原告出版社らの著作権及び著作者人格権の侵害に該当する記載は被告書籍の一部に存するにとどまるが、別紙七「一覧表」記載のとおり、侵害部分は被告書籍の全体にわたっており、しかも、非侵害の部分と不可分であるから、被告書籍全体について差止め等を求めることができると解するのが相当である。 4 なお、被告らは、前述(第二、二3(二))のとおり主張して、差止めの利益の存在を争っているのでこの点につき検討する。 《証拠略》によれば、被告らは、原告個人らの代理人である弁護士から、被告書籍のかなりの部分は原告らの著作権及び同一性保持権の侵害となるので出版を取りやめるよう文書による警告を受けたにもかかわらず、被告書籍を出版し、販売したこと、原告らの申し立てた被告書籍の販売、配達等の差止めを求める仮処分事件(当庁平成七年(ヨ)第二二〇五二号)の審理中、被告鹿砦社は、書籍取次業者等に被告書籍を絶版にした旨の通知をする一方、原告らと徹底的に闘う旨の文書を作成してマスコミ等に配布したこと、右仮処分の申立てが認容された後、被告鹿砦社は、 原告個人らが所属する事務所に関係する書籍を一〇冊以上出版し、そのうちの一冊についてはプライバシー侵害を理由とする出版差止めの申立てを認めた仮処分が発令されていること、被告【G】は、本件を含めて書籍の出版差止めを求められた事件につき、売られた喧嘩は買わざるを得ない旨述べていることが認められる。 右認定の事実によれば、被告らは、被告書籍の発行により原告記事に係る著作権及び著作者人格権を侵害した上、現に右侵害の有無を争っていて、将来的にも同様の侵害行為を繰り返すおそれがあると認められるから、本件において差止めの必要性を否定することはできない。 5 以上によれば、原告出版社らは被告らに対し、原告記事に係る著作権及び著作者人格権の侵害の停止及び予防として、著作権法112条1項に基づき、被告書籍の複製の差止めを請求することができる。また、被告らが原告記事に係る著作権及び著作者人格権を侵害して出版した被告書籍を頒布することは、同法113条1項2号により右著作権及び著作者人格権を侵害する行為とみなされるから、同法112条1項に基づきその差止めを求めることができる。さらに、右侵害の停止及び予防に必要な措置として、同条二項により、被告書籍並びにその原稿、紙型及び版下の廃棄、並びに、被告書籍を販売のために展示することの差止めを求めることができる。 四 争点4(損害の額)について1 まず、著作権侵害による損害につき検討する。 (一) 被告書籍の出版により被告鹿砦社が一五六〇万九一七一円の利益を得たことは当事者間に争いがない。したがって、著作権法114条1項により、原告出版社らは右同額の損害を受けたと推定されるところ、右原告らは、その約半分が右原告らの損害額であるとしてその賠償を求めている。 他方、被告書籍は、標題、まえがき、目次、余白等の部分を除いた本文全体で二一〇頁から成るが(甲一)、著作権侵害部分は別紙七「一覧表」記載のとおり、被告書籍中に約九〇頁にわたって存在しており、被告書籍から著作権侵害に当たる記述を削除すると一冊の書籍として成り立たなくなると考えられるから、右記述は、 被告書籍にとって不可欠な構成部分であり、その重要な部分を占めているということができる。 そして、原告出版社らは、原告記事の大部分について原告個人らとの共同著作に係るものであると主張し、著作権の二分の一の共有持分の侵害に基づく損害賠償を請求しているものであり、これらの事情を総合すると、原告出版社らが著作権侵害により被った損害として本件訴訟において請求する金額のうち認容すべき額は、原告出版社ら合計で四〇〇万円と認めるのが相当である。そして、これを原告出版社各社の被侵害部分の量の割合に応じて案分すると、原告主婦と生活社につき二五〇万円、原告扶桑社につき一五万円、原告学習研究社につき一五万円、原告マガジンハウスにつき一二〇万円の賠償を認容すべきものである。 (二) 著作権侵害に係る弁護士費用の請求については、右(一)の認定額、本件訴訟の内容及び経過その他の事情を考慮すると、著作権侵害と相当因果関係があり、損害賠償の一部として被告らに負担させるべき弁護士費用としては、原告主婦と生活社につき四〇万円、原告扶桑社につき三万円、原告学習研究社につき、三万円、原告マガジンハウスにつき二〇万円と認めるのが相当である。 (三) なお、前述の著作権侵害の態様からすれば、原告記事の著作権を侵害したことにつき、被告らには少なくとも過失があったと認められる。 (四) さらに、被告鹿砦社及び被告【G】がそれぞれ被告書籍の発行所及び発行人であること、被告【G】は被告鹿砦社の代表取締役であること、被告鹿砦社は従業員二〇名未満の出版社であること(乙二)、被告書籍の著者とされている「スマップ研究会」についてはその構成員はもちろん、会の活動内容や存在自体も不明であることからすると、本件の著作権侵害行為は被告らが共同して行った不法行為というべきであって、民法719条1項により、被告らは、原告出版社らの被った損害につき連帯してこれを賠償する義務を負うと解すべきである。 2 次に、著作者人格権侵害による損害につき検討すると、本件における著作者である原告出版社らはいずれも法人であり格別の精神的損害を被ったとは認められないこと、著作権侵害と著作者人格権侵害が同一の行為により生じたものであるところ、右侵害行為による著作権侵害の損害につき前記のとおりの賠償請求を認容していることに照らすと、原告出版社らの受けた損害の回復のためには著作権侵害による損害賠償を認めれば十分であり、これに加えて著作者人格権侵害による損害賠償を認めるまでもないと解するのが相当である。 3 以上によれば、原告出版社らは被告らに対し、民法709条、719条1項、 著作権法114条1項に基づき、原告主婦と生活社につき二九〇万円、原告扶桑社につき一八万円、原告学習研究社につき一八万円、原告マガジンハウスにつき一四〇万円及びこれらに対する不法行為時(被告書籍出版の日)である平成七年六月一二日から各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めることができる。 五 争点5(謝罪広告)について1 著作者は、故意又は過失によりその著作者人格権を侵害した者に対し、著作者の名誉若しくは声望を回復するために、適当な措置を請求することができ(著作権法115条)、この「適当な措置」には謝罪広告の掲載が含まれるが、右の「名誉若しくは声望」とは、著作者がその名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉声望を指すものであって、人が自分自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情を含むものではないと解される。 2 これを本件についてみるに、被告書籍が出版されたことによって原告出版社らに対する社会的な名誉が毀損されたことをうかがわせる証拠はないから、その名誉声望を回復するために、謝罪広告を掲載することが必要であるとは認められない。 六 よって、原告個人らの請求は、いずれも理由がなく、原告出版社らの請求は、 右の限度で理由があるから、主文のとおり判決する(なお、主文二項についての仮執行宣言の申立ては相当でないので、これを付さないこととする。)。 |
| 裁判官 | 三村量一 |
|---|---|
| 裁判官 | 長谷川浩二 |
| 裁判官 | 中吉徹郎 |