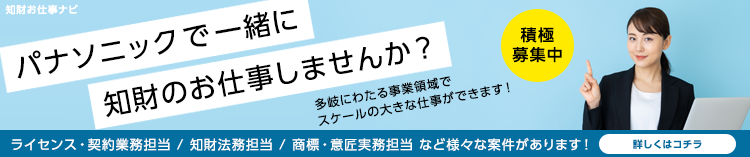この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
| 審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
|---|---|---|
| 平成19・4156著作権侵害不存在確認等請求事件 | 判例 | 特許権 |
| 平成16ワ13725損害賠償等請求事件 | 判例 | 特許権 |
| 関連ワード | 創作性 / 創作的表現 / 著作者 / 表現方法 / 模様 / 二次的著作物 / 翻案 / 同一性 / 類似性 / 公衆送信 / 放送 / 著作者人格権 / 氏名表示権 / 同一性保持権 / 公衆送信権 / ビデオ / 引用 / 著作権侵害 / 損害賠償 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|
| 事件 |
平成
11年
(ワ)
5026号
損害賠償等請求事件
|
|---|---|
|
原告X 訴訟代理人弁護士 井上二郎 被告 株式会社朝日新聞社 訴訟代理人弁護士 秋山幹男 被告 株式会社劇団ひまわり 訴訟代理人弁護士 山本繁樹 被告Y 訴訟代理人弁護士 高木一彦 被告 日本放送協会 訴訟代理人弁護士 杉本幸孝 同 永野剛志 同 梅田康宏 |
|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 2001/08/28 |
| 権利種別 | 著作権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
請求
1 被告朝日新聞社、被告劇団ひまわり及び被告Yは、原告に対し、連帯して金8000万円及びこれに対する平成9年8月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告朝日新聞社は、原告に対し、金1000万円及びこれに対する平成8年11月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告朝日新聞社は、原告に対し、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞及び産経新聞の各全国版朝刊社会面に、別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を各1回掲載せよ。 4 被告日本放送協会は、原告に対し、金1000万円及びこれに対する平成8年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
|
|
事案の概要
1 基礎となる事実(いずれも争いがないか弁論の全趣旨により認められる。) (1) 当事者 ア 原告は、コルチャックの研究者である。ヤヌシュ・コルチャック(1878年生)は、ポーランドのユダヤ人で、医者、作家、教育者であり、第2次世界大戦中にナチスのホロコーストの犠牲となった実在の人物である。 イ 被告朝日新聞社は、日刊新聞等の発行及びこれに付帯する諸事業を営む株式会社である。 ウ 被告劇団ひまわりは、演劇の興行、映画等の企画製作等を業とする株式会社である。 エ 被告Yは、戯曲の脚本等の制作に従事している者である。 オ 被告日本放送協会は、放送法に基づき設立され、国内放送、国際放送その他同法に定められた業務を行うことを目的とする法人である。 (2) 原告の著作権及び著作者人格権 原告は、コルチャックの生涯と教育者としての実践を描いた著作「コルチャック先生」を執筆し、平成2年12月30日、被告朝日新聞社から第1刷が発行された(以下「原告著作」という。)。なお、原告著作は、平成7年に朝日文庫としても被告朝日新聞社から刊行されている。原告は、原告著作について著作権及び著作者人格権を有する。 (3) 被告3名による舞台劇の公演と脚本執筆 被告朝日新聞社及び被告劇団ひまわりは、舞台劇「コルチャック先生」を主催、製作し、平成7(1995)年8月12日から同月23日まで東京のパナソニック・グローブ座で、同月26日から同月30日まで大阪の近鉄劇場で、さらに、平成9年(1997)年8月5日から同月19日まで東京の世田谷パブリックシアターで、同月23日から同月30日まで大阪のシアター・ドラマシティで、いずれも加藤剛の主演により公演した(以下、平成7年の公演を「95年公演」、平成9年の公演を「97年公演」といい、97年公演で上演された舞台劇を「本件舞台劇」という。)。 これらの公演の脚本(台本)は被告Yが執筆した。 また、95年公演では、広告、プログラム、上演台本等において「原作X(「コルチャック先生」朝日新聞社刊)」との表示がされたが、97年公演ではこの表示はされなかった。なお、95年公演においては、同時に「脚本原作A」との表示もされた。 (4) 被告日本放送協会による放送 被告日本放送協会は、平成8年3月25日及び同年9月5日、NHK衛星第2放送(11チャンネル)において、95年公演(東京公演)を収録した番組を放送した(以下「本件放送」という。)。 (5) 被告朝日新聞社による新聞記事の掲載 被告朝日新聞社は、平成8年11月26日の朝日新聞夕刊に、「子どもとともに『死の収容所』行きを選択 コルチャック先生」「過去を直視 高校生熱演」との見出しによる記事を掲載した(以下「本件記事」という。)。この記事には、次のような記載があった。 ・「パレスチナ在住の日本人建築家Aさん(52)の脚本による劇『コルチャック先生-ある旅立ち』がこのほど、ドイツ(旧東独)のケムニッツ市立劇場で、日本の国外では初めて上演された。」 ・「戦後50年を記念して昨年夏、俳優の加藤剛さん主演により日本で初演されたこの劇は、ケムニッツでは、1938年11月9日夜、ドイツ全土で起きた集団的ユダヤ人迫害事件『水晶の夜』を記憶するための行事として行われた。」 2 原告の請求の内容 (1) 請求1項 本件舞台劇は、原告著作を翻案したものであるにもかかわらず、原告の許諾を得ず、かつ、原告を原作者と表示しないで、上演されたものであるから、被告3名は、97年公演を行うことによって、共同して原告の著作権(翻案権、上演権)及び著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)を侵害したものである。よって、原告は、被告3名に対し、共同不法行為に基づく損害賠償を請求する。 (2) 請求2項及び3項 被告朝日新聞社は、本件記事において、本件舞台劇の原作者が原告でないかのような誤った報道をし、これにより、原告は、コルチャック研究者及び95年公演の原作者としての名誉及び信用を著しく害された。よって、原告は、被告朝日新聞社に対し、不法行為に基づく損害賠償及び謝罪広告を請求する。 (3) 請求4項 本件放送は、原告著作を翻案してされた95年公演を、原告の許諾なしに放送したものであるから、それにより、被告日本放送協会は、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したものである。よって、原告は、被告日本放送協会に対し、著作権侵害に基づく損害賠償を請求する。 3 争点 (1) 請求1項関係 ア 97年公演は原告著作の翻案によるものか。 イ 被告3名が97年公演を行うことを原告は許諾していたか。 ウ 損害額 (2) 請求2項及び3項関係 ア 本件記事の掲載が、原告の名誉及び信用を侵害する違法性を有するか。 イ 損害額 ウ 謝罪広告の必要性 (3) 請求4項関係 ア 本件放送は原告の著作権を侵害するものであったか。 イ 本件放送について原告は許諾していたか。 ウ 損害額 |
|
|
争点に関する当事者の主張
1 争点(1)ア(97年公演の翻案性)について 【原告の主張】 (1) 95年公演の舞台劇「コルチャック先生」は、戦後50周年を迎え、被告朝日新聞社が「過去を糧として21世紀を考える」プロジェクトの一つとして、被告劇団ひまわりと共に、被告朝日新聞社が発行した原告著作を原作として製作することを決定した上で、被告Yにこれを脚本化させて製作したものである。97年公演の脚本も被告Yが執筆したものであり、95年公演の脚本を一部改変してはいるが、やはり原告著作に依拠し、95年公演の脚本に酷似する内容のものである。97年公演に当たり、被告Yの執筆した脚本に台本再構成(テキストレジー)を経て実際に上演された本件舞台劇の内容は、別紙「97年公演と原告著作の対照表」(以下「対照表」という。)の上段記載のとおりであるが、これが原告著作の翻案であることは、後記のとおり明らかである。 (2) 「翻案」か否かを判断する基準は、「二次的著作物から原著作の本質的な特徴自体を直接感得し得るかどうか」にあるといってよい。 ア これを本件についてみると、原告著作の本質的な特徴は次のとおりである。 原告著作は、コルチャックの生涯の全体を描いているが、最後の3年をコルチャックの思想の核心として位置づけている。 ポーランドの首都ワルシャワに、コルチャックは二つの孤児院を作った。ナチスの台頭、反ユダヤ主義の激化する状況下、コルチャックはユダヤ人であるがゆえにポーランド人の孤児院ナシュドム(ぼくたちの家)、ラジオ番組「老博士のおはなし」、小評論(小さな瞳)と訣別することになる。コルチャックはカナリアの死を通して、ユダヤ人であることを自覚した幼年時代の原体験に思いをはせる。 ところが、彼の夢を実現し、彼の教育方針、家庭的雰囲気のみなぎった孤児院での生活もナチスのポーランド侵攻によって、一転する。 ワルシャワ・ゲットーでの厳しい、非人間的な日常、コルチャックの生きるための闘いが始まる。コルチャックの人間性すら否定される寄付集め、食糧の確保の中、孤児院の自治による生活は守られ、ポーランド人、地下抵抗組織からクリスマスの贈物も届く。コルチャックは再三の救援の手をしりぞけ、子供たちに安らかな死を願い、演劇「郵便局」を上演する。このコルチャックの報いられぬ果てしない苦悩はギリシャ神話のシジフォスの仕事にも似たものであった。 ゲットーは「ユダヤ人には明日、何が起こるかわからない」状態であった。そして、ナチスは、ワルシャワ・ゲットーから東部への移住を命じた。コルチャックは、ポーランド人の子どたちのホーム(ぼくたちの家)にマリナ・ファルスカを訪ね、別れを告げる。コルチャックの死に対峙しての言葉はゲットー日記に記されたものを原作者の考えで編述したものである。 コルチャックのホームへも移送の命令が届く。エピローグ「かなたへの旅立ち」の前、コルチャックの「あこがれを贈る」は、世紀末から今世紀中葉にかけて、彼の生きた時代、ユダヤ人知識階級の抱いていた共通の感情ー祖国喪失の思いーがあふれているもので、このような背景を踏まえて原告著作は表現したのである。 ナチス官憲がコルチャックに恩赦を告げたとき、コルチャックは「それで、子どもたちは?」と尋ねる。だが、官憲は「子どもたちは(ガス室へ)行かねばならない」と言う。このときコルチャックは「あなたは間違っている。まず子どもたちをーー」と言って、自ら子供たちとともにガス室に消えた。この最後のシーンに原告著作の本質的な特徴が凝縮された表現形式で描かれている(別紙対照表89~91頁中段)。「あなたは間違っている!」、コルチャックのこの最後の言葉は、彼の心の奥底深くからナチスに投げつけた、人間の尊厳に裏打ちされた激しい批判である。コルチャックなら言ったであろうこの言葉は、原告がコルチャックの友人、ネヴェルリイから直接聞いたものである。戦争における子供の悲惨な状況を人類に問うことでもある。重い鉄の扉がガラガラと音を立てて閉まった。コルチャックと200人の子供たちはトレブリンカ絶滅収容所に向かっていった。この最後の叙述に凝縮された形で、原告著作の表現上の本質的特徴が鮮烈かつ如実に示されている。 イ 以上に述べた原告著作の本質的特徴は、95年公演にはもちろん、97年公演にも明確に表れている。 もちろん舞台劇という時空的制約の中でコルチャックの全史を上演することはできない。したがって、97年公演の台本は、原告著作に記述されたコルチャックの全体像に依拠しながら、主として主人公コルチャックのドラマチックな晩年に焦点を当て、彼の生涯の約10%に当たる約6年間を集中的に取り上げストーリーを構成している。そこには、ワルシャワ・ゲットーの中で織りなす人間模様を通して、コルチャックのユダヤ人としての不条理との葛藤、苦悩が描かれ、歴史の苛酷な歩みの中、極限状況下にあっても子供たちを見捨てることなく生き、子供たちと共に死の道を選び、ホロコーストの犠牲者となったコルチャックの軌跡が、原告著作の前記本質的特徴に大きく依拠して表現され、ストーリーが展開されている。したがって、本件舞台劇から原告著作の前記本質的特徴を直接かつ容易に感得できるのである。 95年公演の上演台本は原告著作の翻案によるものであるが、97年公演の内容もこれとほぼ同じである。97年公演が原告著作を翻案してされたものであることは、別紙対照表に具体的に示すとおりである。 ウ 被告3名は、97年公演の上演台本は、原告著作のほか、さまざまな資料を参考にして、登場人物に独自の言葉でセリフを与え、被告Yが創作したものである旨主張するが、翻案に当たり、他の資料を参考にしたり、原作の一部を削除したり、原作にないものを付け加えたりするのは、脚本家の初歩的技法である。原著作を基調としながら、観客の理解を容易にし、観客に大きな感動を与えるように、 脚本家は常に効果的展開を工夫してドラマに仕立て上げるのである。したがって、 原著作以外に他の作品を資料として用いたからといって、そのことで翻案でなくなるわけではない。たとえ多くの他の作品を参考にしたり、その一部を用いたとしても、本件舞台劇から原告著作の本質的特徴が直接感得されれば、それは原告著作の翻案である。本件舞台劇からこれが感得されることは、前記のとおりである。 (3) 95年公演では、「原作X(「コルチャック先生」朝日新聞社刊)」と表記され、原告と被告朝日新聞社及び被告劇団ひまわりとの間で取り交わされた1995年(平成7年)12月14日付け覚書(以下「本件覚書」という。)でも、そのように表記することが定められている。「原作」とは、一般に「もとの著作すなわち翻訳・改作・脚色などを行う前のもとの作品」を意味する用語である。 したがって、95年公演につきこのように表記され、合意されたことが、その「もとの作品」が原告著作であることの証左である。そして、95年公演と97年公演の内容はほとんど同じであるから、95年公演につきされた上記表記及び合意は、97年公演の「もとの作品」が原告著作であることの証左でもある。 【被告3名の主張】 (1) 自己の著作物を創作するに当たり、他人の著作物を素材として利用することは許されないことではなく、他人の著作物における表現形式の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させないような態様においてこれを利用する場合は、著作者や著作権者の許諾を必要としない。そして、以下のとおり、本件舞台劇は、原告著作の創作的表現形式の本質を利用したものとはいえない。 ア 原告著作は、さまざまな文献や歴史資料等にもとづいて、コルチャックの生い立ちから死までの生涯を、時間的順序を追って記載した伝記であり、歴史的事実をまとめたものである。それは小説や戯曲ではなく、歴史的事実やエピソードを記載する以上に創作的なストーリーの展開はない。その点において原告著作は、 同じコルチャックの伝記である他の著作と同一であり、原告著作に記載された歴史的事実の主なものは、他の伝記にも記載されている。 これに対して、本件舞台劇は、コルチャックの生涯のうち、ドイツのポーランド侵攻前の1935年頃から1942年8月にトレブリンカ絶滅収容所に送られるまでの最後の数年間を描いたものであり、まずその点で原告著作と異なるのみならず、対象期間の歴史的動きやコルチャックをめぐる出来事などは、史実に則して取り上げられており、原告著作が創作したストーリーに依ったものではない。 本件舞台劇で示されたコルチャックの軌跡は、コルチャックが歩んだ人生の歴史的経過であり、多くの人々が理解し認識しているコルチャックの生き方であり、原告著作が創作したものではない。 そして、本件舞台劇は、舞台劇であるがゆえに、単に歴史的事実を述べるのではなく、コルチャックと子供たちやその周囲の人々の生き方を物語として生き生きと描くとの構想の下に、ユゼフとフリーダというユダヤ人の架空の兄妹の物語を一つの軸にストーリーを展開し、コルチャックや子供たち、マリーナ、ステファその他の実在の人物についても、史実に依拠しつつ、セリフを創作して与え、生き生きとした人物像やストーリーを作者が具体的に創作しているものである。97年公演の主たる登場人物は原告著作にも登場するが、実在の人物が重なり合うことは当然のことであり、著作権侵害とならないのはいうまでもない。また、97年公演の登場人物名の訳語が原告著作と同一であるものもあるが、外国人の氏名の日本語表記に著作権が生じないことは明らかである。 イ 歴史的事実としての素材の利用について 別紙対照表は、単に、97年上演の各シーンに、原告著作に記載された歴史的事実と同様の事実が示されていること、あるいは同著作に引用されたコルチャックの日記等の資料と同様のエピソード等が含まれていることを示すものにすぎない。いうまでもなく、これらの歴史的事実は原告著作が創作したものではなく、 他のさまざまな文献等にも記載されているものである。また、コルチャックの日記等に示されたエピソード等ももちろん原告が創作したものではなく、リフトン著「子どもたちの王様」、ペルツ著「コルチャック」、ワイダ監督の映画「コルチャック先生」等においても紹介されているものである(別紙「資料比較」参照)。 これらの著作等に記載された歴史的事実やこれらの著作等に引用された歴史的資料の記載内容を素材として利用したとしても、それは基本的に許される行為であり、翻案とはならない。これらの著作等の創作的表現形式を利用したといえる場合に初めて翻案として許諾を要することになるものである。 ウ 別紙対照表に対する具体的反論は、別紙「97年公演と原告著作の対照表に対する反論」のとおりである。 (2) 95年公演の上演台本作成に当たって、被告Yは、原告著作に記載された歴史的事実や同著作に引用されたコルチャックの日記の記載等を参考資料とはしたものの、それを下敷きにして翻案するという作業を行ったわけではなく、原告著作もその一つである関連資料のさまざまな部分に触発されながら、コルチャックをめぐる歴史と人間のドラマを被告Yの構想したプランによって作り出したものである。97年公演の上演台本作成に当たっても、被告Yは、もともと同人の創作である95年公演の上演台本を、更に新たなプランによって改作をしたというにすぎない。97年公演で上演された本件舞台劇は、被告Yが作成した上演台本に舞台稽古を通じての台本再構成(テキストレジー)を経たものであるが、基本的にはこれまで述べたところと同じである。 (3) 95年公演において「原作X(「コルチャック先生」朝日新聞社刊)」と表記した趣旨は、それが原告著作を翻案したものであったからではない。同表記をすることは、被告朝日新聞社が被告劇団ひまわりに対して申し入れたものであるが、被告朝日新聞社がこの原作表記を求めた理由は、被告朝日新聞社が原告著作を刊行しており、同著作を広く世の中に知らしめ、かつ95年公演に対する認識を高めるためであった。また、脚本作成に当たり原告著作が参考資料の一つになっていることや、「コルチャック先生」の舞台劇の企画を持ち込み、資料を提供した原告に敬意を表す趣旨もあった。原告著作の翻案により脚本を作成するということではなかった。 2 争点(1)イ(97年公演の許諾)について 【被告3名の主張】 (1) 原告は、被告朝日新聞社及び被告劇団ひまわりが、平成7年8月12日以降5年間にわたり、被告Yの脚本をもとに作成した上演台本により舞台劇「コルチャック先生」を上演することを本件覚書により承諾したから、97年公演についても原告の承諾があった。 (2) 本件覚書が失効したとの主張は争う。 ア 被告朝日新聞社は、争点(2)アで主張するように、本件記事において、原告が95年公演の原作者でなかった趣旨の報道はしておらず、原告に対する信頼を破壊する内容ではないものであるから、これを理由に覚書による契約の撤回とか解除が許されると解すべきではない。 イ 著作者人格権に基づく撤回の主張は争う。 97年に公演を行うことは、95年公演終了後、被告朝日新聞社及び被告劇団ひまわりから何回も原告に話をしている。また、95年公演において「脚本原作A」と表示されたAが97年公演には関与しないことも話しているのであって、通告などという礼儀を失するような態度はとっていない。97年公演は原告名を表示し、Aの表示は行わない予定であったが、原告は協議に応じようとせず、被告劇団ひまわりの者が原告宅を訪ねても面会を拒絶された。すなわち協議に応じなかったのは原告の一方的理由によるものであり、被告朝日新聞社及び被告ひまわりの側が協議に応じなかったのではない。さらに、97年公演に原作者表示をしなかったのは、原告が表示するなと述べたからであり、この責任を被告朝日新聞社や被告劇団ひまわりに転嫁することは許されない。 ウ 法定解除権の行使の主張は争う。 97年公演については、95年公演終了時から協議を行ってきているし、 被告朝日新聞社及び被告劇団ひまわりは協議のため原告宅を訪ね何回も話をしているが、本件記事掲載以後、原告は態度を変え、協議に応じなくなった。これは原告が難題を提起し、協議を拒否したものであって、協議義務の不履行は原告についていえるのであり、被告朝日新聞社及び被告劇団ひまわりに責任を転嫁することは許されない。 なお、本件覚書3項ただし書は、公演内容について公演ごとに許諾を要するという趣旨ではなく、今後のAの関与をどのようにするかを協議するというものであった。 エ 平成8年12月4日の通告は、本件覚書の撤回ないし解除とは認められない。 【原告の主張】 (1) 原告が被告朝日新聞社及び被告劇団ひまわりとの間の本件覚書により被告3名主張の承諾をしたことは認める。 (2) しかし、本件覚書は、平成8年12月4日、原告が被告朝日新聞社に、原告著作の絶版と舞台劇「コルチャック先生」の公演に一切関わらない旨通知し、その直後ごろ、被告朝日新聞社から被告劇団ひまわりにも伝達されたことにより、失効した。失効の理由は、次のとおりである。 ア 本件覚書による契約は無償契約である。無償契約は、法律的規範意識とともに好意、礼譲、社交などの社会的規範意識によって強く支えられているところにその特色がある。そして、その基盤となっているのが当事者間の好意、信頼関係である。したがって、この好意、信頼関係が破壊された場合、無償契約の基盤は根底から覆ることになり、この場合、好意、信頼関係を破壊された当事者は当該無償契約を撤回・解除できるものと解される。 そして、争点(2)アで主張するように、平成8年11月26日の朝日新聞夕刊において、被告朝日新聞社が、95年公演の原作者が原告でなかったかのような誤報記事を掲載し、これにつき原告が抗議しその訂正を求め、その後被告朝日新聞社と交渉したが、同被告は極めて不誠実な態度に終始したため、原告が本件覚書で与えた好意と信頼関係は、被告朝日新聞社によって完全に覆された。 したがって、原告は、本件覚書による公演の承諾を撤回・解除することができる。 イ 著作者人格権に基づく撤回 原告は原告著作につき著作者人格権を有するところ、著作者人格権には撤回権が含まれている。撤回権とは、著作者が著作物利用者に翻案、公演等を許諾し、公表を承諾した後に、著作者の精神的利益を害するような事由が生じた場合に著作者は許諾を撤回することができる権利を意味する。 本件では、前記アの被告朝日新聞社の不誠実な態度に加えて、次の事情があった。すなわち、舞台劇「コルチャック先生」については、平成8年夏ごろから再演の話が出ていたが、原告との協議を全くしないまま、同年11月20日ころ、被告劇団ひまわりの制作担当のB及びCの両名が原告宅を訪れ、突然「97年に再演を行う、そこでは95年公演と同様『原作X、脚本原作A』と表示するか、 それともいずれとも全く表示しないことにする」旨通告してきた。 しかし、95年公演の際も原作者はあくまでも原告であるから「原作X」とだけ表示すべきであったが、原告は、被告朝日新聞社から懇願されたため、 「脚本原作A」との表示に対し、「私の決めることではない」と答えた。原告が「脚本原作A」との表示を入れることに反対であったのは、脚本執筆は被告Yであり、Aではないし、Aの著作「コルチャック先生ーある旅立ち」は原告著作を原告に無断で翻案したものであり、しかも同著作では原告著作が描いたコルチャック像が正確に示されず、むしろ歪曲されたものになっており、原告著作の翻案というにはおよそふさわしくなく、コルチャック研究者である原告としては、再び原告名と「脚本原作A」が併記されることは耐え難いことであったからである。 また、再演(97年公演)において原作者を表示しないのは、原告著作につき著作権、著作者人格権(氏名表示権)を有する原告として到底許し難いものであることはいうまでもない。 このように、前記通告は、原告著作の著作者である原告の精神的利益を侵害すること甚だしいものである。 よって、原告は平成8年12月4日、前記撤回権を行使し、前記のとおり被告朝日新聞社にその旨の意思表示をしたものである。 ウ 法定解除権の行使 前記のとおり、本件覚書第3項ただし書に、再演に当たっては被告朝日新聞社と被告劇団ひまわりは事前に原告と協議すべき旨の約定がある。いうまでもなく、この協議は、原作者である原告にとっては極めて重要な意味を持つものである。再演に当たって原作がどのように利用されるのか、初演と同じなのか、いくらか改変がなされるのかなどは、著作権者としては重大な関心事だからである。 原告は、被告朝日新聞社と被告劇団ひまわりが平成9年に再演を行うということを平成8年夏ごろ聞いていたが、両被告からの協議の求めは全くなかった。そして、協議が全くないまま、平成8年11月20日ころ、被告劇団ひまわりから前記イで述べた通告がなされた。この通告が原告にとって到底受け入れられないのは前記のとおりである。原告を原作者として表示しないということは、原告を原作者として扱わないとの意志の表明にほかならないから、そこにはもはや協議の余地はなく、協議の催告は無意味である。 そこで、原告は、両被告の協議義務の不履行を原因として、前記のとおり、平成8年12月4日、被告朝日新聞社に対して本件覚書による契約を解除する旨の意思表示をした。 3 争点(1)ウ(損害) 【原告の主張】 被告3名は、97年公演により、少なくとも1億4300万円の利益を上げたから、これが原告の受けた損害の額と推定される(著作権法114条1項)。本件では、このうち8000万円の請求をする。 【被告3名の主張】 争う。 4 争点(2)ア(本件記事の名誉・信用毀損性)について 【原告の主張】 原告は、永年にわたるコルチャック研究活動と、主としてヨーロッパのコルチャックの友人、教え子、コルチャック研究者らとの頻繁・密接な交流・交友を通じて、コルチャック研究者として内外で高い評価を得ているほか、95年公演の舞台劇「コルチャック先生」が原告著作を原作として日本で初演されたことは、ヨーロッパを始め世界各地のコルチャックの教え子、友人、コルチャック研究者らに広く知れわたっていた。 ところが、被告朝日新聞社は、本件記事により、あたかも95年公演にかかる舞台劇「コルチャック先生」の原作者が原告ではなかったかのように報道した。 そして、本件記事がヨーロッパ各地のコルチャック研究者らに流布されたことにより、原告は、95年公演があたかもAの作品によるものであったとの誤解を広く内外で受けることになり、研究者・原作者として誠に耐え難い激しい精神的苦痛を受け、コルチャック研究者としての名誉、声望を著しく害されるとともに、95年公演の原作者として実質的にその氏名表示権を侵害された。 したがって、被告朝日新聞社による本件記事の掲載は、原告に対する不法行為を構成する。 【被告朝日新聞社の主張】 原告の主張は争う。 まず、95年公演は、原告著作を翻案して製作されたものではない。 次に、本件記事は、平成7年に日本で公演されたコルチャック先生の舞台劇について、その原作者については触れておらず、95年公演の原作者が原告でなかったとの事実を伝達するものではない。本件記事中の「この劇」の語は、「コルチャック先生の舞台劇」という意味で用いられたもので、Aの脚本による舞台劇が95年に日本で初演されたとの趣旨ではない。なお、95年公演は、「原作X、脚本原作A」と表示して行われており、表記上は、Aの脚本による劇「コルチャック先生-ある旅立ち」は95年公演の「脚本原作」に当たることになる。 5 争点(2)イ(損害額)について 【原告の主張】 被告朝日新聞社の本件記事の掲載によって原告が受けた精神的苦痛を慰藉するには、少なくとも1000万円の支払をもってするのを相当とする。 【被告朝日新聞社の主張】 争う。 6 争点(2)ウ(謝罪広告の必要性)について 【原告の主張】 本件記事による誤報を訂正するとともに、原告の名誉を回復するには、別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告の掲載が必要不可欠である。 【被告朝日新聞社の主張】 争う。 7 争点(3)ア(本件放送の著作権侵害性)について 【原告の主張】 被告日本放送協会は、本件放送において、原告著作を翻案した95年公演を収録した番組を放送したことにより、原告の著作権(公衆送信権)を侵害した。 【被告日本放送協会の主張】 95年公演が原告著作を翻案したものである点は不知。本件放送が原告の著作権を侵害した点は争う。 8 争点(3)イ(本件放送の許諾)について 【被告日本放送協会の主張】 原告は、本件放送について、予め承諾していた。 【原告の主張】 否認する。 9 争点(3)ウ(損害額)について 【原告の主張】 被告日本放送協会の不法行為によって原告が受けた損害を評価すれば、1000万円とするのが相当である。 【被告日本放送協会の主張】 争う。 |
|
|
争点に対する当裁判所の判断
1 争点(1)(97年公演の翻案性)について (1) 事実経過 証拠(後掲各書証、甲30、乙24ないし26、証人D、同B、同E、原告本人及び被告Y本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。 ア 原告による原告著作の執筆 原告は、高校で教職に就いていたが、昭和49(1974)年にミュンヘンに旅行した際に、コルチャックの「ゲットー日記」に接したことがきっかけとなって、コルチャックについての研究を始めることとなり、退職して、昭和51(1976)年から同55(1980)年ころまではミュンヘン大学等において、 同56(1981)年以降はギーセント大学において研究を行うかたわら、コルチャックに関する論文やエッセイ等を発表し、また、コルチャックに関する映画や絵画等の企画にも参加するなどし、同年、国際コルチャック協会よりコルチャック記念メダル賞(研究と思想紹介)を受賞した。 原告は、1980年代後半になって、コルチャックを講座に取り上げる大学が増えてきたことから、日本にもコルチャックを紹介する時期がきたと考え、 昭和61(1986)年、第2回朝日ジャーナルノンフィクションにコルチャックの伝記を執筆して応募したところ、入賞し、それを基にして、平成2(1990)年12月30日に原告著作(甲1)第1刷が被告朝日新聞社から刊行された。原告著作は、我が国で刊行されたコルチャックの伝記としては、最初のものであった。 イ 原告著作の内容 原告著作は、B6版225頁(あとがきを含む。そのほか、巻末にコルチャック年譜と参考文献が収録されている。)からなる書籍であり、コルチャックの生い立ちから、トレブリンカに移送されるために貨車に乗り込むまでの生涯を、 種々の史料に基づいて記述したものであるが、その概要は、次のとおりである(甲1)。 (ア) 序 トレブリンカの森(3~9頁) 第二次世界大戦中にナチスによるユダヤ人大虐殺の場となったトレブリンカの風景と歴史を記述し、併せてその地で200人の子供たちと共に大虐殺の犠牲となったコルチャックを紹介して、本編への導入としている。 (イ) Ⅰ 生いたちと青年時代(11~51頁) ここでは、コルチャックのポーランドでの生い立ちから、1898年にワルシャワ大学の医学部に入学した後、ワルシャワ慈善協会やさまよえる大学に参加し、1904年に日露戦争に軍医として従軍し、ロシア第一次革命が敗北に終わった後、1906年にベルリン及びパリの大学に留学に出るまでを、当時のヨーロッパにおけるユダヤ人の置かれた状況、ポーランドにおけるユダヤ人の状況、ポーランドの歴史等を織り交ぜて記述している。 (ウ) Ⅱ 「孤児たちの家」と「僕たちの家」(53~97頁) ここでは、コルチャックがユダヤ人の子供たちのために1912年に設立した「孤児たちの家」(「ドム・シェロット」ないし「クロフマルナ」)と、 ポーランド人の子供たちのために1919年に設立した「僕たちの家」(「ナシュ・ドム」)の運営状況を中心に、当時の教育事情とコルチャックの教育思想が記述されている。 (エ) Ⅲ 両大戦の間 1918-1939(99~139頁) 第一次大戦の終了によってポーランドが独立した共和国となった後、 ナチスが台頭して第二次世界大戦が始まるまでの間のコルチャックの活動と思想を、子供たちを対象にした新聞「小評論」の発刊と断絶、各種の文芸活動、パレスチナへの訪問、「老博士のお話」という連続ラジオ番組の放送とその中止、「ナシュ・ドム」との関わりの断絶等を中心に、当時のポーランド情勢やユダヤ人の置かれた状況を織り交ぜて記述している。 (オ) Ⅳ 精神の王国-ワルシャワ・ゲットーのなかで(141頁~208頁) 1939年に第二次世界大戦が勃発し、ドイツ軍がポーランドを占領した後、1940年11月にコルチャックとその子供たちを含むユダヤ人がゲットーに送られた後の、ゲットーでの生活状況と、コルチャックの活動及び思想が記述されている。 (カ) Ⅴ 死への行進(209頁~218頁) 1942年8月に、コルチャックとその子供たちが、トレブリンカに移送されるときの状況が記述されている。 ウ 95年公演に至る経過 (ア) 公演企画の発端 a 平成6年春ころ、日本コルチャック協会東京支部事務局長のFと同協会のAが、被告劇団ひまわりを訪れ、原告著作とAの書いた戯曲「コルチャック先生-ある旅立ち」(以下「A戯曲」という。)を材料として、コルチャックの物語を演劇舞台化できないかとの相談をしたが、被告劇団ひまわりの取締役で劇団の業務統括の任にあったBは、舞台化は難しいと返答した。 しかしその後、Fらから要請を受けた被告朝日新聞社のG編集委員(以下「G」という。)が被告劇団ひまわりを訪れ、「コルチャック先生」の演劇公演の実現を要請し、実現すれば被告朝日新聞社も新聞紙上で協力すると説明したため、被告劇団ひまわりは、再検討した上、同年5月ころ、被告劇団ひまわりが台本作成や出演者等を自由に決定することができることを前提として、企画を進めることとし、G及びFにその旨説明して了承を得た。その際、Bは、原告著作及びA戯曲は、いずれも演劇の脚本を作成するに当たって資料程度にしかならないと主張していた。 b そこで、被告劇団ひまわりでは、平成6年6月ころ、演出の担当として決定したHから脚本の作成者として被告Yの推薦を受け、同被告に脚本の執筆を依頼した。Bは、その依頼に当たっては、A戯曲をそのまま使うのは無理なので、新しい台本についてはどのように書いてもよいと伝えた。 c 他方、被告朝日新聞社では、「コルチャック先生」の演劇公演を、 同社の戦後50年記念事業として、製作費を被告劇団ひまわりと折半して共同で主催することとし、具体的には事業開発本部の映像イベントチーム(チーフはD)が担当となって、被告劇団ひまわりと実務的な作業をすることとなったが、原告やFなど日本コルチャック協会との接触はGが行っていた。 (イ) 原告とAのクレジット表示に係る経緯 a 平成6年7月29日、被告朝日新聞社は、朝日新聞紙上に、「劇団ひまわり『コルチャック先生』公演」と題する社告を掲載した。そこでは、「X氏の著作『コルチャック先生』(朝日新聞社刊)を、劇団ひまわりが上演します。…演出はH氏、脚本はエルサレム在住のA氏。朝日新聞社事業開発本部と劇団ひまわりの共催で、来年夏以降、東京などで公演の予定です。」と記載されていた(甲21の2)。しかし、このようなクレジット表示による社告を掲載することについて、被告劇団ひまわりは全く知らされなかった。 他方原告は、この社告を見て、Gに対し、A戯曲は正しいコルチャック像が描写されていないから上演に賛成しない旨を述べていた。 b 同年8月ころ、Bは、G及びFから誘われて、被告劇団ひまわりの大阪支部で、海外出張から帰国した原告と会った。 c 同年11月4日、Bは、Hと共に京都市の原告宅を訪問した。このときBは、自ら作成した「企画概要」と題する書面(甲19)を持参し、原告に交付したが、そこには、「作品 舞台劇『コルチャック先生』」、「原作X(『コルチャック先生』朝日新聞社)」、「上演台本 未定」等と記載されていた。 同月11日、Gは原告に手紙を送った(甲15末尾)。そこには、 「ひまわり座へのご協力の件、Xさんより快諾をいただいたとB氏が喜んでおりました。私からも厚くお礼を申し上げます。今度の騒ぎは、Aさんが自分の脚本をoriginalと主張したことから始まっており、その点でAさんに責任があります。」と記載されていた。 d 同年12月13日、原告は、被告朝日新聞社東京本社を訪れた際、 「『コルチャック先生』公演概要」と題する同月8日付けの書面(甲20)を渡された。これは、被告朝日新聞社が社内説明用に作成したもので、「作品 舞台劇『コルチャック先生』」、「原作X(『コルチャック先生』朝日新聞社)」、「上演台本A」と記載されていた。 e 同年12月から平成7年1月ころ、被告劇団ひまわりは、95年公演の仮チラシを作成した(甲12の1)。そこには、「原作X(『コルチャック先生』朝日新聞社)」と記載されていたが、台本の担当については記載がなかった。 f 当時、被告朝日新聞社では、aの社告やdの内部説明用資料に見られるように、「原作X(『コルチャック先生』朝日新聞社)」、「上演台本A」のクレジット表示をすることを考えていたが、被告劇団ひまわりは、原告著作は原作ではなく、台本は被告Yが作成するものであるとして、これに反対していた。しかし、被告朝日新聞社のGは、被告朝日新聞社が共同主催者になって費用を負担するためには、社内的に、被告朝日新聞社から出版されている原告著作がその原作となり、95年公演がその宣伝にもなることが必要であり、そのためには、「原作X(『コルチャック先生』朝日新聞社)」のクレジット表示が必要であるとして、同表示を強く求めたため、被告劇団ひまわりは、同表示は著作権法上の原作表示ではないとの理解の下に、同表示をすることに同意した。しかし、Aのクレジット表示については、未解決のまま残っていた。Bが作成したcの「企画概要」やeの仮チラシにおいて、台本の担当は既に被告Yに依頼をしていたにもかかわらず、未定とされたり、全く記載がなかったりしたのは、このような事情によるものであった。 g ところが、Aから、被告朝日新聞社のGやDに対し、原告著作が「原作」と表記されているにもかかわらず、A戯曲については何のクレジット表示もされないことについて強い抗議がなされた結果、平成7年3月23日、被告朝日新聞社、被告劇団ひまわりとAの三者の間で、95年公演においてAに関しては、 「脚本原作:A(『コルチャック先生・ある旅立ち』)」と表記すること等を内容とする覚書(乙10)が作成された。 h その直後の平成7年4月5日、Bは、原告夫妻宛に書簡を送付した。そこには、次のように記載されている(甲12の2)。 「これまでの経過を御説明申し上げますと、今回 '95年8月の『コルチャック先生』公演のベースになるのはX先生の原作によります。 …… これまでA氏のスタッフとしての名称について製作側とA氏との間で意見がまとまらず時が過ぎてしまいましたが、3月31日にA氏との間で覚書がかわされました。A氏のクレジットは『脚本原作』という結論になりました。 劇団ひまわりとしては、原作:X氏、脚本:Y氏、上演台本:劇団ひまわり文芸部としたかったのですが、朝日新聞社のGさんとA氏との係わりがあり、以下の結果となりました。但し、今年度限りの約束であり、来年以降についてはA氏に関しては話し合いをしなければなりません。現在のところ来年以降に劇団ひまわりとの関係を継続する予定はありません。以下決定事項をお知らせ致します。…… 〈主なスタッフ〉 原作: X(朝日新聞社『コルチャック先生』より) 脚本原作: A(『コルチャック先生・ある旅立ち』) 脚本: Y …… 最後までA氏の処遇を巡って、解決される時期が遅くなってしまいましたが、いよいよ本格的に製作スタートとなりました。 X先生の原作料につきましては近々、朝日新聞社と相談したうえで、私の方から御連絡させて頂きますので宜しくお願い致します。」 そして、原告は、GからもAのクレジット表示を了承するよう懇願され、反対ではあったが、自分の決めることではないと答え、クレジット表示の問題は落着した。 (ウ) 台本と製作の進行 a ところで、被告Yは、平成6年6月にBから「コルチャック先生」の台本の執筆依頼を受けた後、7月ころから、資料の収集を開始した。被告Yが、 台本の執筆に当たって参考とした資料は、次のもの等であった(甲10の末尾)。 ・原告著作 ・A戯曲 ・ベティ・J・リフトン「子どもたちの王様」(乙3) ・アンジェイ・ワイダ監督の映画「コルチャック先生」のビデオ(乙5)及びその採録シナリオ(乙6) ・ブラドカ・ミード著「壁の両側 ワルシャワ・ゲットー1942~1945」(乙7。1992年11月18日初版発行) b その後、被告Yは、Hなどと相談をしながら執筆を進めていたが、 Hは疑問点などについて、原告やAに相談をしていた。 また、執筆の途中に、Bから被告Yに対し、原告著作を原作と表記することとなったので、どう使っても構わない、できるだけ使わせていただくようにとの連絡があり(甲34)、これを聞いて被告Yは、資料的に大きな後ろ盾ができたと感じた。 こうして被告Yは、平成6年末までに第1稿を執筆し終えたが、その後もHの希望等による練り直しがなされた。 c Hは、平成7年1月31日付けの手紙に仮チラシを同封して原告に送付した(甲23)。この手紙には、次のように記載されている。 「制作のBがヨーロッパ出張で、帰国(2月中旬予定)しましたらご連絡すると存じますが、目下の進行状況は-- Yさんというプロの脚本家に依頼しまして、上演台本の準備稿を執筆してもらっている最中で、2月中旬には第1稿が出来上る予定です。 A脚本とは大幅に違うものとなるでしょう。 準備稿を更に改稿したものを、上演台本の第1稿として活字にすることになるでしょう。その段階で稽古用の台本という形になるわけです。それをお送りできるのは3月中旬頃でしょうか。 よろしくご一読下さい。」 d また、Bも、平成7年2月9日付けの葉書を原告夫妻宛に出した(甲24)。そこには、次のように記載されている。 「しばらくごぶさたしています。現在英国に出張中です。 『コルチャック先生』はいよいよ製作開始となります。帰国するころには、台本の準備稿も完成する予定です。どうかいろいろと御協力下さい。」 e こうして準備稿として印刷されたものが完成し、平成7年2月24日に原告に送付された。 (なお原告は、前記(イ)cの書面の記載等を根拠として、95年公演の台本の執筆担当者は、原告著作を「原作」とすることが決まった後に、平成7年1月になって初めて決まったものであると主張する。しかし、平成7年8月に公演を行うに当たって、同年1月に台本の執筆が始まるというのでは、公演に間に合わないと考えられる上、前記cのHの書簡に記された台本の仕上がり予定に照らしても不可能なことである。また、前記(イ)cの書面に上演台本が未定であると記載されたのは、前記のとおり、Aのクレジット表記をめぐる問題が解決していなかったことによるものであると認められる。他方、公演予定の約1年前に脚本家に執筆を依頼するというのは、製作のスケジュールからして自然なことといえるから、被告劇団ひまわりが被告Yに台本の執筆を依頼したのは、平成7年6月ころであると認めるのが相当である。) (エ) 製作発表と上演 a その後、平成7年6月に95年公演の上演台本の最終稿(甲10)が完成し、同月27日に製作発表会が行われた。 この間、原告は、脚本の作成や稽古の過程でHから種々の相談を受けたり、登場する子供たちの名前をコルチャックの「ゲットー日記」等から抜き出して一覧表にして送付したり、写真や資料を提供したり(甲13、14)、稽古場に赴く等、95年公演の製作に協力した。 また、被告劇団ひまわりからは、原告に対し、制作発表会の前日に謝礼として約30万円が渡されたが、原告は、これを同年11月ころに返却した。 b また、被告朝日新聞社は、原告著作の文庫版(平成7年7月発行)の帯に「この夏 舞台化!!」と表示し(甲9)、製作発表会の席上、原告を原作者として紹介し、広告(甲21の1)や公演パンフレット(甲6)においてもすべて原告を原作者、原告著作を原作として記載した。 c そして、95年公演は、前記第2の1(3)記載のとおり、平成7年8月に東京と大阪で行われた。 エ 97年公演に至る経緯 (ア) 覚書の作成 原告は、平成7年4月5日にBから書面(前記ウ(イ)h)が送付されると、その内容について契約書を作成するよう求めていたが、同年12月14日に被告朝日新聞社、被告劇団ひまわりと原告との間で覚書(本件覚書。乙1)が作成された。 本件覚書には、次の記載がある。 「 〔本公演〕 作品:舞台劇「コルチャック先生」(以下本作品という) 公演日程:1995年8月12日~23日 東京・パナソニックグローブ座(16回公演) 1995年8月26日~30日 大阪近鉄劇場(7回公演) 1)本公演に於いて丙(注:原告)に関しては、原作:X(『コルチャック先生』朝日新聞社刊)と表記する。 2)「脚本」は、Yとし、以降、『脚本』および『脚本』をもとに作成した『上演台本』は甲(注:被告朝日新聞社)、乙(注:被告劇団ひまわり)が保持する。 3)1995年8月12日以降、5年間に渡り、甲、乙は、本作品の公演を実施する際、甲、乙が保有する『上演台本』を以て、自由に公演を行う事ができる。 但し、甲、乙は、今後行う各公演ごとに事前に誠意をもって丙と協議するものとする。 4)甲、乙より丙に対する報酬は、原作料を無料とする。」 この3項ただし書は、被告朝日新聞社及び被告劇団ひまわりが作成した当初の案文にはなく、協議の過程で原告側からの希望により挿入されたものであった。 (イ) 97年公演をめぐるやりとり その後、Bは、原告に対し、何度か97年公演を行うことについて話をし、そのたびにAのクレジット表示をどうするかということが話題となっていたが、平成8年11月20日、Bが被告劇団ひまわりのCと共に原告宅を訪問した際、Bらは、97年公演については、被告朝日新聞社が被告劇団ひまわりと共催するのであれば、クレジット表示は95年公演と同じ表示になるが、被告劇団ひまわりの単独主催の場合には、原告とAの双方とも原作表示はせず、原告は「製作協力」等の表示になるだろうと見通しを述べた。 (ウ) 本件記事の掲載と原告による抗議 その直後の平成8年11月26日の朝日新聞夕刊に、本件記事(甲7)が掲載され、Bはそのコピーをファックスで原告に送った。 本件記事に対し、原告は、同年12月2日、被告朝日新聞社に対し、 日本での「コルチャック先生」の公演は原告の原作によるものであり、A戯曲を脚本とするものではないから、本件記事は誤報であるので訂正を求める旨のファックスを送信した(甲15)。これに対して被告朝日新聞社のDらは、翌3日に原告宅を訪れて、本件記事は、ドイツでA戯曲が高校生によって上演されたことを伝えるもので、日本での公演について報道したものではないなどと事情を説明したが、翌4日に原告は、被告朝日新聞社に対し、「①朝日文庫『コルチャック先生』の絶版、②演劇公演には一切関わらない」旨をファックスで送信した(甲16)。 (エ) その後の状況 このような状況を受けて、Bは、平成8年12月以降、被告Yに対し、原告著作を原作と表記しないこととなったので、原告著作から離れるように脚本を書き直すよう依頼した。 被告Yは、この依頼に基づき、新たな視点から97年公演用の台本を執筆したが、演出家や出演者等の意見によって95年公演の内容に戻る方向での修正を経た後、平成9年6月5日に決定稿が完成し(甲11)、その後の稽古中にも更に修正が加えられて、同年8月に東京と大阪で97年公演が行われた(検甲3)。97年公演に当たっては、95年公演に見られたような、原告著作を「原作」、A戯曲を「脚本原作」とするクレジット表示はなされず、「監修・企画協力 アンジェイ・ワイダ」と表示された(甲26)。ただし、97年公演のプログラム(甲26)中には、「舞台劇『コルチャック先生』が誕生するまで」と題する箇所で、「舞台劇『コルチャック先生』は戦後50年にあたる1995年8月、東京と大阪で公演され、大好評を博しました。この公演が誕生するまでには、『コルチャック先生』(朝日新聞社)の著者で舞台劇の『原作』を担当された国際コルチャック協会理事のX氏(原告)、戯曲『コルチャック先生・ある旅立ち』(文芸遊人社)の著者で舞台劇実現に努力し『脚本原作』を担当されたA氏……に一方ならぬ協力をいただきました。」と記載されていた。 97年公演の内容(本件舞台劇)は、ほぼ別紙対照表の上段記載のとおりである(検甲3、乙2)。 また、この間、Bは、原告に対し、97年公演の企画書や上演台本を送付するなどした(丙1ないし8)。 (2) 97年公演の翻案性について ア 97年公演に係る本件舞台劇が原告著作を翻案したものであるといえるためには、本件舞台劇が、原告著作に依拠して創作されたものであり、かつ、原告著作の創作性のある部分における表現上の本質的な特徴を直接感得することができるものであることが必要である。 ところで、原告著作は、歴史上実在する人物の生涯を、各種の史料によりながら記述した伝記の範疇に属する文学作品であるといえる。このように歴史上実在する人物の伝記についても、著作権が成立し、その翻案があり得ることはもちろんである。しかしながら、史実や史料の記載は客観的な事実であって、たとえその発見が独自の研究や調査の結果によるものであったとしても、それ自体に著作権が及ぶものではない。したがって、原告著作の表現上の本質的な特徴を本件舞台劇から直接感得することができるか否かは、原告著作が、史実や史料を踏まえてコルチャックの生涯をどのように表現している点に創作性のある表現上の特徴が見られるのか、また、本件舞台劇はそのような原告著作の創作性のある表現上の本質的な特徴を直接感得し得るのものといえるかを検討する必要があるというべきである。 イ そこでまず、原告著作と97年公演に描かれた全体の筋とコルチャックの人物像について検討する。 前記のとおり、原告著作では、コルチャックのほぼ全生涯を対象としているが、97年公演では、ナチスドイツによるポーランド侵攻を間近に控えた1935年(コルチャック57歳)以降を対象としている。 両者に共通する1935年以降の基本的な筋を見ると、①ナチスドイツが隆盛になる中、コルチャックは、ユダヤ人であったために、それまで担当していたラジオ番組を中止され、また自らが設立したポーランド人孤児のホームを追われ、ユダヤ人孤児のホームの運営のみを行うようになった、②その後、ポーランドに侵攻したナチスドイツ軍により、ユダヤ人特別居住区のワルシャワ・ゲットーが作られ、コルチャックとそのホームの子供たちはゲットーに強制移住させられた、 ③ゲットーでの生活は苛酷なものであったが、コルチャックは、子供たちの生活のために、食糧・寄付集めに奔走しつつも、ホームではハヌカの祭りを祝い、劇を上演するなどした、④しかし、ナチスドイツはゲットーのユダヤ人をトレブリンカ絶滅収容所に移送することを開始し、コルチャックとその子供たちにも移送命令が下りた、⑤コルチャックが子供たちと共に移送用の貨車に乗り込もうとしたところ、 関係者の努力で特赦の知らせが届いたが、コルチャックは、自分だけの特赦を受け入れず、子供たちと共に貨車に乗り込んでトレブリンカへ旅立った、というものであり、このような基本的な筋は、両者に共通している。 また、コルチャックの人間像としても、ポーランドに生まれ育ちながら、ユダヤ人であるために迫害を受け、これに苦悩しつつも、極限状態の中で子供たちと共に生き、子供たちと共に死の道を選んだ人物として描かれている点において、両者は共通している。 しかし、コルチャックの生涯については、原告著作が平成2年12月に発刊される以前から、外国においては多数の文献が公表され、映画も製作されている(甲1の巻末参考文献欄参照)。本件において証拠として提出されている主たるものは、乙3(ベティ・J・リフトン著「子どもたちの王様」。昭和63〔1988〕年にアメリカで発刊され、平成3年7月に我が国で邦訳出版された。以下「リフトン著作」という。)、乙4(モニカ・ペルツ著「コルチャック」。昭和60(1985)年にドイツで発刊され、平成6年7月に我が国で邦訳出版された。以下「ペルツ著作」という。)及び乙5(アンジェイ・ワイダ監督による映画「コルチャック先生」のビデオ。この映画は平成2〔1990〕年にポーランドで製作され、我が国では平成3年9月に岩波ホールで上映された。乙6のパンフレットにその日本語版採録シナリオが収録されている。以下「ワイダ映画」という。)であり、それらによれば、前記の基本的な筋は史実であって、原告著作の創作によるものではないと認められる。また、前記のようなコルチャックの人物像は、前記著作においても同様に描かれているところであって、原告著作のみに見られる創作的な人物像というわけではない。 したがって、前記のような基本的な筋や人物像に、原告著作における創作性のある表現上の特徴を認めることは相当でなく、原告著作の創作性は、前記のような筋や人物像の具体的な表現の仕方にあるというべきである。 ウ そこで次に、前記のような基本的な筋及び人物像の、原告著作における表現の仕方と、97年公演における表現の仕方を全体的に検討する。 (ア) まず、表現の方法として、原告著作においては、基本的に、史実と先行資料及び関係者の証言を織り合わせ、それに説明を加えることによって、時代状況やコルチャックの行動、心情、人間関係等を客観的に描き出すという表現方法が採られている。 これに対し、97年公演は、舞台演劇という性質もあって、コルチャックや周囲の人々の会話(せりふ)によって、時代状況、コルチャックと関係者の人間関係や心情等を描くという表現方法が採られている。 (イ) 対象とする期間は、原告著作は、コルチャックの全生涯を対象として描き出しているのに対し、97年公演では、コルチャックが最も受難の時代を過ごす1935年以降に焦点を絞って描いている。97年公演のような時期に焦点を当てて描写することは、ワイダ映画におけるのと同様である。 (ウ) 登場人物については、原告著作では、(ア)のような叙述の関係上、 実在した人物しか登場せず、しかもその行動は客観的に記載され、コルチャック以外の関係者の心情が描かれることはほとんどない。 これに対して、97年公演では、原告著作にも登場する実在の人物のほかに、リフトン著作には登場するが原告著作には登場しない人物(ルビンシュタイン)や、同公演において創作された人物(フリーダ、ユゼフ、イレーナ、ボレクなど)も登場する。このうちユゼフは、妹のフリーダをコルチャックのホームに預けた兄としての役割のほかに、ゲットーにおける少年の代表としての役割を与えられて、ゲットーにおける少年たちの状況やユダヤ人抵抗組織の活動などを描写するに当たって重要な役割を与えられているといえる。また、イレーナは、コルチャックのホームの卒業生であり、ドイツ軍によって収監されたコルチャックの保釈に尽力するとともに、ガンツバイクを初めとするゲットーでのユダヤ人裏社会に通じ、 最後は独力でゲットーを脱出して生き抜く途を選ぶなど、ゲットーの中でコルチャックを慕いつつ、独力で生き抜く女性を描写するものとして、重要な役割を与えられているといえる。さらに、ボレクは、かつてユゼフの近所に住んでいたが、現在ではユダヤ人警察に所属し、同胞を取り締まる立場になった者であって、ゲットー内におけるユダヤ人社会の複雑さを描写するに当たって、重要な役割を与えられているといえる。 ウ 次に、より具体的に、97年公演の各場ごとに検討する。 (ア) プロローグ(トレブリンカ)〔別紙対照表1~3頁参照〕 a この場は、現在のトレブリンカの地を訪れた俳優が、その様子や歴史について独白をするものである。 b 冒頭に現在のトレブリンカの風景をその歴史と共に描写するシーンが置かれるのは、原告著作でも同じであり、これは他の文献や映画には見られない点である。 また、具体的には、97年公演と原告著作とは、ユダヤ人絶滅収容所がこの地にあり、多くのユダヤ人が貨車で送り込まれてガス室に送られたこと、 そのための引き込み線の跡があること、大地から多数の石が突き出していること、 その石は墓であること、それらの石の中にコルチャックと子供たちの墓があることが描写されている点で共通している。 しかし、トレブリンカにユダヤ人絶滅収容所が置かれ、多くのユダヤ人が貨車で送り込まれてガス室に送られたことは歴史的事実であって、リフトン著作364頁以下にも記載されている。 また、コルチャックの生涯は、「第二次世界大戦末期、地獄のようなワルシャワ・ゲットーで子供たちを守り、ついにはガス室で子供たちと共にその生涯を閉じた」(ペルツ著作の表紙カバー)点が一般に注目されていることから、 トレブリンカの地は、コルチャックの生涯の象徴ともいえる地であるところ、歴史的な人物や事件を扱うドラマにおいて、そのドラマを象徴する地の現在の様子の描写から始めることは、多くのドラマに見られる一般的な手法であるといえる。 さらに、トレブリンカにおいては、現在、慰霊碑を中心に多くの角張った石塊が置かれており、その中にコルチャックとその子供たちの名が刻まれたものがあることは、客観的事実である(甲6及び乙7掲載の写真)。また、トレブリンカに置かれた多数の石塊をその地で虐殺されたユダヤ人の墓であると考えることは、リフトン著作(370頁)に「戦後その地に、広大な石の庭園が設置された。ポーランドの石切り場からもちこまれた、1万7千個の岩石は、この地で最期をとげた何百万の男女や子どもの、町や村や国を象徴している。」とあり、乙7(ブラドカ・ミード著「壁の両側」平成4年11月邦訳出版)の436頁において、筆者が現在のトレブリンカに赴いた際の記述として、「私たちは、何度も何度もこの広大な墓地を見渡しました。そして、幻を見ました。石は生き返り、ユダヤ人となって動き始める。」とされていることからして、一般的なとらえ方であると認められる。なお、原告は、「角張った石」と描写しているのは原告著作のみであり、リフトン著作では「岩」と描写されていると主張するが、97年公演は演劇であって、石ないし岩は、背景のセットとして視覚的に描写されているにすぎないから、言葉として「角張った石」とされているか「岩」とされているかを、97年公演の翻案性を判断するに当たって考慮することは相当でないというべきである。 c 原告は、別紙対照表において、①原告は演出担当のHに対して、小さな石を子供とすることやハーモニカの使用等を助言したこと、②このシーンは95年公演の準備稿において既に描かれていたこと、③トレブリンカへの距離は原告著作だけがキロ表示をしていること(他の著作はマイル表示)、④このシーンはI著「コルチャック先生」にも描かれており、演出家は出演者にそれを何回も読ませたことを指摘している。 しかし、①及び④は97年公演が原告著作を翻案したものであるか否かとは何ら関係のない事柄であるし、②も同様である(なおこのシーンは、95年公演の準備稿〔2000年4月13日付け原告第五準備書面添付〕の冒頭のシーンとは内容が異なる。)。また、③については、トレブリンカへの距離は客観的な事実であり、原告著作はそれを単にキロで表示したにすぎず、その点に創作性はない。 (イ) 第1幕・1(ユダヤ人兄妹)〔別紙対照表3~6頁〕 a この場の概要は、次のとおりである。 二人暮らしのユダヤ人の兄妹(ユゼフとフリーダ)の家にユダヤ人排斥の投石等がなされる中、フリーダがおびえながらコルチャックのラジオ番組を待っていると、ユゼフが戻ってきてフリーダに母の形見を渡し、その後、ラジオからコルチャックが担当していた「老博士のお話」が流れてくる。 b このようなユダヤ人の兄妹は、原告著作には登場しない。もっともリフトン著作(318頁)に記載されたユダヤ人兄妹サムエルとギエナに類似するものとも思われ、このことは、Bが製作途中に原告に宛てた手紙の中で、「リフトン氏の引用についてはサミエルとギエナの表現が一番問題です。名前と設定を変更して、プログラムにのみリフトン氏の引用クレジットを入れる方針です。」(甲12の2)と記載していることからも裏付けられる。しかし、その後の場に見られるユゼフとフリーダの役割は、リフトン著作にも見られないものである。 また、当時、ポーランド国内でユダヤ人に対する投石や侮辱が行われていたことは、原告著作にも記述があるが、これは歴史的事実であり、リフトン著作(196~197頁、235頁及び246頁)及びペルツ著作(123頁)にも記載がある。 さらに、コルチャックが「老博士のお話」というラジオ番組を担当していたことも歴史的事実であり(リフトン著作224頁以下)、その中で、少年時代に雪の日に馬車に乗って通学したときの話が語られたことも歴史的な事実である(ペルツ著作7頁以下)。 もっとも、コルチャックが「老博士のお話」の番組で語ったものには多数のものがあると思われる(リフトン著作225頁)のに、その中から紹介されているのは、原告著作でも97年公演でも、少年時代に雪の日に馬車に乗って通学したときの話のみである。しかし、この話はペルツ著作の冒頭においても紹介されているから、この話は、コルチャックの少年時代の代表的なエピソードとして一般に認識されているものと考えられる。 また、97年公演でコルチャックが語る話のせりふは、原告著作における記述と類似しているが、具体的な表現は異なっている。もともと原告著作のこの部分は、その記載態様からして、実際に放送された内容をわかりやすく翻訳したものであると考えられるから、その内容自体に創作性があるわけではない。 c 原告は、別紙対照表において、ラジオ番組の名前を「老博士のお話」としたのは、原告の独自訳であると指摘する。しかし、リフトン著作(224頁以下)によれば、コルチャックは同番組に「オールド・ドクター」として登場したことが認められるから、そこから番組名を「老博士のお話」と翻訳する点に創作性があるとはいえない。 (ウ) 第1幕・2(ぼくたちの家)〔別紙対照表6~13頁〕 a この場の描写内容は次のとおりである。 ①コルチャックとマリーナが運営しているポーランド人孤児のための施設である「ぼくたちの家」において、マリーナが数人の役員から、コルチャックはユダヤ人だから時勢柄ポーランドの子供を教育する「僕たちの家」の役員を解任するよう求められ、コルチャックのホームにおける教育理念が成果を上げていることを示して言い争っているところに、コルチャックが現れ、辞任を受け入れる。 ②役員たちが去った後、コルチャックは、マリーナに「老博士のお話」も中止になったことを伝え、「ポーランドで生まれてポーランドで育ち、ポーランド語を話す自分がポーランド人の子の教師になれないなんて」と嘆く。③そして、コルチャックは、マリーナに、子供のころ、飼っていたカナリヤが死んだとき、管理人の息子から、「カナリヤはユダヤ人だから天国にはいけない」と言われたときのことを話す。 b この場の①で、マリーナと役員がコルチャックの辞任をめぐって口論し、最後にコルチャックが辞任するところは、原告著作ではわずか2行で「『ナシュ・ドム』と、一切かかわりを持たないよう、ファルスカより伝えられた。いずれもその理由は明らかにされなかった。」(別紙対照表10頁の中段参照)と記載されているにとどまる上、これは歴史的事実である(リフトン著作232頁以下、 ペルツ著作123~124頁)。これに対し、97年公演では、マリーナとコルチャックとの人間関係、役員がコルチャックに辞任を求める理由等が、具体的なせりふを通じて描写されており、これらのやりとりは原告著作には記載がない。むしろ、ここの描写は、リフトン著作(232頁以下)にせりふの題材を求めたものと推認される。 原告は、別紙対照表において、この描写について、(a)「ぼくたちの家」とは原告の訳に係るものであること、(b)マリーナが語る「ぼくたちの家」の理念は原告著作にも記載があること、(c)コルチャックの本名である「ヘンルィク・コールドシュミット」の「ヘンルィク」は原告の訳に係るものであること、(d)当時のポーランドの情勢は原告著作に記載があること、(e)コルチャックが濃紺の作業着を着ているのは原告著作に記載があることを指摘する。 しかし、(a)は、「ナシュ・ドム」の訳語であるが、リフトン著作(232頁)では「われらの家」、ペルツ著作(59頁)でも「われらの家」と訳されており、これを「ぼくたちの家」と訳することに創作性があるとはいえない。 次に、(b)のマリーナの語る教育理念は、原告著作によれば「ぼくたちの家」を設立する際にマリーナ(ファルスカ)の書いた設立趣意書によるものであり、原告著作でも当初にぼくたちの家を設立する際の文脈で記載されているにすぎず、97年公演とは語られる場面が異なる上、ペルツ著作(60頁)にも同様の記述がある。また、97年公演のマリーナのせりふはこれらの記述に沿ってはいるが、具体的表現は異なる。次に、(c)のように人名のカタカナ表記の仕方に創作性は認められない。 次に、(d)は歴史的な事実の説明にすぎず、97年公演と具体的表現も異なる。次に(e)は、原告著作にのみ記載がある部分であることは原告主張のとおりであるが、 このような単純な事実の描写に創作性があるとはいえない。 c この場の②で、コルチャックの「老博士のお話」が中止になったのは、歴史的事実である(リフトン著作227頁、ペルツ著作123頁、ワイダ映画)。当時のポーランド情勢も同様である。 また、コルチャックがポーランド的な人物であったこと、コルチャックをとらえるのにはポーランド人とユダヤ人の両方として見る必要があるとの点はリフトン著作(7~8頁)に記載されており、原告独自の見方によるものではないと認められる。そしてまた、この部分のコルチャックのせりふ自体は、97年(及び95年)公演の創作に係るものであって、原告著作を始め、他のコルチャックの伝記にも、このような心情の吐露を直接記載したものは見当たらない。 d この場の③でコルチャックの幼年時代にカナリヤが死んだときのエピソードは、リフトン著作(20~21頁)、ペルツ著作(15~17頁)、ワイダ映画にも描かれているものであり、原告著作の創作によるものではない。また、 記載されている場所も、原告著作では、時系列どおり、コルチャックが5歳のときの箇所で記載されており、この点はリフトン著作でもペルツ著作でも同様であるのに対し、97年(及び95年)公演では、コルチャックがユダヤ人であるために「ぼくたちの家」の役員を辞任させられ、ラジオ番組を中止されるという困難に遭ったときの心情を描写するエピソードとして描かれており、このような描き方は、 原告著作には見られないものである(ワイダ映画では、後のゲットーでの困難な生活の最中に日記を書くシーンで用いられているが、共にユダヤ人であるが故の困難に遭遇した際のコルチャックの心情を描写するエピソードとして用いられている点では、共通するものがある。)。 また、コルチャックにとって、このエピソードがユダヤ人問題の原体験となったことについても、リフトン著作(196頁)に触れられているところであり、原告著作の創作によるものとはいえない。 (エ) 第1幕・3(みなしごの家)〔別紙対照表13~24頁〕 a この場の概要は次のとおりである。 ①ユダヤ人の孤児のためのホーム「みなしごの家」で、身体測定が行われており、コルチャックとステファ、エステルと子供たちの無邪気なやりとりがなされていると、②ネヴェルリイがやってきて、ドイツの動向、食料の備蓄の必要、ポーランド国内でのユダヤ人へのいやがらせなどを話す。③そこへ、マリーナがやってきて、フリーダをコルチャックに預けると、ホームの子供たちは、フリーダに、コルチャックが書いた本の話、ホームでの生活(けんかや裁判)の話、キャンプの話をしてあげて歓迎する。④ユゼフの独白で、1939年にドイツがポーランド侵攻を開始し、ポーランドが占領されたこと、ユダヤ人だけの特別居住地区ワルシャワ・ゲットーへの強制移住が行われたことが語られる。 b この場の①では、身体測定を題材に、みなしごの家におけるコルチャックと子供たちの触れ合いを描写しており、好き嫌いをしないことや、裸で生活すること、歯が抜けたといってきた子供の歯を買い取ることなどについてのせりふのやりとりを通じて、コルチャックがユーモアたっぷりに子供たちに接し、子供たちがコルチャックを慕っている様子が具体的に描写されている。これに対し、原告著作では、コルチャックの子供たちとの触れ合いの様子は、97年(及び95年)公演のように生き生きとは描写されておらず、別紙対照表記載のとおり、「コルチャックは、ユーモアに富んでいて、子供たちを笑わせ、ホームはいつもなごやかな雰囲気に包まれていた。コルチャックは良き父、ステファ夫人はよき母であり、温かい一つの家庭のようであった。」(72頁)等の記載や、コルチャックの教育理念の形で、客観的に記載しているにとどまる。このようなコルチャックと子供たちの関係についての具体的な描写は、むしろワイダ映画におけるキャンプのシーンの描写に類似のものを見出すことができる。 この点について原告は、①「みなしごの家」との訳語は原告の了解の下で使用されたこと、②身体測定は原告著作に記載されていることを指摘する。 しかし、①については、「ドム・シェロット」の訳語として、原告著作における「孤児たちの家」と異なるから、原告著作の翻案性とは直接の関係はない上、リフトン著作では「孤児の家」(224頁)、ペルツ著作でも同様であって(53頁)、それらとも大差がないものである。また、②については、コルチャックがホームで身体測定を実施していたことは、原告著作でもゲットー生活中の日記の記載に見られるにとどまる(184頁、204頁)上、リフトン著作(312頁)及びペルツ著作(63頁)にも記載され、ワイダ映画においても描写されているところであり、原告著作の創作に係るものではない。 c この場の②では、コルチャックがかつて編集長を努めていた子供新聞「小さな瞳」の現編集長であるネヴェルリイがやって来て、ドイツ、ポーランドの情勢を語るが、これらはいずれも歴史的事実である。ただし、これらの内容は、 原告著作の138頁に記された内容と重なる点が多いことから、原告著作の同部分に基づいて作成されたものと推認される。また、「小さな瞳」についても、コルチャックが編集長として始めた子供向けの新聞「リトル・レビュー」で、子供たちが皆通信員となり、子供たちから送られた記事や手紙から紙面が構成されていたこと、初代編集長のコルチャックはネヴェルリイと編集長を交代したことは、いずれもリフトン著作(194~204頁)に記されていることである。 d この場の③では、マリーナがやってきて、フリーダをみなしごの家に預けることとなり、ホームの子供たちがフリーダにホームの紹介をすることを通じて、ホームの運営の実情や子供たちがコルチャックを慕っている様子を描写しているが、このような描写は原告著作にはない。原告著作では、ホームの運営の実情は、客観的に記載されているにとどまる(別紙対照表20頁の中段参照)。このように、ホームの子供たちが、新たにホームに入ってきた子供にホームの案内をする描写は、むしろワイダ映画において、新たに入ってきたシロマをユゼフが案内するシーンに類似するものであるといえる。 また、この部分で、子供たちが語る内容を見ると、コルチャックは注射の嫌いな医者だとの子供の発言は、原告著作(77頁に「彼はホームで仕事をしている時は、いつも濃紺の作業着を着ていた。白衣を着ると注射でもされるのではないかと、子供たちがおびえるのを気にしていたのである。」との記述がある。)に基づくものと思われるが、コルチャックが「王様マチウシ一世」を含む多数の著書を書いていること、子供による裁判が行われること、キャンプに行くことについては、原告著作にも記載があるが、同時にリフトン著作(155頁、270頁)及びペルツ著作(44頁、68頁以下)にも記され、ワイダ映画にも描写されている。また、ルールを守れば殴り合いをしても良いとの点は、原告著作には記載がない。 e この場の④では、ユゼフが独白で、ナチスドイツ軍がポーランドに侵攻し、ワルシャワ・ゲットーが作られてユダヤ人が詰め込まれたことが語られるが、これらはいずれも歴史的事実にすぎない。 (オ) 第1幕・4(ゲットーへの道)〔別紙対照表24~28頁〕 a この場の概要は、次のとおりである。 ①スピーカーから、ユダヤ人に対する各種の制限が告知されているところを、コルチャックと子供たちが列をなして歩いて来ると、ジャガイモの馬車がドイツ軍に没収された旨が報告され、それを聞いたコルチャックは取り戻して来ると言ってステファが止めるのも聞かずに走り去る。②そこへマリーナがやって来て、高熱を出した幼子のエドナを引き取るとともに、コルチャックの身分証明書と隠れ家を用意した旨をステファに伝える。③他方、コルチャックは、ドイツ兵にじゃがいもを返すよう求めるが、ユダヤ人なのに腕章を付けていなかったことを詰問されて、抗弁したために投獄される。 b この場の①でスピーカーから流される布告の内容は、原告著作に記載がある(別紙対照表24頁中段参照)が、リフトン著作(262~263頁、270頁)に記載され、ワイダ映画でも描写されている歴史的事実にすぎない。 また、ゲットーへの移動時にジャガイモの馬車がドイツ軍に没収される点も、原告著作に記載がある(別紙対照表26頁中段参照)が、リフトン著作(276~277頁)及びペルツ著作(139頁)に記載され、ワイダ映画でも具体的に描写されている。 なお97年公演では、ジャガイモの馬車が没収されたことを知ったコルチャックは、直ちにステファの制止も聞かずに抗議に行くように描かれており、これはワイダ映画と同様である。 c この場の②で、ゲットーへの移動の途中に、マリーナが孤児のうちの一人を預かって保護する点、及びその際にマリーナがステファにコルチャックの身分証明書等を用意したと告げる点は、原告著作には記載がなく(ただしマリーナが隠れ家等を用意したとの点は、ゲットーに入ってから後のこととして記載がある。)、むしろワイダ映画中にほぼ同様のシーンがあることから、それとの類似性が認められる。 d この場の③では、コルチャックがドイツ軍に抗議に赴いたところ、 ドイツ軍は最初は丁寧に応対していたが、コルチャックがユダヤ人であると分かるや、腕章を付けないことを詰問し、暴行を加えた上で投獄したことが描写されており、これは原告著作に一応記載があるが(別紙対照表27頁の中段参照)、リフトン著作(276頁)及びワイダ映画では、会話の形でより具体的に描写されており、この部分の97年(及び95年)公演のせりふは、リフトン著作との類似性が認められる。 (カ) 第1幕・5(ゲットーの中・『みなしごの家』の前)〔別紙対照表28~33頁〕 a この場の概要は、次のとおりである。 ①ユゼフら少年がゲットー内の状況を話していると、闇屋の少年がやって来て、抜け道を通って入手したたばこを売りつける。②仲間と別れたユゼフにイレーナが声をかけて、ホームのエステルを呼んでもらうと、イレーナは、ホームで育った身であったが、投獄されているコルチャックの保釈金をエステルに渡す。③イレーナは、ホームから出てきたユゼフと共に歩き出すと、ユダヤ警察に出会い、身分証明書の提示を拒否したが、ユダヤ人警察の一人ボレクがユゼフと知り合いで、親しげに話をして解放してもらう。イレーナはユダヤ人警察を悪し様に言うのに対し、ユゼフは、とてもいい人なんだと言う。 b この場の①で少年たちが語るゲットーの状況は、原告著作では複数箇所に分散して記載されているものであるが(別紙対照表28、29頁の中段参照)、いずれも歴史的事実である。すなわち、サクソン広場がヒトラー広場に改名された点及びゲットーの建設がユダヤ人の資金で行われた点、ゲットー内には、ましな地区と、人間でごったがえしている地区がある点はリフトン著作(270~271頁、280~284頁)に記載がある。 また、子供が抜け道を通って商品や食糧を運搬していたことは、 ペルツ著作(141頁)に記載があり、ワイダ映画にも描写されている歴史的事実であり、原告著作にもその事実の記載がある。しかし、これらの記述がいずれも客観的な説明として記載されているのに対し、97年(及び95年)公演では、闇屋の少年がユゼフらにタバコを売りつけるシーンによって、ゲットー内における少年たちの境遇を具体的に描写している点でこれらの文献の記載等とは異なる。 c この場の②で、ホームの卒業生であるイレーナがエステルにコルチャックの保釈金を渡す点は、原告著作でも、コルチャックの保釈金はかつての教え子が調達したことが記載されている(別紙対照表31頁中段参照)。しかし、この点はリフトン著作(277頁)にも記載されている歴史的事実である。 d この場の③で描写されている、イレーナやユゼフとユダヤ人警察とのやりとりは、ユダヤ人警官の高圧的な態度、イレーナの反抗的な姿勢、ユゼフの知り合いのユダヤ人警官(ボレク)にかつてよくしてもらったことを通じて、ゲットー内におけるユダヤ人社会の複雑さを具体的に描写しているものであり、このようなやりとりは、原告著作のほか、他のコルチャックの伝記にも見られないものである。原告著作には、ユダヤ人警官の非情な面は記載されているが(別紙対照表32頁の中段参照)、ボレクのような人物の存在には触れるところがない。 (キ) 第1幕・6(ゲットーの中の『みなしごの家』・コルチャックの帰還)〔別紙対照表33~39頁〕 a この場の概要は、次のとおりである。 ①「みなしごの家」で子供たちが言い争っているところに、釈放されたコルチャックが帰って来る。②子供たちは喜んでコルチャックに次々と話しかけ、コルチャックの要望に答えて歌を歌うなどする。③その後、コルチャックはステファと話をし、ホームの子供をマリーナなどに預けることについて反対し、ゲットーを出るべきだとのステファの勧めを断り、明日から自分が食糧を調達するなどと言う。 b この場の①については、このようなホームの子供たちの具体的なやりとりは、原告著作には記載されていない。また、コルチャックが投獄から帰還した際の記載は、原告著作にはなく、ワイダ映画にのみ描写がある。 c この場の②について、コルチャックが突然帰って来ると、子供たちが大はしゃぎしてコルチャックに次々と話しかけ、皆で汽車のような列を作って走るという描写は、原告著作には記載がなく、むしろワイダ映画にほぼ同様のシーンがある。 d この場の③には、(a)コルチャックが帰還後、ステファと話し合うこと、(b)ゲットーへの移動時にエドナをマリーナに預かってもらったことやアーリア系の顔立ちの子供は何人かかくまえるという話を聞くと、コルチャックが、子供たちを自分たちが選り分けるのかと反対すること、(c)ステファがコルチャックにマリーナの伝言を伝えてゲットーを出るように勧めたところ、コルチャックが拒絶することが描かれているが、これらは、いずれも原告著作には記載がなく、むしろワイダ映画に極めて類似するシーンがある。前記②と並んで、この部分は、ワイダ映画との類似性が強く認められる部分である。 また、この場の③には、(a)コルチャックとステファが今後の方針について話し合い、物資の調達はコルチャックがすること、(b)子供たちをホームの外に出さないようにしようとしたことが描写されているが、これらも原告著作には直接の記載はなく、ワイダ映画には、コルチャックがホームに帰還した後に、コルチャックとステファのほかエステラ(97年公演のエステル)らが加わった話し合いで同様のことが語られている。ここもワイダ映画との類似性が強く認められる部分である。なお、ここでコルチャックが語るゲットーの状況は、原告著作に記載があるが、リフトン著作(280頁及び295頁)及びペルツ著作(141~142頁)にも記載がある。 (ク) 第1幕・7(ゲットーの中で)〔別紙対照表39~47頁〕 a この場の概要は、次のとおりである。 ①ゲットーの中をコルチャックが歩いていると、古着を売る女、 道化のルビンシュタインに声をかけられた後、イレーナに会う。②コルチャックはイレーナにいつでもホームに来るよう言い、寄付を頼んで回っていると言うと、イレーナは、店で歌を歌っているが、客に金持ちが多いから一度来てみてと言って紙片を渡して去る。③2人が去ると、闇屋の少年(サムエル)が再びやってきて、ルビンシュタインにたばこをやる。 他方、コルチャックは、寄付を依頼に回っており、④ユダヤ人評議会に赴き、チェルニアクフに対し、「子供のために何かすることはとても幸せで、大人の責任である。あなたは寄付をする余力がおありになる。寄付をできる幸せをかみしめて下さい。」と言い、チェルニアクフが100ズウォティ寄付すると言うと、「もっと幸せをかみしめて」と促し、最終的に500ズウォティを引き出す。⑤次の寄付依頼に赴く途中のゲットーの路上で、金をせびるルビンシュタインにチェルニアクフからもらったタバコをやり、⑥ビスケット売りから「ユダヤ人に売ることを禁止されている」と言われると、「それでは寄付すればよい」と応じ、 ⑦肉屋からハムを寄付してもらう。 さらに、⑧ゲットーの路上では、ユゼフら少年たちが秘密集会に集まる打ち合わせをしている。 b この場の①について、ゲットーで、ドイツ兵が巡回し、物乞いや路上生活者が多数おり、生活品の売買がされている状況は、リフトン著作(280~282頁)、ペルツ著作(141~143頁)に記載があり、ワイダ映画でも描写されている。 ルビンシュタインという道化がゲットーにいたことは、原告著作では記載されていないが、リフトン著作(282頁)では触れられている。リフトン著作では、ルビンシュタインは金を恵んでもらわないと、くたばれヒトラーなどとわめくことが記載されており、97年(及び95年)公演のルビンシュタインの描写は、リフトン著作に基づくものであると推認される。 c この場の②について、コルチャックの保釈金がホーム出身者によって調達されたことは、前記のとおり、リフトン著作等にも記載がある。また、ホーム出身のイレーナが歌を歌っている店に富裕者が来ることから、コルチャックに寄付の依頼に来るよう誘う点は、原告著作には記載がない。 他方、ワイダ映画においては、ドイツ兵から腕章を付けないことで詰問されているコルチャックを、ホーム出身のシュルツが救い、慣れた酒場に案内して富裕者から寄付を集める描写があり、97年(及び95年)公演のイレーナは、このワイダ映画の設定に基づくものであると推認される。 d この場の④について、チェルニアクフは、ユダヤ人評議会の議長であり、実在の人物である(リフトン著作266頁など)。チェルニアクフが孤児たちの置かれている境遇に心を痛めていた点は、原告著作に記載があるが、同人が児童福祉に熱心であったことは、リフトン著作(266頁)にも記載がある。また、「ユダヤ人評議会」との訳語は、原告著作に見られるものであるが、リフトン著作では「ユダヤ協会」(266頁)、ペルツ著作では「ユダヤ人評議会」(136頁)、ワイダ映画では「ユダヤ自治会」と訳されており、原告著作の訳語に創作性はない。 ここで、コルチャックは、チェルニアクフに対し、「子どもを助けたい。これは大人の責任であり、義務であり、権利でもあるんです。」と述べているが、これは、原告著作では、コルチャックがポーランド陥落後に出した寄付を求める声明として記載されている。他方、ワイダ映画では、コルチャックが慈善家に寄付を依頼する際に、「これはあなたの義務です。」と述べるくだりが描写されており、ワイダ映画の方により類似している。 また、このシーンで、コルチャックは、チュルニアクフを持ち上げつつ半ば強要するような調子で寄付額をつり上げており、ユーモラスな中にコルチャックのなりふりかまわず寄付を求める姿勢が描写されている。これに対し、原告著作では、コルチャックが寄付を依頼して回ったことと、そのためにある偉い人に後味の悪い手紙を書くこともあったことが記されているが、このようなコルチャックの寄付の依頼の仕方は、ペルツ著作(145頁)にも記載されている。むしろ、97年(及び95年)公演のような具体的な描写は、ワイダ映画(慈善家ブラウネル宅で寄付を依頼するシーン)によく描かれており、そこで、コルチャックがブラウネルの嘆きにもかかわらず、申し出よりも多い寄付を求める姿は、97年(及び95年)公演の本シーンと類似するものがある。 e この場の⑤で描写されている、ルビンシュタインが叫ぶ、ヒトラーとキリストを題材にしたジョークは、原告著作には記載がないが、リフトン著作(294頁)には、当時ユダヤ人社会で語られていたジョークとして記載されている。 f この場の⑥について、コルチャックが、ビスケット屋に対し、「ユダヤ人が作ったビスケットだ。売って悪いなら寄付すればよいじゃないか。」と述べる点は、ビスケットでなくチョコレートで同様の話が原告著作に記載がある(152頁)が、これは原告著作によればチェルニアクフの日記に原典があるもので、 同じ話はリフトン著作(271頁)にも記載がある。 g この場の⑦について、コルチャックが肉屋からハムの寄付を受ける部分では、肉屋は、寄付に反対する妻の手前、ハムの切れ端と言いつつ、ハム1本を寄付することが描かれており、このようなコルチャックに対する協力的な姿勢を示すエピソードは、原告著作には記載されていない。別紙対照表45頁の中段に記載されている肉屋のエピソードは、このシーンとは内容が全く異なる。 h この場の⑧について、ユゼフらが秘密集会の打ち合わせをしているが、ゲットーに秘密のレジスタンス組織があったこと、ユダヤ人の中にはドイツ軍と通じる者もいたことは、原告著作に記載がある。しかし、これはリフトン著作(309~310頁)にも記載のある歴史的事実である。 また、ゲットー内で多くのユダヤ人が死亡していったことは、リフトン著作(301~302頁)など随所に記載がある。 (ケ) 第1幕・8(ハヌカの祭りの夜)〔別紙対照表47~52頁〕 a この場の概要は、次のとおりである。 ①ステファとコルチャックが話をしており、コルチャックが、アメリカが参戦したから希望が出てきたと言うと、ステファは、ゲットーの状況を嘆き、間もなくこのゲットーからの移住が始まるといううわさがあると言う。②みなしごの家でハヌカのお祝いが始まり、コルチャックがあいさつをし、皆で歌を歌っていると、「僕たちの家」の子供たちがユダヤ人地下組織の協力を得て、ゲットーの外からプレゼントを持って来る。 b この場の①について、1941年にアメリカが参戦し、ドイツ軍がロシアで苦戦していたことは歴史的事実であり、これがゲットーのユダヤ人にとって希望の灯火となっていた点は、リフトン著作(304頁)にも記載がある。 また、ここでステファが語るゲットーの状況は、原告著作に記載があるが、リフトン著作(304~305頁、314頁)、ペルツ著作(141頁、 150頁)に記載され、ワイダ映画でも描写されている。 また、このころ、ゲットーで移住のうわさが流れていたことも、リフトン著作(310頁)に記載がある。 c この場の②について、このころ、ホームでハヌカの祭りが行われたが、その数日前に、ごみ運搬車に隠れてポーランド人の地下抵抗組織からホームの子供たちにプレゼントが贈られてきたことは原告著作に記載があるが、同様の記載はリフトン著作(305頁)にも記載がある。もっとも、この場で、プレゼントを持ってきたのが「ぼくたちの家」の孤児たちである点は、97年(及び95年)公演の創作に係るものである。 (コ) 第2幕・10(ゲットー)〔別紙対照表52~55頁〕 a この場の概要は、次のとおりである。 ① ユゼフら少年たちが、ゲットーの路上でユダヤ人がガスで殺されているとのうわさ話をしていると、一人がビラを持って来て、配りに去って行く。 ②路上を歩いていた女性がユダヤ警察からとがめられ、ジャガイモ等を隠し持っていることが分かり、連行される。そこへコルチャックがやって来て、路上に散乱したジャガイモ等を拾い集める。そこへルビンシュタインがやって来て、共にタバコを吸う。 b この場の①について、このころユダヤ人が収容所に送られ、ガス室で虐殺されるとのうわさが流れ始めたことは、原告著作に記載があるが、これは歴史的事実である。 c この場の②では、ユダヤ警察の非情な行為と、それを利用してまで食料集めをするコルチャックの姿が描写されているが、このような生々しい描写は、原告著作にはない。 (サ) 第2幕・11(再会)〔別紙対照表55~63頁〕 a この場の概要は、次のとおりである。 ①ゲットーの路上で、ユダヤ警察がユダヤ人に抵抗を呼びかけるビラを見つけて破り捨てる。②場末風の酒場で、イレーナが酔った男にからまれていると、コルチャックがやって来てイレーナと話をする。背後では、酒場の客がヒトラーに関するジョークを話している。そこへ、ガンツバイクがやって来て、ここの連中は金には不自由していない、金とコネの力で生き残れると信じているなどと話すと、マダムが客たちにコルチャックへの寄付を呼びかけ、歌手が歌っている間にガンツバイクらの客が寄付をする。すると、突然銃声が響く。③ゲットーの街角で、ルビンシュタインがユダヤ抵抗組織だ、ユダヤ人よ立ち上がれなどと叫んでいると、コルチャックが歩いて来、その後をユゼフが銃を持って走って来る。ユゼフが、なぜガンツバイクのような汚い奴の金を受け取るのかなどと問うと、コルチャックは、私には200人の子供がいるだけだと答える。④コルチャックは、歩きながら、「子供であるのはよいことか。もっと悪いのは、貧しくて親を失ったユダヤ人の子供。一番悪いのは、年を取って、お金がなかったら。おまけに200人の子だくさんのユダヤ人、あちこち痛んで疲れていたらもっと悪い。」などと独白する。 b この場の①のようなビラがゲットー内に貼られていたことは、原告著作には特に記載はないが、似たような事実は存したと推認される。もっとも、97年(及び95年)公演では、この貼り紙は、後のガンツバイクの襲撃を予測させる位置づけを与えられている点にドラマとしての工夫が見られる。 c この場の②の酒場のシーンは、原告著作には「ゲットーには、一部の特権階級や、金持ちのために、ナイトクラブ、レストラン、カフェなどが開かれていた。コルチャックはこういうところも訪ね、乞食のように食料を乞い、時には凄まじい形相で、彼らを怒鳴りつけ、脅迫すらしたという。」(172頁)と記載されているのみである。また、ナチス協力者と見られていたガンツバイクにも寄付を求めたとの記載は、リフトン著作(293頁)にもある。 これに対し、ワイダ映画では、コルチャックがホーム出身のシュルツに連れられて場末の酒場に行き、帽子を回して客たちから寄付を募るシーンがあり、ここでコルチャックがガンツバイクと話をしていると、ユダヤ抵抗組織がガンツバイクを暗殺しようとして発砲する事件が起こり、その逃走中に、抵抗組織の青年が「あなたの誇りは?」と訪ねるのに対し、コルチャックが「ない…200人の子供がいるだけだ。」と答えることが描写されている。97年(及び95年)公演の酒場のシーンは、このワイダ映画の酒場のシーンと酷似しており、ワイダ映画に基づいて作成されたものと考えられる。 d この場の③は、先に見たように、ワイダ映画のシーンと酷似している。 なお、ここでルビンシュタインが叫んでいるせりふのうち、「金持ちが腐ってとけてく。これで脂身にありつけるぞ。」とのせりふは、原告著作にはないが、リフトン著作(294頁)には類似の記述がある。また、ルビンシュタインの「燃えている。…」とのせりふは、原告著作によったものであると思われるが、原告著作に引用されたレジスタンスの歌の一節を採ったものであるにすぎない。 e この場の④のコルチャックの独白は、原告著作では、ドイツ軍のポーランド侵攻より前の1930年代前半ころのユダヤ人についてコルチャックが記述したものとして引用されている。また、この独白は、リフトン著作(264頁)でもコルチャックの言葉として記述され、ワイダ映画でも描写されているが、ワイダ映画では、酒場のシーンの直後で描かれており、ここでも97年(及び95年)公演のワイダ映画との類似性が見られる。 (シ) 第2幕・12(飢餓・子守り歌)〔別紙対照表63~64頁〕 a この場では、①食べ物の妄想に襲われたコルチャックが、次々と料理の名を言ってはパンのかけらを食べる一方で、②フリーダがユゼフが連れて行かれる夢を見たと言ってベッドで泣いているのをステファが安心させる。 b この場の①は、原告著作には記載がないが、リフトン著作(316頁)では、ゲットーでの生活中に、飢餓感から、種々の食べ物がまぶたに浮かんだとして、この場でコルチャックが挙げるのとほぼ同じ料理名が記されている。また、ワイダ映画でも、コルチャックがステファに、食べ物についておかしな夢を見るとして、種々の料理を語るシーンがある。 c この場の②は、原告著作には記載がないが、ワイダ映画では、ホームの幼子が、夜中に銃声が聞こえて泣き出すのをコルチャックが安心させるシーンがあり、それとの類似性が見られる。 (ス) 第2幕・13(ネヴェルリイのゲットー訪問)〔別紙対照表64~72頁〕 a この場の概要は、次のとおりである。 ①ネヴェルリイがゲットーのホームを訪問し、身分証明書や隠れ家を用意したから早くゲットーを出るように求めるが、コルチャックは、申し出を拒否する。②ネヴェルリイが辞去すると、エステルがステファに「郵便局」の劇の演出をするよう言われたことを告げ、なぜ死への準備をするのかと問うと、ステファは、子供たちが死を受け入れるようにするためとのコルチャックの考え方を説明する。③暗転の後、子供たちが劇中劇「郵便局」(タゴール作)を上演するシーンに移り、主人公が死ぬシーンが演じられる。 b この場の①では、ネヴェルリイがホームを訪問してコルチャックに脱出を求めると、コルチャックが「みなしごの家」の管理人(料理人)をしていたザレフスキのことを引き合いに出して申し出を断るエピソードが描かれている。これは、原告著作にも記載があるが、同様の記載はリフトン著作(339頁)にも記載がある。 ここでネヴェルリイは、コルチャックの本はドイツでも出版されていると発言しているが、これは原告著作に記載があるものの、ここのネヴェルリイの申し出とは全く異なる1935年の箇所で客観的に記述されているにすぎない。 また、マリーナが隠れ家を用意した点は、原告著作に記述があるが、リフトン著作(339頁)にも記載されている事柄である。 この場でコルチャックは、申し出を断る理由として、ザレフスキのことに触れる以外に、子ども病院の勤めを辞めてホームを設立する際に、脱走したような気持ちが消えないので、そのような裏切りを二度としたくないと述べている。コルチャックがこのような思いを抱いていたことは、原告著作にも記載がある(61頁)が、そこでは、病院を辞めてホームを設立する記述の箇所で、そのときのコルチャックの気持ちとして記載されているにすぎず、トレブリンカに送られる直前にネヴェルリイの申し出を断り、子供たちとゲットーに残ることとすることとの関連は、特に記載されてはいない。また、原告著作と同様の記述は、リフトン著作(64頁、311頁)にも見られるが、いずれもゲットーに残ることとの関連は記載されていない。 また、この場でコルチャックは、「わたしが強い?忙しくしている昼間はまだいい。だが夜になるともうだめだ。食べ物のことばかり考えている。」「わたしはただの老いぼれさ。」と述べ、自分は弱い人間であると言い、さらに、 「犠牲になっているつもりはない。」「わたしにあの子たちが必要なんだ。」と述べるが、このようなコルチャックの心情は、原告著作にも他の文献にも記載されていない。 c この場の②で、エステルが「郵便局」の劇の演出をしたことは、原告著作に記述があるが、リフトン著作(333頁)にも同様の記載がある。 また、コルチャックがこの時期に、子供たちにタゴール作の劇「郵便局」を演じさせた趣旨が、子供たちが「死」を受け入れられるようにするものであったことは、原告著作に記載があるが、この点はリフトン著作(336頁)にも記載があり、ワイダ映画でも描写されている。 しかし、なぜ死の準備をするのかというエステルの問いに答えて、 ステファが、「尊厳を持って『死』さえも迎えられる、そういう生き方をしたいの。」「コルチャック先生の闘いは子どもたちと生きることなの。」と語る考えは、原告著作や他の文献に直接の記載はない点であり、97年(及び95年)公演の創作に係るものである。 d この場の③で、子供たちが演じる「郵便局」の内容は、原告著作に記載があるが、ワイダ映画にも子供たちが演じる様子が描写されている。 なお、ここでコルチャックの声で語られる招待状の内容は、原告著作によるものと思われるが、原告著作のこの部分の記述は、実際にコルチャックが送付した案内状を翻訳したものである。 (セ) 第2幕・14(チェルニアクフの選択)〔別紙対照表72~78頁〕 a この場の概要は、次のとおりである。 ①ユダヤ人評議会において、コルチャックが、強制移送のうわさがあるとするのに対し、チュルニアクフは単なるうわさだと反論しているが、コルチャックは「子供たちは絶対に渡さない」と言い、チュルニアクフは、「子供たちは必ず守る」と約束する。②コルチャックが辞去すると、チェルニアクフは、ユダヤ人とドイツ軍の板挟みにあっている苦悩を妻に打ち明ける。③そこへドイツ兵がやってきて、ゲットーのユダヤ人を強制移送するからユダヤ人評議会も協力するよう告げる。これに対し、チュルニアクフは子供たちまで連れていくのはやめるよう申し入れ、移送通知書にサインするのを拒否したため、ドイツ兵に殴りつけられる。 ドイツ兵は、サインの有無にかかわらず、全員移送すると言い残して去る。チュルニアクフは、今まで私がしてきたことは何だったんだ言って、服毒自殺をする。④ユゼフにより、翌日からユダヤ人の強制移送が始まったことが語られる。そこへイレーナが現れ、ゲットーを出て生きると言い残して去る。そして、ユゼフにより、 エステルが「人狩り」に遭ったことが語られる。 b この場の①のコルチャックとチェルニアクフとのやりとりは、原告著作には記載がないが、リフトン著作(337頁)では、「郵便局」の劇がホームで行われた当時、ゲットーでは、よそのゲットーの人々が列車で強制移送されたことはつかんでいたが、ガスによる大量殺人が行われていることの裏付けは取れなかったことが記載されている。また、ペルツ著作(163頁)では、チェルニアクフが子供たちまでが移送されたら自殺すると言った旨が記載され、ワイダ映画では、 チェルニアクフがコルチャックから孤児たちのことを問われて「私が生命を賭けて彼らに答える」と述べるシーンが描かれている。 c この場の②でチェルニアクフは、自分はこの国を出るべきだったが同胞を見捨てることはできなかった、ドイツ軍とユダヤ人の板挟みで、こんな仕事を誰がやりたくてやっているかという独白をするが、原告著作には、このようなチェルニアクフの立場については記載がある。しかし、チェルニアクフのこのような苦悩については、リフトン著作(338~339頁)にも記載がある。 d この場の③でのチェルニアクフとドイツ軍とのやりとりについては、原告著作には直接の記載がなく、ただドイツ軍による布告の内容と、チェルニアクフが子供たちの境遇に心を痛めており、彼らを救えればとドイツ当局との交渉に努めていたが受け入れられなかったとの記述(202頁)があるにすぎない。また、このような記載は、リフトン著作(341~342頁、344頁)にも記載があり、さらにワイダ映画には、チェルニアクフがドイツ軍の命令書への署名を拒否したため暴行を受けるシーンが描かれている。 さらに、チェルニアクフが服毒自殺をする点は、原告著作に記載があるが、リフトン著作(344頁)及びペルツ著作(169~170頁)にも記載があるほか、ワイダ映画でも描写されている。 e この場の④でユゼフが語る内容は原告著作に記載があるが、リフトン著作(341~342頁、349頁)にも記載があり、エステルが「人狩り」(ドイツ兵に強制的に連行される)に遭うことはワイダ映画でも描かれている。 (ソ) 第2幕・15(別れ)〔別紙対照表78~83頁〕 a この場の概要は、次のとおりである。 「ぼくたちの家」に、ゲットーを抜け出したコルチャックが抱えられてやって来て、マリーナからミルクを受け取って飲む。コルチャックはエステルが行方不明になった旨を告げ、彼女が残したノートをマリーナに渡し、これまでの礼を述べる。マリーナは、このままここに残るよう求めるが、コルチャックは私は子供たちと離れられないと言って、帰っていく。 b この場に描かれているように、強制移送の直前にコルチャックが「ぼくたちの家」に別れを告げにやってきたことは、原告著作に記載されている(別紙対照表78、79頁参照)が、他の著作にはない。コルチャックが、ゲットーでの生活中にゲットーを抜け出してマリーナと会ったことについては、リフトン著作(303頁)に記載があるが、原告著作のように強制移送の直前のこととしては記載されていない。他方、ワイダ映画では、強制移送の直前に、ゲットーを抜け出したコルチャックがマリーナと会い、マリーナによるゲットー脱出の勧めを断るシーンが描写されているが、マリーナがコルチャックに食べ物や飲み物を勧める描写はない。食べ物を勧めたことについて言及があるのは原告著作のみであるから、 97年(及び95年)公演におけるミルクをめぐるやりとりは、原告著作の記述にヒントを得たものと推認されるが、原告著作でもネヴェルリイから聞いた事実として記載されている上、原告著作では、マリーナが食事を勧めても、コルチャックは「子供たちは皆もう何日間も食べていないようなものだから」と言って、出されたスープにも手をつけなかったと記載されている点で、この場の描写とは異なる。 また、この場では、コルチャックがマリーナにエステルのノートを渡し、ゲットーの様子を語ることなど、最後の別れの様子が具体的に描写されている。 この場の末尾でコルチャックが語るせりふは、原告著作に記載があり、この記載は、コルチャックの日記の異なる部分を原告がつなげて配列したものであるから、このせりふは、原告著作に基づくものであるといえる。もっとも、このせりふの後半部分にある「人は死を生の終わりと考えているが、死というのは生きることの続きにあるものだ。つまり死もまた、別の、形の違う生なのだ。」というせりふは、リフトン著作(364頁)にも、コルチャックの「ゲットー日記」からの引用として記されている。 (タ) 第2幕・16(最後の朝)〔別紙対照表83~88頁〕 a この場の概要は、次のとおりである。 ①ホームにドイツ兵がやってきて、東部への移送を命じる。コルチャックと子供たちは、ドイツ兵にせかされながら荷物を整理し、10分間の猶予を得た後、歌を歌い、ホームを出発する。②誰もいないホームにコルチャックの独白が流れる。③するとユゼフが駆け込んで来て、事態を理解して走り去る。 b この場の①の様子は、原告著作にも記載がある。しかし、同様の記述は、リフトン著作(354~358頁)及びペルツ著作(164頁)にもあり、 ワイダ映画でも具体的に描写されている。 c この場の②の独白の内容は、原告著作に記載がある(95~96頁)が、原告著作では、ホームの卒業の際のコルチャックの別れの言葉として1919年に青少年向けの雑誌に掲載されたものとして記載されており、マリア・ファルコフスカ著「ヤヌシュ・コルチャックの生涯、活動そして著作品の手引き」(1989年出版、乙8)にも同様の記載がある。また、ワイダ映画でも同様の内容のコルチャックのせりふがあるが、ホームの教員であったエステラとヘニエックがコルチャックに結婚の報告をしたときにコルチャックが贈った言葉として語られている。 d この場の③の様子は、原告著作や他の文献にも記載はない。 (チ) 第2幕・17(かなたへの旅立ち)〔別紙対照表88~92頁〕 a この場の概要は、次のとおりである。 貨物集積場にコルチャックと子供たちが歌を歌いながら列をなしてやって来る。そして、コルチャックらが貨車に乗り込もうとしたとき、ドイツ兵が、コルチャックに対し、特赦が下りたから残ってよいと告げる。コルチャックが「子供たちもか」と問うと、ドイツ兵は「ばかなことを。戦争中のことだ。おまえひとり生きのびたって誰も責めるものはいやしない。」と答える。すると、コルチャックは、「あなたはまちがっている。」と言って、子供たちの中へと入っていき、子供を抱きかかえ、「未来はここにある。」と述べる。 b この場は、別紙対照表のとおり、原告著作に記載がある。 しかしまず、コルチャックと子供たちが貨物集積場に整然と列をなしてやって来る点は、リフトン著作(356~362頁)及びペルツ著作(165頁)にも記載があり、ワイダ映画にも描写されている(ただし、歌を歌っている点は直接の記載はないが、ペルツ著作〔167頁〕にはそれを示唆する記載がある。)。 また、貨車に乗り込む際の様子については、原告著作においても目撃者の記した出典ごとに4種類の様子が記されているが、最初に記載されているのは、一人の男がコルチャックに特赦が下りたことを興奮して知らせたのに対し、コルチャックは無言のうちにその申し出を退け、貨車に入っていったというものであり、これは、ワイダ映画で描写されているのと同様である。 他方、原告著作(217~218頁)で、「最後にネヴェルリイが……直接目撃したポーランド人から聞いた話を引用しておきたい」として記載されている箇所では、コルチャックらが貨車に積み込まれようとしているとき、コルチャックの名を知ったSS(親衛隊)指揮官が、「あなたは乗らずにここに残ってもよろしい」と告げたのに対し、コルチャックは、「それで、子供たちは?」と聞き、「子供たちは行かねばならない」との返事を受けると、「あなたは間違っている。まず子供たちを-」と述べて自ら貨車へ入っていったとされている。 これらを97年(及び95年)公演のこのシーンと比較すると、ドイツ兵から特赦が下りたことを告げられる点は先の記載と一致しているが、子供たちは行かねばならないと宣告されると、「あなたは間違っている」と述べる点では、後者の記載と一致している。ただ、その後に、「未来はここにある」と述べる点は、原告著作にも他の文献にも記載がなく、被告Yによって創作されたものと認められる(同被告本人の供述)。 また、原告著作に記された後者の様子は、同様のことが、ネヴェルリイが1967年に出版した著作(乙11)及びヴォルガング・ペルツェルが1987年に出版した著作(乙12)でも記されている。 エ 以上に基づき検討する。 前記のとおり、原告著作は、コルチャックの生涯を、コルチャック自身が残した日記その他の資料に基づき、時代背景を交えて客観的に記述したものであって、コルチャックの生涯を描いた著作としては、我が国で最初に出版されたものである。その意味で、原告著作は、我が国におけるコルチャック研究の先導的役割を果たしたものということができる。 しかし、コルチャックの生涯を記した文献は、諸外国においては、原告著作が著される前から既に多数のものが出版されており、映画も数本が製作されていた状況にあり、またコルチャック自身の著作も多数公刊されているのであって、原告著作もそれらの成果に基づいて成立しているものである。 そして、原告著作に描かれたコルチャックの生き方や、その人間像は、前記のとおり、原告著作以前に出版されていた文献等にも見られるものである。 したがって、それらの先行文献等と比較した場合の原告著作の創作性は、 既存の多数の文献等の中から、原告にとって重要と考える記述やエピソードを抽出し、相互に関連づけてコルチャックの生涯を描き出した、その選択と配列及び具体的な表現方法にあるというべきであって、個々の記述やエピソードに97年公演の本件舞台劇と重複する部分があったとしても、それだけで本件舞台劇が原告著作の翻案であるとすることはできない。 そして、97年公演の各場について、原告著作及び証拠として提出されている先行文献等と比較して検討してみると、前記のとおり、97年公演には、原告著作に記載されていないシーンも数多く盛り込まれている反面、原告著作の中で97年公演に盛り込まれていない記述も数多くある。また、原告著作に記載されている内容であっても、同時に他の文献にも記載されている歴史的事実が大半であって、原告著作にのみ記載されているものは断片的なものにすぎない上、原告著作に記載されているものでも、97年公演ではその記載箇所とは異なる文脈で用いられているものもある。 このような検討からすると、原告著作が、既存の文献等を基礎に、それらを取捨選択して記述したコルチャックの生涯の描き方の本質的な特徴が、本件舞台劇において直接感得される程度に再現されているとはいえない。 また、具体的な表現をみても、もともと原告著作はコルチャックの生涯を客観的に記載したものであって、劇場で上演されるためにせりふと動きで描写する本件舞台劇とは基本的に具体的表現方法を異にするものであり、具体的な場面設定やせりふの内容についても、原告著作にも記されている場面設定やせりふはほとんど存しない。むしろ、本件舞台劇は、同じドラマとして制作されたワイダ映画と比較した場合、類似する場面やせりふが随所に見られる。 以上のような検討によれば、本件舞台劇が原告著作の翻案であるとはいえない。 原告は、翻案に当たり、他の資料を参考にしたり、原作の一部を削除したり、原作にないものを付け加えたりするのは、脚本家の初歩的技法であるにすぎないと主張する。しかし、上記検討結果に照らせば、本件舞台劇は、単に原告著作をベースにその一部を削除し、それにないものを付け加えたというようにみることはできず、むしろ、各資料に共通するコルチャックの生涯をベースとして、ワイダ映画に描写されたシーンを取り入れつつ、時代背景や史実を原告著作やその他の著作を参考にして取り込むことによって、製作されたものと評価するのが相当である。 原告は、原告著作の表現上の本質的特徴は、特に最後にコルチャックが「あなたはまちがっている。」と述べる点に凝縮されていると主張する。しかし、 これは、原告著作においてすら、コルチャックが貨車に乗り込む象徴的シーンについて伝えられている4種類のもののうちの一つとして記載されているにすぎない上、もともとは原告著作より前に出版されたネヴェルリイの著書等に記されていることであるから、この部分が原告著作の中で表現上の創作性のある特徴部分であるということはできない。 また、確かに被告Yは、前記認定のとおり、既に95年公演の台本を執筆するに当たって、原告著作を読んでおり、95年台本の執筆過程でBから、原告著作を原作とすることになったと伝えられて原告著作からできるだけ使わせてもらうようにと言われている。しかし、翻案といえるためには、後行の著作物が先行の著作物に依拠して創作されたというだけでなく、後行の著作物において、先行の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できることが必要であって、この要件は、両方の著作物を対比することによって客観的に判断すべきものである。したがって、 被告Yが原告著作に接し、それを参考にして95年公演の台本を執筆し、97年公演の台本もそれと大差がないからといって、直ちに97年公演に係る本件舞台劇が原告著作の翻案であるということはできない。 オ なお、原告は、95年公演は原告著作が「原作」であるとクレジット表示され、97年公演は95年公演とほとんど差がないことから、97年公演も原告著作を原作とするものであると主張する。 確かに、先に認定したとおり、95年公演においては、一貫して、原作が原告著作である旨のクレジット表示と宣伝がなされており、被告Yも、原告著作をできるだけ使うように言われて脚本を執筆したものである。 しかし、著作権法上の「翻案」に当たるか否かは、前記のとおり、先行の著作物と後行の著作物の表現を客観的に対比して判断すべきものであって、先行著作物が後行著作物の「原作」と表示されたからといって、直ちに著作権法上の翻案となるわけではない。この点は、95年公演において、「脚本原作」としてA戯曲がクレジット表示されたのと同様である(原告自身、A戯曲は95年公演の原作でも脚本でもないと供述しているところである。)。また、原告著作に記された翻訳やエピソードを使用したとしても、それが原告著作の表現上の本質的特徴が感得される態様で使用した場合にのみ翻案になるものである。そして、これらの見地から客観的に検討した場合、本件舞台劇が原告著作の翻案と認められないことは先に判断したとおりである(なお、検甲1〔95年公演のビデオ〕によれば、95年公演も97年公演とほぼ同様の内容であり、これまで検討したところに照らして、やはり原告著作の翻案であるとは認められない。)。 したがって、95年公演において原告著作が「原作」と表示されたことから、97年公演が原告著作の翻案によるものであるということはできない。 もっとも、先に認定したように、被告朝日新聞社及び被告劇団ひまわりは、いずれも、95年公演の企画当初の時点から、原告著作は内容的に脚本の基礎となるようなものではなく、脚本は被告Yにおいて自由に執筆することを前提に企画を進めたものであったにもかかわらず、当初から原告著作を「原作」とクレジット表示し、一貫して原告に対し原作者として接している。そして、このようにした理由は、前記のとおり、共同主催者の一方である被告劇団ひまわりの側は、実際に公演を製作するという立場から、劇の製作は被告劇団ひまわりが自由に行うということを当初から強く主張し、その前提で95年公演を引き受け、被告Yにも脚本を依頼したものであるが、他方の主催者である被告朝日新聞社においては、自らが95年公演の共同主催者となり、そのための費用を負担するには、95年公演が自社から出版している原告著作の宣伝にもなるとの社内的な名目が必要であったとの事情があり、そのために、難色を示す被告劇団ひまわりを強く説得して、原告著作を「原作」と表示するに至ったものである。このように、95年公演において、原告著作を「原作」とクレジット表示することは、A戯曲を「脚本原作」とクレジット表示するのとは異なり、被告朝日新聞社自身の必要に基づくものであったといえる。 しかし、証人D及び同Bの証言及び原告本人の供述によれば、当時原告との応接の窓口を務めていた被告朝日新聞社の側では、原告著作を「原作」と表示する趣旨が前記のようなものであったことを原告に伝えたことはなかったと認められるのであり、この点は被告劇団ひまわりにおいても同様である。かえって、被告朝日新聞社及び被告劇団ひまわりは、原告に対し常に原作者との扱いで接し、原告から脚本執筆に必要な資料の提供を受けたり、広告に必要な写真を借り受けたり、登場人物の子供の名前の教示を受けたり、その他演出上の相談をしたりしたのであって、そのために原告は、真に原告著作を原作として95年公演が製作されたものであると信じ、上記のような種々の協力をしたものと認められる。それにもかかわらず、被告朝日新聞社及び被告劇団ひまわりは、平成8年11月の本件記事をきっかけに原告との関係が悪化し、公演に対する協力を得られなくなるや、97年公演と原告著作とは関係がないという態度をとり、本件訴訟においては95年公演も原告著作の翻案ではなかったと主張しているのであって、このような態度は、原告に対する関係では背信的な行為であるといわざるを得ない。 しかしながら、被告朝日新聞社及び被告劇団ひまわりに上記のような背信的な事情があるからといって、本件舞台劇(及び95年公演)が原告著作の翻案とはいえないとの前記判断を左右するものではない。 (3) 以上によれば、97年公演が原告の翻案権及び上演権を侵害するとはいえず、また、著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害するともいえない。 したがって、その余の点について判断するまでもなく、請求1は理由がない。 2 争点(2)ア(本件記事の名誉・信用毀損性)について (1) 被告朝日新聞社が平成8年11月26日の朝日新聞夕刊に本件記事を掲載したこと及びその内容は、前記第2の1基礎となる事実(5)のとおりである。 そして、甲7によれば、本件記事は、A戯曲がドイツのケムニッツ市立劇場で地元の高校生によって上演され、観客に感動を与えたことを伝えるものであるところ、本件記事中には、①Aの脚本による劇「コルチャック先生-ある旅立ち」がドイツ(旧東独)のケムニッツ市立劇場で、日本の国外では初めて上演されたこと、②この劇は、戦後50年を記念して、昨年夏、俳優の加藤剛主演により日本で初演されたこと、が記載されていることが認められる。また、本件記事中には、原告著作や原告について触れるところはない。本件記事のこのような記載内容からすると、本件記事に接した読者は、平成7年に俳優の加藤剛の主演により日本で初演された劇「コルチャック先生」(すなわち95年公演)はA戯曲を上演したものであったとの認識が生じるものと認められる。 95年公演は、被告Yの脚本によって上演されたものであって、A戯曲を脚本として上演されたものではなく、Aの作品を原作とするものでもないことは前記のとおりであるから、本件記事は、この意味で、客観的事実に反するものであったといえる。また、95年公演は、「原作X、脚本原作A」とのクレジット表示の下に行われたものであるから、この面からみても、本件記事が不正確であったことは否定できない。 (2) ところで、原告は、本件記事により、あたかも95年公演に係る舞台劇「コルチャック先生」の原作者が原告ではなかったかのように報道され、それによって名誉及び信用を毀損されたと主張する。 しかし、本件記事は、直接には、Aの脚本による劇がドイツで上演され、かつ、日本でも95年公演で上演されたということを伝えるものであり、95年公演の原作が何であったかということまで言及しているものではない。 本件記事が、95年公演の原作がA戯曲であったということを伝えるものとして読者に認識され得るとしても、一般の読者は95年公演の原作の関係を知らないのが通常であるから、A戯曲がドイツで上演され、かつ95年公演で上演されたということを伝える本件記事から、直ちに原告著作が原作ではなかったとの認識が生じるとはいえない。 また、95年公演の原作関係について知っている読者にとっても、95年公演では、A戯曲も「脚本原作」とのクレジット表示をされたのであるから、A戯曲がドイツで上演されたことの報道を中心とする本件記事において、A戯曲の紹介をするに当たって、それが95年公演の原作となったものであると読者に受け取られるような記載があったとしても、それによって直ちに、原告著作が95年公演の原作ではなかったとの認識が読者に生じるとはいえない。もっとも、原告本人の供述によれば、本件記事の掲載後、原告著作の読者やヨーロッパのコルチャック研究者等から原告に対して、95年公演の原作は原告著作ではなかったのかとの問い合わせがあるなどしたことが認められるが、そのような印象は、95年公演が原告著作のみを「原作」としたとの誤った前提に立って初めて生じるものである上に、前記のとおり、本件記事は不正確な面があるにせよ、原告著作が95年公演の原作であることを否定した趣旨のものでもないから、本件記事によって原告の名誉・信用が毀損されたとはいえない。 (3) 以上によれば、本件記事は、客観的事実に反する内容ではあるものの、原告の名誉及び信用を害するものとは認められない。 したがって、請求2及び3は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。 3 争点(3)ア(本件放送の著作権侵害性)及びイ(本件放送の許諾)について (1) 被告日本放送協会が、平成8年3月25日及び同年9月5日、NHK衛星第2放送(11チャンネル)において、95年公演(東京公演)を収録した番組を放送したこと(本件放送)は、前記第2の1基礎となる事実(4)記載のとおりであるところ、95年公演が原告著作を翻案したものであると認められないことは先に述べたとおりであるから、本件放送についての原告の承諾の有無にかかわらず、本件放送は原告の著作権(公衆送信権)を侵害しないというべきである。 (2) なお、念のため、本件放送に対する原告の許諾の有無について検討する。 ア 証拠(後掲書証、戊7、証人D、同B、同E、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 (ア) 本件放送については、平成7年7月ころに、被告朝日新聞社から、被告日本放送協会に対し、中継の依頼がなされ、被告朝日新聞社、被告劇団ひまわり及び被告日本放送協会の協議の結果、95年公演の主催者(被告朝日新聞社及び被告劇団ひまわり)において公演を収録したビデオを制作し、それを被告日本放送協会の関連会社であるNHKエンタープライズが買い取って放送するということとなった。この合意に関する契約書(覚書)が作成されたのは、平成8年2月1日である(戊2)。 (イ) この合意を受けて、被告劇団ひまわりのBは、そのころ、本件放送を行うことについて、95年公演の主演俳優であった加藤剛を始め、関係者から承諾を取り付け、平成8年8月上旬ころには、原告に対しても、原告の妻を通じて口頭で説明したが、特に異論はなかった。 一方、被告朝日新聞社のDは、何度も原告ないし原告の妻に本件放送のことを話し、同年1月には放送用に収録したテープのコピーを原告に送付し、同年3月には、放送日が3月25日に決まった旨の案内も送付した(甲8)。 (原告本人は、甲8の案内を送付されるまで、本件放送について証人Dと話をしたことはないと供述するが、証人Dを初めとする被告朝日新聞社及び被告劇団ひまわりが、少なくとも95年公演の段階においては、原告を原作者として扱い、そのように尊重して接してきたことは、争点(1)アで認定したことから明らかであるから、前記本件記事が掲載されて原告と被告朝日新聞社らとの関係が悪化する以前の段階で、本件放送を原告に何の断りもなしに行うとは考え難い。したがって、原告本人の前記供述は採用できない。) (ウ) 本件放送の初回放送は、平成8年3月25日に行われたが、その直後の同年4月上旬、自身もコルチャック研究者である原告の妻はBに手紙(戊4)を送り、その中で、「ビデオテープをお送りいただきありがとうございました。また先日はお忙しいところお電話を申し訳ございませんでした。」「テレビやビデオテープをみますとまた感慨も新たになります。本当にいろいろと大変だったのではないでしょうか。」と記載されており、文中に、本件放送に対する抗議は全く記載されていない。 (エ) また本件放送の2回目は、平成8年9月5日に行われたが、その直後の同年10月2日、原告の妻は被告日本放送協会の番組編集局長に手紙を送り、その中で、「B.S.でX原作の舞台劇(劇団ひまわり)を放映していただき厚く御礼申し上げます。」と記載した(戊3。ただし、手紙の本来の趣旨は、別の番組制作に関する疑念を示し、質問をする点にある。)。このときも、原告ないし原告の妻から放送に対する抗議はなかった。 (オ) ところが、その後2年5か月以上を経過した平成11年3月8日、原告は、代理人の弁護士を通じて被告日本放送協会に対して本件放送について著作権侵害であるとして損害賠償を請求する旨の通知を送付した。 (カ) 被告朝日新聞社や被告劇団ひまわりからの原告に対する連絡は、電話でなされることも多く、その際には原告の妻が対応することも多かったが、その場合でも、原告は、妻から電話の内容については報告を受けていた。 イ これらの事実からすれば、原告は、本件放送について、少なくとも黙示の許諾を与えていたというべきである。 原告は、本件放送については知っていたにもかかわらず、初回放送後約3年近くも経過してから初めて抗議の意思を表明したことについて、当初は著作権のことをよく知らなかったので、被告日本放送協会が放送してくれるのかという程度にしか思っていなかったが、その後にこのような放送を行うには原作者としての原告の許可を得なければならないことが分かってきたからであると供述するが、この供述を前提としたとしても、原告が、事前及び事後に、本件放送のことを知りながら、それを黙認していたとの前記認定を左右するものではない。 (3) したがって、請求4は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。 |
|
|
結語
以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないから、主文のとおり判決する。 |
| 裁判長裁判官 | 小松一雄 |
|---|---|
| 裁判官 | 安永武央 |
| 裁判官 | 高松宏之 |