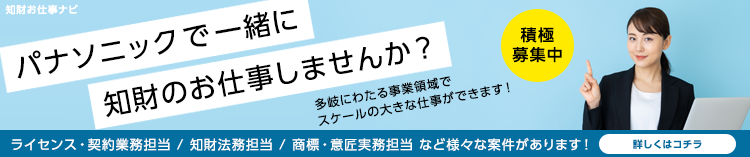この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
| 審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
|---|---|---|
| 平成13ワ10769同15年(ワ)第28982号 著作物使用料請求事件 平成14ワ4003同15年(ワ)第28982号 著作物使用料請求事件 | 判例 | 特許権 |
| 平成13ワ8593同15年(ワ)第28983号 著作権使用料請求事件 平成14ワ4006同15年(ワ)第28983号 著作権使用料請求事件 | 判例 | 特許権 |
| 平成13受952著作権侵害行為差止請求事件 | 判例 | 特許権 |
| 平成10ワ6979著作権侵害行為差止請求事件 平成10ワ9774著作権侵害行為差止請求事件 | 判例 | 特許権 |
| 平成11ネ3484著作権侵害行為差止請求控訴事件 | 判例 | 特許権 |
| 関連ワード | 著作者 / 固定 / 音楽の著作物 / 映画の著作物 / アニメーション / 二次的著作物 / 翻案 / 複製物 / 実演家 / 同一性 / レコード / 商業用レコード / 公衆送信 / 放送 / 放送事業者 / 有線放送 / 有線放送事業者 / 共同著作物 / 録音 / 録画 / 著作者人格権 / 複製権 / 公衆送信権 / ビデオ / 引用 / 補償金 / 登録 / 著作隣接権 / 報酬請求 / 二次使用 / テレビジョン放送 / 有線テレビジョン放送 / 著作権侵害 / 差止 / 損害賠償 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
|
| 事件 |
平成
13年
(ワ)
8592号
著作権使用料請求事件
平成 14年 (ワ) 4002号 著作権使用料請求事件 平成 15年 (ワ) 28981号 著作権使用料請求事件 |
|---|---|
|
甲事件原告 協同組合日本脚本家連盟 乙事件原告 協同組合日本シナリオ作家協会 乙事件原告 社団法人日本音楽著作権協会 乙事件原告 社団法人日本芸能実演家団体協議会 甲事件及び乙事件原告3名訴訟代理人弁護士 田倉栄美 乙事件脱退原告 社団法人日本文芸著作権保護同盟 訴訟代理人弁護士 田倉栄美 乙事件参加人 社団法人日本文芸家協会 訴訟代理人弁護士 辻洋一 被告 成田ケーブルテレビ株式会社 訴訟代理人弁護士 中田祐児 同 島尾大次 |
|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 判決言渡日 | 2004/05/21 |
| 権利種別 | 著作権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
1 被告は,甲事件原告協同組合日本脚本家連盟に対し,4万7115円及びこれに対する平成13年5月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,甲事件原告協同組合日本脚本家連盟,乙事件原告協同組合日本シナリオ作家協会,乙事件原告社団法人日本音楽著作権協会及び乙事件参加人に対し,101万1081円及びこれに対する平成13年5月15日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,甲事件原告協同組合日本脚本家連盟,乙事件原告協同組合日本シナリオ作家協会及び乙事件参加人に対し,13万102円及びこれに対する平成13年5月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 甲事件原告,乙事件原告ら(乙事件原告社団法人日本芸能実演家団体協議会を除く。)及び乙事件参加人のその余の請求を棄却する。 5 乙事件原告社団法人日本芸能実演家団体協議会の請求を棄却する。 6 訴訟費用については,乙事件原告社団法人日本芸能実演家団体協議会と被告の間に生じたものは同原告の負担とし,甲事件原告,その余の乙事件原告ら,乙事件脱退原告及び乙事件参加人と被告の間に生じたものは,これを4分し,その3をこれらの原告ら(乙事件脱退原告を除く。)及び乙事件参加人の,その余を被告の各負担とする。 7 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
請求
1 被告は,甲事件原告協同組合日本脚本家連盟,乙事件原告協同組合日本シナリオ作家協会,乙事件原告社団法人日本音楽著作権協会,乙事件原告社団法人日本芸能実演家団体協議会及び乙事件参加人に対し,485万2224円及びこれに対する平成13年5月15日(甲事件原告協同組合日本脚本家連盟の訴え(平成13年(ワ)第8592号)の訴状が被告に送達された日)から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,甲事件原告協同組合日本脚本家連盟,乙事件原告協同組合日本シナリオ作家協会,乙事件原告社団法人日本芸能実演家団体協議会及び乙事件参加人に対し,56万6092円及びこれに対する平成13年5月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
|
|
事案の概要
本件は,甲事件原告,乙事件原告ら及び乙事件脱退原告と被告との間で締結された被告による同時再送信における著作物使用に関する契約に基づき,甲事件原告及び乙事件原告ら及び乙事件参加人(以下,併せて「原告ら」という。)が,被告に対し,契約に定められた使用料(平成6年度から平成11年度分)の支払いを求めている事案である。 原告らの主張に対し,被告は,①原告らは,著作権法上,被告によるテレビ番組の同時再送信について何らの権利を有していないのに,著作物使用に関する契約に基づき使用料を請求し得ると主張しているものであって,契約自体錯誤無効であるし,そうでなくとも原告らの請求は著作権法に反するものであるから認められない,②被告による同時再送信は,原告らが放送事業者に対して許諾した著作物の使用の範囲に含まれているものであって,そもそも原告らは被告に対して使用料等の請求をなし得る立場にないので,本件各契約はその要素に錯誤があり無効である,③原告らの請求は判例あるいは信義則に反する,④乙事件原告社団法人日本芸能実演家団体協議会(以下「原告芸団協」という。)は,本来被告に対して著作隣接権を行使できる立場にないのに,同時再送信について著作隣接権を有するかのごとく被告を欺罔して契約を締結したものであるから,上記契約は,少なくとも原告芸団協に関する部分については詐欺により取り消されるべきものであるか,錯誤により無効である,⑤原告らの請求は,契約期間満了又は消滅時効により認められない等と主張して争っている。 1 前提となる事実関係(証拠により認定した事実については,末尾に証拠を掲げた。) (1) 当事者 ア 甲事件原告協同組合日本脚本家連盟(以下「原告日脚連」という。原告日脚連の前身は,協同組合日本放送作家組合であるが,以下においては両者を区別することなく「原告日脚連」という。),乙事件原告協同組合日本シナリオ作家協会(「以下「原告シナリオ作家協会」という。),乙事件原告社団法人日本音楽著作権協会(以下「原告音楽著作権協会」という。)及び乙事件参加人(以下「参加人」という。)は,著作権管理事業法に基づき文化庁長官の登録を受けた著作権等管理団体であり,著作物の管理等を行っている団体である(なお,原告日脚連,原告シナリオ作家協会及び原告音楽著作権協会は,平成13年10月1日の著作権等管理事業法施行前においては,著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律(以下「仲介業務法」という。)に基づき著作権に関する仲介業務をなすことの許可を受けた著作権仲介団体であった。)。 原告芸団協は,著作権法第95条,95条の3,104条の3に基づき,文化庁長官により「実演を業とする者の相当数を構成員とする団体」として指定を受けた団体である。 イ 乙事件脱退原告社団法人日本文芸著作権保護同盟(以下「脱退原告」という。)は,平成13年10月1日の著作権等管理事業法施行前においては,仲介業務法に基づき著作権に関する仲介業務を行うことの許可を受けた仲介業務団体であり,著作権等管理事業法施行後においては,同法に基づき文化庁長官の登録を受けた著作権管理団体であった。平成15年10月1日,参加人は,脱退原告から著作権管理業務と共に本件A契約及び本件B契約(以下,両契約を併せて「本件各契約」という。)に基づき被告に対して有する債権を承継した。 これに伴い,参加人は,民事訴訟法47条1項に基づき本件訴訟に参加し,脱退原告は,被告の同意を得て本件訴訟から脱退した。 ウ 被告 被告は,有線テレビジョン放送法(以下「有テレ法」という。)による放送事業等を目的として,昭和62年4月3日に設立された株式会社であり,平成元年9月8日,有テレ法3条に基づき,有線テレビジョン放送施設の設置について郵政大臣の許可を受け,平成2年10月28日からサービスを開始し,以後現在に至るまで,有線テレビジョン放送を継続して行う有線放送事業者である。 (2) 使用許諾契約の締結 ア 原告日脚連,原告音楽著作権協会,原告シナリオ作家協会,原告芸団協及び脱退原告(以下,上記5団体を併せて「原告ら5団体」という。)は,平成3年6月12日,被告との間で,有線テレビジョン放送に関し,次の内容の契約を締結した(甲1,以下「本件A契約」という。)。 第1条(使用許諾) 原告日脚連,原告音楽著作権協会,原告シナリオ作家協会,脱退原告(以下「原告日脚連ら4団体」という。)は,被告に対し,第2条に掲げる使用料を支払うことを条件として,原告日脚連ら4団体がコントロールを及ぼし得る範囲に属する著作物を使用して製作された放送番組をケーブルによって変更を加えないで同時再送信することを許諾する。 2 原告芸団協は,被告が第2条に掲げる補償金を支払うことを条件として,原告芸団協の会員の実演によって製作された放送番組を,被告がケーブルによって変更を加えないで同時再送信することに対し,放送事業者に異議を申し立てないことを約定する。 第2条(使用料,補償金の支払い) 上記使用料と補償金の合計金額は,被告が当該年度に受領すべき利用料総額に,各々次の料率を乗じて算出した額とする。 ① 区域内再送信は,1波について0.015% ② 区域外再送信は,1波について0.09% 但し,被告が支払う使用料と補償金の合計額は,受領すべき利用料総額の0.35%を限度とする。 2 使用料及び補償金に課される消費税は,別途添付の上,被告から原告日脚連ら4団体及び原告芸団協に支払う。 第3条(利用料収入の報告) 被告は,当該年度の利用料収入を原告日脚連ら4団体及び原告芸団協に報告するものとし,当該年度終了後2か月以内に有線テレビジョン放送施行規則36条の規定による業務運営状況報告書の写しにより,原告日脚連ら4団体及び原告芸団協の代表者である原告日脚連に報告する。 第4条(使用料,補償金の支払い) 被告は,原告日脚連ら4団体及び原告芸団協に対し,第2条の使用料,補償金を当該年度終了後2か月以内に,代表者である原告日脚連の事務所に持参または送金して支払う。 第5条(契約の解除) 被告が,本契約の規定に違反したときは,代表者である原告日脚連は1か月間の通知催告の上,本契約を解除することができる。 第6条(差止め請求と損害賠償請求) 被告が,本契約の規定に違反したときは,代表者である原告日脚連は,被告に対し,当該違反行為の停止と損害賠償を請求することができる。 第7条(管轄裁判所の合意) (省略) 第8条(契約期間) 本契約の有効期間は,平成2年10月1日から平成3年3月31日までとする。 本契約の期間満了の日の1か月前までに,原告日脚連ら4団体,原告芸団協又は被告から本契約の廃棄,変更について特別の意思表示が文書によってなされなかった場合は,期間満了の日の翌日から起算しさらに1か年間その効力を有する。以降の満期のときもまた同様とする。 イ 原告日脚連,原告シナリオ作家協会,原告芸団協及び脱退原告は,平成3年6月12日,被告との間で,有線ラジオ放送に関し,次の内容の契約を締結した(甲2,以下「本件B契約」といい,本件A契約と併せて「本件各契約」という。)。 第1条(使用許諾) 原告日脚連,原告シナリオ作家協会,脱退原告(以下「原告日脚連ら3団体」という。)は,被告に対し,第2条に掲げる使用料を支払うことを条件として,原告日脚連ら3団体がコントロールを及ぼし得る範囲に属する著作物を使用して製作されたラジオ放送番組を,ケーブルによって変更を加えないで同時再送信することを許諾する。 2 原告芸団協は,被告が第2条に掲げる補償金を支払うことを条件として芸団協の会員の実演によって製作されたラジオ放送番組を,被告がケーブルによって変更を加えないで同時再送信することに対し,放送事業者に異議を申し立てないことを約定する。 第2条(使用料,補償金の支払い) 原告日脚連ら3団体及び原告芸団協に対する前条の使用料と補償金の合計金額は,被告が当該年度に受領すべき利用料総額に,各々次の料率を乗じて算出した額とする。 ① 区域内再送信は,1波について0.015%×10/100 ② 区域外再送信は,1波について0.09%×10/100 但し,被告が支払う使用料と補償金の合計額は,受領すべき利用料総額の0.35%×10/100を限度とする。 2 使用料及び補償金に課される消費税は,別途添付の上,被告から原告日脚連ら3団体及び原告芸団協に支払う。 第3条(利用料収入の報告) 被告は,当該年度の利用料収入を原告日脚連ら3団体及び原告芸団協に報告するものとし,当該年度終了後2か月以内に有線テレビジョン放送施行規則36条の規定による業務運営状況報告書の写しにより,原告日脚連ら3団体及び原告芸団協の代表者である原告日脚連に報告する。 第4条(使用料,補償金の支払い) 被告は,原告日脚連ら3団体及び原告芸団協に対し,第2条の使用料,補償金を当該年度終了後2か月以内に,代表者である原告日脚連の事務所に持参または送金して支払う。 第5条(契約の解除) 被告が,本契約の規定に違反したときは,代表者である原告日脚連は1か月間の通知催告の上,本契約を解除することができる。 第6条(差止め請求と損害賠償請求) 被告が,本契約の規定に違反したときは,代表者である原告日脚連は,被告に対し,当該違反行為の停止と損害賠償を請求することができる。 第7条(管轄裁判所の合意) (省略) 第8条(契約期間) 本契約の有効期間は,平成2年10月1日から平成3年3月31日までとする。 本契約の期間満了の日の1か月前までに,原告日脚連ら3団体,原告芸団協又は被告から本契約の廃棄,変更について特別の意思表示が文書によってなされなかった場合は,期間満了の日の翌日から起算しさらに1か年間その効力を有する。以降の満期のときもまた同様とする。 2 争点及び当事者の主張 (1) 被告の同時再送信するテレビ番組は映画の著作物であって,原告らは著作権等の主張をすることができないものであり,本件A契約は詐欺により取り消し得べきものか,あるいは錯誤無効か (被告の主張) 映画の著作物であるテレビ番組の同時再送信に関し,原告ら及び脱退原告は,そもそも著作権,著作隣接権の主張をなし得る立場にないのであって,原告ら及び脱退原告が被告に対して著作権等の主張をなし得るという誤った前提で締結された本件A契約は詐欺により取り消し得べきものであるし,あるいはそうでなくとも錯誤により無効である。 ア テレビ番組は「映画の著作物」であること テレビ番組は,「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され」,かつ,生放送番組を除き,ビデオテープ等の「物に固定されている著作物」であるから,著作権法にいう「映画の著作物」に該当する。そして,著作権法においては,映画の著作物について,著作権者は「その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」と定められるとともに,「その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物」の著作者が,映画の著作物の著作者に当たらないことを明確にしている(著作権法16条)。 ところで,著作権法16条が映画の著作物について著作者を「映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」と定めたのは,著作権法が著作によって著作権が発生するという無方式主義(17条2項)と,著作者に著作者人格権を認めていることから必然的に生じた結論であるが,著作権法16条がそのまま適用されれば,映画の著作物について複数の著作権者が存在し,著作物の利用が著しく困難になる。また,著作権法の本質は,所有権と同様に,「一定の著作物の利用を直接に支配して利益を受ける排他的の権利」ということにあるから,共同著作物のような場合を別とすれば,複数の著作権者が存在することは著作権の本質に反する。 そこで,著作権法29条においては,「映画の著作物の著作権は,その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは,当該映画製作者に帰属する」と定めている。その結果,映画の著作物については,他の著作物と異なり,著作権は映画製作者に帰属し,著作者は著作人格権のみを行使することになった。そして,映画著作者が行使する著作権は,映画の著作物を一般的,全面的に支配する権利であり,客体に対する種々の権能の束ないし総合とはみなされない。 イ 映画の著作物において,小説,脚本,音楽の著作者に留保されている権利はないこと このように,著作権法は,「映画の著作物」という概念を認め(著作権法2条3項など),一般的な著作物とは異なった扱いをしている。すなわち,それは映画の著作物の著作者を法定し(16条),著作権が映画製作者に帰属する(29条1項)と定めている点である。このような著作権法上の特別な扱いは,映画の著作物の特殊な性格,すなわち,その製作に多数の関係者が関与し,しかも,莫大な費用がかかることから,投下資本の回収を容易にし,映画製作の意欲をかき立てる目的で,その権利関係を明確,単純化するためである。 ところが,映画の著作物に使われた音楽その他の著作物の著作者が当該映画の著作物について何らかの権利を留保し,映画の著作物の著作権とは別に,自らの権利を主張することができるということになれば,著作権法がわざわざ映画の著作物という概念を認め,映画の著作者を「その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」と法定し,著作権が映画製作者に帰属すると定めた意味が全く失われてしまう。さらに,映画の中身を構成する音楽その他の著作者は,当該映画の製作に当たり,著作物を使用することを許諾しているのである。それにもかかわらず,なお権利の留保を認める必要性がどこにあるのか理解できない。 被告が放送するテレビ番組は,いずれも多数のスタッフが関与しているものである。原告ら主張のように一部のスタッフについて著作権の主張が認められるとすると,そのいずれもが権利を留保することになり,放送をはじめ映画の著作物としての利用が不可能になる。また,原告が主張する音楽など一部の著作者に限って権利の留保を認めるとすれば,なぜ,それ以外のスタッフには権利の留保が求められないのか,その合理的区別が明らかではない。実質的に考えても,わずか1分程度しか流れない主題歌の作詞・作曲者,編曲者が,1時間の番組の全体について権利を行使し得るというのは妥当とは思われない。また,複数の楽曲が利用されている場合,いずれの音楽スタッフが権利を有するのかも不明確となってしまう。 このように,原告らの主張を認めると,一つの映画の著作物について,あまりに多数の権利者が存在することになり,複雑極まりない権利関係を生ずる。 しかも,原告らが請求する使用料等を支払ったとしても,原告ら5団体に加盟していない権利者からは,被告の同時再送信を差止めされる場合もあることになってしまう。すなわち,原告ら5団体に使用料等を支払うことは本件の問題を何ら解決することにならず,かえって,映画の著作物の利用関係,権利関係を複雑にし,その利用を不可能ならしめるだけなのである。 この点,著作権法16条は,映画の著作物の著作者から「その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除く」と定めているが,これまで述べてきたことを踏まえて考えるならば,この趣旨は,映画の著作物に関しては,小説,脚本,音楽などの著作者を著作権法28条の原著作者と認めないと法が定めたものと理解することができる。 原告らの主張は,著作権の権利としての本質に反する考え方であり,このような複雑な権利関係の発生を否定するために,映画の著作物という概念を想定し,その著作者を限定し,かつ,著作権を映画製作者に帰属せしめた著作権法の規定とも相容れないものであって,到底認められない。 ウ 仮に映画の著作物について著作権法28条の適用が認められても,原著作者の有する権利は,著作者人格権にとどまること まず,著作権法29条1項,2項が適用される場合,映画の著作物の著作者(監督ら)は,映画の著作物の著作権を原始的に有さず,少なくとも,放送権を有さない。したがって,監督らは,映画の著作物の放送を差し止めたり,使用料を請求したりすることはできない。 ところで,著作権法28条によって原著作者の有する権利は,「当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利」である。 よって,仮に原告らが映画の著作物について原著作物の「著作者」であったとしても,その行使できる権利は,「著作者」である監督らが有する権利にとどまり,監督らが原始的に有さない権利にまで及ばないから,被告に対して,映画の著作物の放送を差し止めたり,使用料を請求することはできない。 要するに,原著作物の著作者は,二次的著作物の「著作者」が有する以上の権利を行使できないし,このように解して初めて,映画の著作物に関しその著作権の帰属を定めた著作権法29条と28条を整合的に理解することができる。 エ テレビ番組に使われているからといってすべてが原著作物になるわけではない。 (ア) 二次的著作物とは,「著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物」(著作権法2条1項11号)である。したがって,小説,脚本,音楽などの著作物が,映画の著作物に使われているからといって,常に両者が原著作物と二次的著作物の関係に立つわけではない。 この点,東京地裁平成6年2月18日判決(判例時報1486号110頁)等の示した基準を前提とすれば,映画の著作物についても,これが別の著作物を翻案した二次的著作物といえるためには,①それが原著作物に依拠して製作されたこと(依拠性),②その内容において,原著作物の内容の主要な部分と同一の思想,感情を表現していること(思想,感情の同一性)の2要件が必要である。 (イ) 音楽の著作物はテレビ番組の原著作物にはなり得ない しかし,原告らが著作権等を主張する番組表(甲4)の番組欄には各番組のBGM,主題歌などが列挙されている。音楽に依拠し,かつ,音楽の主要な部分を含み音楽が表現している思想,感情の主要な部分と同一の思想,感情を表現するものとして,映画の著作物が製作されることは通常あり得ないから,これらの音楽はいずれも映画の著作物について原著作物とは認められない。 それゆえ,音楽の著作物が被告の有線放送するテレビ番組の原著作物であるとの原告音楽著作権協会の主張は失当である。 (ウ) 原告らが引用する脚本はテレビ番組の原著作物にはなり得ない (a) 原告らの引用する番組表の脚本欄には,あらゆる番組について脚本が存在するかのように記載されている。しかし,ニュース,ワイドショー,トーク,歌番組のように性質上,脚本としての文芸性(著作権法2条1項1号)が認められず,単なる進行予定を記載したにすぎないものについてまで,原著作物ということはできない。 (b) また,多くの脚本は,映画の著作物の製作のために,これに付随して作成されているから,当該脚本が独自の著作物として保護されるのは格別,当該映画の著作物との関係では,映画の著作物がその脚本に依拠して作成されたとはいえない。 (c) さらに,前記番組表には,原作の存在するものも相当数あり,原作の存在するものについては,原作とテレビ番組の間で原著作物,二次的著作物の成否が考えられるべきであり,脚本とテレビ番組との間にその関係が成立する余地はない。 すなわち,著作権法28条によると,原著作物の著作者は,二次的著作物の著作者が有するのと同一の権利を専有するとされており,また,原著作物と二次的著作物の関係が成立するためには,前記のとおり「依拠性」と「思想,感情の同一性」の2要件が必要とされるが,このような関係は原作とテレビ番組との間に成立する。そして,原作が存在する場合には,脚本は原作を映画化(テレビ番組化)するための手段にすぎず,独立に原著作物にはなり得ない。 ところで,本件の場合,原作の多くは「無所属」であるから(脱退原告の得ている年間使用料は4億円程度にとどまっていることからもこのことは明らかである),原告らは原著作物,二次的著作物の関係が成立することを理由に,使用料を請求することは許されない。 (エ) これまで述べてきたことから明らかなとおり,原作ないし脚本とテレビ番組との間に,常に原著作物と二次的著作物の関係が成立するわけではない。 それゆえ,原告らは,原作ないし脚本とテレビ番組との間に,原著作物と二次的著作物の関係が成立することを理由に使用許諾をして使用料を請求するのであれば,前記番組表の原作ないし脚本と実際に放送(同時再送信)されているテレビ番組との間で,テレビ番組が原作ないし脚本に「依拠」して製作され,テレビ番組に原著作物の表現している思想,感情の主要な部分と同一の思想,感情が表現されていることを立証しなければならないが,本件においてこのような立証は全くなされていない。 オ まとめ 以上述べてきたことをまとめると次のとおりとなる。 (ア) 原告らの主張を認めると,1つの映画の著作物について,あまりに多数の権利が存在することになり,複雑極まりない権利関係を生じ,このようなことを著作権法が認めているとは到底考えられない。しかも,原告らが請求する使用料等を支払ったとしても,原告ら5団体に加盟していない権利者との関係で,被告の同時再送信は差し止められかねない。すなわち,原告らに使用料等を支払うことは本件の問題を何ら解決することにならず,かえって,映画の著作物の権利関係,権利処理を複雑にし,その利用を複雑にし,その利用を不可能ならしめるだけなのである。 (イ) 映画の著作物について別途権利を留保している旨の原告らの主張は著作権の権利としての本質に反する考え方であり,このように複雑な権利関係の発生を否定するために,映画の著作権という概念を想定し,その著作者を限定し,かつ,著作権を映画製作者に帰属せしめた著作権法の規定とも相容れないものであって,到底認められない。 (ウ) また,原告らの主張する小説,脚本,音楽などと被告が同時再送信しているテレビ番組との間に,原著作物と二次的著作物の関係が成立しているとは認められず,少なくともその立証がなされたとはいえないから,この点についての原告らの主張も失当である。 以上のとおりであって,本件A契約は,著作権法に反して,原告らが被告による同時再送信について許諾をなし,あるいは使用料を徴収し得るという前提で締結されたものであるから,詐欺により取り消し得べきものであるし,そうでなくとも錯誤により無効である。 (原告らの主張) ア 本件A契約においては,被告の行う有線テレビジョン放送に関し,被告が原告ら5団体に対して一定の使用料を支払うべき旨が定められているものである。著作権法23条に明らかなとおり,著作権者は,公衆送信権を専有しているところ,著作者より著作権等の信託等を受けた原告ら5団体は,被告の行う放送番組の同時再送信について許諾権を有するのは当然である。本件A契約は,かかる許諾権限に基づき原告ら5団体と被告との間で締結されたものである。 イ 被告は,放送番組は映画の著作物であるとして,当該映画の著作物の著作権の帰属を問題としているが,この問題と著作者が有する著作権法23条の公衆送信権とは全く異なる問題である。 もとより,放送事業者は,「専ら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物」について, その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物を有線放送し,又は受信装置を用いて公に伝達する権利を有しているが(著作権法29条の2),これによって著作者の公衆送信権が制限されるというものではない。また,著作権法28条は「二次的著作物の原著作物の著作者は,当該二次的著作物の利用に関し,この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の権利を専有する。」と定めており,「二次的著作物の利用」という関係としても同様である。 原告らは,これら著作者らの権利に基づき,被告の行う放送番組の有線同時再送信について本件契約を締結したのである。 ウ 被告は,原告らは映画の著作物たるテレビ番組について原著作者として権利を有さないと主張するが,誤りである。 著作権法16条の規定によれば,脚本・音楽等の作者は,映画の著作物の著作者ではないが,映画の著作物の原著作者として,あるいは映画の著作物において利用されている著作物の著作者として,それぞれ当該映画の著作物の利用について別途権利を留保していることは明らかなことである。 なお,被告の主張のうち,「当該番組のために作られた脚本はそれゆえに原著作物にならない」という主張は,全く根拠のない主張であるし,著作権(脚本)の買取りがされているという趣旨なら,そのような事実はない。 エ 以上より,原告らは,被告の行う放送の同時再送信に対して著作権上の権利を有しているものである。本件A契約においては,これら著作者の著作物あるいは実演家の実演により製作された放送番組を被告が有線放送で同時再送信することを許諾するについて,その範囲を「甲らがコントロールを及ぼしうる範囲」と定めたものである。 被告が主張するまでもなく,放送番組には様々な番組がある。このため,本来であれば,被告は,放送番組を有線放送で同時再送信するについて,当該番組に関わる原著作者(原作,脚本,音楽)及び実演家の許諾を得ることが必要であるところ,これには実際上多くの労力を要することから,包括的な権利処理を行うべく,本件A契約により権利処理をしているものである。したがって,原告らの権利行使が著作権法に反して許されないということもないし,本件A契約が錯誤無効ということもあり得ない。 (2) 被告による同時再送信は,原告ら5団体が放送事業者に対して許諾した著作物の使用の範囲に含まれているものであって,被告は改めて許諾を得る必要はなく,本件各契約は錯誤無効か (被告の主張) 有線放送事業者による放送の同時再送信は,以下に述べるとおり,著作物の新たな利用ではないし,原告ら5団体も同時再送信を前提に放送事業者に許諾しているから,放送の同時再送信は原告らが放送事業者に対して許諾した著作物の使用の範囲に含まれている。したがって,被告は,原告ら5団体から改めて許諾を得る必要はなく,原告ら5団体からの被告に対する使用許諾を内容とする本件各契約は,錯誤無効である。 ア 同時再送信は,委託放送事業者が放送するテレビ番組の電波について,有線放送事業者が委託放送事業者の許諾を得た上で,受信すると同時に有線で送信する行為である。つまり,有線放送は,委託放送事業者の範囲内の行為であって,実質的には放送の中継行為にすぎない。 同時再送信の対象となる番組は,当該地域で一般に無線送信されている番組である。一般視聴者は,本来,これらのチャンネルを無線経由で受信して視聴できるはずであるが,建築物,自然障壁などによる電波障害がある地域では鮮明な画像が確保できないため,共同アンテナを立てて電波を受信し,ケーブルで各家庭に流して視聴することが行われてきた。 ケーブルテレビは,このような共同アンテナのシステムを発展させ,有線放送事業者としての免許を付与したものである。すなわち,引き込み端子の数が500を超えれば有テレ法上の許可が必要な施設となり,500以下であれば許可が不要な,いわゆる共同アンテナとなる(有テレ法3条1項,同法施行規則3条)。なお,共同アンテナの場合も,営利業者がアンテナを保有,管理し,施設管理料等の名目で料金を徴収することがある。 このように,ケーブルテレビは,同時再送信については,本質的に共同アンテナと全く同じ法的性質を有する。 イ 上記アで述べたとおり,同時再送信は,当該区域内の視聴者が,本来的に無線経由で視聴することが可能なはずなのに,何らかの事情で視聴ができない放送について,視聴可能な状態に回復するという役割を有する。 このように,同時再送信は優れて公共性が高く,有テレ法も一定の場合に同時再送信を義務付けている。現在のところ,有テレ法13条に基づく義務再送信の区域指定は行われていないが,これは,電波障害を受ける地域を有線放送事業者がカバーしているため被害が顕在化していないということなのである。 ウ このような同時再送信の性質に鑑み,欧米等の諸外国においても,放送を直接受信できる地域内において放送を受信して行う有線伝達は,通常の家庭用受信機による放送の受信と同じであり,公の伝達に該当しないという議論があり,また,放送を直接受信できる地域内における有線伝達は,放送事業者が著作権者から得ている放送の許諾によってカバーされており,公の伝達として別個に許諾を得る必要はないという議論がなされ,現に同時再送信が著作権侵害に該当しないという制度,判例法が構築されている。 このような諸外国の例は,我が国も加盟しているベルヌ条約下における公衆送信の解釈として,我が国の著作権法の解釈と直接かつ密接な関連性を有するのであり,基本的に我が国でも妥当する。 エ 上記のような諸外国の状況を受けて,我が国においても学説上同様な議論がされているところであり,区域内再送信については新たな許諾は不要との議論がなされているところである。我が国の著作権法はベルヌ条約のなかに体系に位置付けられることからすれば,当然である。 また,著作権者の合理的意思という観点から見ても,著作権者は,放送事業者に対して,その著作物を使用した映画の著作物たる番組の放送を許諾しているが,その際に受領する著作権料は,その局の放送エリア(ネット放送する場合は,そのネット局の放送エリア内も含む。)のすべての視聴者が視聴する対価として支払われているのであり,著作権者は,放送事業者の放送エリア内の視聴者が,放送か有線放送かを問わず,公衆送信により当該番組を受信することを許諾しているものと解されるのである。 そして,有線放送事業者の行う放送の同時再送信は,放送の届く範囲の視聴者を対象とした,本質的には中継にほかならないものであるから,有線放送事業者の同時再送信と放送事業者の無線放送のいずれにしても,放送事業者の放送エリア区域内の視聴者が,当該番組を視聴したという実態には何ら変わりがないのであって,このような実態に鑑みて,同時再送信の概念を実質的に再構成すれば,同時再送信は,著作権者が許諾した放送事業者の放送の範囲内における視聴手段の1つに過ぎず,著作物の新たな使用には当たらず,著作権者等の当初の許諾の範囲内に含まれるというべきである。 オ また,有テレ法13条2項は,有線テレビジョン放送事業者が放送を再送信する場合に放送事業者の同意を要求しているが,その同意の条件として,全番組の再送信義務及びチャンネルの確保義務が課されている。すなわち,人気がある番組の「つまみ食い」的放送が許されず,かつ,チャンネルイメージを確保するために,特定のチャンネルを当該放送事業者用に確保させることになる。 この,全番組の再送信義務及びチャンネルの確保義務が課される関係で,同時再送信は,放送事業者が自ら放送するのと異ならず,視聴者にもそのように受け止められている。当然,コマーシャル収入など放送の効果も,放送事業者に直接に帰属し,同時再送信したコマーシャルについて有線放送事業者が対価を徴収するわけではない。 カ 結局,同時再送信において番組を公衆送信している主体は,有線放送事業者ではなく,放送事業者である。 そもそも,放送事業者は,放送の補完として自ら有線放送を行うことができるのであり,放送事業者が自ら有線放送する場合と,有線放送事業者に下請けや履行補助させて有線放送する場合とで,著作物の新たな使用の有無が決まるというのは相当ではない。 したがって,放送事業者が原告らの許諾の範囲内で自ら著作物を使用していると法的に解されるのは,単に放送事業者が自己の有する事業設備を使用して,自ら直接に有線放送する場合だけを指すものではなく,これに加えて,放送事業者が事業設備を有する有線放送事業者に許諾を与えて,自己のためにのみ特定のチャンネルを確保させて許諾を得た番組を放送する場合をも含むと解するのが相当である。 キ まとめ (ア) 同時再送信の著作権法上の位置付けについては,各国で様々な議論がなされており,これらの議論を踏まえ,著作権法9条の2の規定をも勘案し,有線放送の概念を実質的に再構成すれば,少なくとも区域内同時再送信については,原著作者等の放送事業者に対する許諾の範囲に含まれており,新たな著作物の使用には当たらない。 放送事業者と有線放送事業者とは法人格を異にするが,同時再送信は,社会通念上,放送事業者の放送として扱われており,同時再送信の効果も放送事業者に帰属すること,放送事業者自らが有線放送した場合と下請会社に有線放送させた場合とで実態が異ならないことに鑑みれば,同時再送信は,放送事業者の著作物の使用の一態様にすぎない。 (イ) また,原著作者等は,放送事業者の放送に際して既に一旦報酬を得ており,許諾の範囲内の視聴者が,無線経由ではなく,有線経由で視聴すればさらに報酬を得られるというのは不合理である。同時再送信によって,著作物の使用料を請求すべき新たな市場が生じるわけではないのである。 さらに,同時再送信は,もとの放送に全く手を加えていないから,原著作者等の人格的利益を害するおそれもない。かえって,同時再送信は,本来あるべき放送秩序の回復ないし実現を図る方法であり,公益目的を有し,かつ,放送事業者の放送秩序に包含されるのであり,決して異質の新たな著作物の利用ではない。 そして,有線放送事業者が放送事業者から無償で同時再送信することの同意,許諾を得ているにもかかわらず,原著作者等が,有線放送事業者に直接使用料等を請求できることを認めれば,上記の放送秩序が混乱するのみならず,同時再送信の公益性を認めて,無償で放送の同意をした放送事業者の意思に反する結果ともなる。 (ウ) また,使用料等の請求権を認めた場合,著作権者は,放送同意の段階で著作権使用料の支払いを受けた上,更に有線放送事業者に対する請求も行い得ることとなって,著作権使用料の「二重取り」になるばかりか,そのコストは,結局,受益者たる同時再送信の視聴者に転嫁される。 視聴者は,本来アンテナで受信すれば,無料で視聴できるものを有線で受信すると有料になる。このようなことは,放送の公共性に照らして不公平であり,ひいては,難視聴地域の居住者などの視聴を経済的に萎縮させる結果を招く。 (エ) 以上に述べたところによれば,被告の区域内同時再送信行為は,共同アンテナで放送を送受信するのと全く法的性質を同じくするものであり,原告らの放送事業者に対する許諾の範囲内に含まれ,著作物の新たな使用には実質的に該当しないというのが著作権法の合理的解釈というべきであるから,原告らの主張は失当である。 (オ) したがって,被告の同時再送信について,放送事業者とは別に許諾をなし得ることを前提にした,本件各契約は契約の要素に錯誤があるものであって,無効であるし,仮にそうでなくとも,原告らの請求は,著作権法に違反するものであって認められない。 (原告らの主張) 被告の主張は争う。以下に述べるとおり,原告らの請求が著作権法上の根拠を欠くとする被告の主張は,いずれも誤りであり,本件各契約が錯誤により無効となる余地はないし,原告らの請求が著作権法に違反するということもない。 ア 被告は,「有線放送は,放送事業者の放送の範囲内の行為であって,実質的には放送の中継行為にすぎない」と主張するが,否認する。有線放送は,放送とは著作権法上異なった公衆送信の方法であり,「放送の範囲内」であるとか「放送の中継行為」といったものでなく,放送とは別個の著作物の使用・利用方法である。被告の主張する「同時再送信の法律的性格」がいかなる意味なのか判然としないが,原告らは,事実としてテレビ,ラジオの放送を許諾するについて,有線による同時再送信の許諾をしていない。 被告は,放送についての使用料と同時再送信についての使用料が「二重取り」になっていると主張するが,放送と同時再送信とでは著作物の使用方法が異なっているのであるから,「二重取り」ではない。 イ 被告は,著作権者の合理的意思という観点からみれば,「同時再送信の視聴者は,原著作者等が当該番組の視聴を許諾した対象者にすぎない」と主張するが,本件各契約で原告らが被告に許諾しているのは,被告のテレビ・ラジオ放送の同時再送信という「被告の利用行為」であって,「視聴者云々」とは関係がない。 被告は,これを混同あるいは意図的に置き換え,同時再送信は,原著作者等が与えた許諾の範囲を実質的に逸脱して,新たな著作物の使用を生じさせているわけではないといった議論を展開しているのであって,明らかに失当である。被告は,「放送秩序の回復ないし実現を図る方法である同時再送信」の意義を強調するが,その意味内容は別として,こういった問題と原著作者に対する権利侵害とは別個の問題である。 被告は,「同時再送信において番組を公衆送信している主体は,有線放送事業者ではなく,放送事業者であることが実態であり,外観上もそのように見える」旨主張するが,否認する。同時再送信の主体は,形式的にも実質的にも,当該有線放送(同時再送信)を行っている被告(有線放送事業者)である。 被告は,さらに「放送の同時再送信に同意をした放送事業者の意思に反する結果となる」と述べるが,放送事業者は,有線放送事業者に対する同意書等の中で「再送信に関し,著作権など第三者の権利の処理を必要とする場合は,その処理は貴方において行うこととなる」とか「再送信に際して生ずる番組に関わる著作権問題は貴殿の責任に於いて処理すること」と記載しているものであって,被告(有線放送事業者)に原著作者の権利処理を行うことを明示しており,それが放送事業者の意思である。 (3) 原告らの請求は,権利の濫用あるいは信義則違反か (被告の主張) ア 最高裁平成12年(受)第798号同13年10月25日第一小法廷判決・裁判集民事203号285頁(以下「キャンディ・キャンディ事件上告審判決」という。)は,二次的著作物に関し,二次的著作物の著作者は,原著作物の著作者の合意によらなければその権利を行使できないと解されることを明らかにした。この最高裁判例は,二次的著作物について共有著作物に関する著作権65条の規定を事実上,類推適用または準用して,二次的著作物の著作者と原著作者との合意によらなければ権利を行使できないことを明らかにしたものと評価し得る。 この最高裁判例の趣旨は,映画の著作物たるテレビ番組における原著作者についても及ぼすことが可能と思われる。すなわち,三次的著作物であるテレビ番組の権利行使については,放送事業者,脚本家,原作者の3者の合意が必要であり,二次的著作物である脚本の権利行使については,脚本家,原作者の2者の合意が必要である。 イ アニメーションについていえば,三次的著作物であるテレビ番組の同時再送信が適法になるのは,漫画家,脚本家,放送事業者の3者の合意による利用(有線放送事業者に対する許諾)がなされた場合のみである。 三者の合意による利用ではない場合には,その利用は,原著作者等との関係で違法な不法行為になり,差止め,損害賠償請求の対象となる。このように,原告らの主張によれば,原告らに使用料等を支払っても同時再送信が適法にならないばかりか,原告ら自身も,原作者からの差止めを受けるおそれがあることになる。 ウ 本件において,原告らは,放送事業者が被告に対して同時再送信を許諾することには反対しておらず,また,放送事業者に対して著作権侵害の不法行為を理由に差止めをしたり,損害賠償を請求したりしていない。 このことは,原告らが,放送事業者に対して同時再送信のための送信を許諾していることを裏付けている。その結果,放送事業者が被告に対して同時再送信を許諾する行為及び許諾に基づいて放送する行為は,原告らと放送事業者の合意に基づく権利行使になるから,原告らは,被告に対してもはや差止めを請求できない。 エ まとめ (ア) 以上のとおり,小説,脚本,音楽の著作者が,番組について権利を留保していることを前提に,有線放送事業者が同時再送信するには,これらの著作者全てに改めて使用料等を支払って許諾を取り付けなければならないとする原告らの主張は,実態に合致しないばかりか,原告ら自身をも不法行為者としてしまうものであって,法理論として完全に破綻している。 また,被告は,原告らに使用料を支払っても,同時再送信が適法になる余地はないことになってしまい,不合理である。 (イ) これに対し,原告らは,原告ら各自が原作者,放送事業者,無所属の権利者などの他の権利者との合意によらずに単独で権利を行使することが許されるかのように主張する。 しかし,前記最高裁判例は,二次的著作物である漫画の作者である漫画家が,原著作物である脚本の作者である原作者との合意に基づかずに,権利を行使することが違法である旨判示している。もし,漫画家が二次的著作物である漫画の利用権を「専有」し,漫画については漫画家の権利と原作者の権利とが「併存」しているならば,最高裁判例のような結論になるはずがない。 このように,原告らの主張は,最高裁判例を理解しないものであって失当である。 (ウ) なお,原告らは,テレビ番組について,原作者,音楽家,脚本家,放送事業者,その他無所属の権利者などの総員の合意によらなくても,ある権利者が単独で権利行使をすることは可能であり,当該権利者から許諾を受けた者が,順次,他の権利者の同意を得ていけば足りると考えているようである。 しかし,最高裁判例は,二次的著作物である漫画について,二次的著作物の著作者(漫画家)と,原著作物の著作者(原作者)の総員の合意を二次的著作物利用の前提と考えていることは明らかである。 このとき,仮に,事後的に他の権利者総員の許諾が得られたとしても,総員の許諾が得られるまでの間の無断使用が遡って適法化されるわけではなく,無断使用した権利者はその間の利用について損害賠償義務を負うことになる。 よって,「順次同意」または「順次許諾」という考え方は失当である。 (エ) さらに,原告らは,脚本を二次的著作物とした場合の漫画家など,自らの著作物の原著作者等に対しては,同時再送信について使用料を支払っていないが,自ら原著作者の権利を侵害しながら,被告に対する権利を主張するのは,権利の濫用,信義則違反として許されない。 (原告らの主張) 被告の主張は争う。以下に述べるとおり,被告の主張は,判例を正解しないものであって,失当である。 ア 被告が挙げるキャンディ・キャンディ事件においては,一審(東京地方裁判所),二審(東京高等裁判所),上告審ともに「長編連載漫画が,原作原稿を原著作物とする二次的著作物に当たり,長編連載漫画の主人公を描いたリトグラフ用原画の作成等が,当該漫画の原作原稿の著作者が二次的著作物たる当該漫画につき原著作者として有する複製権を侵害するとして,原作原稿の著作者による差止請求」を認めたものである。 被告は,上記最高裁判例の判旨中にある「上告人の権利は上告人と被上告人の合意によらなければ行使することができない」との部分の意味を誤解し,論旨を展開しているものであって,失当である。 上記判例の事案は,漫画の著作者である被告(控訴人・上告人)が原著作者である原告(被控訴人・被上告人)の許諾なしに,二次的著作物である長編連載漫画の主人公を描いたリトグラフ用原画の作成等を行ったことから,原告が被告にこの差止めを求め,これを裁判所が認めたものである。これを上告人と被上告人の「合意」といおうが,被上告人の「許諾」といおうが同義である。 本件は,原告らが放送等の同時再送信をしているわけでなく,(本件各契約がないとした場合)被告が原著作者である原告らの許諾なしに二次的著作物である放送作品の同時再送信を行うという事案であって,上記判例からしても,これは原著作者が有する公衆送信権を侵害することになるのは明らかである。 イ 被告の同時再送信に係る放送作品について原告ら加盟員(信託者)以外にも原著作者がいる場合に,その者の許諾がなければ,当該原著作者が被告に対し,同時再送信の差止請求や損害賠償請求を行うことができることはもちろんであるが,そのことと原告らの被告に対する本件契約による使用料の請求あるいは差止請求・損害賠償請求とは全く別の問題である。 著作権法21条ないし27条は,著作者は各権利を「専有」していると定めており,二次的著作物においては,原著作者が複数いる場合の各原著作者の権利,当該二次的著作物の著作者の権利は,当該二次的著作物においてはまさしく併存しているのである。 (4) 原告らの請求は仲介業務法に違反するものか (被告の主張) 以下に述べるとおり,仲介業務法に定める認可を受けていない本件各契約書の使用料に関する規定は無効であって,少なくとも原告日脚連ら4団体)の請求は許されない。 ア 仲介業務法及び同法施行規則においては,著作物使用料規程において定めるべき事項が厳格に定められ,一定の手続を経た後に文化庁長官の認可を受けるべきこととされていた。仲介業務法にこのような定めがおかれたのは,国の政策として特定の団体に著作権に関する仲介業務を独占させていたため,仲介団体に使用料規程を自由に作成させたのでは,仲介団体にとって一方的に有利で,利用者にとって不利な使用料規程が作成されるおそれがあり,このようなことを防止するために,文化庁長官に契約内容及び使用料率のチェックをさせ,その内容の合理性を確保し,使用者の利益を保護するためである。したがって,認可を受けていない使用料規程に基づいて請求を行うことは,仲介業務法に違反することになる。 イ ところで,原告日脚連ら4団体は,本件各契約のみならず,同契約中のテレビジョン及びラジオの同時再送信の使用料規定のいずれについても,文化庁長官の認可を受けていない。このような契約は以下に述べるとおり無効と解すべきである。 (ア) 仲介業務法は,上記のとおり,著作権の仲介,管理業を国策として育成するために,これを文化庁長官の許可にかからしめたものであり,実際にも著作権のジャンルごとに仲介,管理業務を行い得る団体を原則として一つに限定してきた。 その結果,仲介,管理団体は,それぞれのジャンルで独占的地位をもつこととなり,管理著作物の使用を当事者間の自由な契約に任せたのでは,利用者に対して仲介,管理団体に都合のよい契約内容,使用料が押しつけられ,ひいては視聴者の利益が害されるおそれがあり,これを防ぐために,契約約款及び使用料規程を文化庁長官の認可にかからしめ,認可を受けた契約及び使用料規程によらないで業務を行うことは,刑事罰をもって禁じられている。 (イ) 近年消費者取引の分野においては,取引秩序あるいは消費者行政法令に違反する行為については,私法上の効果をより積極的に否定すべきというように考えられている。すなわち,消費者を保護するため,あるいは自由な経済活動を保障するために,最も有効な方法は,これらを阻害する行為に刑事罰や行政罰を科すにとどまらず,私法上の取引行為の効力を否定することであると考えられており,現に,このような考え方を採用したと考えられる判例(最高裁昭和44年(オ)第364号同45年2月26日第一小法廷判決・民集24巻2号104頁)も存在する。 (ウ) 仲介業務法も,国家が原告らに著作権の仲介,管理業務を独占することを許した反面,独占の弊害から使用者を守るために,約款及び使用料規程を文化庁長官の認可にかからしめているのである。これは,まさに,公正な取引秩序の観点から,契約自由の名の下に行われる商慣習の見直しが行われているものというべきであり,契約約款及び使用料規程について文化庁長官の認可を受けることは,著作権の仲介,管理業務を行う上で「公序」をなしているのである。 それにもかかわらず,原告日脚連ら4団体が,文化庁長官の認可を得ないで,著作物使用について利用者と契約を行い,使用料を請求することを許すことは,「公序」に反することとなる。このような場合,契約を無効とすることが「公序を維持するために最も有効な方法である。 したがって,本件各契約は無効であり,原告日脚連ら4団体は本件各契約に基づき著作権使用料を請求することはできない。 ウ また,原告日脚連ら4団体の定めている使用料規程においては,具体的な使用料率を定めていない。 仲介業務法施行規則が,使用料規程に「使用料率」を定めなければならないとしている趣旨は,仲介機関が独占的ないし寡占的地位を占めることに対応して使用料を規制する必要があるためである。本件でいえば,原告日脚連ら4団体の主張する「テレビジョン放送の同時再送信については,被告の得た受信料総額に,①区域内再送信は1波について0.015%,②区域外再送信は1波について0.09%を乗じて計算する」という計算式そのものについて認可を受ける必要があったというべきである。 しかしながら,原告日脚連ら4団体の主張する使用料規程においては,このような具体的な定めはなく,使用料率について認可を受けたとはいえないのであって,この点からも原告日脚連ら4団体が被告に対して請求をすることはできないというべきである。 (原告らの主張) 被告の主張は争う。以下に述べるとおり,被告の主張は失当である。 ア 原告日脚連ら4団体の文化庁長官から認可を受けた使用料規程のうち,本件の有線放送による同時再送信に適用される規定の内容は,別紙1のA欄記載のとおりである。 原告日脚連ら4団体は,上記の使用料規程の規定に基づき,使用者(有線放送事業者)である被告(その上部団体である社団法人日本ケーブルテレビ連盟及びその前身である社団法人日本有線テレビジョン放送連盟(以下両者を区別せずに「ケーブルテレビ連盟」という。)を含む。)との間で著作権等の包括的許諾及びその使用料等につき協議し,被告と本件各契約を締結しているものである。 イ 被告が述べるところの,原告日脚連ら4団体の請求は,文化庁長官の認可を受けていない使用料規程に基づくものである等の主張は,次に述べるとおり失当である。 (ア) 原告日脚連ら4団体の使用料規程には,原告音楽著作権協会の使用料規程を除いて,他の著作権団体等との関係を踏まえた形の使用料規程はないが,だからといって放送の有線同時再送信に関する使用料規程が存在しないということにはならないし,また,原告日脚連ら4団体が有線放送事業者である被告と著作権等の包括的許諾及びその使用料等について協議し,これに基づいて本件各契約のような契約を締結できないとか,これが違法であるということにもならない。 (イ) 被告は,本件各契約の第2条に定める使用料等の計算式自体について文化庁長官の認可を受けていないから,原告日脚連ら4団体の本件各契約に基づく請求は失当であると主張する。 しかし,原告日脚連ら4団体の使用料規程(「使用者(事業者)と協議の上定める」)は,上記アに述べたとおり文化庁長官の認可を受けたものであって,使用料規程は必ずしも計算式をもってのみ定められるものではないし,原告日脚連ら4団体は,当該使用料規程に基づき,すべての有線放送事業者と画一的に同内容の契約を締結し,使用料等を徴収しているものであって,これによって使用者の利益が害されるといったこともない。 (5) 本件各契約は,原告芸団協に関する部分についての詐欺もしくは錯誤により,取り消されるべき,あるいは,無効というべきか (被告の主張) ア 原告芸団協は,同時再送信について著作隣接権を有さないこと 同時再送信の対象となる番組は,①実演家が生出演しているもの,または,②実演家の実演を録音,録画等しているものである。そして,原告芸団協及びその構成員である実演家個人は,番組製作者又は放送事業者に対し,①の場合には自らの実演が放送されることを,②の場合には自らの実演が放送を前提として録音,録画等されることを,それぞれ許諾している。 そうすると,上記①,②は,著作権法92条2項1号,2号にそれぞれ該当するから,結局,同時再送信の対象となる番組には,実演家の有線放送に関する著作隣接権が及ばない(いわゆるワンチャンス主義)。 したがって,被告の同時再送信行為は,いかなる意味においても,実演家の有線放送に関する著作隣接権を侵害しない。 イ 被告が本件各契約を真意に基づいて締結したものではないこと それにもかかわらず,本件各契約は,著作権法上支払義務がない原告芸団協に対する補償金を支払うことを内容としている。しかし,一般に,法律上の支払義務のない金員を,あえて契約を締結して支払うことは考えられない。殊に,被告のように商法上の商人である株式会社の場合,法律上の支払義務がない金員をあえて支払うはずがない。 結局,本件各契約は,一方で,被告に対し,法律上の原因を欠く贈与にも等しい支払いを強い,他方で,原告芸団協に対し,法律上の原因を欠く「不当利得」を得させるという極めて不合理で,かつ,一方的に原告芸団協に有利な内容となっている。 このような契約を被告が真意に基づいて締結するはずがない。 ウ 原告ら5団体は,原告芸団協が同時再送信について著作隣接権を有するかのごとく,被告を欺罔したこと 原告ら5団体が,被告に対して本件各契約の締結を促すために送付した書面(乙1)には,「私ども放送に係わる権利者5団体」との表記がされ,原告芸団協とその余の原告ら,脱退原告で何の区別もされていない。 次に,「放送番組を有線により再送信する場合は,著作権法第23条(著作者は,その著作物を放送し,有線放送する権利を専有する。)により著作者の許諾が必要です。」と記載され,「原告芸団協以外の原告らに関する著作権の条文」は引用されているが,「原告芸団協に関する著作隣接権の条文」は引用されていない。 また,原告ら5団体が,被告に対して契約の締結を促すべく更に送付した書面(乙2)には,「ご存じのとおり,著作権者の許諾なしに放送番組を有線により再送信することは,著作権法違反行為となります。」との警告がなされているが,原告芸団協が有線放送による同時再送信について著作隣接権を有していないことについて,一切触れられていない。 もちろん,原告芸団協が著作隣接権者,その余の原告ら及び脱退原告が著作権者であるとの説明は全くなされていない。 この原告らの勧誘文言は,次の諸点において,原告芸団協が同時再送信に対する権利者であるかのように意図的に誤信せしめるものである。 ① 著作権と著作隣接権の区別を明示していないこと。 ② 著作権者と著作隣接権者の区別を明示していないこと。 ③ ことに,原告ら5名を単純に併記し,いずれが著作権者で,いずれが著作隣接権者であるかを区別していないこと。 ④ 引用される条文は,著作権法23条という著作権に関する条項に限られ,著作隣接権については一切触れられていないこと。 ⑤ 「郵政省の許可を受けている営利法人とは昭和48年度から(ラジオ同時再送信は昭和59年度から)契約し,使用料も支払っていただいております。」,「社団法人日本CATV連盟と話し合いの上,決めたものです。」といった表現により,原告芸団協も,同時再送信に関し,あたかも他の原告と同じ権利(補償金請求権)を有していることが公的に認められているかのような印象を与えていること。 ⑥ 仮に契約締結に応じなかった場合には,原告芸団協との関係でも他の原告と同じく著作権侵害を生じる記載になっていること(原告芸団協には,著作権法上,差止請求権及び損害賠償請求権がないことが記載されていない。) このように,原告ら5団体は,原告芸団協が,同時再送信についてその余の原告ら及び脱退原告と同様,著作権法23条に基づく権利を有しており,もし,被告が原告芸団協に使用料を支払わないで同時再送信を行えば,著作権法に違反し,同原告の権利を侵害する不法行為になるかのごとく被告を欺罔した。 そして,原告ら5団体は,著作権と著作隣接権の区別について十分な説明をしないまま,独占的,優越的地位を利用し,一種の抱き合わせとして,本来,同時再送信について著作隣接権を有しない原告芸団協に対する支払いを上乗せした契約を被告に締結させたのである。 エ 原告らの請求が認められないこと (ア) 上記ウにおいて述べたとおり,被告は,原告ら5団体の欺罔行為により錯誤に陥って本件各契約を締結したのであり,著作権法上,原告芸団協が同時再送信について著作隣接権を有さず,同時再送信が原告芸団協との関係で違法となる余地がない(損害賠償義務を負わない)ことを知っていれば,本件各契約を締結しなかった。 しかるに,原告ら5団体は,原告芸団協が同時再送信について無権利者であるのにこれを秘し,むしろ,積極的に原告芸団協が同時再送信について権利者であるかのように装って,被告に本件各契約を締結させたのであるから,本件各契約は全体(少なくとも原告芸団協に関する部分)について,詐欺を理由に取り消し得る。 (イ) また,被告は,原告ら5団体の前記欺罔行為の結果,有線放送による同時再送信について,原告芸団協について,著作権使用料を支払わなければならないものと誤信して本件各契約を締結した。 本件各契約は,原告芸団協に対する使用料の支払をその内容とするものであるにもかかわらず,著作権法92条2項1号,2号の規定からすれば,原告芸団協は被告に対し使用料を請求できないのであるから,法律行為の要素に関する錯誤である。 したがって,本件各契約は,全体(少なくとも原告芸団協に関する部分)が錯誤により無効である。 (原告芸団協の主張) 被告の主張は争う。原告芸団協が被告との間で本件各契約を締結し,補償金を請求することは何ら著作権法に反するものではない。 ア 著作権法上,放送される実演を同時に有線放送する場合(著作権法92条2項1号)には,実演家は有線放送権を主張できないとされている。しかしながら,この規定の趣旨は,実質的に実演家の権利を否定したものではなく,実演が放送されれば,その放送波の利用の問題は放送事業者の権利によって処理することとなるので,その放送事業者の権利を通じて実演家の権利を実質的にカバーしてもらうことを予定して,法律上は,有線による同時再送信には実演家の権利が及ばないこととしたものにすぎない。 このように,著作権法は,放送される実演を同時に有線放送することについて,放送事業者の権利を通じて実演家に対して一定の対価(報酬)が支払われることを予定しており,これにより実演家の権利(利益)が確保されるものと考えているのである。 しかるに,本件各契約が規定する放送される実演を同時再送信することについては,本来,実演家側が放送事業者側から支払いを受けるべき対価(報酬)の支払を受けていないため(放送事業者との契約締結はない),本件各契約により,放送事業者からではなく,有線放送事業者である被告から上記の対価(報酬)相当分の支払を受けることを被告との間で合意したものである。 イ 著作権法92条2項1号は,昭和45年の著作権法の改正により設けられたものであるが(昭和46年1月1日施行),その後ケーブルテレビ連盟との間において原著作者,実演家の権利の包括処理について議論が繰り返され,本件各契約が締結されたものである。 したがって,著作権法上は,有線による同時再送信には実演家の権利がないとしても,原告芸団協は,本件各契約により,放送事業者からではなく,有線放送事業者である被告から前記の対価(報酬)相当分の支払を受けることを合意しているものである。したがって,原告芸団協(実演家)が被告からの支払いを受ける対価は「補償金」の名称とされており,本件各契約に基づき請求するものであって(契約上の請求権),著作権法上の報酬請求権とも有線放送権の許諾に係る使用料とも性格は異なるものである。このため,本件各契約では,原告芸団協(実演家)は,「丙(被告)がケーブルによって変更を加えないで同時再送信することに対し,放送事業者に異議を申し立てないことを約定する。」と取り決めているのである。 この理は,被告の加盟団体であるケーブルテレビ連盟も理解しているものである。 したがって,被告の原告芸団協に対する反論は失当である。 (6) 原告らの請求権は契約期間満了,時効消滅により認められないものか(被告の主張) ア 本件各契約は契約期間満了により終了している 本件各契約は,いずれも有効期間が平成2年10月1日から同3年3月31日までであるから,既に契約期間が満了し,失効している(本件各契約第8条) この点,本件各契約には自動更新条項のごとき記載があるが,本件各契約の本質が使用料,補償金(以下「使用料等」という。)の支払いにあること,前述のとおり契約内容自体が不合理であること,被告が原告らに対して一貫して使用料等を支払っていないこと等に照らせば,被告が本件各契約を更新する意思がなかったことは明らかである。 よって,契約終了後(平成3年4月1日以降)の使用料等の請求は失当である。 イ 使用料等の一部は時効消滅している 仮に,本件各契約が現在も有効に存続しているものとしても,原告らの請求する使用料等の少なくとも一部は,時効により消滅している。 すなわち,被告は,株式会社であり,使用料等の支払いも営業のためにする行為であるから,使用料請求権は,商事債権として5年の短期消滅時効に服する(商法503条,522条) ところで,本件各契約においては,使用料等は被告が「当該年度」に受領すべき利用料総額に基づいて計算すること(A契約第2条1項,B契約第2条1項),その弁済期は「当該年度」終了後2か月以内であること(A契約第4条,B契約第4条)が規定されている。 「当該年度」については,格別の規定がないから,毎年1月1日から12月31日までと解されるところ,被告が本訴提起より5年以上前に弁済期を迎えた年度分の使用料等は,時効により消滅している。 (原告らの主張) 被告の主張はいずれも争う。 ア 契約期間満了について 本件各契約には,いずれも自動更新の規定(第8条)が存するところ,原告らは,本件訴訟前に被告から口頭・文書を問わず本件契約の解除の意思表示を受けていない。 よって,本件各契約は,少なくとも平成14年3月31日までは有効に存続しているものである。 イ 消滅時効について まず,使用料算定の基準となる「当該年度」とは,毎年4月1日から翌年3月31日までである。 本件使用料等の算出の前提としては,本件各契約第3条に定められているとおり,被告が,当該年度の自身の利用料収入を原告らに報告する必要がある。 具体的には,被告から利用料収入の報告(有テレ法施行規則36条の規定による業務運営状況報告書の写しの添付)を受け,原告らは被告に対し,使用料等を請求し,被告は当該年度終了(毎年3月31日)後2か月以内に原告らに支払をするのである。 ところが,被告は,本件事件で原告らが請求している年度分に関して,原告らに利用料収入の報告をしていない。このため,原告らの請求が遅れたものである。 このように,自己の契約上の義務を履行しないにもかかわらず,消滅時効を援用することは信義則上許されない。 (7) 原告らの使用料等 (原告らの主張) 本件各契約に基づく使用料等(補償金を含む)は次のとおりである。 ア A契約(テレビ放送番組) (ア) 被告の年間の利用料収入 ①契約総世帯数 8000軒 ②月額利用料 3000円 ③年間の利用料収入 ①×②×12か月=2億8800万円 (イ) 料率 ①区域内再送信 12波×0.015%(1波あたり)=0.18% ②区域外再送信 1波×0.09%(1波あたり)=0.09% ③①+②=0.27% (ウ) 単年度使用料 (ア)×(イ)=77万7600円 イ B契約(ラジオ放送番組) (ア) 被告の年間の利用料収入 アの(ア)と同じ 2億8800万円 (イ) 料率 ①区域内再送信 3波×0.0015%(1波あたり) =0.0045% ②区域外再送信 3波×0.009%(1波あたり) =0.027% ③①+②=0.0315% (ウ) 単年度使用料 (ア)×(イ)=9万0720円 ウ 請求金額 (ア) A契約について ①平成6年から平成8年分の消費税相当額合計 77万7600円×3(年)×1.03=240万2784円 ②平成9年から平成11年分の消費税相当額合計 77万7600円×3(年)×1.05=244万9440円 ③合計額 ①+②=485万2224円 (イ) B契約について ①平成6年から平成8年分の消費税相当額合計 9万0720円×3(年)×1.03=28万0324円 ②平成9年から平成11年分の消費税相当額合計 9万0720円×3(年)×1.05=28万5768円 ③合計額 ①+②=56万6092円 (被告の主張) 原告らの主張は,争う。 仮に,本件において本件各契約に定める使用料相当額を支払うべき義務が被告にあるとしても,その額は,別紙2の合計欄に記載する額が限度とされるべきである。以下詳述する。 ア 利用料収入について (ア) 有線放送では,契約世帯数が毎月変動するため,逐一,利用料収入を算出するのは不可能である。このため別紙2においては,一般の有線放送事業者の例にならい,利用料収入を次の算式に基づいて計算している。 (算式Ⅰ)当年度の契約世帯数×月額利用料×12か月 なお,算式Ⅰにおける「当年度の契約世帯数」は次の算式による。 (算式Ⅱ)期初の契約世帯数+{(期末の契約世帯数-期初の契約世帯数)÷2} (イ) 原告らは,業務運営報告書上の利用料収入額を用いるべき旨を主張するが,そうすると,当該年度の途中から加入した者の利用料が正確に反映されないこととなるし,業務運営状況報告書上の利用料収入には本来利用料に含まれていない加入金も含まれているので,この数値を用いるのは適切といえない。 イ 電波障害施設等維持費について 電波障害施設等維持費(別紙2では「電波障害回線利用料収入」と表示)とは,電波障害により正常に電波を受信できない場合における対策施設の維持費である。この電波障害施設等維持費は,有線放送事業者が,電波障害の原因者の委託を受けて行う電波障害対策の維持費であるから,原告らにおいて,著作物使用料を算定する基礎となる利用料収入には当たらない。 それゆえ,別紙2においては,電波障害施設等維持費を利用料収入から控除すべき項目として計上した。 ウ コンバーターリース料について コンバーターとは,各契約世帯に設置する多チャンネル用の受信装置であり,ケーブルの信号を変換してテレビ(受像機)に伝達する働きを有する。このように,コンバーターは,契約者がテレビを視聴するために必要な機材であり,本来,契約者が各自購入すべきものである。 しかし,有線放送事業者は,有線放送の普及のため,契約者が手軽に有線放送を視聴できるように,コンバーターのリースを手配し,本来的に契約者がリース業者に支払うべきリース料の回収を代行しているにすぎない。 すなわち,コンバーターリース料は,コンバーターという機械のリース料であり,かつ,リース業者に帰属すべき収入である。 したがって,有線放送事業者が著作物を利用したことに対する対価とはいえず,利用料収入に含まれないから,原告らが使用料を課すべき根拠がない。 それゆえ,別紙2においては,コンバーターリース料を利用料収入から控除すべき項目として計上した。 エ 自営柱電気代について 自営柱とは,各契約世帯に送信すべき電波を増幅する増幅器(ブースター)に電気を供給するための電柱であり,自営柱電気代とは,自営柱を稼働するための電気代である。契約世帯が増加するのに応じて増幅器,ひいては自営柱の設置が増えるため,自営柱電気代も増加することになる。 このように,自営柱電気代は,契約世帯数の増加によって変動する設備の維持管理のための経費なのであって,有線放送事業者の利用料収入とは全く関係がない。すなわち,有線放送事業者が原告らの管理する著作物を利用したことに対する対価とはいえず,利用料収入に含まれないから,原告らが使用料を課すべき根拠がない。 それゆえ,別紙2においては,自営柱電気代を利用料収入から控除すべき項目として計上した。 オ 番組費について 番組費(別紙2においては「番組購入費」と表示)とは,有線放送事業者が同時再送信の対価として,委託放送事業者に支払う代金である。原告らは,番組費について,委託放送事業者に課金しているのであるから,これをさらに有線放送事業者の収入に計上し,使用料を課金するのは完全な二重取りであり,不合理であることは明らかである。 それゆえ,別紙2においては,番組費を利用料収入から控除すべき項目として計上した。 カ 番組表費について 番組表とは,有線放送の番組内容を紹介するプログラムであり,番組表費(別紙2においては「番組表通信費」と表示)とは契約者に番組表を配布した対価(製作配布の実費)である。 このように,番組表は,契約者が番組を視聴するために必要なプログラムであり,本来,契約者が各自入手すべきものである。しかし,有線放送事業者は,有線放送の普及のため,契約者が手軽に有線放送を視聴できるように,番組表を製作し,契約者に実費で配布しているにすぎない。すなわち,番組表費は,番組表の対価(雑誌の代金)であり,有線放送事業者が原告らの管理する音楽著作物を利用したことに対する対価とはいえず,利用料収入に含まれないから,原告らが使用料を課すべき根拠がない。 それゆえ,別紙2においては,番組表費を利用料収入から控除すべき項目として計上した。 (原告らの再反論) ア 本件各契約において,被告の支払うべき使用料,補償金の合計金額は,被告が「当該年度に受領すべき利用料総額に,各々次の料率を乗じて算出した額とする」(本件各契約第2条)とされ,計算の基となる金額は被告の「当該年度に受領すべき利用料総額」である。 そして,この利用料総額は,有線放送事業者が総務大臣(郵政大臣)に提出する業務運営状況報告書に記載された利用料収入によっているのであり,何ら不合理ではない。 イ ただし,業務運営状況報告書に記載された利用料収入の中に,①電波障害施設利用料収入,②ペイチャンネル収入,③ホームターミナル利用料収入及び④番組ガイド誌購読料収入のような収入が含まれている場合には,これらが同時再送信にかかわる収入(基本利用料,受信料)でないことから,原告らは,被告がその金額を証明する帳簿書類等を提出した場合には,当該金額を控除した金額を基とした使用料,補償金を計算する扱いとしている。 被告の提出した証拠に記載された金額を基にして,上記の扱いにより計算した使用料,補償金の合計金額は別紙3の「請求金額」欄記載の金額となる |
|
|
当裁判所の判断
1 争点(1)(被告の同時再送信するテレビ番組は映画の著作物であって,原告らは著作権等の主張をすることができないものであり,本件A契約は錯誤により無効か)について (1) 被告は,被告が同時再送信するテレビ番組は,映画の著作物であるから,その著作者となり得るのは,製作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に寄与した者,具体的にはテレビ番組の番組製作者のみであるから,原告らはテレビ番組について著作者として権利を行使し得る立場にないにもかかわらず,テレビ番組の同時再送信について権利を留保しているかのように被告を誤信させて本件A契約を締結させた旨主張する。 (2) しかしながら,被告の上記主張を採用することはできない。その理由は次のとおりである。 まず,著作権法2条3項において,同法において保護される「映画の著作物」には,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物に固定されている著作物を含むものとされているところ,同規定によれば,物に固定されていないような表現は,視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されているものであっても,同法において保護される「映画の著作物」には該当しないこととなると解される。 被告が同時再送信するテレビ番組は,テレビドラマのように録画用の媒体に固定され,しかる後に放送される番組もあるが,生放送番組のように媒体に固定されずに放送される番組もあることは当裁判所に顕著である。このような,媒体に固定されずに放送されるテレビ番組は上記の「映画の著作物」に該当しないものと解されるところであって,およそテレビ番組はすべて「映画の著作物」に該当することを前提とする被告の主張を採用することはできない。 仮にこの点を措くとしても,著作権法16条においては,映画の著作物の著作者は,「その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き」映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする旨規定されているところ,同規定の趣旨は,映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者(いわゆるクラシカル・オーサー)については,映画の著作物の著作者とは別個に映画の著作物について権利行使することができることをいうものと解される。したがって,被告が同時再送信するテレビ番組の中に映画の著作物に該当するものがあったとしても,本件原告ら5団体のうち,少なくとも,原告日脚連,原告シナリオ作家協会,原告音楽著作権協会及び脱退原告(原告日脚連ら4団体)については,クラシカル・オーサーとして,テレビ番組の著作者とは別個にテレビ番組について権利行使を行うことが可能なのであって,上記原告らがテレビ番組の著作者と別個に被告の行う同時再送信について権利行使することができないとする被告の主張を採用することはできない。 被告は,上記のような解釈は,テレビ番組に関する権利関係をいたずらに複雑化し,放送コンテンツの利用に不当に制約を加えるものであって妥当でない旨主張するが,著作権法16条が明文をもって,映画の著作物の著作者とは別に原著作物の著作者が存在することを認めている以上,被告の主張するように原著作物の著作者が権利行使できないと解釈することは困難である。 以上のとおりであって,被告の同時再送信するテレビ番組は映画の著作物であるから被告の行う同時再送信に原告らが著作権を行使することはできないという点を前提として,本件A契約の詐欺取消あるいは錯誤無効を主張する被告の主張は,その前提を欠くものであり,採用することができない。 (3) よって,被告の上記主張は理由がない。 2 争点(2)(被告による同時再送信は,原告ら5団体が放送事業者に対して許諾した著作物の使用の範囲に含まれているものであって,被告は改めて許諾を得る必要はなく,本件各契約は錯誤無効か)について (1) 被告は,被告が行う放送の同時再送信は,放送事業者が行う放送の単なる中継行為と変わらないものである上,難視聴解消という公益目的も有するものであるから,放送事業者に対して許諾した放送での使用の範囲内に含まれているものであって,被告は放送の同時再送信について原告ら5団体から放送事業者とは別に許諾を得る必要なく,それにもかかわらず,原告ら5団体に許諾権限があるかのように被告を誤信させて締結させた本件各契約は詐欺あるいは錯誤に当たると主張する。 (2) しかしながら,被告の上記主張を採用することはできない。その理由は次のとおりである。 著作権法上,放送も有線放送も公衆送信の1形態として位置付けられ,著作権者は放送事業者の行う放送及び有線放送事業者の行う有線放送とも,自己の専有する公衆送信権(著作権法23条1項)に基づき許諾するものであるけれども,放送事業者の行う放送と有線放送事業者の行う有線放送とは,送信の主体が異なるだけでなく,著作権法上別個の公衆送信と位置付けられていること(著作権法2条1項8号,9号の2,63条4項参照)に加えて,現実の送信の態様も大きく異なるものであるから,放送事業者に対する放送の許諾の際に,有線放送事業者に対する有線放送の再許諾権限を放送事業者に対して付与していたと認められる特段の事情がある場合を除き,放送事業者に対する放送の許諾によって,有線放送事業者の行う有線放送までを許諾したということはできないというべきである。 この点につき,被告は,著作権者において放送事業者が放送に著作物を使用することついて許諾をした場合,当該放送事業者の業務区域内で視聴者がテレビ番組を視聴することは当然想定した上で許諾しているものであるところ,このことに,有線放送事業者の同時再送信は,社会通念上放送事業者の放送として扱われており,同時再送信の効果も放送事業者に帰属すること,放送事業者自らが有線放送したり,下請け会社に有線放送させたりした場合と実態が異ならないことを併せ考慮すれば,同時再送信は,新たな著作物の使用ではなく,放送事業者に対する著作物の使用の許諾があった場合には,著作権法上有線放送による同時再送信の使用の範囲内であると主張する。 しかしながら,上記のとおり,放送事業者の行う放送と有線放送事業者の行う有線放送とは,送信の主体が異なるだけでなく,著作権法上別個の公衆送信と位置付けられていること,現実の送信の態様も大きく異なるものであること等の事情に加え,著作権法38条2項において非営利の同時再送信について著作権が制限されることを規定している趣旨に鑑みれば,有線放送事業者が行う同時再送信については,著作権法上,放送事業者の行う放送とは独立して公衆送信権の侵害となると解さざるを得ない。 被告は,テレビ番組の原著作物の著作権者に,放送事業者による放送の段階と有線放送事業者による同時再送信の段階の2回にわたる権利行使を認めるならば,実質的に著作物使用料の「二重取り」を許すことになり不当であると主張する。しかしながら,上記のとおり,著作権法が,放送と有線放送について,同時に行われるものであっても,別個の公衆送信と位置付けている以上,双方に対して別個に権利行使すること自体を不当ということは到底できないのであって,被告の上記主張を採用することはできない。 したがって,上記のとおり,テレビ番組の原著作物の著作権者において,放送事業者に対する放送の許諾の際に,有線放送事業者に対する有線放送の再許諾権限を放送事業者に対して付与していたと認められる特段の事情がある場合を除き,放送事業者に対する放送の許諾によって,有線放送事業者の行う有線放送までを許諾したということはできないと解すべきところ,本件においては,本件全証拠によっても,放送事業者に対する放送の許諾の際に有線放送事業者の行う同時再送信の再許諾権限まで与えていたものと認めることはできない。 (3) 以上のとおりであるから,被告は放送の同時再送信について原告ら5団体から放送事業者とは別に許諾を得る必要ない旨の主張を前提とする上記被告の詐欺あるいは錯誤の主張はいずれも理由がない。 3 争点(3)(原告らの請求は,権利の濫用あるいは信義則違反か)について (1) 被告は,キャンディ・キャンディ事件上告審判決の趣旨に従えば,二次的著作物ないし三次的著作物たるテレビ番組の原著作物の著作者たる原告らは,脚本の原作となった漫画の著作者等の他の著作権者と共同しなければ,被告に対して権利行使することはできないにもかかわらず,原告らが被告に対して他の著作権者と共同せずに許諾をするのは,権利の濫用であり,信義則違反であると主張する。 (2) しかしながら,被告の上記主張を採用することはできない。理由は次のとおりである。 著作権者は,それぞれ他人に対し,著作物の利用を許諾する権限を有しているのであり(著作権法63条1項),このことは二次的著作物の場合であっても変わりがない。したがって,二次的著作物の原著作物の著作者は,他の権利者と共同しなくても,それぞれ自己の著作権に基づく権利行使をなし得るものである。 被告は,キャンディ・キャンディ事件上告審判決の趣旨に照らすと,二次的著作物の原著作者は,当該二次的著作物の著作者を含む他の権利者と共同しなければ権利行使なし得ないと主張するものであるが,上記判決は,二次的著作物の著作者による当該二次的著作物の複製行為に関し,原著作物の著作者は,当該二次的著作物を合意によることなく利用することの差止めを求めることができる旨を明らかにしたにすぎず,二次的著作物の原著作物の著作者が単独で第三者に許諾権限を行使することができない旨を述べたものとは解されない。したがって,被告のこの点の主張を採用することはできない。 (3) 以上のとおりであるから,テレビ番組が二次的著作物ないし三次的著作物に該当する場合であっても,当該テレビ番組の著作物の原著作物の著作者らは,それぞれ個別に権利行使をすることが可能であるから,これと異なる前提に立って論旨を展開する被告の上記主張を採用することはできない。 4 争点(4)(原告の請求は仲介業務法に違反するものか)について (1) 被告は,著作権等の仲介事業者が定める本件各契約に定める使用料等の規定は,仲介業務法に定める文化庁長官の認可を受けない限り効力を有しないものであることろ,本件各契約について文化庁長官の認可を経ていない以上,原告日脚連ら4団体(原告日脚連,原告シナリオ作家協会,原告音楽著作権協会及び脱退原告)は本件各契約に基づき被告に対して使用料等を請求することはできないと主張する。 (2) この点,証拠(甲23の1,24の1,25の1,26の1)によれば,原告日脚連ら4団体は,本件各契約締結当時,それぞれ文化庁長官の認可を受けた使用料規程を有していたこと,原告日脚連,原告シナリオ作家協会及び脱退原告の使用料規程のうち,有線放送事業者の行う放送の同時再送信について適用される規定は,「著作物の性質,利用の目的,態様及びその他の事情に応じて,使用者と協議の上定めるものとする」旨の内容であり,同様に原告音楽著作権協会の規定の内容は「原告音楽著作権協会を含む著作権・著作隣接権団体が有線放送事業者と協議して定める料率によることができる」旨の内容であること,本件各契約においては,テレビジョン放送の同時再送信及びラジオ放送の同時再送信について,それぞれ使用料の算定方式が定められているものであることがそれぞれ認められる。 (3) 以上の事実によれば,原告日脚連ら4団体は,文化庁長官による認可を受けた使用料規程に基づき,それぞれの規定において,有線放送事業者と協議の上で定めることとされている使用料の額について,本件各契約において有線放送事業者である被告との間で定めたものであることが認められる。 そうすると,文化庁長官による認可を経て定められた原告日脚連ら4団体の使用料規程の範囲内において,本件各契約が締結されたものということができるから,仲介業務法に違反するとまでは解することができない。 (4) 被告は,仲介業務法3条を受けて定められた同法施行規則4条においては,使用料規程には著作物の使用料率に関する事項を定めるべきものとされ(同法施行規則4条1項),かつ,その使用料率の定めについては著作物の種類及びその利用方法の異なるごとに各別に定めることとされているのは(同施行規則4条2項),具体的な使用料の額についても監督庁の監督に服せしめる趣旨であって,使用料規程において具体的な額を定めず,それ以外の契約で使用料を定めるのは,上記の法の趣旨を逸脱するものであり,許されないと主張する。 しかしながら,仲介業務法3条は,著作物の利用者を保護する観点から,仲介事業者の恣意的な使用料設定を防止するために,いくら支払えば著作物等を利用することができるかを利用者に明らかにし,その内容の適正さを確保するために,使用料規程について文化庁長官の認可にかからしめることとしたものと解されるところ,同法施行規則4条1項の規定により定められる「使用料率の定め」とは,当該定めに基づき一義的に適正な額の使用料が導かれるものであれば足り,具体的な使用料の額を定めることが困難なものについても一律に具体的な使用料の額や使用料算定方式の定めを要するとまでは解されない。原告日脚連ら4団体の各使用料規程においては,有線放送事業者の行うテレビジョン放送の同時再送信についての使用料は,有線放送事業者との協議の上定められるべきことが定められているものであるが,情報通信分野においては技術革新等により急速に事情が変化し得るものであり,あらかじめ利用態様を想定して使用料の額や算定式を使用料規程で規定することが困難であることに加え,有線放送事業者と原告らの協議によって適正な額の使用料が定められることは十分に可能であることに照らせば,上記の原告日脚連ら4団体の使用料規程の定めが仲介業務法に違反するとまではいうことはできず,そのような使用料規程を受けて締結された本件各契約が無効であるということはできない。 (5) 以上のとおりであるから,本件各契約の定めが仲介業務法に違反するという被告の上記主張を採用することはできない。 5 争点(5)(本件各契約は,原告芸団協に関する部分についての詐欺もしくは錯誤により,取り消されるべき,あるいは,無効というべきか)について (1) 前記前提となる事実関係に証拠(甲1,2,乙1,2,27)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められ,これを左右するに足る証拠はない。 ア 平成2年10月3日ころ,協同組合日本放送作家組合(原告日脚連の前身)は,原告ら5団体の代表として,被告に対し,概ね次の内容を記載した書簡を送付し,本件A契約の締結を促したが,同書簡では,実演家の権利について特に区別することなく,有線放送の同時再送信には原告ら5団体の許諾が必要である旨を述べている。 「私ども放送に係わる権利者5団体(中略)は,各々の団体の構成員に代わり,それぞれの分野の著作権及び著作隣接権の管理を行っております。つきましては,貴社は有線による放送番組の同時再送信を実施されるご予定のようですが,放送番組を有線により再送信する場合は,著作権法23条(著作者は,その著作物を放送し,有線放送する権利を専有する。)により,著作者の許諾が必要です。私ども放送に係わる権利者5団体は,有線放送事業者と一括契約することによって,各団体加盟の著作者に代わり,放送番組の有線による同時再送信を許諾しており,同封いたしました許諾契約書は,社団法人日本CATV連盟と話し合いの上,決めたものです。」 イ さらに,平成3年5月22日ころ,原告日脚連は,原告ら5団体の代表として,被告に対し,概ね次の内容を記載した書簡を送付し,本件各契約の締結を重ねて促したが,同書簡中においては,原告芸団協の著作隣接権が有線放送による放送の同時再送信に及ぶかどうかについては触れていない。 「放送番組の有線による同時再送信について,ご契約いただくよう再三お願いいたしておりますが,本日に至るもまだご契約いただいておりません。改めて契約書を同封いたしますので,6月15日までにご契約くださいますようお願いいたします。なお,ラジオ(FM他)放送番組の同時再送信につきましても,(社)日本CATV連盟と合意に至りましたので併せてご契約願います。ご存じの通り,著作権者の許諾なしに放送番組を有線により再送信することは著作権法違反行為となります。私ども放送に係わる権利者5団体は,郵政省の許可を受けている営利法人とは,昭和48年度から(ラジオ同時再送信は昭和59年度から)契約し,使用料も支払っていただいております。」 ウ 平成3年6月12日,原告ら5団体と被告は本件各契約を締結したが,本件各契約においては,原告芸団協は,被告が本件各契約に定める補償金を支払うことを条件として,原告芸団協の会員の実演によって製作された放送番組(又はラジオ放送番組)を,被告が変更を加えないでケーブルによって同時再送信することに対し,放送事業者に異議を申し立てないことを約する旨が定められた。 (2) ところで,原告芸団協は,著作権法95条5項,95条の3第4項に基づき,文化庁長官により実演を業とする者の相当数を構成員とする団体として指定を受けた団体であるところ,同団体は,著作権法の規定に従い,実演家の有する商業用レコードの二次使用料請求権や商業用レコードの貸与の許諾に係る使用料請求権を実演家から委任を受けて自己の名をもって権利行使すべき権限を有する。そして,原告芸団協はこのような立場に基づき本件各契約を締結したものと認められる。 しかしながら,被告の同時再送信するテレビジョン放送及びラジオ放送の番組のなかには,実演家の生実演を放送する番組や市販の目的をもって製作されるレコードの複製物を利用した番組が存在していることは顕著な事実であるが,いずれの番組についても,放送される実演を有線放送する場合には,著作権法92条2項1号により当該有線放送に実演家の権利は及ばないものと解される。すなわち,実演家は,有線放送事業者の行うテレビジョン放送及びラジオ放送の同時再送信について,原告芸団協を通じて行使すべき権利を有しないのであり,有線放送事業者に対して許諾を行うことができる立場にないのはもちろんのこと,放送事業者との契約において同時再送信を許諾してはならない旨の取り決めが存在するなどの特段の事情の存在しない限り,同時再送信が行われたことにつき放送事業者に対して異議を述べることもできないものと解される。 この点につき,原告芸団協は,著作権法は,有線放送による同時再送信について著作権者が権利行使を行うことを禁じておらず,放送事業者から支払いを受けるべき対価の支払いを受けていないような場合には,有線放送事業者との間に契約を締結して,有線放送事業者に対して対価相当額の支払を求めることも許されると主張する。しかしながら,著作権法92条2項1号において有線放送による放送の同時再送信の場合に実演家の著作隣接権が及ばないこととされているのは,同号の規定が実演家が放送を許諾しているかどうかを区別せずに一律に有線放送による同時再送信について権利が及ばないとしていることに照らせば,実演の無形的利用については当初の利用契約によって処理すべきものとするいわゆるワン・チャンス主義の観点から,放送の段階についてのみ権利行使を許容する趣旨であると解される。したがって,実演家は,放送事業者から十分な対価を得ていたかどうかにかかわりなく,有線放送事業者の行う同時再送信について著作隣接権に基づき二次使用料を請求することはできないものと解され,上記の原告芸団協の主張を採用することはできない。 (3) 上記(2)で述べた点に(1)において認定の事実を総合するならば,本件においては,有線放送による放送の同時再送信について,実演家の著作隣接権に基づき対価を徴収することは実際は法律上許されていないにもかかわらず,これが可能であると被告において信じ,かかる誤信にもとづき本件各契約が締結されたものと認められる。 被告の上記誤信は,動機に関するものではあるが,上記(1)に認定した本件各契約締結時の,原告ら5団体と被告との交渉経緯に照らすと,被告が上記誤信に基づいて本件各契約を締結したことは原告芸団協も認識していたものと認められ,かつ,被告の上記誤信は契約の要素に関する錯誤であるというべきであるから,本件各契約のうち原告芸団協に関する部分は錯誤により無効であるというべきである。 また,被告は,原告芸団協に関する部分の錯誤により,本件各契約は全体が無効になる旨も主張しているが,しかし,本件各契約は,原告ら5団体がそれぞれ管理等を行う著作物等に関する個別の権利関係について,被告との間で締結された契約であって,原告ら5団体のうちの一部と被告との契約につき無効事由が存在するとしても,他の契約当事者との契約の効力に影響を及ぼすものではない。 したがって,本訴請求中,原告芸団協の請求は理由がないので,棄却すべきものである。 6 争点(6)(原告らの請求権は契約期間満了,時効消滅により認められないものか)について (1) 契約期間満了による契約終了の主張について 被告は,本件各契約は,契約期間満了により終了した旨を主張する。しかしながら,前記前提となる事実関係記載のとおり,本件各契約においては,契約期間満了の日の1か月前までに,契約当事者から契約の廃棄,変更について特別の意思表示が文書によってなされなかった場合は,期間満了の日の翌日から起算しさらに1年間その効力を有すること,それ以降の満期のときもまた同様であることが定められている。 本件においては,全証拠によっても,本件で原告らが使用料等の請求の対象期間としている平成6年度から平成11年度の間に被告から本件各契約を解除する旨の意思表示が行われた事実を認めることはできない。被告は,使用料等を支払っていなかった以上,被告が契約を継続しない意思を有していたことは明らかであった旨主張するが,単に契約上の義務を履行していなかったことをもって契約を継続しない意思があったということができないものであり,上記のとおり,本件各契約においては文書による意思表示を契約終了の要件としているものであるから,被告の主張を採用することはできない。 (2) 時効消滅の主張について 前記前提となる事実関係記載のとおり,本件各契約においては,被告は,各年度において定められる使用料等を,当該年度の終了後2か月以内に原告ら5団体の代表である原告日脚連に持参又は送金して支払うべき旨が定められている。したがって,本件各契約に基づいて発生する使用料等の支払義務は,各年度(4月1日から3月31日と認められる。(乙38の1ないし6))終了後2か月の経過(具体的には5月31日の経過)をもって履行期が到来し,原告ら5団体ないし原告ら4団体において,被告に対して請求をなし得るものと解される。 ところで,本件各契約は,商人たる被告がその営業のために締結したものと認められるから,同契約に基づき発生する使用料等の請求権は商行為によって生じた債権として,履行期から5年の経過をもって時効により消滅するものと解される(商法522条)。したがって,本件においては,原告日脚連の分については,原告日脚連が本訴を提起した平成13年4月26日より,原告音楽著作権協会,原告シナリオ作家協会及び参加人の分については,これらの原告及び脱退原告(民事訴訟法49条参照)が本訴を提起した平成14年2月26日より,それぞれ5年以上前に履行期の到来した使用料等請求権(具体的には原告日脚連の平成6年度分の使用料等請求権,その余の原告ら及び参加人の平成6年度,7年度分の使用料等請求権)については,消滅時効が完成しているものである。 被告が上記消滅時効を援用したことは,当裁判所に顕著であるから,原告らは,消滅時効に係る上記の使用料等を被告に対して請求することはできない。 原告らは,原告らが被告に対して使用料等の請求をしていなかったのは,被告が契約に定められた業務運営状況報告書の写しの提出をしなかったためであり,このように自己の契約上の義務を履行しないにもかかわらず,消滅時効を援用することは許されない旨主張するが,原告らにおいて使用料等を請求するにつき法律上の障害があったものとは到底いうことができない本件において,上記のような事情があるからといって被告による時効の援用が信義則に反するということはできない。上記原告らの主張を採用することはできない。 7 争点(7)(原告らの使用料等)について (1) 本件各契約における「利用料収入」について 本件各契約において使用料等算定の基礎となる「利用料収入」については,各年度の業務運営状況報告書添付の損益計算書に計上されている利用料収入から,①電波障害回線利用料収入,②コンバーターリース料,③ペイチャンネル収入,④番組ガイド製作費及び通信費(番組ガイド代金及び送料)は控除することとするのが相当である。けだし,これらの収入は,損益計算書上利用料収入の費目に計上されているとはいっても,放送の同時再送信とは無関係に被告が得ている収入であるから,使用料算定の基礎となる「利用料収入」と解することはできないからである。被告は,これらの費目に加えて,自営柱電気代及び番組購入費も控除すべき費目に加えるべきものと主張するが,本件各契約において「利益」ではなく「収入」を基礎として使用料等を算定すべきものと規定されていることに照らせば,これらの経費を控除すべきものとはいえない。 また,被告は,業務運営状況報告書添付の損益計算書に計上されている利用料収入では,期間中の利用者の増減が反映されないこととなるので,(当年度受信契約者数-前年度受信契約者数/2+前年度受信契約者数)×単価3000円×12か月という算式による収入を基礎となる収入とすべきと主張する。しかし,本件各契約3条において,被告は業務運営状況報告書により利用料収入の報告を行うべき旨が定められていることに照らすならば,本件各契約においては,期間中の利用者の増減にかかわらず,業務運営状況報告書に記載された利用料収入を基礎とし,そこから同時再送信と関係のない収入を控除することが想定されているというべきである。被告の上記主張を採用することはできない。 (2) 本件各契約に基づく原告らの使用料等 以上より,本件各契約に基づき発生する各年度ごとの使用料等を計算する。 まず,乙38号証によって認められる業務運営状況報告書記載の利用料収入から,乙43号証によって認められる電波障害回線利用料収入,乙28,34号証によって認められるコンバーターリース料及びペイチャンネル収入,乙28,45号証によって認められる番組表製作費,番組表通信費を控除して本件各契約における「利用料収入」に該当する金額を算定する(ただし,平成6年度分はすべて時効消滅しているので算定しない。)。 その上で,甲1,乙37の1及び弁論の全趣旨によれば,本件A契約については,①区域内再送信は11波,②区域外再送信は1波と認められるため,本件A契約に基づく使用料等としては,上記において算定される利用料収入に,契約において定められた区域内再送信の使用料率0.165%(=①11波×0.015%)及び区域外再送信の使用料率0.09%(=②1波×0.09%)の合計である0.255%を乗じ,さらに平成7年度分及び平成8年度分の使用料等には3%の,平成9年度分から平成11年度分の使用料等には5%のそれぞれ消費税相当額を加算して,各年度ごとの使用料等を算定すると(平成7年度及び平成8年度については,別紙使用料等計算表の本件各契約における「利用料収入」欄記載の金額×0.255%×1.03,平成9年度ないし平成11年度については,別紙使用料等計算表の本件各契約における「利用料収入」欄記載の金額×0.255%×1.05),別紙使用料等計算表の本件A契約(含消費税)欄記載の金額となる。 さらに,本件B契約については,①区域内再送信は3波,②区域外再送信は4波であることは当事者間に争いがないから,本件B契約に基づく使用料等としては,上記において算定される利用料収入に,同契約において定められた使用料率の上限である0.035%を乗じ(区域内再送信の使用料率〔①3波×0.0015%〕+区域外再送信の使用料率〔②4波×0.009%〕の合計は0.0405%となるが,同契約2条により,上限である0.035%を乗ずるものである。),さらに平成7年度分及び平成8年度分の使用料等には3%の,平成9年度分から平成11年度分の使用料等には5%のそれぞれ消費税相当額を加算して,各年度ごとの使用料等を算定すると(平成7年度及び平成8年度については,別紙使用料等計算表の本件各契約における「利用料収入」欄記載の金額×0.035%×1.03,平成9年度ないし平成11年度については,別紙使用料等計算表の本件各契約における「利用料収入」欄記載の金額×0.035%×1.05),別紙使用料等計算表の本件B契約(含消費税)欄記載の金額となる。 (3) 小括 原告らは本件A契約に基づく請求につき各自の債権額を5分の1ずつとして請求をしており(前記第1(原告の請求)の第1項),原告ら(原告音楽著作権協会を除く。)は本件B契約に基づく請求につき各自の債権額を4分の1ずつとして請求をしている(前記第1の第2項)ところ,本件各契約に基づく使用料等についてはそれぞれ契約当事者たる原告ら及び脱退原告(参加人)の間で平等の割合で帰属するものとされていたと認められるから(第20回弁論準備手続期日において,原告ら及び脱退原告は,本件A契約に基づく請求につき,各自の債権額を5分の1とすることに異論はない旨を陳述しているところであり,かかる原告らの陳述からすれば,本件B契約に基づく請求について各自の債権額を4分の1ずつとすることにも異論はないものと解される。また,本件各契約に基づく使用料等の原告ら及び脱退原告(参加人)の間における分配については,被告も争っていない。),本件A契約に定める使用料等の額として認められる金額から原告芸団協の請求分である5分の1の金額,本件B契約に定める使用料等の額として認められる金額から原告芸団協の請求分である4分の1の金額を,それぞれ控除すべきものである。 したがって,本件A契約について5分の1を,本件B契約について4分の1をそれぞれ控除すると,別紙使用料等計算表記載の芸団協分控除後欄記載のとおりとなる。 さらに,平成7年度分の使用料等請求権については,原告日脚連の分を除き時効消滅しているので,同年度分の本件A契約に基づく使用料等については,原告日脚連分として控除後の上記金額の4分の1である4万216円,同じく本件B契約に基づく使用料等については,原告日脚連分として控除後の上記金額の3分の1である6899円に限って認められることとなる(合計4万7115円)。 そして,別紙使用料等計算表記載の各契約に基づく平成8年度ないし11年度の使用料等の額(原告芸団協分控除後)を合算して各契約ごとの使用料等の額を算定すると,本件A契約の使用料等の合計額が101万1081円,本件B契約の使用料等の合計額が13万102円と認められる。 8 結論 以上のとおりであるから,原告らの本訴請求については,①原告日脚連が平成7年度分の本件各契約に基づく使用料等として4万7115円及びこれに対する履行期の経過後である平成13年5月15日以降の年5分の割合による遅延損害金,②原告日脚連,原告シナリオ作家協会,原告音楽著作権協会及び参加人が平成8年度ないし11年度の本件A契約に基づく使用料等として101万1081円及びこれに対する履行期の経過後である平成13年5月15日以降の年5分の割合による遅延損害金,③原告日脚連,原告シナリオ作家協会及び参加人が平成8年度ないし11年度の本件B契約に基づく使用料等として13万102円及びこれに対する履行期の経過後である平成13年5月15日以降の年5分の割合による遅延損害金,の各支払いを求める限度で理由がある。 よって,主文のとおり判決する。 |
| 裁判長裁判官 | 三村量一 |
|---|---|
| 裁判官 | 松岡千帆 |
| 裁判官 | 大須賀寛之 |